一九三〇年。ドイツ国内で反ユダヤ主義的風潮が強まるころ、本書は出版された。執筆したのは、亡命先(チェコスロバキア)でナチ党員の手で暗殺されたドイツ系ユダヤ人の哲学者・政治 ジャーナリストであるテオドール・レッシング(一八七二~一九三三)である。
本書の刊行後、ほどなくしてヒトラーが政権を掌握すると、レッシングは娘を連れてプラハ行きの列車に乗った。亡命中、レッシングが憂いたことはユダヤ人の悲劇的運命ではない。「自己憎悪」に囚われた同胞たちの不幸である。本書は、ユダヤ人自身による反ユダヤ主義的な「自己憎悪」の歴史と病理とを明らかにし、その治癒を訴えるものである。
自己憎悪する人は、自らの生を否定するばかりではなく、自己自身が他者によって裁かれることを望んだ。まさに「生命がみずから自身に逆らい、生命と対立し、最終的に生命を憎悪するように仕組むのは、精神自体の驚異」である。長年、世界の「よそ者」として暮らしてきたユダヤ人は、ときに馴染みのない言葉や風土、精神にまで「同化(帰依)」し、また洗礼を受けることによって生きながらえてきた。しかし、この寄る辺なき民族の生存戦略〈自己を抑圧し、他者に依存していく態度〉が、自己分裂の契機となった。また、ユダヤ人には、「自分に降りかかる不幸」を「自分が犯した罪の贖罪」ととらえる傾向があり、それが自己の「生」を二重にあやうくしたのである。
他方、反ユダヤ主義の反動としてシオニズムが起こると、レッシングもこれに賛同した。が、著者はその賛同の理由を「ユダヤ人であると自覚したからであって、ユダヤ人として傷つけられたと自覚してのことではなかった」と振り返る。レッシングにとってシオニズムは、ただ社会に認められたいという願望だったのだろう。長い困苦の歴史の末、民族固有の魂を失い、近代化された「ユダヤ人」には当事者意識が欠けていた。この点、ユダヤ人自身によるユダヤ人の迫害は、近代化の歴史において必然であったとレッシングは指摘する。
とはいえ、もちろん、その「同化」と「自己憎悪」の歴史はレッシングとも無縁ではなかった。ドイツ出身のレッシングは、プロテスタントに改宗することでユダヤ精神に抵抗した人物でもある。では、一体何が彼を「自己憎悪」へと追いつめたのか。一つはユダヤ人である父母の不仲と、父が母親似のレッシングを憎んでいたという不幸な幼少期による。生みの親に愛されず、魂の故郷を愛せないという二重苦がレッシングと反ユダヤ主義を強く結びつけたのだった。が、やがて父の呪縛から解かれたレッシングは、大学の私講師として教育に力を入れる。その後も絶え間ない社会的抑圧と民族の悲劇的宿命が著者を襲ったが、それに耐えることができたのは、彼が自分の生まれについて感謝することができたからである。本書はレッシングが生前出版した最後の書物となった。
〈編集部より〉
最新号『表現者クライテリオン2024年1月号』が好評発売中です。
ぜひお手にお取りください!
購入予約・詳細はこちら
定期購読にお申込みいただくと毎号10%OFF、送料無料で発売日までにお手元に届きます。

執筆者 :
NEW

2026.01.30
NEW

2026.01.30
NEW

2026.01.29

2026.01.23

2026.01.23

2026.01.22
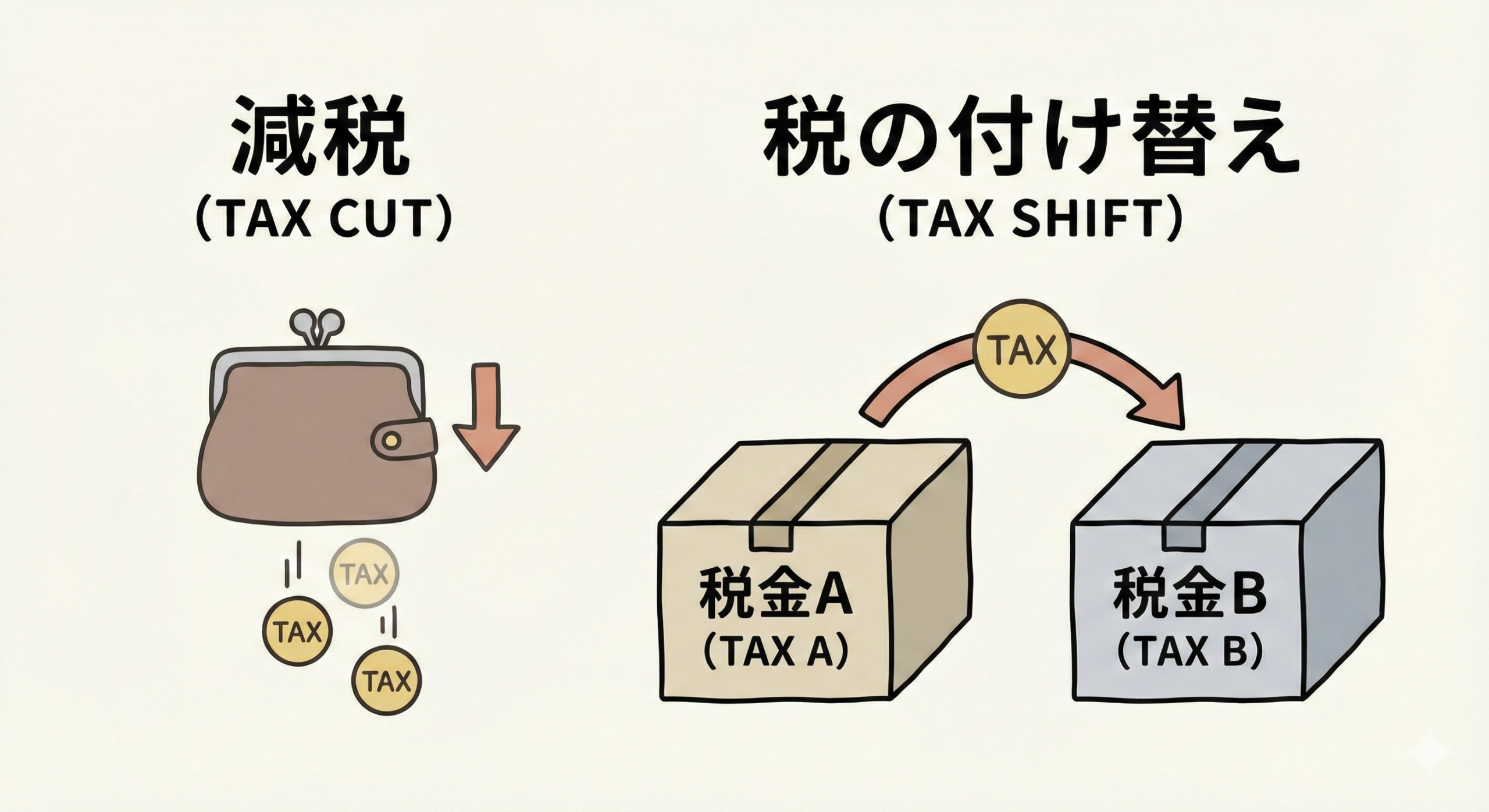
2026.01.18

2026.01.20

2026.01.30

2024.08.11

2026.01.30

2018.04.06

2026.01.22

2018.09.06

2026.01.29

2018.03.02