「無償化」というキーワードは疑った方がいい。「これからは一銭も払わなくていいですよ」と聞こえる。高校授業料無償化は、大阪府や東京都の先行事例で既に多くの疑問の声が上がっていたのに、晴れて全国規模で適用されることになり、高額所得者の保護者も在日外国人の保護者も、公立私立の区別なく、いままで負担していた授業料を「全国の納税者の負担」で賄ってもらえるようになった。高校生活は3年間だが、納税義務はほぼ生涯である。なんだか朝三暮四みたいに誤魔化されたような気がする。
教育費の公的負担が少ないと言われている日本で、教育の財政支出について議論されることは結構なことではある。けれども高校授業料無償化は、「公立も私立もタダにしろ」とか「高所得者にも適用しろ」とか、配分というよりバラマキの話である。国民の税金をつぎ込むというのに、どのような人材育成をしたいのかというグランドデザインが見えない。授業料は、既に都道府県への交付金もある。有権者の財布に阿るよりも、教育の質を上げるために支出してほしい。「質」の問題になると、これは小手先の改革というわけにはいかない。百家争鳴の騒ぎになるだろうし、個別のケースを考えたら「満点」の改革などありえない。まして、維新と自民の御都合で決められるような話ではない。
資源のない日本では、人的資源は極めて重要である。教育は個人の人生に関わる大きな問題であるが、学校教育は、国家が投資すべき「資源開発」でもある。子供の生物学的な発達から見たら、まず幼児・児童教育を充実させて幼少期の健全な知能・身体の発育に投資すべきだろう。初期の段階で躓けば、学校が楽しくなくなる。幼少期の知識の獲得や意味の理解は身体を通じて子供たち自らが獲得するもので、この時期の教育の質は一生を左右する。
義務教育の給食費を無償化し、教員数を確保するといったことに資金を投入する方が、高校授業料無償化よりも緊急性が高いと思う。現在、中学の給食費の無償化が実施されていない自治体もあり、給食費を払えない家庭がある。また、いじめや不登校や自殺者数の増加も大きな懸案事項である。明治初期に日本を訪れた欧米人たちが、日本の子供たちが楽しそうに遊んでいるのを見て「子供の楽園だ」と言っていたのが噓のようだ。小学校や中学校の教員不足で、児童生徒に十分に対応できず、教員の超過勤務で疲弊する現場をなんとかしなくてはならない。足りない教員数を確保するのにも、教員の報酬を改善するのにも、資金が不足している。校舎や設備の老朽化を改善できない学校もある。まず、義務教育の充実が先決だろう。
お金がなくて高校へ行けないというのは、家庭の問題である。高校授業料の問題ではなく、母子家庭や非正規就労や就職氷河期に当たった親世代など、日本の社会や経済の問題である。授業料をタダにする以前に、貧困化した保護者が公立学校の学費を払えるくらいの収入を得られるような経済政策が必要ではないか。
都市と地方の抱える問題は違う。地方では、過疎化で廃校になったり、統廃合で通学範囲に学校がなくなったりする事例があるのに、東京では修学旅行でシンガポールに行く区立小学校がある。教育問題は格差の象徴で、同時に、都市化や一極集中の問題である。格差が意識されるのは、進学と就職だろう。この点では、経済的にも情報面でも選択肢においても、圧倒的に都会が有利である。
社会生活に必要な学習と人格形成のための学習なら、基本的にはどこに居ても学べるはずである。本来、地方の公立学校は「地域社会の核」であり、医療機関や他の行政施設よりも、地域に溶け込んだ精神的支柱としての存在だと言える。ところが、地域によっては、授業料無償化によって近隣都市の私立高校との競争で定員割れや廃校になる可能性が指摘されている。都会の大学が将来の学生数減少の懸念から、地方の学校を系列化して入学者数を確保しようという動きもあるそうだ。大学進学に有利な条件のある私立高校に人気が集まれば、県立高校は定員割れで地盤沈下する。量販店の進出で地元商店街がシャッター街になったように、結局、利益を得るのは私立と塾だろう。
私立学校は、もともとその理念や学風によって選ばれていた。早稲田と慶應義塾の学風の違いは、創立者の建学の精神の違いであるし、ミッション系の学校なども、教育理念や親の価値観や生活スタイルが進学先の選択に影響していた。公立と私立では、学習の進め方や自由度が違う。公立にはない「特別な」教育を望むには、相応の負担が要求されるのは当然である。私立学校の選択をする親には、それだけの覚悟があった。しかし、公立高校の低落と共通試験の実施によって、学校は、中等教育も高等教育も偏差値という一元的な基準で測られるようになった。いまでは、親も子も、学風や理念ではなく偏差値で学校を選ぶ。
公立も私立も平等に無償化するというのは「都市の発想」である。地方では、地域社会に公立高校という物理的基盤を持つことで、多様な人々を結びつけることができる。都会と違って、価値観の同質性や限られた経済的階層が集まる私立高校が地域社会に与える利益は小さい。公立学校の地盤沈下は、地方創生どころか地方消滅を加速させるだろう。
私の情報収集能力が低いせいか、教育制度改革によって教育の質が改善されたという話をあまり聞いたことがない。ゆとり教育とか大学の独立行政法人化とか法科大学院制度とか小学校の英語学習義務化とか、思いつくのは「やってみたら悪手だった」という話ばかりである。だいたい、東京の都立高校の進学実績が低下し私立高校が台頭するようになった原因も、1967年に発足した学校群制度だった。それまで東京大学合格者数のダントツ1位を誇っていた都立日比谷高校が「単独」の希望先として受験できなくなった結果、「同じ学校群内の他校」に割り当てられた優秀な受験者たちが私立高校に流れて、信じられないほど凋落してしまった。日比谷以外にも健闘していた戸山、上野、両国、西などの上位校が、軒並み私立高校の滑り止めになってしまったのだ。それまで都立の上位校を追う立場だった比較的質のいい私立高校の実績が伸びるようになり、受験生の人気が逆転した。
いろいろと教育制度の改革が行われたが、成果があったのだろうか。日本の教育改革の多くは、制度や方法や経済性や平等を考えていて、人材を発掘して育てようという学力獲得のための厳しさには欠ける。そのせいか、世界ランクで日本の大学の学力低下が目立ってきている。近年、世界的に学力重視が強まっていて、この傾向は今後ますます強化されるだろう。この潮流は、日本一国で抵抗しても何とかなる勢いではない。とくにI T化が不可避になっている時代に、「ソフトウェアはI Qビジネスだ」というビル・ゲイツの言葉は、嫌でも現実のものになっている。
この3月25日にアメリカ国家情報長官室が発表した「世界脅威年次報告書」では、A I 分野で中国が2030年までにアメリカを凌駕するだろうという予測が出た。世界のA I トップ研究者の出身国の割合は中国が約半数で、アメリカが約2割、ヨーロッパが約1割である。この分野の研究の上位100大学でも、中国が半分以上の56校を占め、その殆どが40位以上のランクにある。アメリカは第29位にやっと登場し、合計では12校、オーストラリアが9校、イギリス7校、韓国4校、以下、シンガポール、イラン、カナダ等々と続く。100校の中に、勿論、日本の大学はない。高校進学率が95パーセント以上で、そのうち約半数が大学に進学するというのに、この実力結果はあまりにも惨めである。数カ月単位で進化を続ける分野に、石器時代のような硬直した高校の学習指導要領では太刀打ちできない。
おそらくこの傾向は、A I 分野に限ったことではなく、殆どの分野に共通しているのではないかと思う。進学率は高く小学校から塾通いをしているのに、何故こんなに実力がないのだろう。世界比較は英語で行われるから、言語の壁があることは確かだろう。しかし、中国は英語圏ではない。語学は言い訳にはならないということだ。
日本では、教育問題は受験制度や授業料ばかりが議論されるが、学校でどのような人材を育てるのかという問題意識がないのだと思う。生徒や学生だけでなく、教育関係者も行政も経済界も同様で、人材育成に対する社会全体の意識の低さである。
実現不可能だと重々承知の上で言わせて頂くと、日本の学校の「履修主義」に原因があるのではないだろうか。高校へ進学した95パーセント以上の同世代の生徒たちが、ほぼ全員卒業できるということがおかしいと、誰も思っていない。小学校から高校まで「落第」や学業不振による「退学」はなく、出席日数があれば大抵卒業できる。つまり、何も修得していなくても「免許皆伝」の証書を貰えるのである。大学はもっと深刻で、殆どの私立大学では授業に出席して単位を取得していれば卒業できるが、社会に通用しない粗悪品を量産しているだけである。大卒のギグワーカーが大勢いるのは教育の歩留まりの悪さを表わしていて、時代や運の悪さだけではないだろう。
嘗て、小学校の運動会で、全員が手を繋いで一緒にゴールするという「かけっこ」があった。平等がいいことで、差がつくのはよくない、足の速い子が1等賞なのは「いいこと」ではなく、負けた子が「かわいそう」だから、競走はよくないということだった。こんな日本で「落第」を容認したら、蜂の巣をつついたような騒ぎになるだろう。
医師国家試験や司法試験や公認会計士試験に落ちたら、資格は貰えない。実力が伴わなければ、致命的な「害」を引き起こすからだ。学校の勉強がまるでわからなくても「卒業資格」が貰えるのは、「命にかかわる害」がないと思っているからだろう。入学時の選別で通過すれば、そのあとは勉強しなくてもいいのが日本の学校である。勉強するために学校へ行くのではなく、「卒業証書」をもらえばそれでいい。
履修さえすればいいという態度では「緊張感」は生まれない。日本人に緊張感がないのは、「命を賭ける」必要がない社会だからだろう。いまの日本社会は、日常から「死」を覆い隠す。本気で「生きる」ことを考えるのは「死」に直面したときである。
緊張感や危機感がないのは「兵役」がないからではないだろうか。戦前は、国を守るのは国民だった。戦地で敵を前にして「履修しましたが、修得していません」では通用しない。戦場では、兵士一人の無知やミスが部隊を全滅させかねない。実力の保証のない兵士は信用できない。だから、履修しても成果が保証できない者は「落第」させられた。戦後は、「アメリカが守ってくれるから、できなくてもいい」ことになった。
卒業時に実力の保証を要求されるのならば、自分に合った仕事で勝負できるように、中学以降は多様な進路を用意することだ。普通高校だけが評価されるのではなく、農業高校や工業高校などを充実させればいい。しかし、普通高校や大学で、単位さえ取れば進級できる現状を打破するのは難しそうだ。教員の負担も増すし、今後の少子化で入学者数の減少を考えると、「厳しさ」は「お客さま獲得」に不利な条件になるからだ。むしろ、「お土産付き(十万円の商品券?)」で卒業させるような私立大学も出て来そうである。
緊張感や危機感を欠いたままでは、日本の大学は高等教育機関としての国際基準に届かない。どこかで社会全体が意識改革をしなければ、日本の衰退は加速するだろう。教育の質も意識もそのままで、無償化さえすればいいというのでは絶望的である。
トランプ大統領は、日本から米軍を撤去させると言い出すかもしれない。それは、やっと巡って来た「日本が独立する」チャンスであるが、80年という年月は日本人から「危機感」を失わせてしまった。「(黒人奴隷は)服従し、従うことしか学んだことがないのである」「すなわち隷属は彼を愚かにし、自由は身を破滅させる」と、トクヴィルがアメリカの解放奴隷が陥った精神的劣化を指摘したように、日本人はその自覚がないほど隷属に慣れきってしまった。何の「覚悟」もないまま同盟を破棄されれば、中・ロの餌食になりかねない。そのときになって慌てても遅い。高校授業料無償化では、危機意識は生まれない。
『学力喪失——認知科学による回復への道筋』今井むつみ著 /岩波新書 2024
アメリカを圧倒する中国AIトップ人材 米「世界脅威年次報告書」 | 中国問題グローバル研究所
『アメリカのデモクラシー』第1巻 トクヴィル著/ 岩波文庫
4月の第1回は、特別ゲストとして高市早苗議員をお呼びすることとなりました!
表現者塾は『表現者クライテリオン』の編集委員や執筆者、各分野の研究者などを講師に迎え、物事を考え、行動する際の「クライテリオン=(規準)」をより一層深く探求する塾(セミナー)です。
◯毎月第2土曜日 17時から約2時間の講義 ※4月だけ異なります。
◯場所:新宿駅から徒歩圏内
◯お得な動画会員(ライブ配信・アーカイブ視聴)あり
◯期間:2025年4月〜2026年3月
◯毎回先生方を囲んでの懇親会あり
執筆者 :
CATEGORY :
NEW
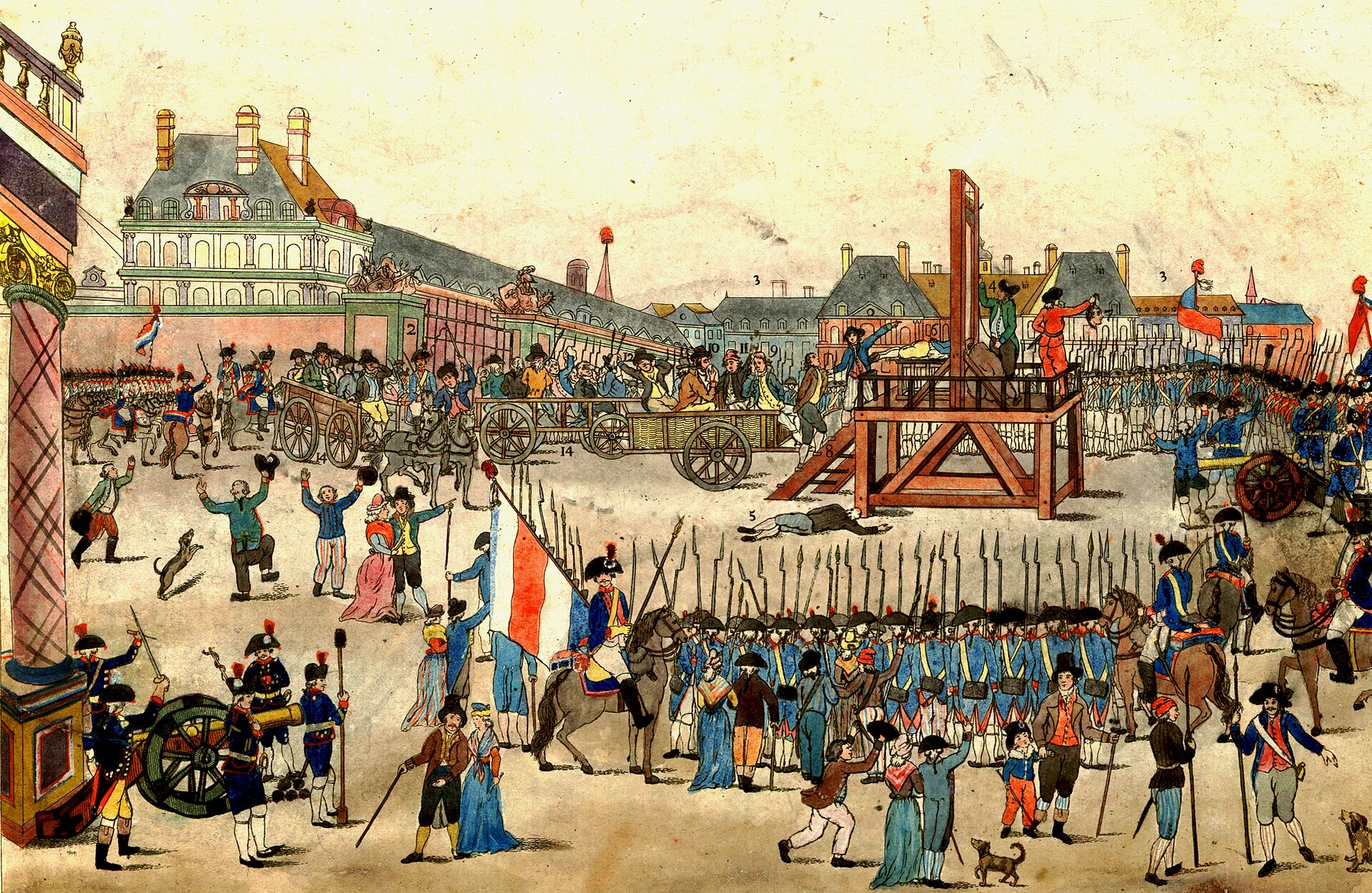
2026.02.20
NEW

2026.02.19
NEW

2026.02.18
NEW
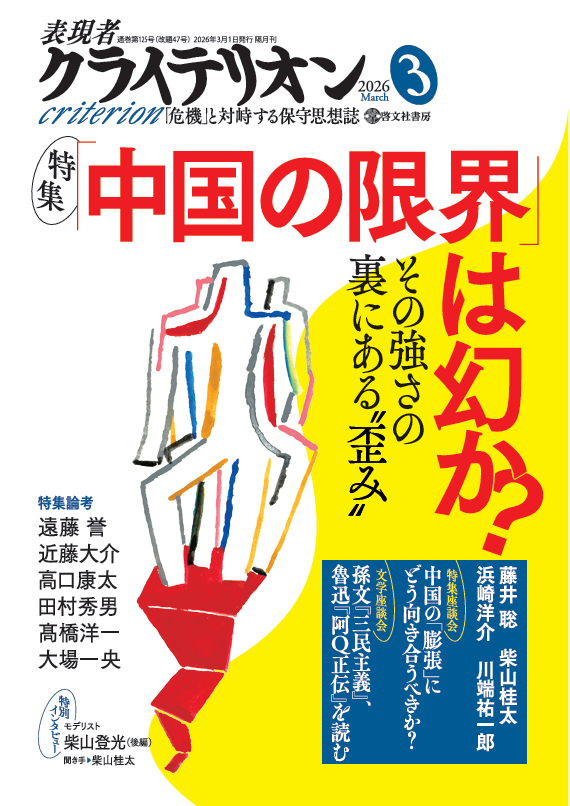
2026.02.16
NEW
.png)
2026.02.16
NEW
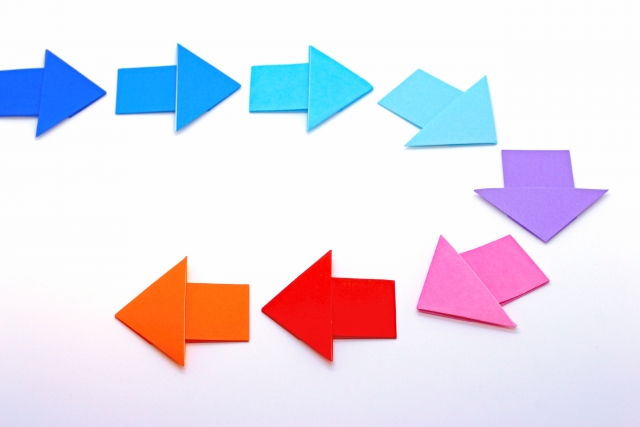
2026.02.16

2026.02.19
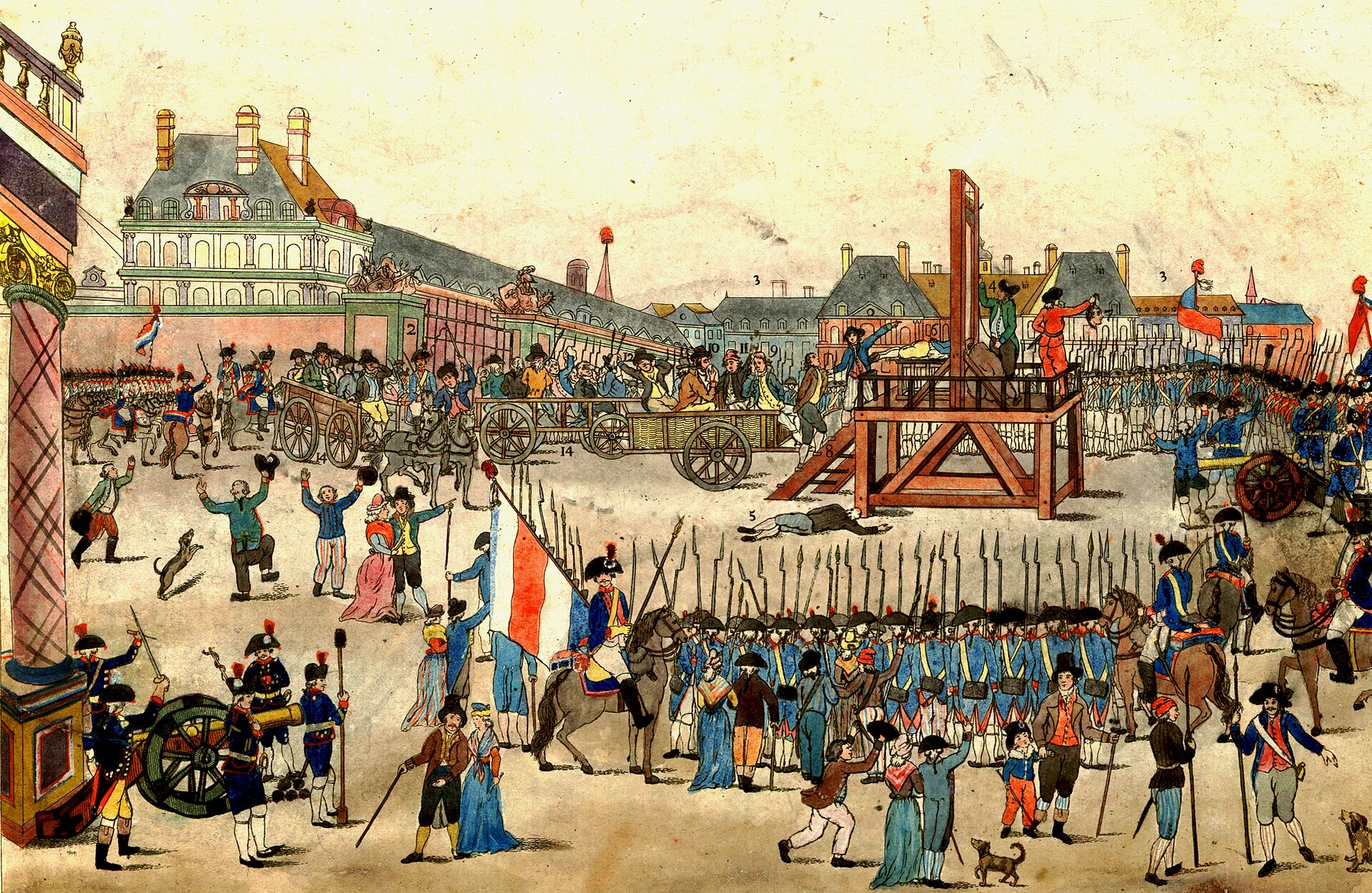
2026.02.20
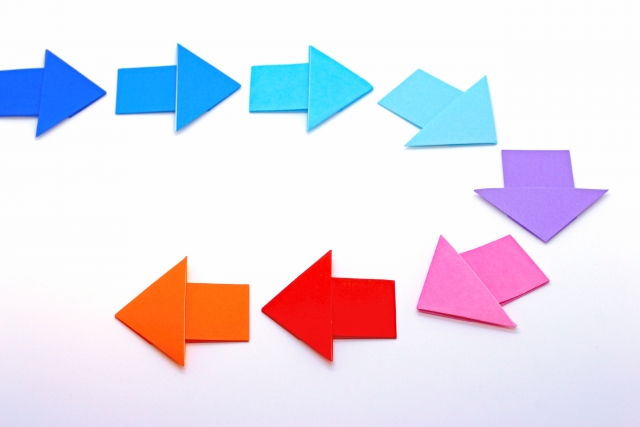
2026.02.16
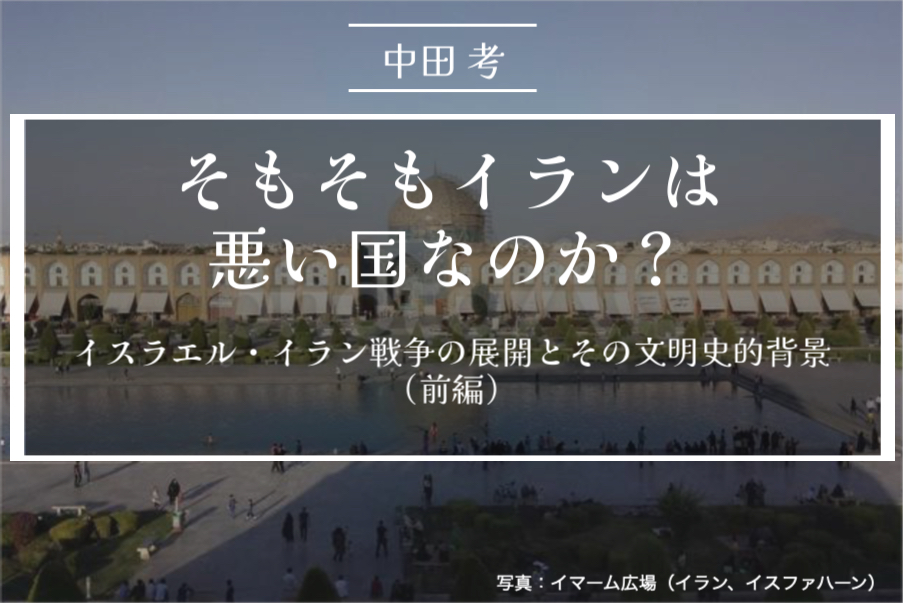
2025.06.24
.png)
2026.02.16

2026.02.11
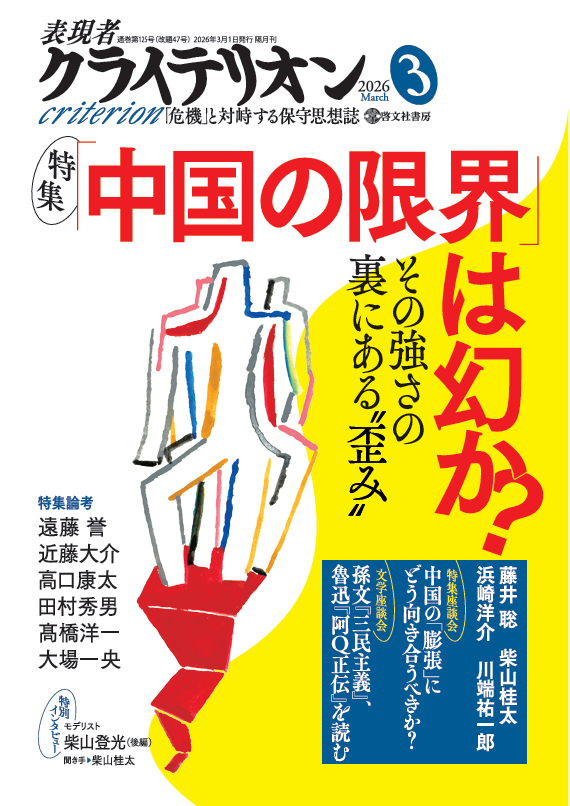
2026.02.16

2026.02.18

2026.02.12
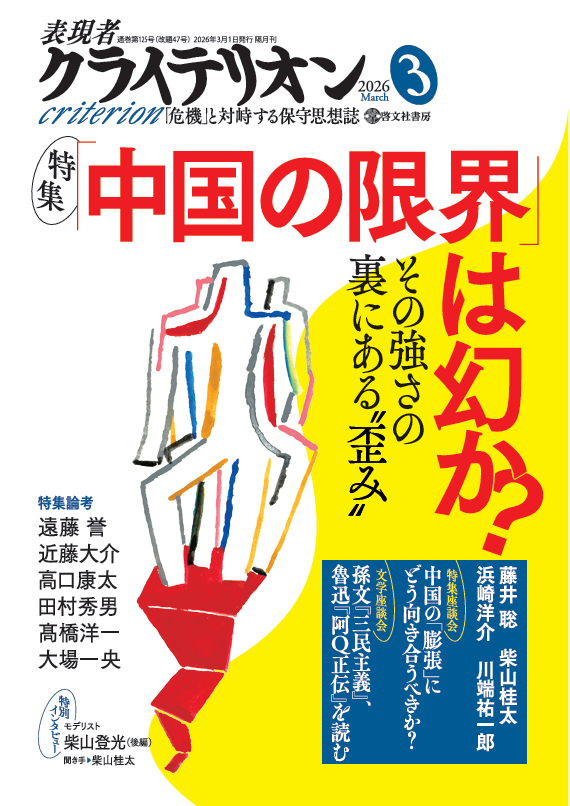
2026.02.16