日本人の幸福度が低いと言われて久しい。国際的な調査では、どんな調査方法でも低い順位に居座って指定席のようになっている。特に若者の幸福感が低いのは、現在の満足度だけでなく将来の展望も明るくないということだろう。幸福感というのは感覚だから、データとして表示するには何を基準にするかが難しい。それでも、どんな風に調べてみてもここまで幸福度が低ければ、大抵の日本人が自分の人生を幸せだとは思っていないことは確かなようだ。
随分前のことだが、チャールズ・マレーがアメリカ人の幸福度を調査したのは、アメリカの分断が誰の目にも顕著になってきたころで、分断が居住エリアを境に明確になっていて、地域差は住民たちの幸福度を反映していることを確かめた。彼は、いくつかのサンプル地域を選び、それぞれの地域の多くの住民アンケート結果の分析から、「家族」「仕事」「信仰」「コミュニティ」の4つの領域が幸福度に関わっていると結論付けた。(『Coming Apart』2012 / 邦訳『階級「断絶」社会アメリカ——新上流と新下流の出現』)
チャールズ・マレーが調査したのは、調査対象の地域住民の現在の職業や学歴や所得、彼らが育った環境(親や隣人の職業・居住地の街や都市の人口規模・親の学歴など)である。アンケートはダイレクトな質問形式ではなく、「近隣50世帯で、大学教育を受けていない人が過半数を占めるような場所で1年以上暮らしたことがあるか」「工場の中の作業現場に入ったことがあるか」「エイボンの商品を買ったことがあるか」、いくつかのテレビ番組を挙げて「これらの中によく見ているものはあるか」「高校時代に何かの代表になったことがあるか」などの間接的な問いから、彼らの現在と過去の「社会経済的背景」をあぶり出し、さらにそれぞれのグループについての特徴を分析している。そして、彼らに現在の幸福度を尋ね、先の4つの幸福度の条件が現状とどう関わっているのかを明らかにした。
J.Dヴァンスの『ヒルビリー・エレジー』を読んだときの既視感は、このマレーの調査結果だった。彼が育ったアメリカの貧困地域であるオハイオ州ミドルタウンやケンタッキー州のアパラチア山麓の街の住民たちが置かれた状況には、幸福感に関わるこの4つの要素がすべて欠落していたのである。マレーの調査対象となった時代は、ヴァンスの少年期から青年期と重なっている。
マレーが着目した4つの領域のなかでも「家族」というのは重要な要素だが、特に「結婚」を重視している。「よい結婚ほど効果的に幸福をもたらすものはないし、逆に悪い結婚ほど効果的に不幸をもたらすものはない」という結論は、あまりにも単純で当然すぎると自分でも言っているが、事実、結婚が幸せだと感じている人の58パーセントが、人生についても「とても幸せ」だと答えた。これは、配偶者との形式で見ても同様な結果であった。例えば、調査時点で一人暮らしの人々を、それぞれ「別居、離婚、死別、未婚」の結果としての独居と捉えると、配偶者に先立たれて一人になった人は、「人生」について最も幸福度が高い。次に「離婚」「別居」と続くのは、婚姻関係を続けるのに問題があれば幸福度が低くなることを示す。そして、最も幸福度が低いのが誰とも関係を持たない「未婚」であった。
「子供」は幸福の源であるが、同時に苦労の種でもある。また、別居や離婚で一人親が育てる場合や未婚による片親、若すぎる結婚での育児問題、家庭の経済問題なども関係していて、「結婚」ほど幸福度との明確な因果関係を示せないという。
「仕事」に関しては興味深い結果がある。「全体として、自分の仕事についてどの程度満足しているか」という設問に対して、専業主婦が家庭の仕事を「ジョブ job」ではなく「家庭を育む」という意味での積極的な家事と捉えている場合に最も幸福度が高く、意外なことに「有給雇用者」よりも「とても幸せ」に感じていたのである。仕事と所得の相関関係は複雑で、まったく関係がないわけではないが、「満足度」に関係するのは「やり甲斐」や「評価」のほうが大きい。無給の家事を仕事とする専業主婦の幸福感が高いのは、「よい結婚」の場合で、そこには、やり甲斐や家族の評価を伴う充実感があるからだろう。
「信仰」については、日本の社会では関わり方が異なるので単純に一般化できないが、アメリカでは頻繁に礼拝に参加し、信仰をもっている人ほど幸福感が高かった。宗教というよりも、そこから得られる「倫理観」や「生き方の確信」が関係しているのだろう。『ヒルビリー・エレジー』のなかで、ヴァンスのまわりには信仰心をもつ親族がいて、特に祖母の強い信仰心と明確な倫理観が、貧困やドラッグや絶望死が蔓延する環境での過酷な少年時代の支えになったと言っている。
「コミュニティ」については、何らかのグループに参加していることを尋ね、「幸福度」を調査している。地域活動やスポーツ団体、ボランティア活動、慈善寄付活動、交友関係などの社会的交流を行っている人ほど「幸せ」だと感じている。何かに参加していなくても、政治や国の問題に関心を持つことは、社会や共同体の一員であるという自覚があるということでもあり、この領域に含まれる。自分以外の他者にも関心を持ち、社会的信頼を得ていることが幸福度に関係する。
これらのどの領域も「幸福度」に大きな影響をもっているが、とくに「結婚」にはマイナス面よりプラス面が多く、リスクを伴っても報われる場合が多いという。社会的信頼にも関係していて、「幸福感」との相関が最も高いようだ。これらの領域の満足度は、明確に地図上の分布に現れる。マレーの調査対象の人々の職業・学歴・所得・育った環境が恵まれた地域であれば「幸福度」は高く、所得の低い労働者階級の居住地では家庭崩壊やドラッグや福祉に頼る家族も多く、「幸福度」も低い。「幸福度」の地域差は相当に大きいという結果だった。
恵まれない人々を救おうとして、福祉という考えが生まれた。ガザのような飢餓状態を救うには食糧援助が必要だし、災害で住居を失った人々に住む場所を提供することも必要だ。極限状態でのセーフティーネットは必要である。しかし、日常的な社会生活では、人々のニーズは単純に分解できない。食や住を獲得する「手段」は、それ以外のニーズと関係をもっている。福祉という手段によって食と住を得ても、そこには自尊心が伴わない。人間には自尊心がある。そして、自尊心は自力で獲得するものだからだ。
自尊心や親しい人間関係や自己実現は、自ら選んで行動し葛藤を乗り越えて獲得するものである。人生を切り開く自由とそれに伴う責任が、結果における達成感によって満足感や幸福感に繋がる。マレーが示した4つの領域は、どれも「責任」と切り離せない。男が家庭を持つのは、妻と子供の人生に責任を持つことである。母親が子育ての苦労をすることは、子供に対する責任である。近代社会では、それすら難しくなっている。家計を満たしていれば、何をしても(または、何をしなくても)いいという父親も、子育てを託児所に預けて社会的自己実現を目指したり、家計の不足を補うために仕事に出る母親も、所得の低い家庭で福祉に頼る親たちも、誰にも咎められないかわりに、人生の深い満足は得られない。家族には、家族でなければできない大切な務めがあり、その責任を果たしていない(あるいは、果たしたくても果たせない)からだ。
『ヒルビリー・エレジー』で、貧困地域に配られるフード・スタンプが本当の意味で貧しい者たちを助けることにならないと述べているのは、与えられた食べ物には獲得した食べ物にある「報酬の味」が欠けているからである。エリートたちは、人々に不足しているものを分類して、それを与えれば解決すると考える。分割されたニーズに対する支援には、達成感や生き甲斐が振るい落とされている。
家族・仕事・コミュニティ・信仰が、どれも弱体化しているのは、そこから「責任」が免除されているからだ。単純労働であっても、仕事に精を出して家族を養う男たちの誇りを、貨幣価値に換算する学歴社会は認めなくなった。専業主婦が家族に持っていた責任感も軽視されている。生活の雑事は際限がなく、誰かがそれを引き受けなければ家庭はうまくいかない。家事が「負担」と捉えられるようになって軽んじられれば、主婦は社会進出を制限された男女差別の被害者的存在になり、女たちも誇りを奪われる。
マレーは、彼が見た貧しい労働者の居住地域で何が必要なのかを次のように述べている。「必要なのは政府援助ではない。彼らが守ろうとしている価値観や道徳規範を認めること、それでいいのだと後押ししてくれる力である。」 子供時代のJ.D.ヴァンスが、祖母に言って欲しかったのは、「何が正しいのか」の答えであり、「お前の信仰は正しい」という保証だった。その確信があれば、行動に責任を持てる。
マレーは、政府の福祉、LGBTや移民に対する「普遍的優しさ」は、「いい子の掟」であって、個人的判断を否定してしまう欠陥があるという。「普遍的優しさ」は明確な行動規範ではない漠然とした命令で、支配的少数派にしか通用しない仲間うちの価値観であり、「社会の基準」になるものではないとも述べている。マレーは明言を避けているが、「普遍的優しさ」による「いい子」としての行動がエリートの偽善だと感じているのだろう。
プロテスタントの国のアメリカで、最近カトリック信者が増加しているらしい。人々の心が共同体に回帰している気配がある。個人主義が行きつくところまで行ってしまって、帰る場所が欲しくなった人が出て来たのかもしれない。疲れた彼らを迎えてくれるのは家族であり教会であると気づいた人々なのだろう。
日本の若者たちを、マレーが示した4つの領域から眺めてみると、幸福度が低いのも頷ける。婚姻率が低下し、特に男性の生涯未婚者が増加している。彼らには、自分が帰る場所がない。帰る場所も責任を果たす場所も作ることができなかった人たちである。生産性向上のための効率化で正規雇用から零れ落ち、学歴の壁に突き当たり、低賃金のまま、気がつくと年金受給年齢が近づいて、納付を滞納したままで愕然とする者が、幸福感を持てるわけがない。婚姻率の低下は世界的な傾向で、グローバル経済による専門化や学位取得の必要性など高学歴化が関係していて、国内だけで解決できる問題ではないようだ。
いまでは、労働は休暇のためにある。労働時間は短いほうがいいこととされ、労働は自己実現の手段ではなくなり、快適に過ごす余暇に価値が移行した。「残業はお断り」が正しい雇用関係で、仕事に責任を取る者はいない。「働き方改革」は、一部のブラック企業や非常識な上司には必要な措置だが、やる気のある労働者の働く意欲を削ぐことにも繋がり、企業にも労働者にも責任を負わせないシステムと言える。若者は、働くことに意味を見つけられなくなっていないだろうか。
人手不足といっても、いずれは人口動態に左右されないAIが、休暇も要らず不平不満を言わない労働力となって、人間の地位を脅かし、労働者の賃金低下が進むだろう。世界の動きは目まぐるしく、求められるスキルは刻々と変化している。引っ張りだこのIT技術者でさえ、進歩のスピードが飛躍的に速い分野では使い捨てになるかもしれない。
誰にも必要とされないという感覚、責任を期待されない仕事や人間関係、それらはバラバラにアトム化した個人が陥る深い孤独である。家庭にも仕事にもコミュニティにも、どの領域にも責任をもつほどの関わりがない人々が、オープンAIのチャットGPTを話し相手にするようになった。生身の人間と違って、疲れることもなく、鬱陶しがることもなく、いつまでも愚痴や悩みを聞いて寄り添ってくれる相手は、カウンセラー以上の友になる。自分を傷つけることを言わない心地よい対話が、現実の友達以上の共感を示してくれる。メンタルヘルス市場は、人間のカウンセラーが不要になるかもしれない。
生身の人間との関係は、いつもうまくいくとは限らない。寧ろ、不本意な摩擦や誤解で傷つくことのほうが多い。思い通りにいかない「場」だからこそ、責任が問われる。子供が最初に思い通りにいかない現実を知るのは、動作によってである。体をうまく動かすことによって、思い通りの行動ができる。高いところに手が届かない、お箸をうまく使えない、跳び箱が飛べない、楽器をうまく弾けない。現実と最初に向き合うのは「身体」だ。幸福感を掴むには、まず、身体を使うといい。出来なかったことが出来るようになれば、達成感が得られる。達成感を得るための忍耐力を知る。子供の外遊びが大切なのは、身体を使うからだ。身体は脳化への抵抗力である。
アトム化されていく社会に必要なものも、抵抗力である。個人の自由のために脱ぎ捨ててしまった古臭い時代に共有されていた常識の中に、社会の抵抗力が潜んでいるのではないだろうか。日本のデジタル化の遅れは、案外、グローバリゼーションによるアトム化への抵抗力なのかもしれない。家族には家族でなければできない務めがある。友達でなければできない付き合いがある。国民にしかない使命がある。それを自覚することが、不幸への抵抗力にならないだろうか。
2025年世界幸福度ランキング 日本は55位、前回から4ランク下がる トップはフィンランド8年連続 | nippon.com
日本の幸福度は22カ国で最下位、若者は世界で低く 米大学など調査 – 日本経済新聞
『階級「断絶」社会アメリカ——新上流と新下流の出現』チャールズ・マレー著 橘明美訳/草思社 2013
『ヒルビリー・エレジー』J.D.ヴァンス著 関根光宏・山田文訳 /光文社未来ライブラリー 2022
『大格差——機械の知能は仕事と所得をどう変えるか』タイラー・コーエン著 若田部昌澄訳 /NTT出版 2014
『新しい封建制がやってくる——グローバル中流階級への警告』ジョエル・コトキン著 寺下滝郎訳 中野剛志解説 /東洋経済新報社 2023
橋本由美
<編集部からのお知らせ1>
10/16発売の最新号『表現者クライテリオン2025年11月号 この国は「移民」に耐えられるのか?ー脱・移民の思想』。
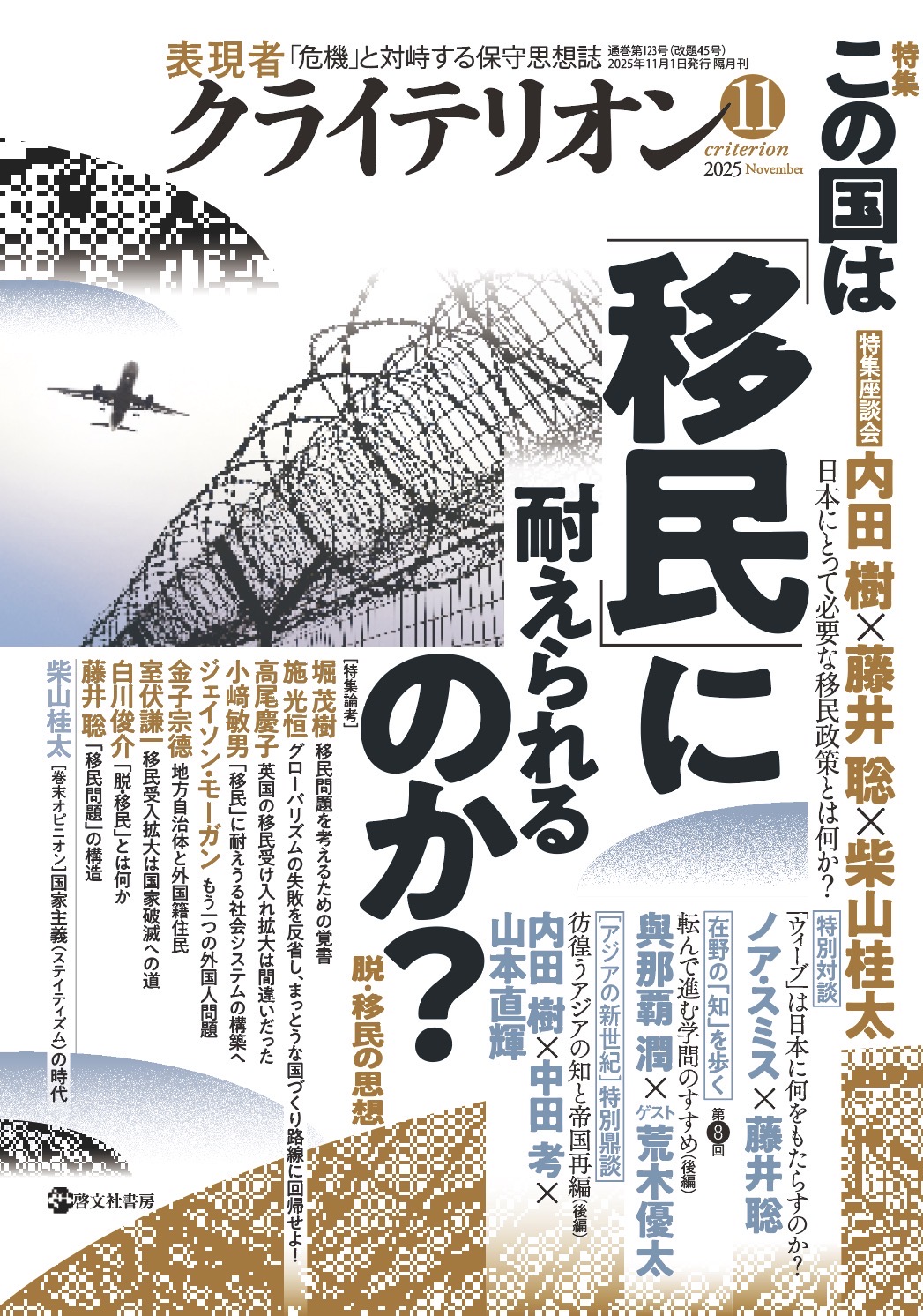
Screenshot
<編集部からのお知らせ2>
クライテリオン叢書第5弾、『敗戦とトラウマ 次こそ「正しく」戦えるか』、書店・Amazon等で公表発売中!
|
|
敗戦とトラウマ |
執筆者 :
CATEGORY :
NEW

2026.01.23
NEW

2026.01.23
NEW

2026.01.22
NEW

2026.01.20
NEW

2026.01.18

2026.01.16

2026.01.18
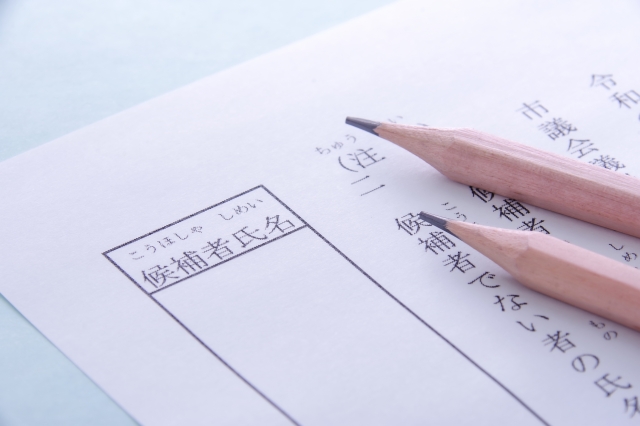
2026.01.13

2026.01.20

2026.01.16

2024.08.11

2026.01.22

2026.01.15

2018.09.06

2026.01.23

2026.01.23