「平成」が終わり、いよいよ「令和」の時代が始まろうとしています。
これに合わせて、本誌でも「『令和』への建白書 新時代を切り拓く国家戦略の提言」と題した特集を組み、「『令和八策』建白のクライテリオン『実践・漸進・発展・有機体・長期展望』という五つの柱」と名付けた座談会と共に、著者それぞれの立場から、国防、政治、経済、憲法、文化、外交など、およそ20の分野についての「建白書」を提示ています。
詳しい内容については16日発売の本誌に譲ることにしますが、今回は、それに因んで、「令和」の出典である『万葉集』について、少し考えてみたいと思います。
というのも、この日本最古の歌集である『万葉集』は、後で見るように、日本の危機に際して、繰り返し参照されてきたという歴史があるからです。
まず、『万葉集』を手に取ったとき、誰もが驚くのは、歌人の出身階層の多様さ、その地域の多彩さ、そこに収められた歌の時代の幅広さでしょう。そこには、およそ400年間に渡って各階層で詠まれてきた歌――伝承的な古代歌謡から、天皇や貴族の歌、下級役人や防人、漁民・農民などの歌まで――が、約4500首も収められています。
なるほど、それもあって『万葉集』には「素朴」な歌が多い。たとえば、後に「たをやめぶり」(手弱女振り―女性的で優美・繊細)と評される『古今集』などに比べれば、『万葉集』の歌は、たしかに「ますらをぶり」(益荒男振り―男性的でおおらか・素朴)と評される直接的な表現が多くみらます(その内実から言えば、男・女の比喩は正確ではありませんが、『古今集』『新古今集』と比べて、『万葉集』が技巧的でないことは明らかです)。
実際、この度の「令和」の出典である「梅花の歌三十二首」の序文―「初春の令月にして気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披(ひら)き、蘭(らん)は珮(はい)後の香を薫(かお)す」にしても、そこから感じられるのも、まさに「素朴」といっていい「自然」でしょう。
ただし、ここで見落としてならないのが、この「素朴」な「梅花の歌三十二首」が、当時、九州大宰府長官だった大伴旅人(665~731年)が、友人たちを招いて、月の下で詠もうとした宴の歌だったということです。つまり、「梅花の歌三十二首」とは、貴族たちが宮廷のなかで個人的に詠んだ歌と言うよりは、対外的脅威を知る大宰府の役人たち(将軍である大伴旅人を中心としたサークル)が集って詠んだ歌だということです。
そして、おそらく、この大陸文化に対する緊張こそ、あの『万葉集』独特の調子――共同体と個、公と私の「あいだ」にある感覚――を可能にしているものなのでしょう。
実際、『万葉集』第一期の主な歌は、「大化の改新」(645年・最初の元号)の頃を中心に集められていますが、それは同時に、日本が統一国家を目ざして歩きはじめた時期でもありました(「日本」という国号自体が、「大化の改新」以後につくられたものです)。
それを促したのは、言うまでもなく、7世紀初めに登場してくる唐ですが、その対外的脅威に直面した「日本」(中臣鎌足と中大兄皇子)が、百済派の蘇我蝦夷・入鹿親子(大臣専制主義)を排して、大陸に負けない中央集権国家を創ろうとして起こしたクーデター、それが「大化の改新」だったのです(実際、「大化の改新」から15年後の660年に、唐は朝鮮の百済を征服することになりますが、救援を求められた中大兄皇子は「白村江の戦い」に兵を送り、それに敗れてから後は、国土防衛に集中することになります)。
その後「日本」は、「壬申の乱」(671年)に勝利した天武天皇(大海人皇子)の下で、天皇中心の律令制国家の建設(藤原京の建設)を加速していくことになりますが、この「統一国家の確立」、「中央集権国家の実現」という大きな時代の流れのなかで、『古事記』や『日本書記』の編纂、そして『万葉集』の編纂も進んでいくことになります。
そしてここに、日本における最初の「政治と文学」の問題が現れることになったのでした。
中央集権化とは、すなわち「中国化(唐化)」であり、その限りで、国家の公文書(歴史)は全て漢文(意味)で記されることになります。が、おそらく、そのことが逆に、当時の日本人に、「政治」では汲み取れない自分たちの土着の生活感情(カミガミの古言の振り―日本語の振り)を保存しておきたいという欲望を喚起することになったのです。
実際、「壬申の乱」を起こした天皇や貴族たちが詠むのは、その権力闘争が嘘であるかのように繊細な「相聞歌」(恋愛を中心とした贈答歌)であり、また、その乱世が信じられないほどに厳かな「挽歌」(死の哀悼歌)なのでした。そこにあるのは、漢文では表すことが難しい日本人の細やかな生活感情であり、また、その〈長い息=なげき〉だったのです。
この「政治」によって抑圧され、排除された感情を、再び「文学」によって取り戻そうとする姿勢は、その後の日本文学を貫く根本性格を形作っていきますが(そこが、政治への関心を歌う唐詩とは明らかに違います)、しかし、それゆえに『万葉集』は、その後の日本人が自分自身のアイデンティティを確かめるための道として――たとえば、儒教イデオロギー(朱子学)に抵抗した「国学」の根拠(契沖―賀茂真淵―本居宣長)として、あるいは日本の近代短歌を支える拠点(正岡子規―斎藤茂吉)として、また、戦争遂行の精神的支え(保田與重郎―蓮田善明)として――繰り返し参照されることになっていくのでした。
なるほど、それが、強張った「皇国イデオロギー」と、全く無縁だったと言えば嘘になるでしょう。が、そこに共通して見られる欲望は、「外」から持ち込まれた「物差し」によって、自分たちの「ありのまま」の感情が侵されそうになった時の抵抗の感覚です。
この抵抗の在り方について、たとえば保田與重郎は次のように語っていました。
「國學の人々は、長流、契沖を先頭として、隠遁詩人の志をうけついだ人々であつた。政治上の革新論を云ふまへに、道のべのかりそめ言にも、わが國ぶりの道の現れをきき、己の道心をたしかめて、わびるやうな人々であつた。(中略)この詩人の生き方を云ひ、創造の據所を云ふ美の学問は、わが国学以外に、西歐の美學文藝學にはなかつたのである。神の歴史観を失つた彼らには、さうした思想の生まれる道はなく、彼らの考へた體系上の神話も、つひに一個の要請された人智にすぎなかった。」『万葉集の精神』「序」昭和17年
つまり、『万葉集』とは、常に「政治上の革新論」とは別の位相で、「わが國ぶりの道の現れ」を、もっと言えば、日本人における「神の歴史観」を担ってきたのだということです。
果たして、この度の「令和」の典拠に出てくる「梅」とは、「厳しい寒さが残る早春に、桜に先駆けて凛と咲く花」との意味ですが、まさに私たちは、グローバリズム(ネオリベラリズム)という厳しい「冬」に覆われていた平成時代を乗り越えて、再び「梅花」を咲かせることができるのか。自然な「我が國ぶりの道」を見出すことができるのか。
「令和」の新時代を迎えるに当たって、私が思うのは、まず、この一事にほかなりません。大阪ダブル選での維新の勝利など、依然として厳しい状況は続きますが、諦めずに歩いて行きたいと思います。今年度も、どうぞ、『表現者クライテリオン』をよろしくお願いします!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メルマガのバックナンバーはこちらで閲覧頂けます。
https://the-criterion.jp/category/mail-magazine/
雑誌『表現者criterion』の定期購読はこちらから。
https://the-criterion.jp/subscription/
その他『表現者criterion』関連の情報は、下記サイトにて。
https://the-criterion.jp
ご感想&質問&お問合せ(『表現者クライテリオン』編集部)
info@the-criterion.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
執筆者 :
CATEGORY :
NEW

2026.01.30
NEW

2026.01.30
NEW

2026.01.29

2026.01.23

2026.01.23

2026.01.22
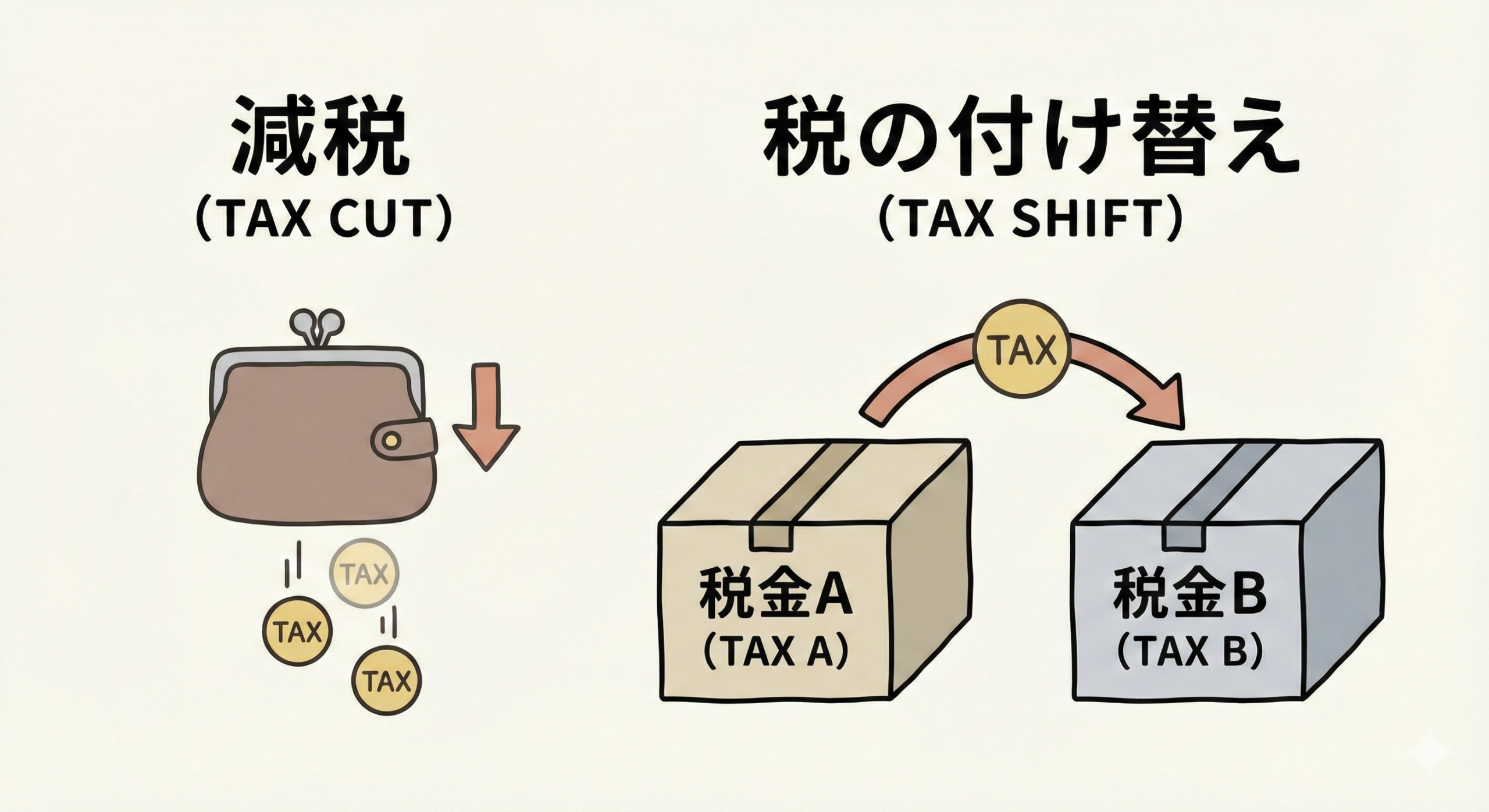
2026.01.18

2026.01.20

2024.08.11

2026.01.22

2026.01.23

2026.01.23

2018.09.06

2026.01.13

2025.04.01

2018.04.06