本日は3月30日開催の「表現者クライテリオン沖縄シンポジウム〜戦後80年、沖縄から考える対米独立への道〜」
の開催を前に7年前の2018年の沖縄シンポジウムに関する記事をお送りいたします。
シンポジウムの詳細・お申し込みはこちらから
現地に赴くということは、その土地が持つ時間と空間のなかに、この身を浸しに行くということである。今回の沖縄・与那国島訪問ほど、そのことを感じたことはない。
沖縄戦の激戦地である摩文仁の丘で過去を想い、普天間基地を眺めながら現在を感じ、沖縄シンポジウムや懇親会で交わされた言葉から現地の方々の感情に触れ、また、与那国の地元議員や自衛隊との交流を通じて、「国防」の最前線がどのような緊張を孕んでいるのかを知ることができた。その一つ一つを、編集委員及び関係スタッフと二泊三日で議論できたという時間は、現在の日本及び日本人を考える上で、この上もなく貴重な体験となった。
なかでも印象的だったのは、やはり、本土とは違う沖縄独特の「温度」である。もちろん、その「温度」だけを強調しすぎてしまえば、それは「沖縄独立論」などの極論(空想)を引き寄せてしまいかねない。が、だからこそ、現に今、私たちが生きている「日本のナショナリズム」において考えるべきなのは、本土と沖縄との差異と軋轢を「抑制し、収縮させ、静めること、そして折り合わせること」(M・オークショット「保守的であるということ」)ではないのだろうか。そして、その「折り合い」の方途のなかに、この国のあるべき姿を見出すことではないのか。「折り合わせること」への願いなしに、国民の「自由」などあり得ない。
沖縄に限らず、「お国自慢」の土着性(パトリオティズム)は、今でも日本各地にその独特の性格を刻んでいる(会津は薩長が嫌いで、京都は東京を下に見、大阪は京都を毛嫌うなど)。が、沖縄のそれが、普通一般の郷土愛と違うのは、その土着性自体が、国家との抜き差しならぬ関係のなかに醸成され、また、それが今に続く歴史となっているからである。
さすがに、琉球王国を幕府との冊封体制に組み入れた「島津侵入事件」(一六〇九年)は措くにしても、その琉球王国を否定して沖縄県を設置した明治の「琉球処分」(明治十二年)という国家的事件から、沖縄の歴史は始まっていた。さらに、大東亜戦争(太平洋戦争)末期、圧倒的物量を誇るアメリカ軍相手に三カ月を戦い抜き、当時の人口の二五%~三〇%が犠牲になったと言われる苛酷な沖縄戦や、その後のアメリカ軍による「軍事植民地化」(基地と軍人最優先の支配体制)なども、沖縄が国家の歴史と切り結んだ独特の記憶だと言えるだろう。
しかも戦後は、そこに日本国家との感情的縺れが複雑に加わってくる。サンフランシスコ条約調印時に本土から切り離された(見捨てられた)という思いに加え、復帰四十六年を経ても、なお果たされない「核抜き・本土並み」(佐藤栄作首相)という約束。いや、米軍基地に関してだけ言えば、「本土並み」どころか、むしろ復帰後(一九七二年~)の方が、その負担率は上がっているのだ。一九七二年以降、本土では六割以上縮小されてきた米軍基地は、沖縄では二割程度の縮小に留まっており、復帰前、五九%(沖縄)対四一%(本土)だった基地負担率は、今では七一%(沖縄)対二九%(本土)になっている──しかも、国土面積の〇・六%の沖縄に、米軍基地の七一%が集中している――と言うのだから、その基地を必要としてしまう沖縄の地政学的条件を考慮しても、政府に対する沖縄の不満が溜まらないわけがないではないか。
くわえて、その不満の燻りに火をつけたのが、米兵三人による少女暴行事件(一九九五年)だった。日米地位協定を盾に容疑者の身柄引き渡しを拒否した米軍と、その決定を追認することしかできなかった外務省に対して、沖縄県民は「米軍基地の整理縮小と日米地位協定の見直し」を求めて、八万五千人の県民総決起大会を開催することになる。基地行政の悪化を恐れた政府は、慌てて普天間基地の全面返還を米軍と合意するものの、その発表後に、その移転先が同じ沖縄県内の名護市であることが明らかにされるに及んで、移設自体が沖縄の基地負担軽減に繋がらないのではないのかという疑念が囁かれ出す。が、それを取り返しのつかないまでに炎上させてしまったのが、当時の鳩山由紀夫首相の「(移設先は)最低でも県外」発言だった。その後、鳩山氏は発言を撤回したものの、すでに後の祭りだった。この〈言葉の耐えられない軽さ〉は、基地問題を収拾がつかないレベルにまで悪化させてしまうのである。
しかし、だからこそ「ナショナリズム」において、筋を通した冷静な言葉を、沖縄県から立ち上げる必要があるのではないだろうか。中央政府への不信に根差した感情論──「沖縄独立論」や「絶対平和主義」──に身を任せるのではなくて、逆に、戦後の不条理を一身に引き受けてきた沖縄こそが、むしろ先頭に立って、〈九条─安保〉体制に雁字搦めになった日本政府を問い質し、「対米従属」の卑屈さのなかに沈んで行く日本政府に対して、「日本よ、国家意識を取り戻せ」と言うべきではなかろうか。つまり、沖縄の内からこそ、「九条改正」(決して「加憲」ではない!)の議論を立ち上げ、日本政府の顔を、アメリカから国民の方へと向け直す「ナショナリズム」の声を上げるべきではないのかということである。
なるほど、それが困難な道のりであることは百も承知である。が、少なくとも、それだけが、基地問題において最も筋の通った言葉を用意することができるのもまた確かだろう。その意味で言えば、辺野古=基地移設問題を、「親米保守の現実主義」と、「反米左派の理想主義」の対立に矮小化してはなるまい。基地問題の総体を、今後どのようにして米国からの「自立」を勝ち取っていくかを問う「日本のナショナリズム」の問題として捉え直すこと。それだけが、辺野古問題を、単なる〈左右の対立=政治現象〉に堕していくことを防ぐ道であり、また、私たち国民の「折り合い」と、それによる「自由」を可能にしていく道でもある。
沖縄シンポジウムの翌日、自衛隊の与那国駐屯地を訪れた私は、そこでの地元住民と自衛隊との交流を見るにつけ、沖縄本島にある基地が、「米軍基地」ではなく、「自衛隊基地」であったなら、と思わざるを得なかった。一歩一歩、歩いていくしかない。
<編集部よりお知らせ>
日時:3月30日14時~
第1部 14時00分〜15時00分
ポスト2025の世界と沖縄—第二次トランプ政権がもたらす試練
第2部 15時10分〜16時30分(質疑・応答含)
戦後80年の検証 ー 沖縄に見る対米関係の実像
懇親会 17時00分〜19時30分
会場:沖縄県市町村自治会館
(那覇空港から車で10分、バスターミナルから徒歩3分、旭橋駅から通路直通、徒歩5分)
会費:一般、3000円、塾生・サポーター:2000円
懇親会:5000円
<お知らせ2>
表現者塾は『表現者クライテリオン』の編集委員や執筆者、各分野の研究者などを講師に迎え、物事を考え、行動する際の「クライテリオン=(規準)」をより一層深く探求する塾(セミナー)です。
◯毎月第2土曜日 17時から約2時間の講義
◯場所:新宿駅から徒歩圏内
◯期間:2025年4月〜2026年3月
◯毎回先生方を囲んでの懇親会あり
◯ライブ配信、アーカイブ視聴あり
NEW

2025.06.27
NEW

2025.06.26
NEW

2025.06.24
NEW
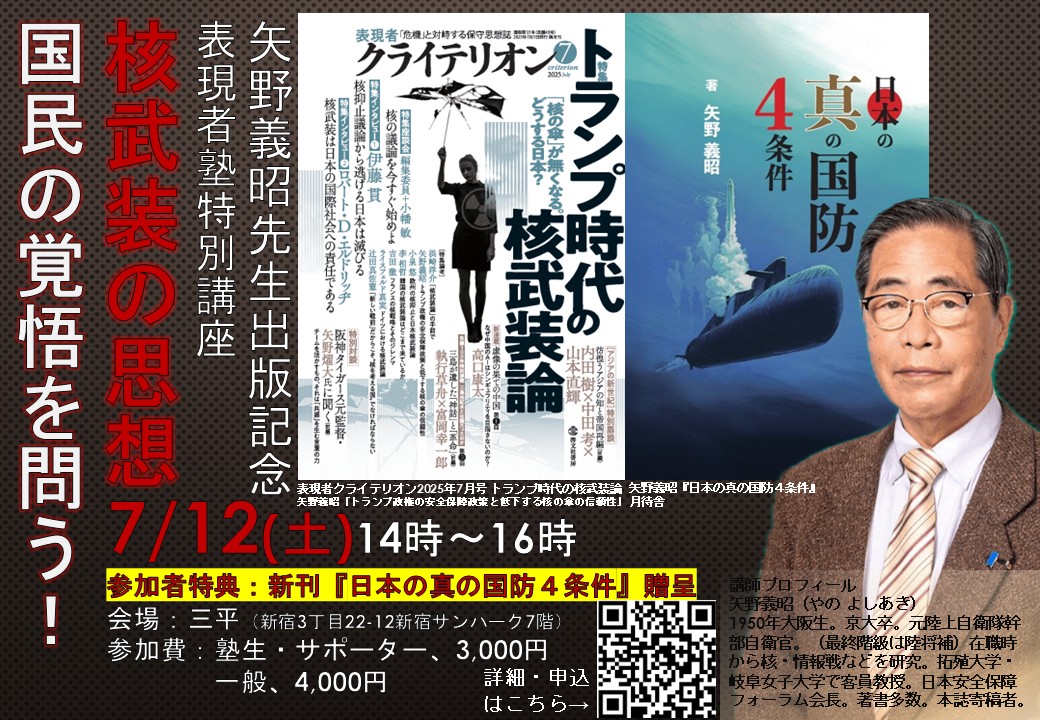
2025.06.24
NEW
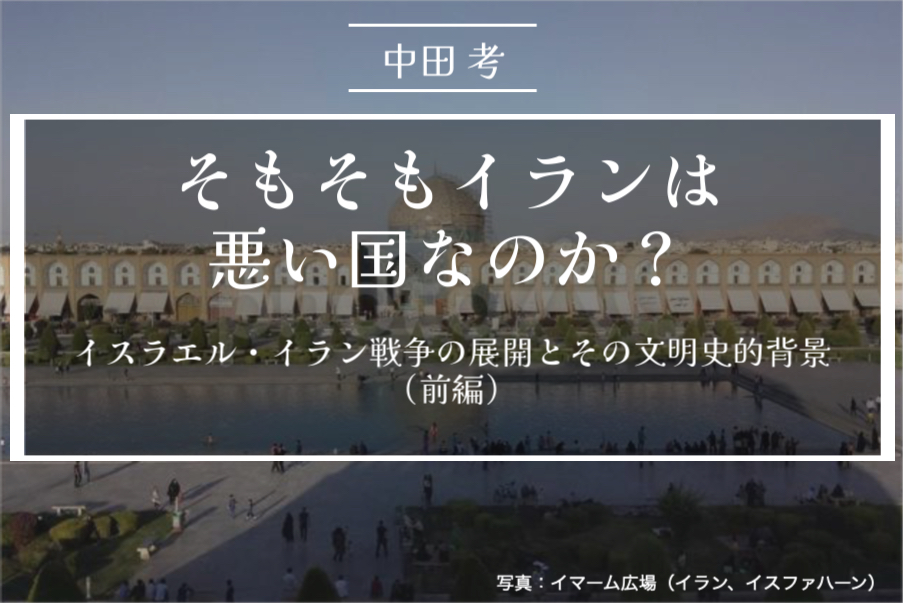
2025.06.24
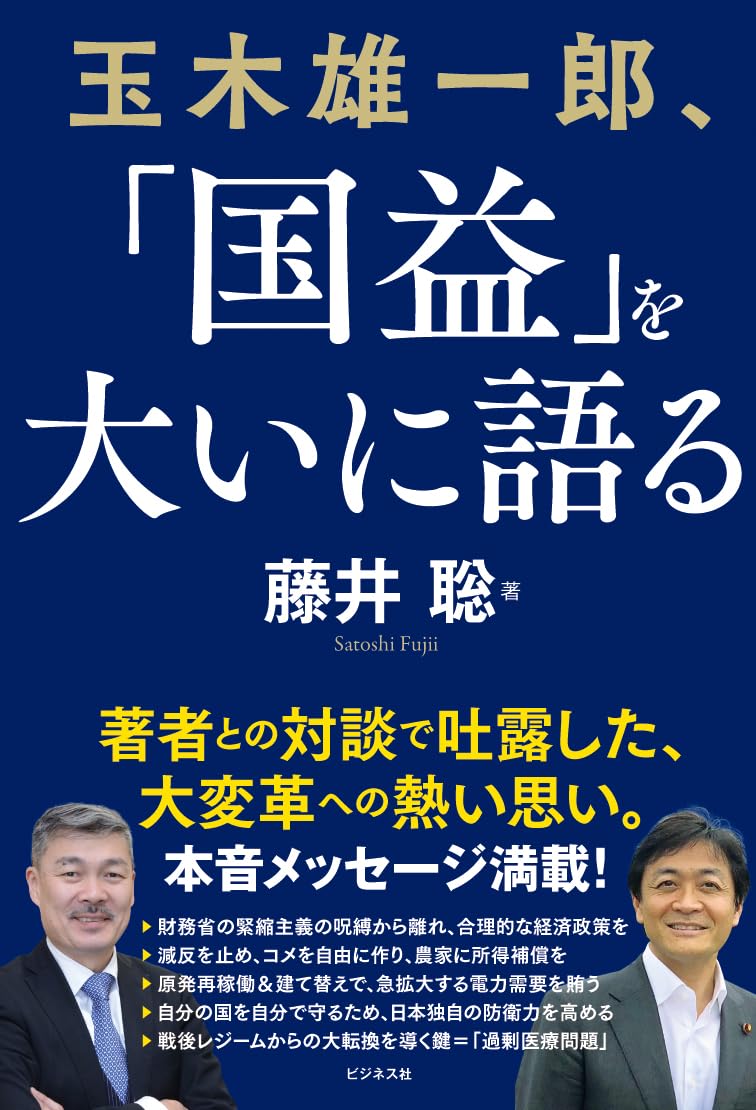
2025.06.21
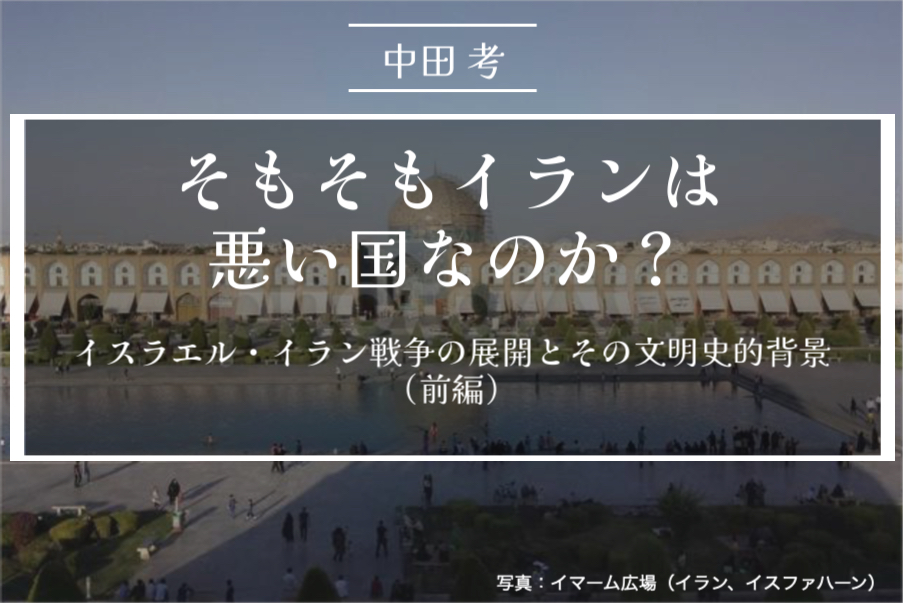
2025.06.24

2025.06.26

2024.08.11

2025.06.27
.jpg)
2025.06.03

2024.07.13

2025.06.20

2025.06.24
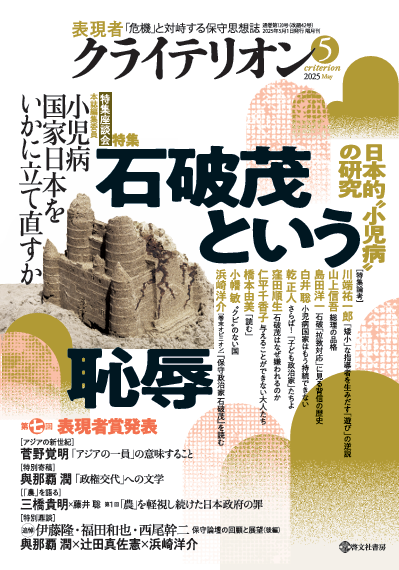
2025.04.21
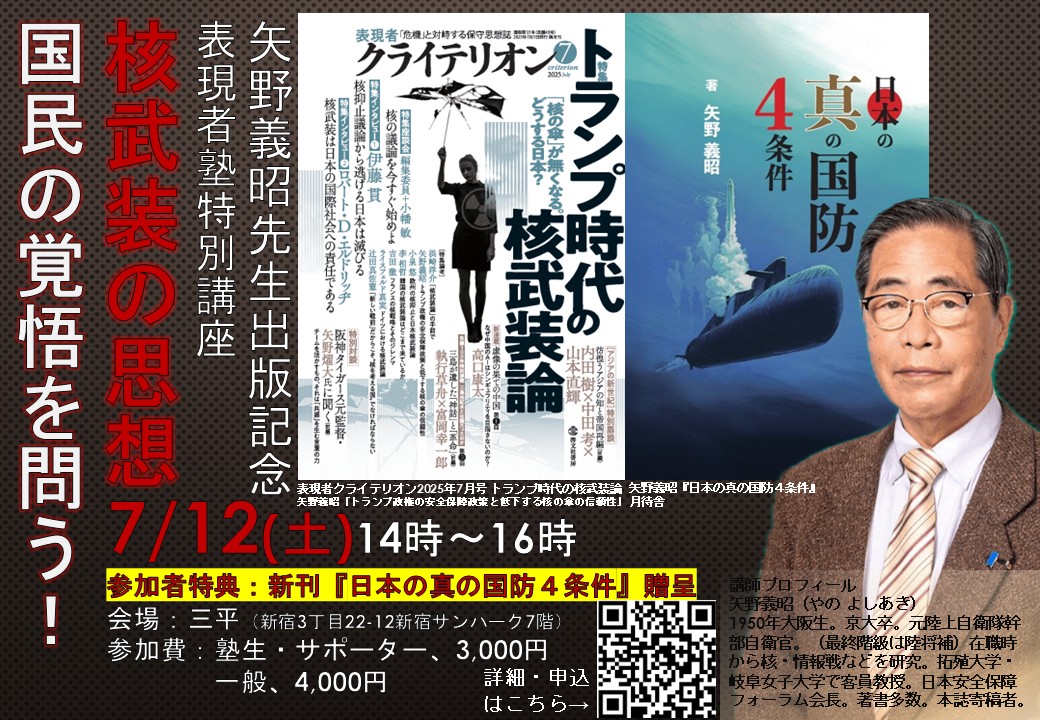
2025.06.24