こんにちは。表現者クライテリオン編集部です。
本日発売となりました!最新号『表現者クライテリオン2023年11月号』の特集タイトルは、
本日は巻頭コラム「鳥兜」を公開いたします。ご一読いただき、是非本誌をお手にお取りください。
購入予約・詳細はこちら
定期購読のお申し込みはこちら(10%OFF、送料無料)
--------------------------
フィリップ・アリエスは、『死と歴史西欧中世から現代へ』(みすず書房)のなかで、西洋人における「死」に対する態度の変化を、大きく三つの時代に分けて描き出している。
中世から十八世紀までに経験された「死」は、個人(私)のものというよりは、社会(公)のものであり、それは教会の儀式によって包まれ、その傍には必ず親戚や友人、隣人たちが立ち会っていたという。そのために「死」は、常に自分自身の身近にあって、なじみ深いものであり、さらには、人々の「生」への情熱を掻き立てるものだったと言われる。
しかし、十八世紀末に一つの切断が起こる。「死」が、なじみ深いものから「断絶の観念」へと変化するのである。アリエスは、その変化の背景について詳しく論じてはいないが、常識的に考えれば、それには絶対王政の崩壊と国民国家概念の誕生、そして「神の死」が大きく預かっていたはずだ。実際、この頃から天国を信じられなくなった芸術家たちは、己の個人的想像力を介して、エロティックな幻想を「死」に投影しはじめるのである。
そして、大きな切断が再び二十世紀にやって来る。「死」は、恥ずべきもの、あるいはタブーとして蓋をされねばならない対象となってしまうのだ。「死」に纏わりつく諸観念(老病死の苦しみ)が、周囲にあまりに激しい感情(悲しみや嫌悪感)を引き起こしてしまうがゆえに、「死」は隠されるべき禁忌となってしまうのである。その背景には、もちろん産業技術社会の発展及び大衆消費社会の拡大によって導かれた、「人生はつねに幸せなものであるか、つねに幸せなものであるかのように見えねばならぬ」という観念があった。
が、ここで注意すべきなのは、「死」を押し隠すことにおいて、現代医療が一役買っているというアリエスの指摘である。「死」を司る主体は、地域から家族へ(十九世紀)、そして、医師や看護スタッフへ(二十世紀)という形で次第に変移していくことになるが、それと共に「死」は、ますます人の目につきにくいものになっていくのだった。
しかし、それは裏を返せば、産業技術社会が進歩すればするほど、私たちの「自然」が、私たちの眼から覆い隠されていったということを意味している。
かつて三島由紀夫は、近代の「文化主義」を定義して、「文化をその血みどろの母体や生殖行為から切り離して、何か喜ばしい人間主義的成果によって判断しようとする一傾向である。そこでは、文化は何か無害で美しい、人類の共有財産であり、プラザの噴水の如きものである」(「文化防衛論」)と書いたが、まさしく、我々の「生と死」を孕んだ「血みどろの母体」は、それへの感情を浄化するための文化・伝統によって包まれるのではなく、今や、「プラザの噴水」のごとき近代技術によって押し隠され、消毒され、ときに完全に消されてしまうのである。
そして、その事実は、時代が進むに従って、私たちが私たち自身の「運命」と向き合えなくなりつつあることをも意味している。トルストイは『イワン・イリイチの死』で、死に行く裁判官に「間違っている。おまえがこれまで生きがいとし、今でもそれによって生きているもの──それは全部、お前の目から生と死を隠す噓であり、まやかしだ」と言わせていたが、それはそのまま「運命」を抑圧してきた近代人の内なる呻きでもあった。
「過剰医療」批判、それは単なる医療批判ではない。産業技術社会の「まやかし」を排し、自分の「運命」をこの手に取り戻すこと、そんな人間の倫理が賭けられているのである。
執筆者 :
NEW

2026.02.13
NEW

2026.02.12
NEW

2026.02.11
NEW

2026.02.09
NEW

2026.02.07

2026.02.06

2026.02.09

2026.02.06

2026.02.07

2026.02.12

2026.02.11

2026.02.05

2024.08.11

2026.01.20
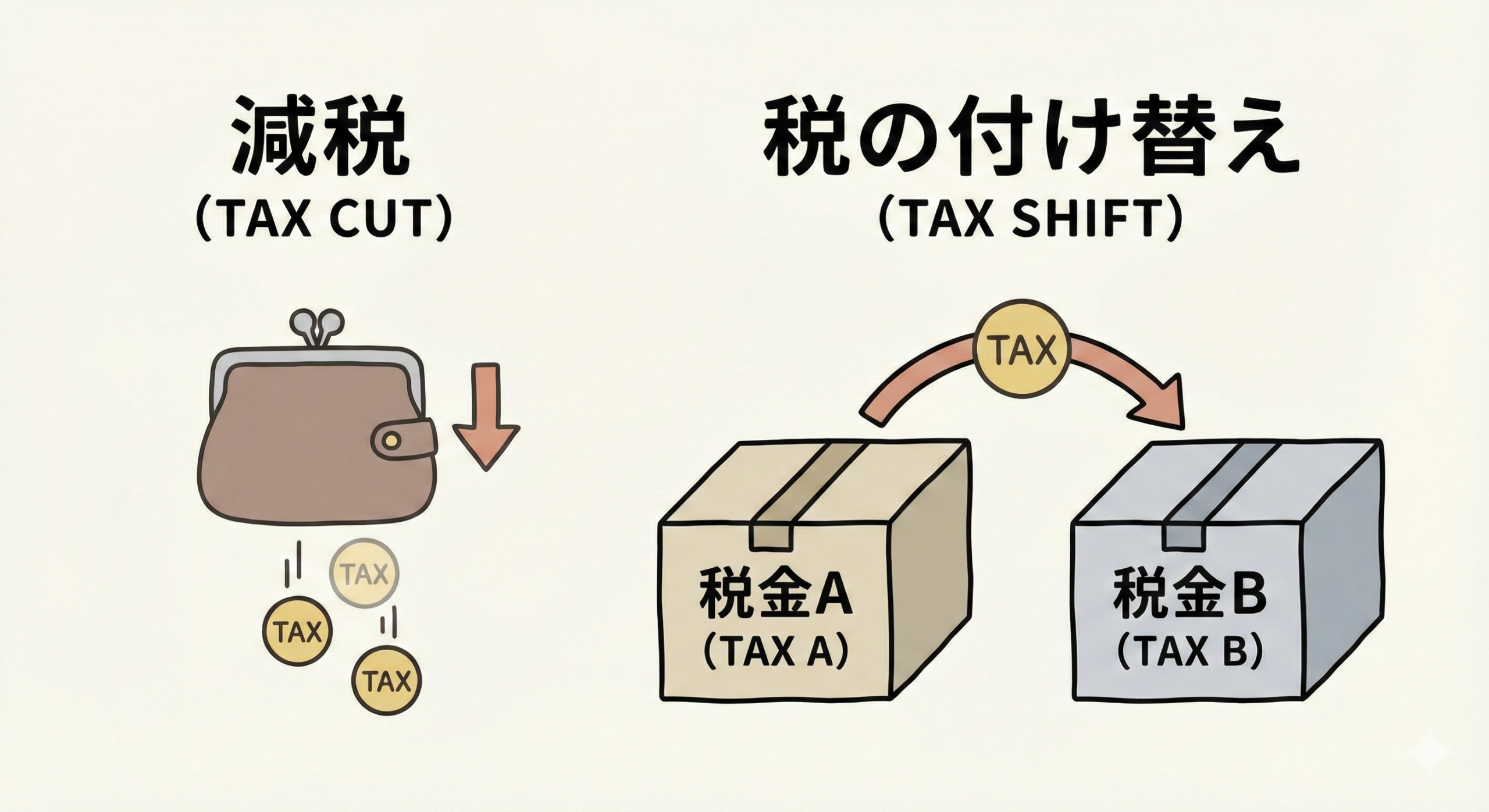
2026.01.18

2018.09.06