本日は6月14日発売、『表現者クライテリオン2024年7月号 [特集]自民党は保守政党なのか?』より、特集座談会①「日本において「保守政治」は可能か?」から一部をお送りいたします。
本書のご予約はこちらから!
よりお得な年間購読(クライテリオン・サポーターズ)のお申し込みはこちらから!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本の政界に「保守」は存在しない?
藤井 今回は同志社大学教授で政治学者の吉田徹先生と、京都精華大学准教授で同じく政治学者の白井聡先生をお招きし、「自民党は保守政党なのか?」という切り口で議論したいと思います。自由民主党は下野した時に「自由民主党は保守政党である」と綱領で宣言していますが、少なくとも五五年体制の頃の自由民主党は、「保守政党」という自己規定を特にしていません。かつ、英語では“liberal Democratic Party”というように、どちらかというとリベラル政党であり、社会党や共産党が革新政党という位置づけであったわけですから、五五年体制の頃から自民党がエドマンド・バークが言うような「保守」の政党であったと規定することは基本的にできないと言うこともできます。
本誌は「『危機』と対峙する保守思想誌」と銘打っており、日本には「保守政治」というものが必要であるという立場をとっています。現在の自民党は、本来の「保守思想」や「保守政治」からかけ離れた新自由主義に親和的であるという大きな特徴があり、同時に、単なる現実主義という範囲を大きく逸脱した「対米従属」路線の影響が強く、これで果たして「保守政党」なのかという問題があります。
一方で、二十世紀が終わった頃から「保守」ブームが起こっています。かつては朝日新聞を中心とした「左翼」や「革新」と呼ばれる勢力が非常に大きな力を持っていましたが、現在の世論はそういうものに対するシンパシーを徐々に失っています。その一方で、「安倍一強」が続いていた中で、日本会議に影響を受けたような、あるいは「ネトウヨ」と呼ばれるようなある種のファッションとしての「保守」が拡大してきています。
言論界でも『Hanada』や『WiLL』といった雑誌が存在感を放っており、その影響を受けて日本保守党が出てきたり、維新の会も「保守」を意識して政治を展開していたり、さらに最近では参政党も登場しています。いわば、ある種の大衆的な気分を反映するような格好で「保守」を名乗る政党が続々と出てきているということです。
このように、思想的に非常に混乱を極めた状況の中で、日本の政治が必ずしも適正と言えない方向で歪んできています。そこで「真の保守」を主張する勢力が必要ではないかという問題意識のもと、日本の政治を適正化していく方途はないだろうかという趣旨で今回の特集を企画した次第です。
とはいえ、いろいろなお立場があるでしょうし、「リベラル」や「保守」の定義だけでもかなりのディスカッションが必要になると思いますから、一面においては政治思想的な概念を整理しつつ、もう一面では現状の政治の混乱や腐敗とどう対峙していくべきなのかというプラグマティックな議論もできればと思います。
まずは吉田先生と白井先生にお話しいただき、編集委員からも一通りお話しいただいた上でディスカッションを深めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
吉田 よろしくお願いします。慶應義塾大学で計量政治学をやっている谷口尚子さんの研究に基づけば、先進国の保守政党の公約集(マニフェスト)を比較してみると、自民党の掲げている政策は他国の保守政党と比べてウイングがかなり広いという特徴があります。そういった意味で、自民党は鵺的な存在なのだろうと思います。
一方で、自民党が保守政党とされてきたのは、ひとえに冷戦構造の中で「保守」と「リベラル」が同一視されていたためです。社会主義と共産主義との対比でもって、リベラルの側が保守政党だと冷戦構造の中では理解されてきました。例えば九〇年代初頭には、安倍晋三が「リベラルの会」というものを作ってそこのメンバーになっています。今から見ると冗談みたいな話ですが(笑)。それはなぜかというと、「リベラル」は「保守」であり、「保守」は「リベラル」であるという冷戦時代の構図を引きずっていたためです。
しかし、冷戦が終わって大きなシャッフルが起こります。九〇年代半ば以降、社会主義が通用しなくなったことを背景に徐々に政治的な再定義がなされ、旧社会党を含めた非自民の側が「リベラル」という錦の御旗を掲げるようになったわけです。それがポスト冷戦、あるいはポスト五五年体制以降続いてきた構図だと思います。
以上の観点からすると、日本にはそもそも保守主義ないし保守政党があったのかという疑問が浮かび上がります。自由民主党が守るべき何かがあるとして、それは何なのだろうかという問題です。例えばイギリスでは王党派やトーリー(保守党)、ドイツでは世俗主義に対するキリスト教民主主義を掲げたキリスト教民主同盟などの系譜がありますが、これらの保守政党と日本の自民党は大きく違う存在です。宇野重規さんが『日本の保守とリベラル』(中公選書)で指摘しているように、そもそも日本の保守は思想的には明治時代に依拠しています。ところが、「明治レジーム」がそもそも明治維新によって作られたものなので、過去からの断絶によって成り立っているわけです。
一方で、宇野さんは「リベラル」に関しても、本当の意味での個人主義的なものは日本に存在せず、よって日本において保守とリベラルという対立軸を求めること自体に無理があるのではないかと指摘されています。それが自由民主党を保守政党として定義できるかどうかという難しさにつながっているのだと思います。
藤井 冒頭の話にも通じますが、日本の政界にはもともと「保守」と呼ばれるものが存在せず、戦後レジームの中で何となく「保守」と名乗り出したところに混乱を生み出す根本的な構造があったということですね。白井さんはいかがでしょうか。
「親米保守」から「売国利権保守」へ
白井 この座談会のコンセプトにも関わってくると思うのですが、いわゆる「保守論壇」と自民党との距離をどのようにとりながら言論活動をしていくのかということを僕からはお聞きしたいと思います。というのは、自民党は保守を名乗っているけれども、そもそも「親米保守」として出発しているわけです。この「親米保守」という名前に締まりがないですよね(笑)。保守なら愛国精神に満ちているはずなのに、なぜか接頭辞に「親米」と付いてしまうという、気の抜けたコーラみたいなものとして始まっているわけです。
でも、冷戦時代にはソ連のコミュニズムの脅威があり、それに飲み込まれないためにはアメリカと手を組むしかないんだという一応の言い訳ができました。アメリカは原爆を落とし、日本人を大量に殺して許せないが、そこはグッとこらえてアメリカにくっついていくんだという理屈だったわけです。ところが、ソ連が崩壊したことによってこの理屈が成り立たなくなります。
そこで、自民党が標榜している「保守」なるものの再定義が必要だったはずなのですが、そんなことはせずに結局は与党としての権力を保守しているわけです。そして、権力を保守するために一番合理的な方法がグローバリズム、新自由主義であると考え、国民の生活や国益を顧みず、むしろそれを売り払ってそのマージンを自分のポケットに突っ込んでいる。要するに、「親米保守」から「売国利権保守」へ、さらには単なる犯罪者集団へと変貌したというのが、この三十年間の自民党の姿にほかならないと思います。
だから、あんなものを「保守」と呼んだら「保守論壇」的にはいかんのではないかということは、最初に問題提起として申し上げたいところです。
藤井 白井さんがおっしゃったことに反対する本誌編集委員はいないのではないでしょうか。そもそも今回の「自民党は保守なのか?」というテーマの中には、「自民党は保守政党にあらず」というメッセージも濃密に込められています。
その一方で、自民党が下野していた時には自民党内に「保守思想勉強会」が作られ、西部邁を毎回講師として呼んで「保守思想とは何か」を勉強していました。僕も何度か講師として参加したこともありましたが、この勉強会の会長は、参議院の幹事長をやっておられた脇雅史氏で、今回の特集にも寄稿いただいている西田昌司参議院議員はじめ、多くの自民党議員が毎回参加しておられました。そんな勉強会を作られたくらいですから、脇さんや西田さんの保守思想についての認識は至って正当なものであったと思います。
しかしながら、その西田さんが今回の特集で書かれているのは、自民党は単に「戦後レジーム」を保守しているだけであって、本来の「保守」とは似ても似つかないものだということ。同様のことは、今回特集でお話をお聞きした伊吹文明氏も、かねてから様々なところで、バークやハイエクを引用しながら発言しておられます。
そういう意味で、自民党の中には「保守」というものを、表層的にではなく、あくまでも思想的な理解も含めた上でその重要性を語っている方々が自民党の中の趨勢ではないにせよ、一部に存在しているわけです。そういった人々の思想が自民党の中で拡大するべきだという思いも、本誌で今回の特集を企画する一つの重要な動機だったというわけです。
ヨーロッパの保守主義に見られる三つの軸
柴山 日本に保守主義はあるかという問題ですが、教科書的には「吉田ドクトリン」の吉田茂に始まり、石橋湛山、池田勇人に続く宏池会の路線と、そこから枝分かれした田中派も含めたものが戦後の自民党の保守本流ということになるのでしょう。でも、そこで何を保守しようとしてきたのか、よく分からないところがあります。大きく見れば、戦後憲法を守り、その体制下で経済成長を実現して国民の生活水準を上げていく、ということなのでしょうが、そこに「保守主義」と呼べるほどの強い理念があったのかと言われると、怪しいところがあります。一方、最近は保守を標榜する小政党が出てきましたが、その主張には硬直したイデオロギーに転化する危うさがあって、いろいろと問題がありそうです。
先ほど吉田先生から、ヨーロッパの保守とリベラルの色分けは日本に当てはまらないのではないかというお話がありましたが、ヨーロッパの保守主義にははっきりとした軸が三つあると思います。
一つは、ヨーロッパで保守主義を名乗る人間はほぼ必ずキリスト教徒だということです。アメリカの共和党員やイギリスの保守党員でキリスト教徒でない、というのは考えにくい。政教分離という言葉は日本では誤解されていますが、本来の意味は教会権力が政治権力にタッチしないという意味であって、政治家の信仰を禁じているわけではなく、特に保守政党は伝統宗教と親和的ですね。道徳規範の源泉に宗教が存在するということは、保守派の基本認識ですから。ドイツのキリスト教民主同盟のように、キリスト教が党名に付いている国もあります。
二つ目に、バークがそうであるように家族を単位とする相続財産を重視するということです。だから十九世紀初頭の保守主義は土地財産を持っている上流階級のイデオロギーだったわけですが、十九世紀の終わり頃からウィングが広がり、中間層や貧困層にも家族財産を保障して、安定した社会を作ろうという考え方になっていきます。
三つ目が憲法、“constitution”です。ここでのコンスティテューションは狭義の憲法というより歴史的に形成されてきた国柄、国体のことであり、それを擁護するのが「保守」だ、となる。フランスなら共和国の精神ですし、イギリスなら王室と議会政を中心とした混合政体ですね。保守はその意味での「護憲」であって、長く続いてきた国制を保ち守ろうとするところに本義がある。アメリカの共和党は意地でも銃規制を認めませんが、それは武装権が建国の精神の一部だからです。
この三つの軸を日本に当てはめてみるとどうなるか。一つ目の宗教に関しては、戦前は天皇制や国家神道を打ち立てましたが、戦後は難しいところがありますね。家族財産については自民党も重視していて、そういった観点から所得倍増計画が立案されたりもしました。世界システムの周縁に位置するので、どうしても上からの開発主義という形を取らざるを得なかったわけですが、そういう意識は今も自民党に残っていると思います。
三つ目の憲法が一番ややこしい。戦後憲法は日本の国体の連続性を意図的に断絶させるために作られているので、素直にそれを保守するとは言えない部分がある。自民党の結成初期には、岸信介をはじめとする日本民主党系の政治家が自主憲法の制定を訴えていました。今もその意識はあると思いますが、すでに八十年近くが経った今、戦後憲法を根本から書き換えるのは現実的に難しくなっています。自民党も繰り返し改憲案を出していますが、どれも今の憲法を部分的に修正するというところにとどまっていて、日本の国体を十全に表す憲法を打ち立てるというところまでいっているかというと、疑問です。そうなると結局、戦後の憲法体制になし崩し的に吸い寄せられていく形になる。
ヨーロッパの基準を日本に持ち込む必要はないのですが、その限界を踏まえた上でいうと、戦後日本で保守主義の政党を作るのは難しい試みだった、とは言えると思います。
自民党が「親米化」していった歴史的経緯
浜崎 今、柴山さんから保守思想の観点からの議論がありましたが、僕は、自民党そのものについて論じてみたいと思います。まず、結論から申し上げると、政党史を紐解けば分かりますが、どう考えても、自民党は「保守政党」とは言えないところがあります。
確かに、自民党の「親米」に同情の余地が全くないとは言いません。例えば、明治維新政府が「攘夷のための開国」をやろうとしたのと同じように、戦後の自民党も「独立のための親米」をやろうとしたんだという言い訳はあるでしょう。でも、いつの間にか「独立のための」が抜け落ちてしまって、ズルズルベッタリの「親米の仮面」だけが残ってしまった。
簡単に歴史を振り返っておきます。まず、占領下の傀儡政権として吉田茂内閣が作られます。「軽武装・経済重視」と言えば聞こえはいいですが、要するに、残存する戦前勢力(軍人)を抑えながら、米国の占領政策に沿った対米協調路線(外資の導入と、自由主義経済の発展)を徹底すること、これが「吉田ドクトリン」と呼ばれるものの本質でした。
そして、一九五二年の占領解除とともに反動が起こる。それが、吉田内閣の次に登場する鳩山一郎内閣です。鳩山内閣は自主憲法制定と自主外交を言って、日ソ国交回復を果たしますが、それが米国務長官ダレスの顰蹙を買い、健康問題もあって短期政権で終わってしまう。
そして、この二つの流れ、つまり、親米一辺倒の吉田内閣の問題と、自主外交によって米国の顰蹙を買ってしまった鳩山内閣の限界を見据えて登場してくるのが、岸信介だったわけです。つまり、親米というテーゼと、離米というアンチテーゼの「あいだ」で、その両者に対するジンテーゼを出したのが岸信介ではなかったかと。実際、岸は「自主憲法制定」(反―吉田)を唱えるとともに、経済復興のための親米路線(反―鳩山)も唱えることになる。そして、その一番具体的な政策が「安保改定」でした。岸は、ジラード事件(米兵が薬莢を拾いに来た女性を撃ち殺した事件)などで高まった国内の反米感情なども考慮して、旧安保条約の内乱条項を削除するとともに、条約の双務性を一定程度向上させます。それは一見、独立回復の一里塚のようにも見えますが、しかし、それが日米安保の固定化を招いたという意味でいえば、やはり「日米基軸路線」を決定づけた瞬間だったと言えるでしょう。
しかも興味深いのは、一九五九年六月の参院選後の内閣改造時に、今まで対立していた池田勇人が岸内閣に入閣(通産大臣)していることです。岸に弟の佐藤栄作が協力することは分かりますが、吉田学校出身の池田勇人が、岸の「日米基軸路線」に頷いたことが、その後の自民党の運命を決めます。これ以降、清和会(岸派)、経世会(佐藤派)、宏池会(池田派)という自民党の「保守本流」は、一貫して「親米」を守り通すことになるわけです。
そして、実際、この時に自民党の基本的綱領も決まります。柴山さんに教わった奥健太郎さんの「自民党の『保守主義』――早川崇の『保守主義の政治哲学要綱』に注目して」(『戦後日本保守政治家の群像――自民党の変容と多様性』増田弘編著、ミネルヴァ書房、二〇二三年に所収)という論文によれば、一九六〇年に「自民党基本問題調査会」というところで、早川崇という議員が中心になって「保守主義の政治哲学要綱」をまとめているんですが、そこで早川は、バークなどの議論を参照しながら、「中庸の精神」、「新国民主義」、「民主主義の擁護と政治の限界」、そして「新しい資本主義と福祉国家への道」などと、なかなかいいことを言っている(笑)。でも、そこで議論を避けている決定的な論点が二つあるんですね。それが、天皇問題と安全保障問題だったわけです。しかし、この二点こそ、国内的な伝統と国体、そして、対外的な自立の問題が凝縮されている点であり、それこそ自民党の「保守思想」が問われるところなのですが、しかし、自民党はそこに全く手がつけられない。
後は省略しますが、それ以降、この「国体論なしの親米」が自民党のDNAとなっていったわけです。そう考えると、今の岸田政権の対米依存ぶりも何の不思議もありません。つまり、自民党は「保守政党」でも何でもない、単なる「親米政党」だということです。
白井 その五九年六月の内閣改造というのは、岸政権が初めは石橋湛山政権の居抜きだったのを、内閣改造をやって本当の意味で自分の内閣にしたということですか。
浜崎 そう言っていいと思います。それまではずっと、戦前派の岸に対して、戦後派の池田が反発するという構図の中で、河野一郎なんかが分裂工作をしていたんですが、選挙後に、なんと池田が岸側につくと。そういう形で自民党がまとまったということです。
「保守本流」と「保守傍流」に大差はない
白井 私は石橋政権が短命に終わり、岸が首相になって安保改定が進んでいったことが戦後史の大きなターニングポイントだったとつくづく思います。要するに、そこで岸が内閣改造して主流の派閥を全部まとめることができたというのは、言うなれば石橋湛山的な開かれた可能性を全部捨てることができたということでしょう。
戦後政治史の分析ではしばしば、吉田茂的な「保守本流」と鳩山一郎・岸信介的な「保守傍流」という図式が使われ、保守本流は護憲派で再軍備反対だったみたいな捉え方がありますが、あれは嘘だと思います。吉田が憲法九条を永久に守る気があったかというと、そんなことは全くなかったわけです。今のところは金もないから再武装なんて無理だし、また軍人がデカい顔をするのもたまったもんじゃないと思っていたわけですが、いずれ国力が回復してくるだろうから、その時には再武装をせにゃいかんと思っていたのは確実です。そう考えると、吉田と鳩山、岸には大差がないんですよね。せいぜいタイミングの問題で、それを大声で言うか言わないかぐらいの差でしかなかったと思います。対米従属レジームを死守するという意味では全然差異はなかった。保守本流と傍流の差異が過大評価されてきた観があります。
最近宮澤喜一の文書が発見されて、朝日新聞が抱え込んでいるみたいですが、朝日がやりそうなことは今から目に見えます。その文書を引っ張り出してきて、「宮澤さんはやっぱり賢かった。やはり保守本流は正しかったんだ」とやるに決まっている(笑)。宮澤喜一は、確かに安倍晋三みたいな反知性とは全くレベルの違う人間だったかもしれないけれど、結局彼は自民党の殻を破れなかったじゃないですか。自民党には戦前、戦中からのファシスト分子が入っていて、彼らは戦後アメリカと癒着することで生き延びて甘い汁を吸ってきた。ずっとそれを清算しないまま来てしまったから今こうなっているわけですよね。
安倍晋三は国力が衰退する中で、エスノナショナリズムに依拠して自分の支持を高めるという最低の悪手を打ってしまい、それで今のこの体たらくになっているわけですが、いわゆる自民党の中の良識ある保守の連中は、そういうことをやる奴らをどこかのタイミングで粛清しなきゃいけなかったんです。それができなかった宮澤は責任重大ですが、どうせ朝日新聞は「この時代は良かったですね」と褒めそやすのでしょう。「良識ある保守本流」という幻想にいつまで浸っているつもりなのか。
柴山 やはり湛山はひと味違いますね。彼の積極平和主義は戦前から一貫していますし、吉田を明確に批判していて、単なる状況論に流されないものがあります。湛山がもう少し長く権力を持って自民党の中軸となっていれば、その後の「保守本流」の流れは変わっただろうということですね。
白井 そうだと思います。前にある岩波の編集者と、「湛山の挫折と鳩山由紀夫さんの挫折はちょっと重なるところがありますよね。湛山が体調を崩さなければどうなっていたでしょうか」みたいな話をしたのですが、その編集者は「湛山が理想を追求したら殺されちゃって、変わらなかったんじゃないか」と言うんですよ。
僕も最初はそうかと思いましたが、でもやはり違うのではないか。というのも、日本のトップとして国の独立を貫こうとして死んだ奴は一人もいないんです。言ってみれば、保守陣営において道徳的模範になるキャラクターがいなかったということです。
ノンポリ的な自民党右派勢力
川端 僕は、昭和の時代の自民党は一応、当時の意味では「保守政党」だと言えたのだと思います。自民党のホームページには、結党時に作られた宣言文が掲載されていて、「立党宣言」、「綱領」、「党の性格」、「党の使命」、「党の政綱」といくつもあってややこしいんですが、大雑把に言ってしまえば、伸長する社会党に対抗して日本の社会主義化を防ぐためのカウンター政党なのだという立場が述べられているわけです。社会党の支持層を意識して「社会福祉は大事だ」とか「我々は進歩的政党だ」といった話をするのと同時に、「日本国内に階級対立を起こすべきではない」とか、「国際共産勢力や社会主義勢力と戦うんだ」という文言も随所に入っています。つまり、冷戦時代の反共政党としての立場は、結構分かりやすいのです。
ただ、あくまで社会主義運動に対するカウンターなので、自民党自身に明確なイデオロギーはないし、もともと各地の名望家の集まりですから、社会党や共産党に比べると組織としての統合も緩い。面白いのは、社会党のような組織政党と戦っていかなければならなかったので、「党近代化論」というのが繰り返し出てきていることです。金権政治や利益誘導は国民に批判されるからこれを打破しようとか、派閥政治をやめて中央集権化した強い組織を作るために、小選挙区制にすべきだといった議論です。こういう風潮は九〇年代頃から強くなったのかなと思っていたのですが、中北浩爾氏の本などを読むと、五〇年代からずっと似たような議論があったらしい。
いずれにしても、社会主義政権の誕生を阻止するために集まり、そのために少しずつ党改革を進めてきたという政党なので、「自民党の保守主義」というものを取り出して議論するのは難しいし、正直、政治思想的にはあまり面白くない性格の政党なのかなと思います(笑)。
平成以降の話をすると、冷戦が崩壊してから十年ぐらいは、自民党の中でリベラルが強かった時代ですよね。宮澤喜一、野中広務、加藤紘一、河野洋平といった、後の安倍政権的なものとは対極にあるリベラル派が活躍していた。普通に考えたら、冷戦崩壊はアメリカの勝利を意味するので右翼的になってもよさそうなのですが、リクルート事件で自民党の主流派への不信が募るなどした影響で、九〇年代には自社さ政権とかも含めて一時的にリベラルに傾いたのだと思います。
問題はその後で、九〇年代末の小渕政権の頃から、国旗国歌法とか日米防衛ガイドライン関連法など、右派寄りの政策が出てきました。その頃、僕自身は右翼少年みたいな感じで「新しい歴史教科書をつくる会」に入ってシンポジウムに行ったりしていたのですが、あの雰囲気は確かに右傾化と言っていいもので、白井先生が「ファシスト」と呼ばれるようなネトウヨ型の保守が出てきて、安倍政権につながっていったと思います。
で、リベラルや左派の人たちは、この頃に出てきた「草の根保守」とか「ぷちナショナリスト」とか「ネトウヨ」みたいなものをすごく批判されますよね。しかし僕は、そういう右派を擁護したいわけではないのですが、彼らは本格的な右派という感じがしないんですよね。
白井 彼らはもともとノンポリでしょう。自己不全感とメディア環境によって過激化したにすぎないので、歴史についてもロクに知らない。
川端 そうです。すごくショボい感じの連中で、正直、ファシストとしての迫力が足りない(笑)。それが左派やリベラルの方から過大評価されている気がします。「自民党は保守なのか?」という議論をする上で、近年のいわゆる右傾化と言われるものには触れた方がいいと思うのですが、実は大した右傾化ではない。もちろん、中には思想の強い人や行動派の人もいますが、それを自民党の政治家が真に受けているわけでもありませんし。柴山さんがおっしゃったように、ヨーロッパの右派には家族とか宗教とか何かしらの軸があるのだとして、日本の右派勢力は軸が曖昧なので、自民党と同じでつまらないですね。
白井 思想的に空虚だからといって社会的に無意味だということにはならないと思うのです。草の根保守というか草の根ファッショ化みたいな現象は、愛国心ではなく自己意識のかさ上げを動機としたものでしょう。だからこれは社会病理です。それを見過ごせないのは、かつては「一部の変な人たち」の運動にすぎなかったのだけど、彼らの主張がメジャーメディアなどに薄められた形で浸透するようになったためです。
本来日本の保守は、軸とすべきは天皇陛下しかないでしょう。でも、安倍晋三は天皇陛下に対して不敬な態度を見せていましたけれど、この戦後日本で保守派の軸は実質的にはアメリカになっているから、あんな不敬を犯しても保守派から全然非難の声が上がらないわけです。
「保守主義」は存在し得ないのか?
吉田 政党論についてですが、ヨーロッパの保守政党は一般的に「国民政党」であることを自認します。社会民主主義政党の側が「階級政党」と自己規定していたので、それに対して「国民政党」と謳っていたわけです。一方で、自民党の場合は政治学で言うところの「議員政党」なので、もともと組織など必要ありません。議員が勝手に合従連衡して物事を決めるというのが議員政党のあり方であって、それが自民党の分かりにくさの一つにつながっていると思います。
その上でいうと、日本において「保守思想」というのはあり得ても、「保守主義」はないのではないか。ちなみにバークは「保守」という言葉は使っても「保守主義」という言葉は一度も使っていません。保守思想が生まれたのはフランス革命の時ですが、基本的には人智でもって物事を統治していくのが長らく「近代」と呼ばれている時代の趨勢であり、バークはそれに対して異議申し立てをした。人智が暴走した場合には、伝統や歴史が蓄積してきたものに依拠すべき、と主張したわけです。つまり、本来的には近代化を進める勢力がリベラルだとしたら、リベラルに対してブレーキをかけるのが保守思想です。
日本でも海外でもそうですが、思想家として有名なのは社会科学者というよりも作家を含めた人文学の人間ですよね。日本では小林秀雄や福田恆存に代表的ですが、それは社会科学における理性や理知といったものと保守思想との相性の悪さを示しているのだと思います。
それから九〇年代以降の自民党の右傾化路線ですが、冷戦の中で自民党の保守主義は社会主義と対比されて定義されてきたため、冷戦が終わってから軽く脳死状態に陥ってしまったわけです(笑)。九〇年代後半以降、冷戦構造を前提としない保守主義を再定義しなければいけないと自民党の人たちもようやく気づいて、そこから「右傾化」が始まったのだと思います。
こうした転回は、政治学的には「保守化」というよりも、「極右化」と見なされます。なぜかというと、原理的にいえば、そもそも保守主義を理知的に追い求めること自体が保守思想に反するからです。日本保守党や参政党も、世界基準から見たら「極右」なわけですよね。憲法にしろLGBTにしろ、家族の問題にしろ、国旗や靖国の問題にしろ、そういったものを政治的に再定義すること自体が「極右」になってしまうんです。それが、日本において保守主義が存立し得ない一つの証左になっているのではないかと思います。
柴山 福田恆存は、保守は生活態度であって主義ではないと言っていて、確かに一理あると思います。近代社会は古い封建的な制度を壊して進歩的に進んでいくわけで、その動きにブレーキをかける役目が保守であるのはその通りだと思うのですが、それだけだと結局、その時々の状況に流されてしまうのではないかという危惧も感じます。つまり、何らかの「軸」がいるのではないかということです。状況の中で「ベスト」より「ベター」を選ぶ現実主義ということだけでいくと、「今さら自主独立など出来ないのだから、アメリカにくっつきながら外交していった方が良い」とか、経済に関しても「グローバル化や新自由主義に逆らわず、受け入れて国益を最大化しよう」という形になりやすい。
「主義」と言ってしまった瞬間に硬直化したイデオロギーになって、現実政治から乖離してしまう危険があるのですが、それでもやはり「主義」となる思想の軸が必要なのではないでしょうか。丸山眞男が「反動の概念」という論文の中で、「日本には生活保守はあるが保守主義がない。それは進歩派にとっても不幸である」という趣旨のことを書いています。やはり国家の背骨となる「コンスティテューション」があるはずだと構えて、それを探して守るという態度があっていいし、その意味での「保守主義」が日本においても追求されるべきなのでは、と思います。
藤井 「保守主義」あるいは「保守思想」が追い求めているのはリベラルと全然違うものではなくて、伝統を大事にする「保守主義」や「保守思想」と、創意工夫を大事にする「リベラル」をいかにアウフヘーベンさせるのかが大事になってくるはずです。そう考えると、日本の場合は「皇室」とか「忠心」、あるいは「忠義」といった「コンスティテューション」を幾分大事にする人々が一部いた方がいいだろうとは思います。
続きは本誌にて…

雑誌と書籍の年間購読を通じて、『表現者クライテリオン』をご支援ください!
https://the-criterion.jp/lp/r6supporters/
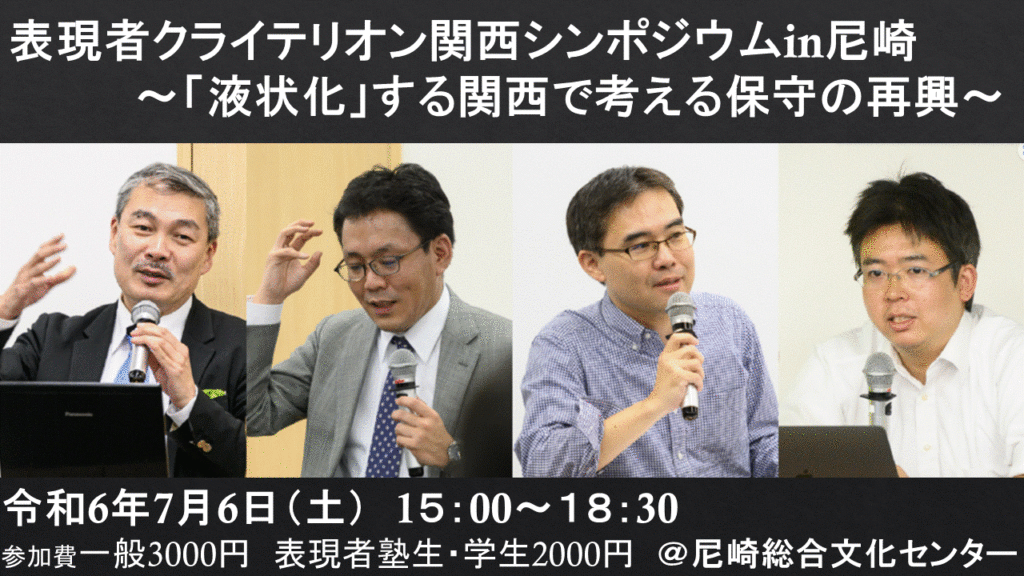
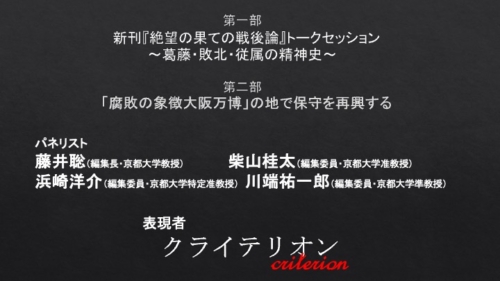
3年ぶりに関西でシンポジウムを開催!
「革新」の標語が力を強める関西において、本当の保守主義をどのように実践していくべきか、『表現者クライテリオン』編集委員が徹底議論!
詳細はこちらから

クライテリオン誌上で行われた「座談会 対米従属文学論」がクライテリオン叢書第4弾として待望の書籍化!
第二部に浜崎洋介先生の戦後文学批評の決定版とも言える論考「観念的な、あまりに観念的なーー戦後批評の「弱さ」について」を収録!
※本体価格2,600円ですが、6月から始まるクライテリオン・サポーターズの特典に加えることが決定しました。
サポーターズ加入がますますお得になりましたので、ぜひご検討ください。
執筆者 :
NEW

2026.01.30
NEW

2026.01.30
NEW

2026.01.29

2026.01.23

2026.01.23

2026.01.22

2026.01.18

2026.01.20

2024.08.11

2026.01.22

2026.01.23

2026.01.23

2018.09.06
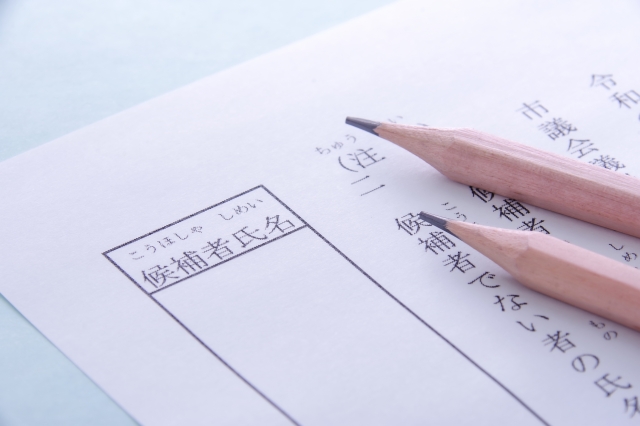
2026.01.13

2025.04.01

2018.04.06