そもそも日本人にとって「大学」とは何なのだろう。幕末維新の当時、西洋にはuniversityという教育機関があるとは知っていても、実感としてイメージできる者はいなかったと思う。ただ、一刻も早く近代国家建設の担い手としての実務や技能の持ち主を育てるために高等教育機関の設立は優先課題で、省や軍が専門学校を作ることから始めた。10年ほどかけてuniversityという形に統合するが、明治維新は「王政復古」でもあったから、「大学」という名称は唐の律令制を取り入れた官僚候補生の教育という古代の「大学寮」を念頭に置いたものだろう。Universityとは、大分意味が違う。
実務や技能の教育ではなく、学問の場として、幕府の昌平黌や、幕府天文方の後継で勝海舟が組織改革をした蕃書調所や、神田お玉が池の種痘所などを母体とした学問所を統合再編成していくわけだが、明治初年には儒学中心の昌平黌の教授陣と、光格天皇(在1779-1817)以来の京都の皇学所の学者たちとの間でイデオロギーの対立が激しくなっていた。儒学と国学の大喧嘩がエスカレートして収拾がつかなくなったため、明治政府は教科の編纂を組み替え、この分野を廃止してしまったのだという。国家建設が急務であったときに、喧嘩の相手をしている暇はなかったということだろうか。結局、保守勢力が内紛で自滅した結果、「洋学派」が漁夫の利を得ることになったらしい。
西洋文明、とくにその圧倒的な軍事力が国家存続の脅威として強く意識されたことで、明治政府が洋学を積極的に取り入れたことは確かである。しかし、「王政復古」として意識されていた保守的な思想が大学教育に導入されなかったのは、単に「洋学偏重」というだけではなかったということになる。西洋の学問を学ぶ医学所や工部大学校や農学校だけでなく、開成所もそれまでの「漢学・国学・洋学」というバランスから「洋学」中心になった背景には、内紛による「保守勢力の自滅」が関係していたというのだから、どこか今日の自民党を髣髴とさせる話だ。
ペリー来航に前後して日本各地で洋学への学習意欲の高まりがあった。江戸、大阪、長崎などの都市で知識人が開いていた蘭学塾は、幕府の学問所よりも熱気があった。緒方洪庵の適塾や佐久間象山の象山書院などの各地の私塾のネットワークを自由に往来する「在野の志士」たちが、官吏養成の目的とは別に、新時代への共闘意識を培っていた。外来の知の普遍性を拠り所にして旧体制を打破しようとしたともいえるが、寧ろ、洋学を通してナショナリズムを自覚・醸成したともいえる。日本を取り巻くグローバルな世界を感じ取ることによって、自国の価値を問い直し、世界のなかでの位置づけを真剣に考えるようになったということだろうか。
それまでの当たり前な社会では理解できないものに出会ったとき、人は反発するか理解しようとするかのどちらかの態度をとる。最初から否定して理解しようという努力を放棄すれば何の進展も起こらないが、理解しようと試みる態度があれば「学問」の第一歩になる。日本という東の果ての国にとって、異質なものは、いつも「西」からやって来た。古代の儒教であり、西方極楽浄土の仏教経典であり、南蛮の耶蘇教であり、近代思想や科学技術である。実際、古代において中華文明は東アジアで飛び抜けて高度な文明であった。古代のグローバルスタンダードである。日本にとって幸運だったのは、日本海によって隔たれていたために中華による現実の「支配」ではなく、波状的な「刺激」としてグローバルスタンダードと接したことだろう。実際の支配を免れた幸運は、文字を学び漢籍を翻訳することが学問だという受け身の姿勢を作った。日本人にとって、学問が発信ではなく、西からやって来るグローバルな思想を翻訳することになったのは、古代に文字を受け入れたときから始まった。
律令という「法」による統治は、多民族が混在する広域支配に有効性を発揮する手段であって、古代においてその仕組みを完成させたのが中華帝国である。中華帝国の律令に「支配」されたのではなく「概念」として理解したことで、日本人は律令が理想的な制度だと考え、自らが律令の中心になろうと試みたが、日本社会の実情には適さなかった。律令のような絶対性をもつグローバルな思想は広域を画一的に支配するもので、具体的な人や風土はほとんど無視される。日本のような絶対性・普遍性を拒む風土に於いて、結局、名称だけが残されて消滅した。日本人は普遍的な思想を理想として学んだが、体質に合わない薬を処方されたようなものだったのかもしれない。人間の都合で作られた律令などが太刀打ちできない度重なる災害のほうが「効き目」があった。
16世紀から17世紀にかけて、世界の各地域がそれぞれ独自に動き出している。おそらく、それは貨幣経済によるもので、「銀」の流通がもたらした世界的な現象である。この頃、スペイン・ハプスブルク家の新大陸の銀と江戸幕府が直轄する銀山の開発で、世界の銀の流通量が飛躍的に伸びていた。貨幣経済の活発化は、社会の再分配機能をも活性化させる。ヨーロッパでは、既に活版印刷技術によって変化の可能性が準備されていて、商業的な印刷物の普及は「知の爆発」をもたらした。プロテスタントの闘争や思想・国家・法の体系の劇的な変化のなかで、中世都市を基盤とした大学が衰退し、「財力」のある保護者(メセナ)をバックにした知識人の移動が起こり、彼らの交友が知の世界を牽引していくようになる。同じころ、アジアの海の貨幣交易圏は、この地域を中華冊封体制から脱却させる準備をした。貨幣経済は文化文明の違いを超えて波及する。貨幣にはイデオロギーが付着しない。地域ごとに変化していた経済活動が、貨幣(銀)を通して一気に世界規模で動き出したのが、17世紀から18世紀である。
停滞した経済活動はそれなりの安定を社会にもたらすが、それは固定化された階級社会である。貨幣経済は動的で不安定な社会を招いたが、階層間の移動によって経済活動や市場の拡大をもたらした。このような流動的な時代は、思想・学問の世界にも当然影響を与える。最近出版された先崎彰容氏の『本居宣長』で、貨幣経済による社会の流動化と国学誕生との関係に言及していることは、刺激的な指摘である。ウェストファリア会議を通過し、「王権神授説」に導かれた絶対王政を経て国民国家形成に至るヨーロッパの思考経路とどこか類似した「価値の問い直し」が、鎖国時代の日本にも起こっていたということだろうか。本居宣長の生家が伊勢松坂の木綿問屋であったことを考えれば、確かに世界的な資本主義経済の波の末端が「商い」の世界に及んでいたのだろう。自らの所属する社会は、当たり前すぎてなかなか思考の対象にならない。問題提起は比較によって生じるが、比較を喚起するものがなければ意識に上らない。この時代に、それを肌で感じ取ることができる都市の知識層が既に形成されていたことになる。
明治初期の知識人たちの儒学から洋学への意識変化と大学での外国人教師による講義は「学ぶ側の語学力」に支えられていたはずだ。そのまま、外国語での講義が続いていたら、いまの日本の大学は世界レベルの語学力をもっていただろう。しかし、語学だけ堪能でも、それが学問の本質ではない。この時代の最大の業績のひとつに、どの分野も母国語で学べるように語彙を創造したことがある。多くの知識人が、科学や西洋哲学の術語から文学作品の微妙な表現に至るまで、発想の異なる概念を日本語の言語体系に取り込もうと格闘した。例えば、西周はEncyclopediaのことを「百学連環」と翻訳した。あらゆる学問が連環しているcycleのイメージを表わしている点で「百科事典」よりも奥深い表現といえるが、この一語だけでも多くの人が「格闘」していたのがわかる。
母国語で学べるということは、国民の学問への裾野を広げることになる。外国語をそのまま使用すればただの記号に過ぎないが、漢字という表意文字を巧みに組み合わせることで、初心者にも新しい概念のイメージを掴ませることができた。このことは、高等教育だけでなく、初等・中等教育の充実にも繋がっている。いまでは子供でも知っているような日常語になった言葉もある。エリートではない人々の基礎教育や、実社会での現場の実務や技能の向上には、母国語での教育でなければ対応できない。
母国語を通して世界中の学問ができるようになったことは教育の普及に効果があったが、それが英語の不得意な国民という劣等意識をもたらした。非英語圏の大学は、すべてこの問題に突き当たっている。日本の近代化が世界的にも早い段階で着手され、語彙や術語の母国語化に成功したために、外来語彙をそのまま使う後発国に比べて、どんな分野の学問でも英語を必要とせずに行うことができるようになった。グローバルマーケットにおいては不利になったが、母国語の豊かさは、国民の豊かさなのだ。英語圏の思想体系を、日本語体系で思考するのは、悪いことではない。そこには、英語体系では気づかない、新たな知の発見があるかもしれない。
他言語を学ぶことは大切である。他を知ることで、己を知ることが可能になるからだ。他言語を学ぶのは、他に染まるためではない。グローバル・メリトクラシーに収斂していく価値観に対するアンチテーゼは母国語である。母国語が消滅したときが敗北である。言語はそれ自体、武器になる。日本の大学には、グローバル・メリトクラシーのランクより大切なものがあるはずだと思う。
『日本語の科学が世界を変える』松尾義之著 /筑摩選書 2015
『グローバル化と銀』デニス・フリン著 秋田茂・西村雄志訳 /山川出版社 2010
『大学とは何か』吉見俊哉著 /岩波新書 2011
『本居宣長 ——「もののあはれ」と「日本」の発見』先崎彰容著 /新潮選書 2024
画像出典:ウィキペディア「東京外国語大学」より
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%A4%96%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E5%A4%A7%E5%AD%A6
好評発売中の『表現者クライテリオン2024年7月号 [特集]自民党は保守政党なのか?』。
本書のご購入はこちらから!
よりお得な年間購読(クライテリオン・サポーターズ)のお申し込みはこちらから!
この度、京都大学経営管理大学院レジリエンス経営科学研究寄附講座では、「レジリエンス―人間と社会の強靭性を考える」と題した連続講座を開催いたします。
本講座では、人文社会科学および社会工学における探求を通して、多角的な視点から人と共同体のレジリエンス力を高めるヒントを探ります。地震・風水害等の自然災害やパンデミック、地政学的紛争リスク、世界同時不況等、あらゆるリスクに直面してなお、人を動かし、一定の共同性・凝集性を維持し、事業継続を可能とするものは何か。
本講座を通して、レジリエンスへの理解を深め、自己と社会を理性的に捉える力を育みます。
執筆者 :
CATEGORY :
NEW

2026.01.30
NEW

2026.01.30
NEW

2026.01.29

2026.01.23

2026.01.23

2026.01.22
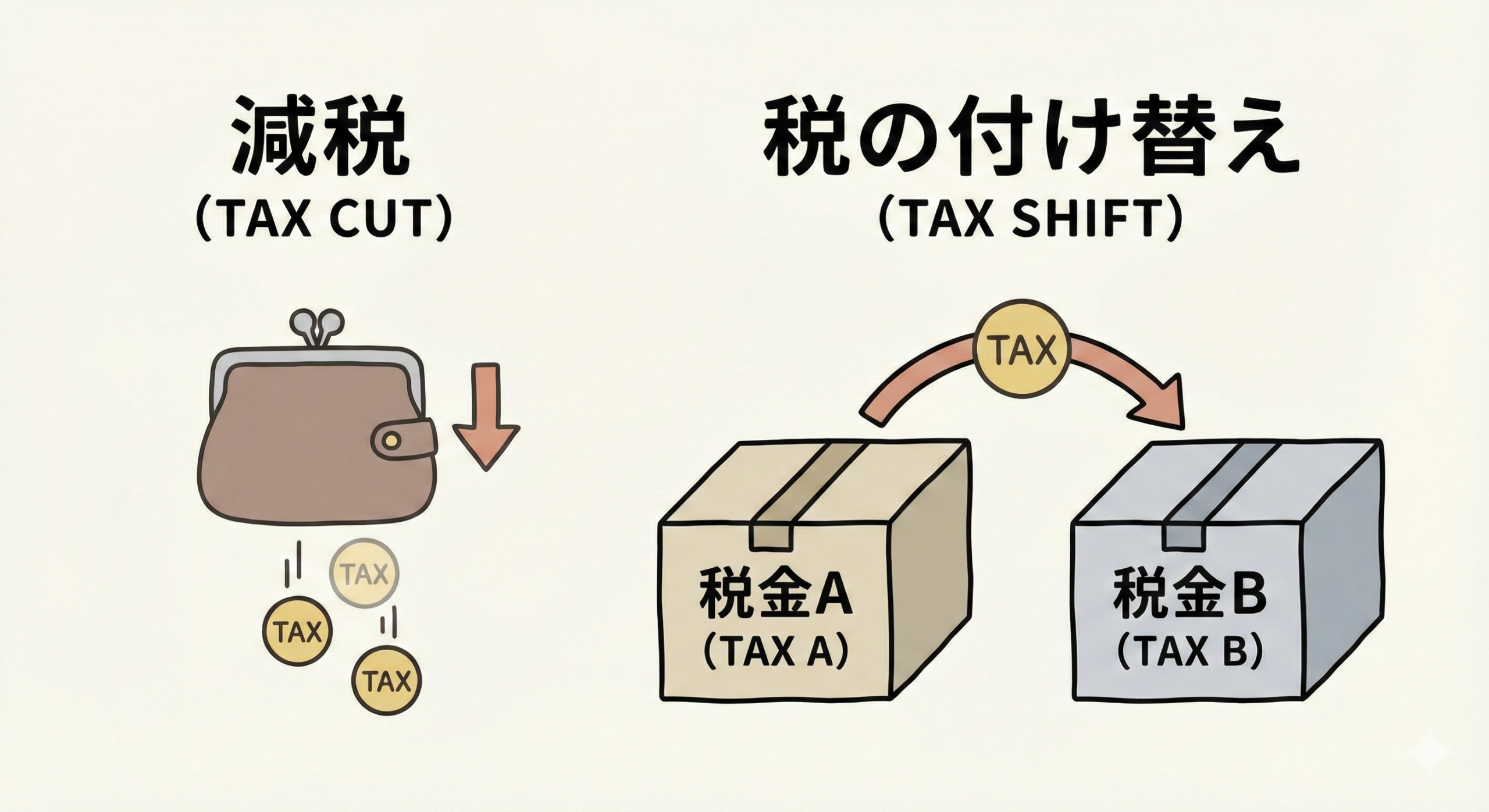
2026.01.18

2026.01.20

2026.01.30

2024.08.11

2026.01.30

2018.04.06

2026.01.22

2026.01.29

2018.09.06

2018.03.02