2025年3月30日、「戦後80年、沖縄から考える対米独立への道」とのテーマを掲げて、7年ぶりに開催した『表現者クライテリオン』沖縄シンポジウムには100名近くの方々にご参加いただき、時間的な制約と不慣れな進行役のために「十分に論議を尽くすことができなかった」等の討論会には付き物の不満は残りましたが、盛況のうちに幕を閉じることができました
また、シンポジウムの翌日には、沖縄大学の宮城能彦教授と琉球・沖縄歴史研究家の賀数仁然氏にガイドをお願いして、琉球王国時代に貿易の拠点であった那覇港・三重城(ミーグシク)からスタートし、現在、修復作業が進められている首里城(沖縄戦における陸軍第32軍総司令部壕跡でもある)を経て、米軍那覇港湾施設(那覇軍港)の移設先とされる「カーミージ―」(浦添市港川の自然海岸)を巡るエクスカーションを実施しました。
シンポジウム本編と同様、時間的な制約があり、かなり慌ただしい行程となってしまいましたが、宮城教授と賀数氏による素晴らしい解説のおかげで、琉球王国時代から沖縄戦を経て、戦後80年が経過したにもかかわらず、未だに「基地問題」を抱え、日米間で翻弄され続けている現在の「沖縄」に思いを馳せながら視察するという、一般的な観光旅行では味わうことができない時間を共有していただけたのではないかと自負しているところです。
沖縄シンポジウムで議論した内容の詳細については、今後、『表現者クライテリオン』本誌において紹介したり、改めて論じたりする機会があるかと思いますので、今回は、進行役を務めた私が、シンポジウムの際に語り尽くせなかったこと、上手く伝えることができなかったことについて論じてみたいと思います。
シンポジウムの後半で、川端祐一郎氏がDA PUMPの大ヒット曲「U.S.A.」に言及し、「僕はあの曲がホンマに気持ち悪くて、あれの歌詞を読んだら、要するに『アメリカのファッションはカッコいい、アメリカの音楽はカッコいい、アメリカの映画はカッコいい、アメリカにはアメリカン・ドリームがあって素晴らしい、アメリカ万歳』みたいな内容で、それを極めて子供じみた言葉で綴っている」「僕はあの歌がテレビとかラジオで流れていた時、ホントにけっこうショックだったのですよ」「DA PUMPのISSAさんが雑誌のインタビューに答えて『僕はとにかく子供の頃からアメリカに憧れていて仕方がなかった』と言っているだけで、ホントに素朴に『アメリカ=カッコいい=先進的な国』と言っている」「あれを見たときに沖縄の人に『勘弁してくれ』と思わなくもなかった」「我々日本人は『対米独立』に向けて、『アメリカ万歳』を言っちゃいかんということですよ」との見解を示しました。
川端氏は、沖縄シンポジウム以前に、昨年の私との「今週の雑談」の際にも、「U.S.A.」について同様の見解を示しており、その上で「アメリカ文化にある種の憧れを持つことはいいのだけれども、もう少し恥ずかしげや躊躇があって欲しい」と論じています。
私自身、DA PUMPの「U.S.A.」が大ヒットしたことは知っており、後で資料を見返して、2018年当時、一般の人たちが、その「いいねダンス」と称する「ダサかっこいい」ダンスを真似して踊る姿をSNSに投稿する“踊ってみた”現象の流行など社会現象となり、DA PUMPが多くの音楽賞を受賞し、16年ぶりに紅白歌合戦に出場したことなどを思い出しました。
しかしながら、シンポジウムの時点では「U.S.A.」について深く考えたこともなく、その歌詞で語られている内容を覚えてさえいなかったので、川端氏の指摘に対して「その通りだと思う」と答えつつ、「『U.S.A.』は、沖縄だけでなく全国的にヒットしたのであり、現在の(本土の)日本人が、沖縄の人間と比べて、ちゃんとした意識を持っていると言えるのか?」「アメリカニズム、アメリカナイズされたものに憧れているという点においては、日本本土も沖縄と大して変わらないのではないか」などといった、ありきたりなコメントを返すことしかできませんでした。
シンポジウム終了後、議論を聞いていた友人に呼び止められ、「DA PUMPの『U.S.A.』の歌詞が日本人として恥ずかしいと言っていたけれど、それは違う」「あれはアメリカをアウフヘーベンしている(乗り越えた)歌で、ウチナーンチュ(沖縄人)であるISSAだからこそ歌える歌だ」「藤原さんには、もっとはっきりと反論してもらいたかった」と言われてしまい、前述したように、「U.S.A.」の歌詞について、きちんと考察したことがない私には返す言葉がありませんでした。
後日、「U.S.A.」の基本情報を確認したところ、DA PUMPのオリジナル楽曲ではなく、イタリア人歌手のジョー・イエローが1992年にリリースしたユーロビートの同名曲のカヴァーであることを知りました。
“U.S.A. / You are catching me with some desire” と始まるオリジナル版が、擬人化されたアメリカを性的に誘惑する内容であったのに対して、DA PUMP版では、原曲の歌詞の韻を踏みつつも、その作詞を手掛けたshungo.の言葉を引用すれば、「『U.S.A.』の歌詞は1960~70年代の米国に憧れる少年をイメージしたもの」として異なる意味の単語に置き換えられており、その内容は全く異なります。
日米文化史研究者の阿部幸大氏は、「『無邪気にアメリカへの憧憬を歌う』日本のポップスとして消費されている『U.S.A.』を読み解くには、やはり日米関係に着目する必要がある」として、その非政治性を批判的に捉える一般的な評価―「政治や社会の問題から目を背け、音楽を娯楽として消費するばかりの日本を象徴している」とする評価―とは一線を画す分析を提示しています。
阿部氏は、「U.S.A.」のオリジナル版とDA PUMP版の歌詞の比較を通して、「アメリカが性的な欲望の対象から文化的な憧れの対象へとシフトしている」ことに加えて「時制が過去形へと大きく変化している」ことを指摘し、DA PUMP版では「日本人がアメリカのカルチャーに憧れていたのはずっと昔の話である」と歌い、「半世紀前には『憧憬』の対象であった『アメリカ』が『競合』相手へと変わっている」ことを明らかにしています。
すなわち、「U.S.A.」という楽曲において、DA PUMPは世界レベルのダンス・パフォーマンスでお道化て見せながら、(日本人にとって)かつて遠い憧れの存在であった「アメリカ」を自らと対等な「競合」相手へと引きずり降ろし、「カモン!=かかってこいや!」と叫んで挑発してみせていると解釈することができるのです。
なるほど、確かに総合的に分析してみると、こうした解釈の方が、より妥当であるように思えます。
今回の記事を執筆するにあたり、前述の発言の中にあった川端氏が読んだと思われる記事を見つけることはできなかったのですが、ネット上で確認できるISSA氏のインタビュー記事をいくつか読んでみたところ、ISSA氏自身が語った「U.S.A.」を初めて聴いたときの感想を見つけました(注1)。
正直、最初は「おい、まじか。これかよ」という思いもありました(笑)。でも、僕らにできることは“完璧に仕上げること”なので。そこでスイッチも入りましたし、“U.S.A.という場”で、“しっかり遊ぶ”“真剣にふざける”などの方向性が見えた時点で、違うものに見えました。自分たちのものとして、きちんと落とし込めているし、しっくりきている。だんだん自分たちの曲に育っていった感じですね。今ではメンバー全員が“すごくいい曲だ”と思っているし、そういう自分たちの中の変化も、おもしろかったです。かけ離れていると思っていたものと自分たちの心が、近づいていく感じ。今は、僕らのところに舞い降りてきてくれてよかったなって思っています。
ISSA氏の「『アメリカ=カッコいい=先進的な国』と語っておしまい」とするインタビューへの回答と、「U.S.A.」を初めて聴いたときの「おい、まじか。これかよ」との言葉との間には大きな隔たりがあり、矛盾しているかのようにも感じられます。
2018年10月8日放送のNHKの情報番組『ニュースウォッチ9』にISSA氏がゲスト出演し、普段のバラエティー番組や音楽番組では見せない“真面目な顔”を覗かせたことが話題となったことがありました(注2)。
同番組でのインタビューで「U.S.A.」について問われたISSA氏が「アメリカの文化がなければ、自分たちはいなかった。そのことに感謝し、恩返しをする気持ちでこの楽曲を歌っている」と答えていることからも、川端氏が読んだインタビュー記事で、ISSA氏が語っている「アメリカ」への憧れ、「アメリカ=カッコいい=先進的な国」との思いは、嘘偽りのない彼自身の本音であったのだと思えます。
その一方で、ISSA氏が語る「おい、まじか。これかよ」との第一印象から始まり、“U.S.A.という場”で“完璧に仕上げること”に向けて “真剣にふざける”などの方向性を見出し、かけ離れていると思っていたものと自分たちの心が近づいていくと感じながら、自分たちの曲に育てていくというプロセスには、ISSA氏がエンターテイナーとしての自分に与えられた役割を俯瞰的・客観的に捉えて、自らに提供された素材(楽曲と歌詞)をより完成度の高い作品へと昇華させるために努めるプロフェッショナルとしての矜持を読み取ることができます。
私には、一見するとあたかも矛盾するとも読めるISSA氏の言葉が、「アメリカ」をカッコいい「憧憬」の対象として仰ぎ見る思いと、「アメリカ」を自らの対等な「競合」相手と看做して「カモン!=かかってこいや!」と挑みかかる思いが併存している、彼自身のアンビバレントな心情を素直に表象しているように思えるのです。
シンポジウム翌日のエクスカーションの際に、賀数氏が解説してくれていましたが、ISSA氏の本名は邊土名一茶(へんとな・いっさ)といい、1972年に国の重要無形文化財に指定され、2010年にユネスコの無形文化遺産リストに登録された「組踊」の創始者である玉城朝薫(たまぐすく・ちょうくん)の末裔であることが知られています(注3)。
前述したNHKの情報番組において、ISSA氏が米軍基地について意見を求められた際に、自らが嘉手納基地のすぐ近くの沖縄市で過ごしてきたこと、幼い頃から沖縄戦を経験した「おじぃ」や「おばぁ」の話を聞いて育ってきたことなどに触れつつ、「4分の1アメリカの血も入っているので、僕がやっぱりそういうことを言える立場ではまずない」と断った上で「(米軍基地と)共存していくことが、争いもなく、街が栄えていく方法のひとつではないか」との持論を述べたことが、「戦後生まれの素直な思いの発言という感じで好印象だ」「誰も傷つけないように、慎重に言葉を選んでいるのが伝わった」「沖縄出身として冷静に意見を述べたのは素晴らしい対応であった」など多数の賞賛の声を集めました(注2)。
ISSA氏が自らのアイデンティティに言及した上で「共存」を語った背景にあるのは、日本とアメリカの間で翻弄され続ける沖縄において「ウチナーンチュであると同時に日本人であり、かつアメリカの血脈を受け継いでいる、さらには『玉城朝薫』という沖縄では知らない人はいないと言っても過言でないような琉球芸能史の重要人物の末裔であるという彼自身の多層性と多面性を有する複雑なアイデンティティ」と、彼(に限らず多くのウチナーンチュ)の心の中に「同胞としての日本」と「隣人としてのアメリカ」に対するアンビバレントな感情が渦巻いているという事実であり、彼の政治意識が「沖縄の現状を無邪気に肯定している」と看做すことができるほど単純なものではないことは明らかです。
こうしたISSA氏のアンビバレントな沖縄的自意識を念頭において再び「U.S.A.」に戻れば、「そのアイロニー戦略がすぐれてハイブリッドなもの」(阿部幸大氏)であることが見えてくるのであり、自らのアンビバレントな心情を率直に語るISSA氏の言葉が、日本とアメリカとの間で翻弄され続けた沖縄の地で生きる多くのウチナーンチュの共感を得たことは、至極当然のことであるように思えます。
沖縄シンポジウムでも言及しましたが、かつて「沖縄保守のドン」と呼ばれ、日本復帰後の沖縄で長らく県知事を務めた西銘順治氏(故人)が「沖縄の心とは何か」という記者の質問に対して「ヤマトンチュー(大和人)になりたくて、なり切れない心だろう」と答えています。沖縄が節目を迎える時に繰り返し引用される歴史的な発言であり、沖縄県民の複雑なアイデンティティを表現した名言として、沖縄では広く知られています(注4)。
私たちウチナーンチュが「同胞としての日本」と「隣人としてのアメリカ」に対峙するに際して目指すべきは、自らの「複雑なアイデンティティ」を否定し、「日本人=ヤマトンチュ―(大和人)」と同化することで「日本」と「アメリカ」に対するアンビバレントな感情を解消することではなく、そのアンビバレントな沖縄的自意識と上手く付き合いながら、「複雑なアイデンティティ」を自らの「弱み」ではなく「強み」として活路を見出していくことであるように思えてなりません。
ウチナーンチュの「複雑なアイデンティティ」を自らの宿命と認識したとき、ISSA氏による「カモン!=かかってこいや!」との叫びが、「アメリカ」に対する挑発であると同時に、私たちウチナーンチュに「喝」を入れる一声であるかのように聞こえてきます。
(注1) DA PUMP「U.S.A」誕生の裏側 ISSA「ダサいは褒め言葉」 | コラム | エイベックス・ポータル
(注2) 沖縄基地について質問されたDA PUMPのISSA 返答に「おっしゃる通り」「素晴らしい」 – grape [グレイプ]
(注4)『沖縄県知事―その人生と思想―』 野添文彬 | 新潮社
(藤原昌樹)
<編集部よりお知らせ1>
最新刊!、『表現者クライテリオン2025年5月号 [特集]石破茂という恥辱 日本的”小児病”の研究』、4月16日発売!

よりお得な年間購読(クライテリオン・サポーターズ)のお申し込みはこちらから!サポーターズに入ると毎号発売日までにお届けし、お得な特典も付いてきます!。
サポーターズPremiumにお入りいただくと毎週、「今週の雑談」をお届け。
居酒屋で隣の席に居合わせたかのように、ゆったりとした雰囲気ながら、本質的で高度な会話をお聞きいただけます。
<編集部よりお知らせ2>
表現者塾は『表現者クライテリオン』の編集委員や執筆者、各分野の研究者などを講師に迎え、物事を考え、行動する際の「クライテリオン=(規準)」をより一層深く探求する塾(セミナー)です。
◯毎月第2土曜日 17時から約2時間の講義
◯場所:新宿駅から徒歩圏内
◯期間:2025年4月〜2026年3月
◯毎回先生方を囲んでの懇親会あり
◯ライブ配信、アーカイブ視聴あり
執筆者 :
CATEGORY :
NEW
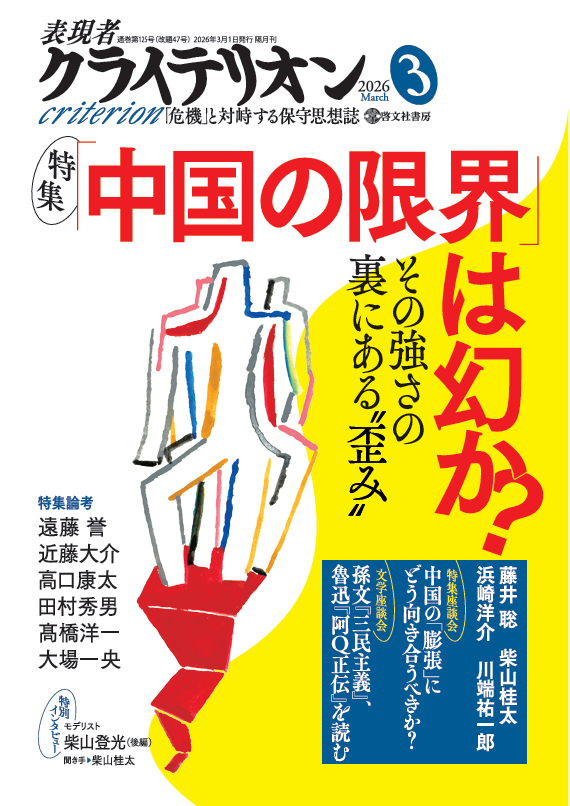
2026.02.16
NEW
.png)
2026.02.16
NEW
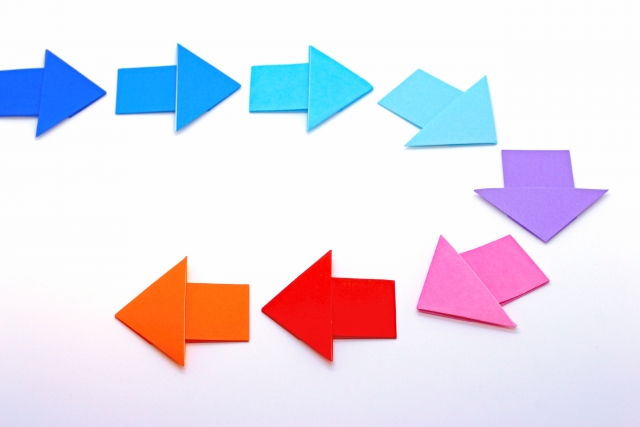
2026.02.16
NEW
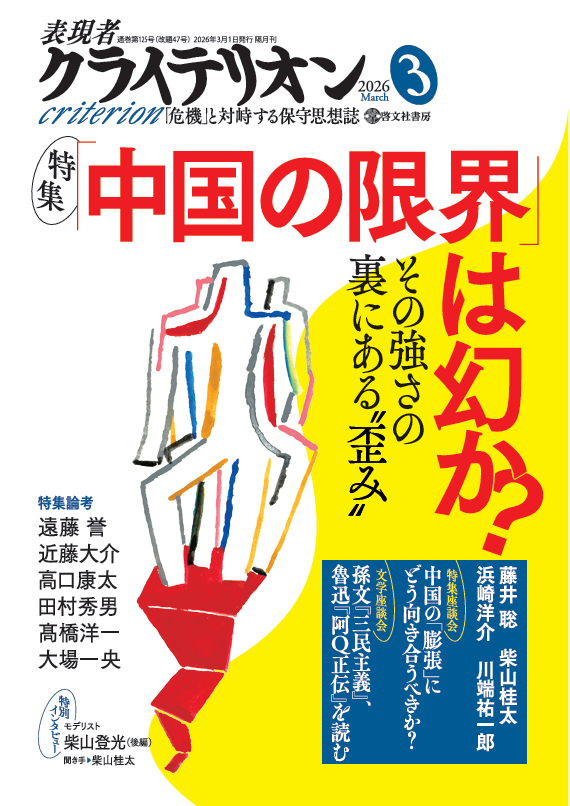
2026.02.16
NEW

2026.02.13
NEW

2026.02.12

2026.02.12

2026.02.11

2026.02.13

2026.02.09
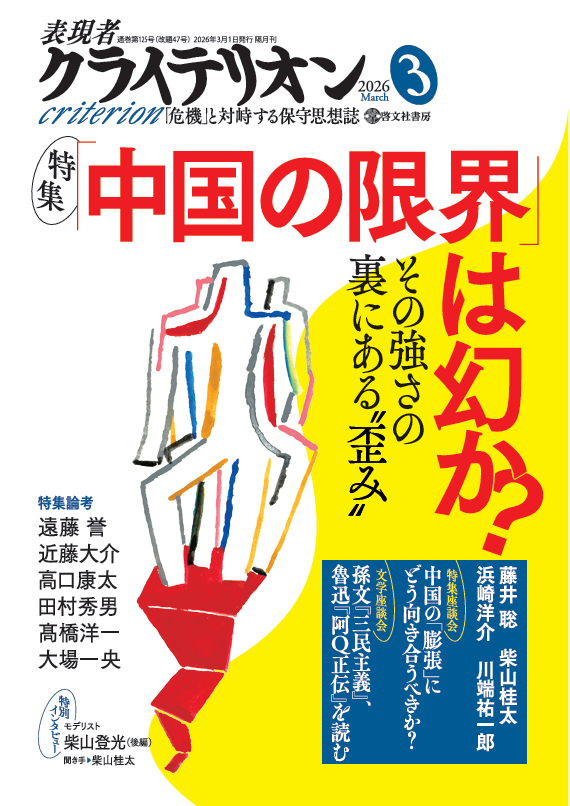
2026.02.16

2024.08.11
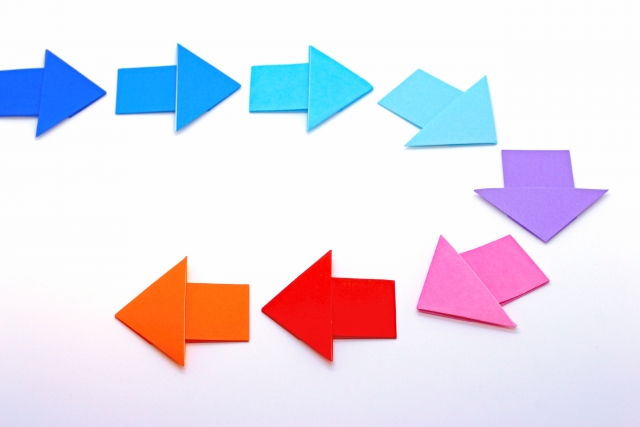
2026.02.16

2022.10.25

2026.01.20

2018.03.02