7月になった。参議院選挙が公示された。国政選挙が終わるたびに必ず「一票の格差」が憲法違反だという訴訟が起こる。判決は毎度同じで、憲法違反ではあるが選挙は無効ではないという、使い回した文章を朗読することで「儀式」は終わる。きっと、今回も選挙後の儀式があるだろう。
違憲判決が出ると、選挙区の区割りや立候補者の定員を変更して「一票の重み」ができるだけ均等になるように「是正」する。その結果、都市部の立候補者数が増えて、過疎地は減る。この調整を繰り返して、都市の声はますます強くなり有利になって、地方の声は小さくなる。一票の格差を是正することで、東京一極集中へのアクセルを踏む。
民主国家に選挙制度が必要なのは、危ない権力者の変更を可能にするからだ。権力者を変えられないと独裁になる。あいつはとんでもない奴だと思ったら、もうちょっとましなリーダーに変えることができる修正機能が、選挙制度にはある。扇動に乗せられて危険人物を選んでしまう恐れもあるが、うまくいけば軌道修正できる。
選挙や投票は、いろいろな場面で利用される。学級委員や自治会長の選出や同好会での取り決めなど、仲間で何かを決めるときにも利用される。学級委員を選ぶのはその学年のクラスの生徒たちだ。株を保有していれば、株主総会で一応の議決権がある。自治会長は地区の住民に投票権がある。スポーツ同好会でユニフォームのデザインや色を決めるときも、器具を選ぶときも投票で決めることがある。そして、どの場合も投票するには資格が要る。クラスの生徒とか、株主とか、同好会の会員とか、その組織に何らかの関係がなければ投票権はない。ただ「人間」であるというだけでは一票は与えられない。つまり「人権」だけの問題ではないということだろう。
国政選挙で「一票の重み」に差があるという場合、選出議員数と住民の人口比を問題にしている。都市部の人口が多いのだから、選ばれる議員数も多くなる。多くの人の声を反映するのが「多数決」で、都市部の住民の意見が大きくなる。東京都の人口は、最も少ない鳥取県の人口の約26倍である。2つの地域に限って単純に計算すれば、東京都選出議員が鳥取県の26倍の人数なら、両者の間は「公平」になる。人口密度で言えば、同じ面積あたりに東京都は北海道の約100倍の人間がいることになる。一票の格差で人間の数だけを基準にしたら、三大都市やその圏内だけで議員数をほぼ総取りしてしまうだろう。都市部選出の議員ばかりになって、地方選出の議員がいなくなったら、地方の意見を代弁する者がいなくなる。
抽象的な個人の権利だけしか考えないから、このような「不公平感」が生じる。株主総会では株の所有者、学校なら在校生、同好会ならクラブのメンバーが投票権を持つということは、「投票権」には、なにかの「意味」「レッテル」「色」がついているということになる。投票する個人は、「抽象的な人間たち」の中の「任意の個人」ではなく、「投票する権利」を持つ有資格者としての個人である。
国政選挙というのは、まず、国民としての資格を持っていなければならない。第一関門である。そして、次の関門は、選挙区の住民でなければならない。その土地に住んでいることが資格である。その「土地」が、投票権が意味する「色」であり「レッテル」であり「資格」である。住民票のない人間は、流浪の民であって、投票権はない。他所の土地の住民にも、その地域の投票権はない。札幌に住民票のある個人は、大阪府での選挙権はない。金沢の住民には、鹿児島県での立候補者を選べない。その地域の「住民」に対して投票権が与えられるのである。つまり、投票するときの私たちは、ただの個人ではなく、その土地を背負っているということだ。
「一票の重み」には、個人の重みだけでなく、生活の基盤となる土地の重みも含まれているのではないだろうか。何代も前から、土地は、そこに住みついた人々に恵みを与えて来た。人間と土地は、お互いに与え与えられる関係である。その地に定住し、できれば、何世代か住み続けていなければ、その土地のことを熟知できない。土地は、人間の寿命よりずっと長くそこにある。そこには人間だけでなく動物や昆虫も住んでいて、お化けや妖怪も仲間で、たまに顔を出す。土地の歴史と価値を知っている人々が、地域のことを考えてくれそうな候補者を選ぶために「選挙区」がある。
土地の価値は、それぞれである。広い水田の中には、案山子はいても人は住んでいない。農村部の人口密度は市街地より低い。水田と同じ面積が住宅地なら、何万人も住めるだろう。農地に住宅を敷き詰めたら、農産物を作れない。人が住んでいないから、農地になる。農地には、作物を生み出す力がある。それが土地の価値である。山岳地にも人は住んでいない。山麓の住民の数は少ない。それでも、山には山林がある。森に覆われた山々は水源になる。河川を作るのは山岳地帯である。過疎であるからこそ生み出す自然の価値は、その土地の価値である。鉱山は幕府の直轄地になるほど重要な土地である。その土地にしかない鉱物資源は大きな価値である。良好な港や河川は、漁や交易に欠かせない重要な土地である。人の少ないところは自然が豊かで景観に優れ、いまでは観光地やリゾート地として人気がある。自然資源は経済効果を生む。
人が居住することで価値を生み出す土地もあれば、人間が開発しないことで価値を保つ土地もある。「一票」は、さまざまな自然を擁する「土地」と結びついた人間に与えられる。「一票の重み」は、一票を持つ人間を同質なものと見做して、人間の数という数量単位に換算するが、「一票の意味」は、質の異なる土地の価値と結びつくから簡単に数量化できない。
都市部にも勿論、土地の価値はある。経済は都市を中心に動く。もともとは港湾や交通の要衝に人が集まった場所である。人が多くなれば、そこには町ができて寺社ができて商人が集まる。人の多いところには、仕事がある。そこへ行けば、稼ぎ口があり生きていける。人の集まりは人を呼ぶ。経済効果という価値があるから、人が集まる。
都市の住民は入れ替わりが頻繁である。いろいろな土地から、仕事を求めてやって来る人たちは、その時点ではディアスポラである。そのまま居着いて長く根を下ろす人もいるが、都市では土地の利用目的が時代と共に変わるから、開発や整備のために住民は流動する。住み続ける者が少なければ、土地の歴史は忘れられる。もともと棲み着いていた人も動物も少なくなり、妖怪や精霊も鳴りを潜める。ゲニウス・ロキが沈黙し、機能優先の無機質な人工物で埋まる。どこにでも見られる、似たようなショッピングセンターやビルや観光施設は、土地の個性を失わせる。野生が目の前に見えないから、人間の権利だけが気になる。人工の街の住民の思考は抽象的になる。「一票の重み」に抽象的な個人の「人権」しか見ないのは、都市化した人間の発想なのだろう。
都市の土地は「資産」であり「所有」するものである。土地が生み出す価値は「金銭的価値」であり、土地の意味するものが根本から変化する。個人は国土ではなく金銭と結びついている。ディアスポラというのは土地から離れた人々である。どこへ行っても生きられるように、世界中で通用する能力とお金に価値を認め、自分自身の実力を磨き資産を作る。たとえ、やむを得ない事情で生地を離れたとしても、離れた以上は自分だけが頼りだから、「人権」を最大化する。
人口密集地に住んでいると自分の「票」の価値が過小評価されていると思う。けれども、土地や自然に彩られていない「票」よりは、国土の自然と結びついている地方の「一票の重み」の方が何倍も重いかもしれないのだ。地方再生に力を入れるなら、人間中心の「一票の格差」を云々するよりも、土地の評価を票に与えて加重平均してみたらいい。
国政選挙で誰を選ぶかというのは、地方自治の選挙とは違う。いまは、国際情勢も考慮しなくてはならないだろう。コメも大事だし、年金も大事だ。インフレや少子化や雇用や医療や介護や増税や社会保障や安全保障……重要課題は山ほどある。だが、国内案件であっても、いまでは国際情勢と切り離せない。戦争が起これば物価が上がる。他国の紛争や貧困が、移民や難民を招く。これからの選挙は、波乱含みの世界での日本の在り方も考慮しなくてはならなくなる。歴史観や国家観を持たない候補者には任せられない。
戦争は予測がつかない。アメリカの「ミッドナイト・ハンマー作戦」には、驚いた。この時点でイランを相手にするとは思っていなかったからだ。国防次官エルブリッジ・コルビーは、著書の中で、現時点で「イランからの脅威に対処する必要は米国にはない。」と言っている。「たとえば台湾をめぐって中国を打破したあとに、イランのいかなる部隊でもすぐに排除し攻撃できる。」とも述べていて、優先事項は中国の脅威で、それに対抗するためにはウクライナでも中東でも戦争などしたくないのが本音だろう。いまのアメリカにとって、イランを侵略するのは代償の大きな失敗になるのは確実で避けるべきだが、核兵器の保有は絶対に認めないという。(『拒否戦略 中国覇権阻止への米国の防衛戦略』 日本経済新聞出版 2023 / p.409~411)
イランは最重要課題ではないという認識だが、それでも、アメリカがバンカーバスターを使ったのは、「核」の拒否に関しては本気だと示すためだろうか。空爆作戦がイランの核開発を数カ月遅らせただけなら、かえってイランの核開発の決意を強固にするだけでなく、周辺国に核拡散を促進させる恐れがあるとも言われている。空爆の評価はまだ先になるだろう。
トランプ政権もハメネイ政権も戦争をしたくなくても、その周りにはイスラエルやサウジアラビアやロシアやヨーロッパなど、多くの摂動力が働いている。ウクライナでも中東でも停戦や休戦が模索されているが、戦争をやめたくない者や、やめたら困る者は必ずいる。東アジアはもっと危ない。中国の意思とアメリカの意思だけでなく台湾や北朝鮮や、そしてロシアもいる。核を持っている国が4つも関係している。誰も戦争などしたくなくても、何が発火点になるかわからない。
21世紀が始まったとき、いまの世界を想像できた者がいただろうか。騒がしくなった世界で、不測の事態にもしっかり対処できる人物が国の代表者として選出されるなら、一票に多少の格差があっても差し支えないのではないか。大事なのは、一票の格差の是正よりも、国土を守り国民の安全を護る意思と能力を持つよい指導者が選ばれることである。
橋本由美
<事務局よりお知らせ>
~『日本の真の国防4条件』出版記念~
元陸将補・軍事評論家 矢野義昭先生による新刊『日本の真の国防4条件』の刊行を記念し、特別講座を開催いたします。
本講座では、単なる技術論にとどまらず、「核武装」の是非を思想的側面からも深く問い直します。矢野先生自らが問題提起を行い、参加者とゼミ形式で議論を交わす双方向型の講座です。質疑応答の時間をたっぷり確保。直接質問し、意見交換ができる貴重な機会です。
ご参加の皆様全員に、矢野先生の著書『日本の真の国防4条件』を一冊進呈!
日時:2025年7月12日(土)14:00〜16:00(13:45開場)
会場:日本料理 三平 7階 サンホール(新宿駅徒歩5分)
会費:一般 4,000円/塾生・サポーター 3,000円
講師:矢野義昭(軍事評論家/元陸将補)
詳細・お申込みはこちら
書籍『日本の真の国防4条件』の内容紹介はこちら

執筆者 :
CATEGORY :
NEW

2026.02.27
NEW

2026.02.26
NEW

2026.02.26
NEW

2026.02.24
NEW
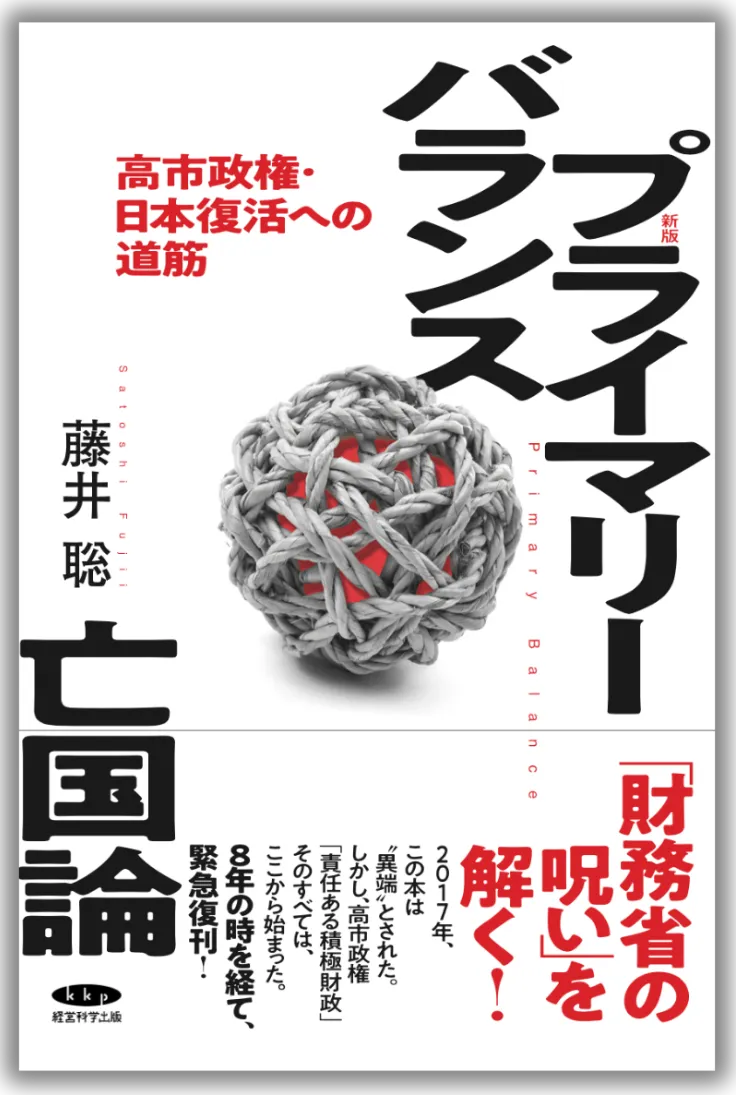
2026.02.23
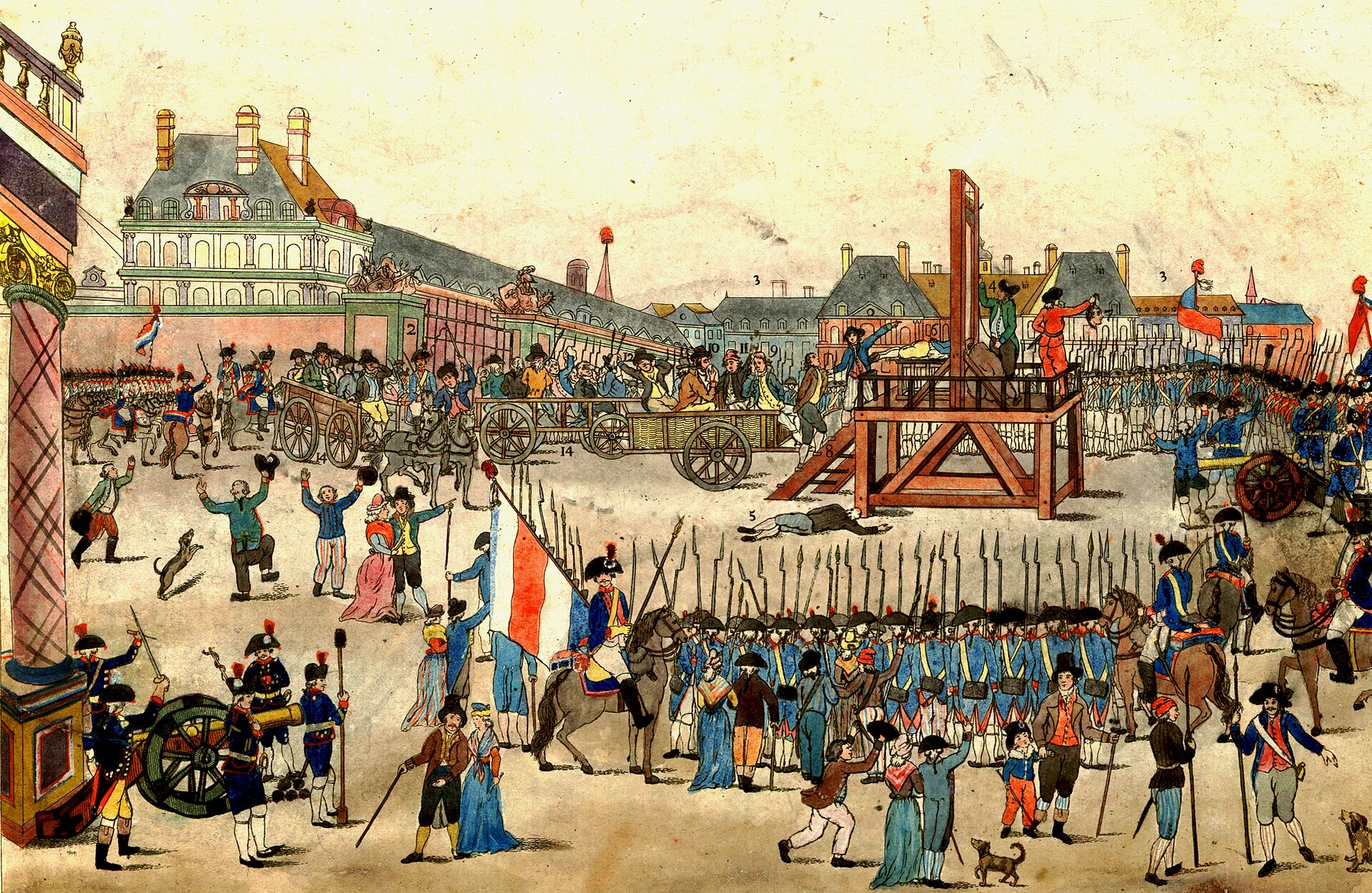
2026.02.20

2021.06.23

2021.06.22
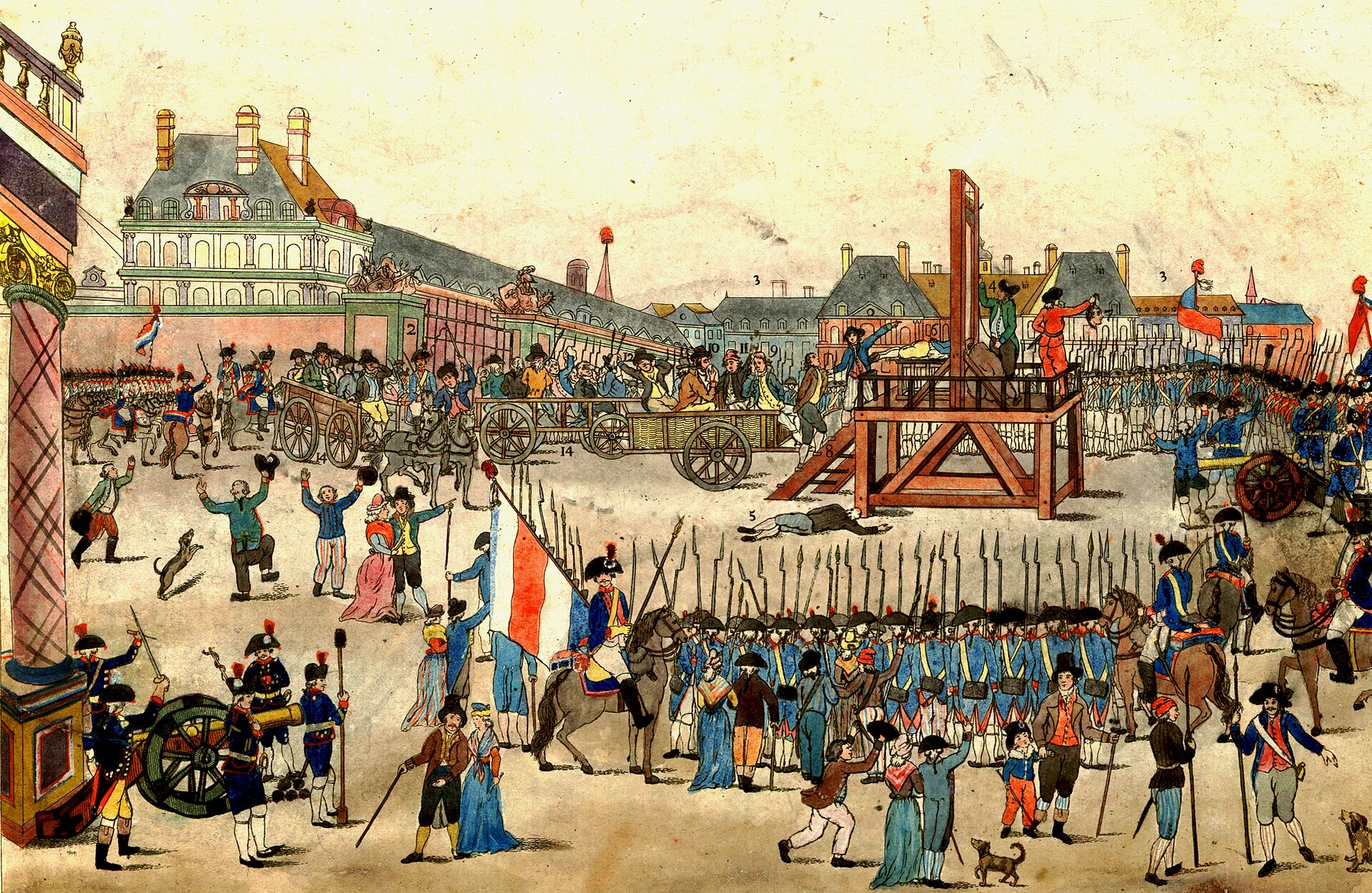
2026.02.20
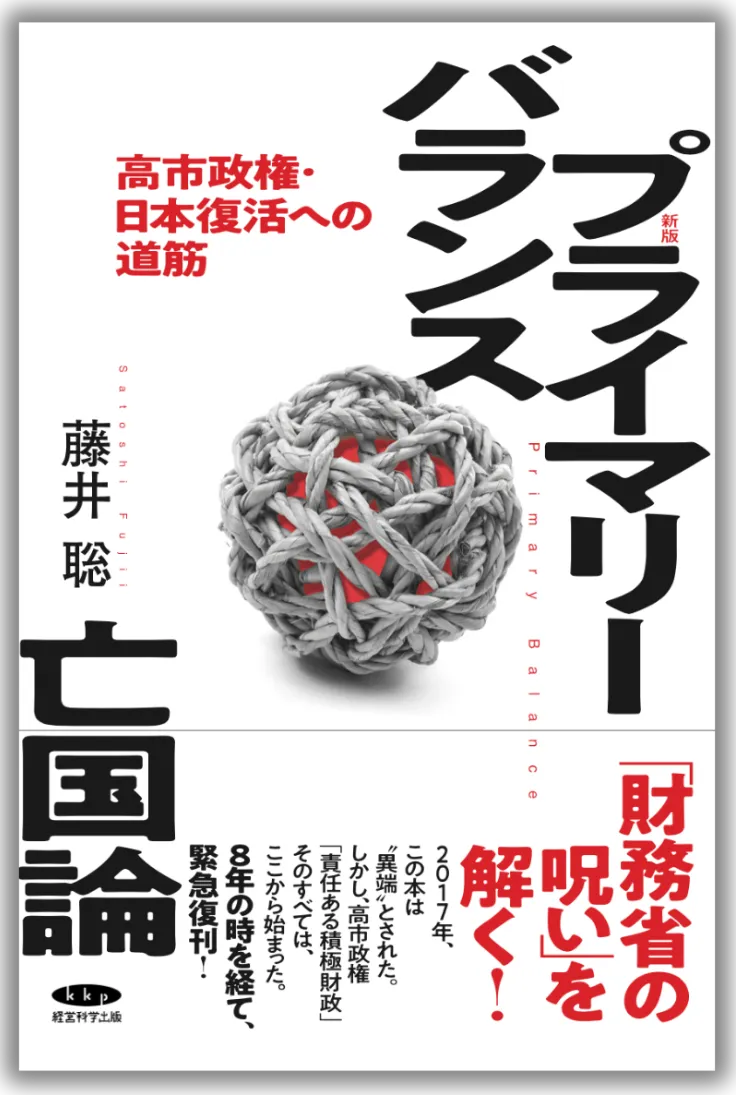
2026.02.23

2026.02.27

2026.02.26
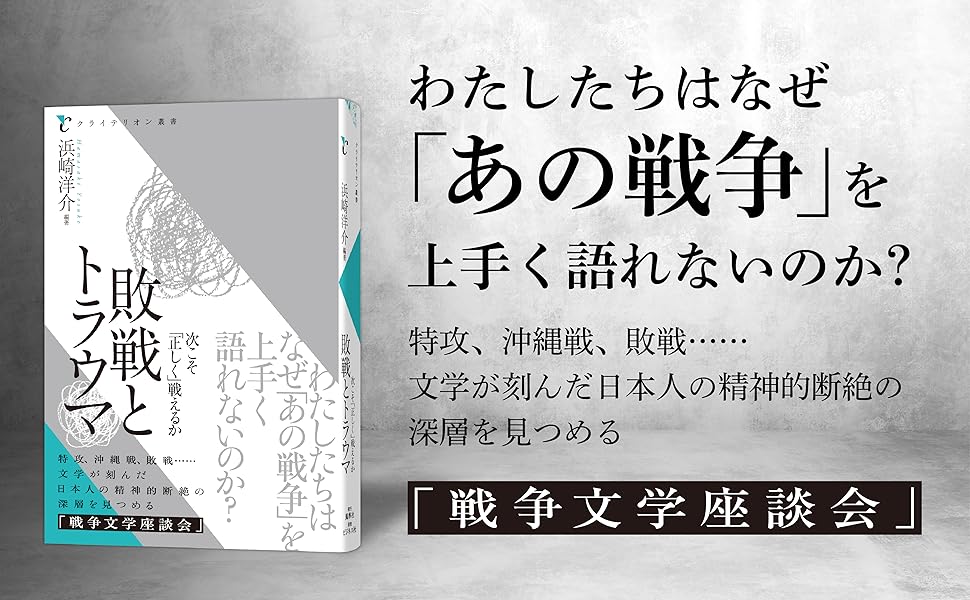
2025.08.01

2026.02.19

2026.02.11
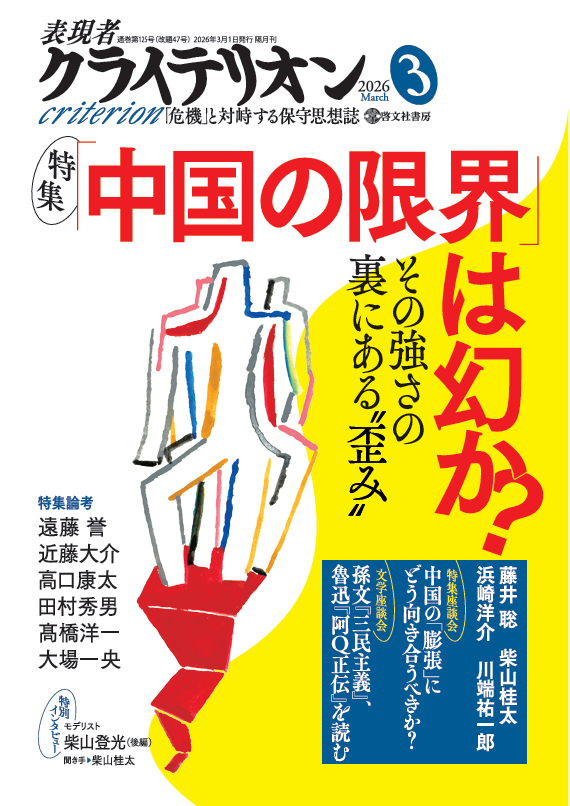
2026.02.16