
現在、『琉球新報』『沖縄タイムス』を主たる舞台に「陸上自衛隊宮古島駐屯地のトップが市民を恫喝した」として陸上自衛隊宮古警備隊長の比嘉隼人司令(1等陸佐)を非難するネガティブキャンペーンが繰り広げられています(注1)。
陸上自衛隊宮古島駐屯地では、8月5日から6日にかけて公道を使用した徒歩防災訓練を実施しました。
同訓練では、長期の台風で空港や港湾が一部損壊し、街路樹や電柱が倒れて車両での物資輸送ができない上、観光客が行方不明となり、負傷者がいる状況を想定し、5日午後7時に隊員16人が宮古島市伊良部島の長山港を出発、担架搬送訓練をしながら、隣接する下地島を含めて約35キロにわたって公道を行進、6日午前7時頃に目的地の佐良浜漁港に到着して救援、人命救助訓練などが行われました(注2)。
公道を使用する訓練に対して、現地では賛否の声が上がっています。
「ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会」(以下、「連絡会」)は1日、「(訓練は)行進ではなく行軍だ」と抗議して中止を求める会見を開き、「災害救助訓練と称しているが、紛れもなく戦場での実地訓練に他ならない。沖縄防衛局との交渉の中で『基地の外での訓練はしない』と住民に約束したことを反故にしている。島が戦場となることを前提にした、このような行軍訓練の中止を強く要請し、訓練強行には抗議する」との声明を発表しました。
訓練の当日、「連絡会」の会員らは「戦時中を彷彿とさせる行軍。島を戦場に見立てた訓練を認めるわけにはいかない」と抗議の声をあげていました。
その一方で、宮古地区自衛隊協力会や宮古島市議会防衛議員連盟、家族会などは「地形を把握しないと、災害が起きた時に対応できない」「公道使用の有無を取り上げるのはナンセンス。いざという時に対応できるよう積極的にやってほしい」として駐屯地外で行われる訓練を歓迎する意向を示し、訓練に参加する自衛隊員たちに「頑張れ」「いってらっしゃい」などと声援を送る光景が見受けられました。
公道で実施される訓練について、宮古島市の嘉数登市長は6日午前の定例会見で「南西諸島を取り巻く安全保障環境は厳しいものがある。国防の最前線に立つ自衛隊は、練度を上げる訓練は必要」と理解を示した上で「迷彩服を着た隊員がいると『何事か』となるので、地域住民に対しては、事前に説明していただきたい」と要望しました(注3)。
訓練終了後、取材に応じた比嘉隼人宮古警備隊長(1等陸佐)は、訓練への反対意見について「耳を傾け改善できるところは改善する」とした上で「自衛隊としてやらなければならないことがある。その部分については丁寧に説明しながら、今後も訓練は実施していく」と訓練の継続を明言しています(注4)。
「宮古島陸自トップが市民を恫喝した」とされるトラブルが起こったのは、徒歩防災訓練の終盤、6日早朝のことです。
『琉球新報』『沖縄タイムス』両紙が「陸上自衛隊宮古島駐屯地のトップで、宮古警備隊長の比嘉隼人司令(1等陸佐)が6日、同駐屯地が実施した訓練に対し、抗議活動をしていた市民に『許可を取ってこい』などと恫喝的な態度で詰め寄っていたことが分かった」と報じました(注1)。
具体的には、「連絡会」の会員2人が訓練の様子を撮影しようと「いらぶ大橋海の駅」の駐車場で待ち構えていたところ、徒歩防災訓練の隊員約20人が来て休憩し始め、「連絡会」の清水早子共同代表が拡声器で「奇麗な朝日に戦闘服姿は似合わない」と語りかけたのに対して、比嘉警備隊長が怒気をはらんだ口調で「そもそも(駐車場利用の)許可取っているのか」「許可を取ってこい」と怒鳴りつけたとの当日の現場の様子と、比嘉警備隊長が詰問したとされる「(『海の駅』の駐車場を利用する)許可の有無」について、実際には「許可は必要なかったこと」を施設を管理する宮古島市や県に確認した旨を伝えています。
その後、『琉球新報』『沖縄タイムス』両紙は、「連絡会」の主張を全面的に支持し、比嘉警備隊長を非難するネガティブキャンペーンを展開しています。
まず手始めに、『琉球新報』が「陸自の恫喝行為、市民の『表現の自由』侵害」と題する山田健太専修大学教授の談話を掲載しました(注5)。
山田教授は「市民の行動を制限する行為は、憲法が保障する『表現の自由』を侵害するもので極めて問題だ」「自衛隊基地からの出入りを含め隊員の行動を基地の敷地外から監視することは、市民の活動として当然に認められる」「守られるべき『表現の自由』の範囲は表現活動に限定されない。表現活動のために情報を収集する行為も活動の一環で、この範囲に含まれる」「市民は、基地の敷地内に侵入したり、軍事機密にアクセスしようとしたわけではなく、市民側に行動制限の対象になり得るような問題行動もなかった」「陸自側が、恣意的に対象を選別し、主観的な判断に基づいて当然に保護されるべき市民の活動を制限しようとしたとみられても仕方がない」「市民に歩み寄ることなく、感情的な態度で接する幹部の態度を見ていると、陸自の教育体制のあり方も疑われる。市民から監視される立場にあるという陸自側の自覚が足りなかったと言わざるを得ない」と厳しく批判しています。
山田教授の談話に加えて、同紙は「宮古陸自市民どう喝 非を認め直ちに謝罪を」と題する社説で「軍事的な実力組織である自衛隊の構成員が、一般市民を威圧する言動をとることは絶対に許されない。しかも市民が許可を得る必要のない公共の場所にもかかわらず、警備隊長は根拠のない理屈で市民を責め立てていた。非を認め、直ちに謝罪すべきだ」「自衛隊の行動を基地の敷地外から監視することは、市民の活動として当然に認められる。警備隊長の言動は、虚偽の主張を振りかざし、訓練への抗議を排除しようとした看過できない行為だ。威圧的な物言いで市民を萎縮させることの問題と合わせ、『表現の自由』の侵害につながる事態として認識すべきだ」「理解されないことへのいら立ちに任せ、自衛隊や警察が市民に敵意を向けるなど、どんな理由があろうと正当化できるものではない。今回は範を示すはずの組織の責任者が、多くの隊員を前に市民をどう喝する姿を見せたという点でも問題は深刻だ。抗議者を蔑視する風潮があるならば、とんでもないことだ」「自衛隊は批判の声にも誠実に向き合わなければならない」と論じています(注6)。
また、『沖縄タイムス』も社説で「陸自隊長が市民どう喝 この言動は行き過ぎだ」として「市民が撮影した動画には、詰問調で怒鳴り続ける姿が映っている。まさに『どう喝』だ」「憲法は『表現の自由』を保障しており、その中には政治的な表現の自由も含まれる。隊長が主観に基づいて市民を追い出そうとしたのなら、表現の自由の侵害に当たり看過できない」「一連の対応について駐屯地は『大きな音声による抗議を中止してもらうためだった』との見解を示すが、それであれば静かに話せば済むことだ」「市民に対し威圧・どう喝する隊長の姿には『おごり』のようなものもうかがえる。駐屯地側がそれをいさめるでもなく適切だったとの認識を示すに至ってはあきれるほかない」と厳しく論難していました(注7)。
『琉球新報』『沖縄タイムス』両紙は、「連絡会」の清水早子共同代表が「初めて口をきく人にいきなり罵声を浴びせられ驚いた。市民は自衛隊の部下でなく、命令される覚えはない」として発言の撤回と謝罪を求めており、比嘉警備隊長と清水早子共同代表とのやり取りの様子を動画撮影した「連絡会」の会員が「拡声器で激しく抗議したわけではない。きれいな朝日に迷彩服は似合わないと語りかけたら、司令が飛んできた」と当時の状況を振り返り、「体を鍛えた自衛官が自分の意に添わないからと恫喝、威嚇するような態度を取った事に自衛隊の本質を垣間見た」と話したと報じています。
『沖縄タイムス』の取材に対して同駐屯地は、「(比嘉警備隊長の対応は)周辺施設への迷惑を考えて大きな音声による抗議を中止してもらうためであり、適切であった」と説明していますが、「連絡会」は「拡声器は使ったが、決して大きな音声ではなく控えめに話した。警備隊長の怒鳴り声の方がよほど大きかった」と反発し、「比嘉隊長は私たちの声の大きさを注意していなかった。駐屯地の説明は全く当たらない」と批判しています(注8)。
「連絡会」の清水早子共同代表らは9日、抗議声明と公開質問状を準備して宮古島駐屯地を訪ねて比嘉警備隊長との面談、発言の撤回と謝罪を要求しましたが、不在を理由に面談は叶わず、改めて8月19日に同駐屯地で面談の機会が設けられることになりました(注9)。
8月19日の面談の場において、比嘉警備隊長は「連絡会」の清水早子共同代表らに対して「威圧的だと捉えられたのなら私の本意ではなく、そのことについては申し訳ございませんでした」と限定的に謝罪し、「許可を取れ」と恫喝したとされていることについては、「周辺施設への迷惑と隊員の安全に配慮し、拡声器を用いた活動のための駐車場の使用許可を緊急的に確認した」と釈明しました(注10)。
抗議文と公開質問状を手渡した清水共同代表は面談の終了後、比嘉警備隊長の姿勢を「開き直りだ」と断じて謝罪とは認めず、「紋切り型の答弁で全く誠意が伝わらなかった。有耶無耶にすると居丈高な物言い、恫喝するようなことが当たり前になる。今後は法的な措置を含めて検討したい」と述べており、仲里成繁共同代表は「信頼できる組織でないことが分かった。おうむ返しで謝罪ではなく、ただ駐屯地で面談をしただけだ」と振り返りました。
この度の騒動の様子を「連絡会」が動画撮影して『沖縄タイムス』『琉球新報』両紙に提供しており、『沖縄タイムス』は、その動画を自社の公式動画チャンネルで公開した上に、ご丁寧にも比嘉警備隊長と「連絡会」の清水早子共同代表とのやり取りの文字起こしまでしてくれています(注11)。
『沖縄タイムス』が公開した動画では、その状況に至るまでの経緯と背景を考慮することがなければ、比嘉警備隊長が「市民」に対して「威圧的」と受けとめられ、「恫喝」と表現されても致し方ない強い口調で語りかけていることを確認することができます。
その事実を思慮すると、比嘉警備隊長が「威圧的だと捉えられたこと」について限定的に謝罪したことは(騒動を早期に収束させるための)妥当な判断であるように思えます。
しかしながら、そもそも今回の騒動の原因が、比嘉警備隊長ではなく「連絡会」側にあることは明らかであり、私自身の個人的な感情としては、活動家の集団である「連絡会」の理不尽な挑発に対峙せざるを得ない状況に遭遇し、本来であれば、する必要もない謝罪をしなければならない事態に追い込まれてしまった比嘉警備隊長に対する同情を禁じ得ません。
「連絡会」は「拡声器は使ったが、大きな音で抗議はしていない」と言い訳をしていますが、朝日が昇る早朝の時間帯(午前6時過ぎ)に拡声器を使って呼びかけること自体が非常識な迷惑行為であることは子供でも分かる自明のことです。
現場となった「いらぶ大橋海の駅」の近隣(半径約100mの範囲)には複数のホテルがあることから、(動画で確認できる)比嘉警備隊長が「(近隣に)ホテルあるだろ、ホテル!」「(抗議活動の)許可取っているのか」と「連絡会」の清水早子共同代表を問い質したことは、強い口調で言葉足らずであることは否めないものの、同駐屯地のマスコミに対する説明や比嘉警備隊長自身による釈明と矛盾なく合致しており、決して理不尽な恫喝などではありません。「周辺施設(ホテル)に迷惑がかからないように」「入隊して間もない新隊員たちを守らなければ」と考えての言動であったことは明らかです。
この度の騒動の当事者である「連絡会」は、以前の記事で取り上げた、今年の宮古島トライアスロン大会で宮古島駐屯地の自衛隊員が迷彩服を着て支援活動を行うことに対して「組織ぐるみの懐柔策だ」と抗議した組織です。また、前回の記事で取り上げた8月31日に開催予定の「日米ジョイントコンサート」に抗議している団体は「日米合同音楽会に抗議する実行委員会」との名称になっているのですが、「連絡会」のFacebookページで「日米ジョイントコンサート」に対する抗議活動への参加を呼びかけていることなどから、同一の組織が(抗議する対象にあわせて)名称を変えて抗議活動を展開しているか、少なくとも緊密な関係があるものと推察されます(注12)。
すなわち、「ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会」は、良識ある「一般市民」の集まりではなく、「市民」を騙る活動家の集団であり、彼らが極端で非現実的な「反戦平和」思想に基づき展開している一連の抗議活動が「常識(コモンセンス)」からかけ離れていることは明らかです。
そしてまた、この度の騒動をめぐる『琉球新報』『沖縄タイムス』両紙の報道には、報道機関として真摯に事実と向き合い、「何故、今回の騒動が起こってしまったのか」を検証しようとする姿勢が見受けられず、「連絡会」の主張を鵜呑みにして自衛隊と比嘉警備隊長を非難する論調に終始しており、あたかも「連絡会」のスポークスマンであるかの如くであり、「報道が偏向している」と言って過言ではありません。
これまでにも何度か拙稿で言及したことがありますが、沖縄県では、様々な要因が重なり合って地元紙である『琉球新報』『沖縄タイムス』が圧倒的なシェアを占めている寡占状態にあり、最近ではネットなどを活用して全国紙の記事を読む人が増えてきてはいるものの、全国紙がほとんど読まれていないという、他の都道府県では見られない「特殊な新聞事情」があることが良く知られています(注13)。
『琉球新報』『沖縄タイムス』両紙のネガティブキャンペーンによって、比嘉警備隊長に対する非難の声や自衛隊に対する否定的な感情が広がってしまうのではないかと懸念していました。
恐らく、「連絡会」や『沖縄タイムス』『琉球新報』は、動画を公開することで多くの人々が比嘉警備隊長や自衛隊そのものを非難するように仕向けて、自衛隊に対する抗議活動や反戦平和運動に対する賛同を集めようと目論んでいたものと思われます。
しかしながら、厳密な検証をした訳ではなく、あくまでも本稿を執筆している時点において私自身が受けている印象でしかないのですが、例えば、『沖縄タイムス』が公式動画チャンネルで公開した動画に寄せられている数々のコメントのように、どちらかと言えば、この度の騒動をめぐっては、比嘉警備隊長を擁護し、非常識な抗議活動をする「連絡会」に対して批判的な声が多いように見受けられます。
今後、この度の騒動がどのように推移していくのか、現段階ではまだ予断を許しませんが、彼らの非常識で卑劣な目論見が崩れ去ることを願わずにはいられません。
『八重山日報』(8月12日)に掲載されたメルレ祐子氏の寄稿「陸上自衛隊宮古島駐屯地の隊員達を身体を張って守った比嘉司令の勇気」が、今回の騒動について非常に分かりやすく論じています(注14)。
まず、自衛隊の徒歩防災訓練を撮影しようと、ご苦労なことにも早朝から道の駅の駐車場で待ち構え、拡声器を使って言わんでも良いことをわざわざ言う必要があったのか。そこが事の発端である。常識的に考えたら、あのようなことは言う必要も言う権利も全くないことであった。
市民団体側の主張として、拡声器で激しく抗議したわけではない、語りかけただけだとのことだが、これは激しい声であろうが穏和な声であろうが声のトーンが問題ではないのだ。何度も言うが「人権」として認められていること(公道を歩いて歩行訓練をする、制服である迷彩服を着る、朝日を眺める、通行の妨げになっているわけではない中で、道の駅の駐車場で小休止をとる 引用者註)に対して、拡声器を使って抗議し、かつ穏和なトーンであったかもしれないけれども人の心に突き刺さる言葉の凶器を持って隊員達を侮辱したと言うこと。
厳しい訓練のゴールが見えた新隊員たちの歓喜に溢れるその輪に向かって、いきなり拡声器で人権を侵害する言葉をぶつけられたら、隊員たちに湧き上がる怒りと悲しみの入り混じる複雑な感情がどれだけのものか、わからないのか。それを爆発させることができない自衛隊員達を知っていて、それを逆手に取って故意にあのような言葉をぶつけてきたとしたらそれは悪質だ。あの場で隊員達を守ってあげられるのは司令しかいなかっただろう。
冷静さを失うような人が上官でいいのか、などという発言が記事に載っていたが、それは違う。あの場で最高上官である司令が声を荒めて抗議しなかったら、若い隊員達の精神は壊れていたかもしれないのだ。そして近隣住民へかかる騒音迷惑も最短時間の最小限に食い止め、この場を収めるために声を荒めたと思われる。司令とてこれが後で問題になるかもしれないことを充分に分かっていながら、この行動に出たのは相当の勇気と決断が要ったと思う。
今回も先に仕掛けて行ったのは市民団体の方だ。それを棚に上げて自衛隊に謝罪を求めるのは筋が違う…(自衛隊員達は)日々命懸けの訓練をこなし命懸けで任務に就いている。ただ自分の意に反するからと言って部外者が遊び感覚で乱入してきて隊員の精神を搔き乱すような妨害は常識ある大人のすることとは思えない。拡声器で抗議した女性の年齢からして、訓練に参加していた新人隊員は孫の年代だ。自分の孫に同じことを言えるか。(太字引用者)
この度の騒動の推移を見ていく過程で、小幡敏氏の論稿「現場指揮官に見る指導者の条件」(本誌2024年9月号)における「言うなれば、小隊長こそが、世にあるすべての地位役職の中で、最も純粋な指揮官であり指導者である」との言葉を思い出しました(注15)。
小幡氏は、同論稿の「小隊長(現場指揮官)としての生き方」の節で、次のように述べています。
行軍の辛さはやってみなければわからない。池田(元陸軍少佐 引用者註)は足中マメだらけにして、ヨーチンを含ませた木綿糸を針で真皮と表皮の間に通しつつ歩いたというが、柔軟性のない軍靴で歩き続けると、一歩ごとに灼ける様な痛みが来る。肩には背嚢や銃の負い紐、装具が食い込み、ごつごつしてバカに重い鉄帽が頭にのしかかる。夏でも腕まくりさえ許されず、体中蒸れ、背中は始終虫が這いまわるように痒い。一時間に十分の休みは前後の準備を除けば実質七分もない。その間に足の手入れや飲水、小用をしながら少しでも休憩を取るが、小隊長は隊員に異常がないかを見て回る。痛い、一刻でもいいから荷物を降ろしたい。ところがどっこい、小隊長にはろくろく休み時間さえ許されていない。
小隊長(新品少尉)というのは、実に辛い。私の軍務経験は五年に過ぎないが、小隊長の辛さというのは特異的だと断言出来る。あれほど逃げ場のない、度胸と根性、気転と要領が試される役割は他にない。ごまかしというのは凡そ通用しないのである。寝食をともにする部下の目が常に注がれている。寝るのも食べるのも、自由ではない。三日寝ていなくても、部下を先に寝かす、どれだけ疲れていても、涼しい顔で先頭を行く、そういうことが全て出来たとはとても言えないが、そういうつもりでやらねば務まらぬのが小隊長という役割である。
現在、我が国では緊迫化する国際情勢、特に「台湾有事」に対する懸念の高まりを背景にして「南西諸島の防衛力強化」が進められており、防衛費の増額、防衛装備品の強化が図られていますが、それに併せて、自衛隊員たちが本来担うべき国防の任務に専心することができるような状況を整えていかなければならないのではないでしょうか。
「表現の自由」が認められている以上、非現実的な妄想に囚われている「連絡会」のような反戦平和運動家・活動家達の言論活動そのものを封じ込める訳にはいきません(封じ込めるべきではありません)が、そのことが「反戦平和」のお題目を掲げてさえいれば「理不尽な抗議活動が許される」ということを意味している訳ではなく、理不尽な抗議活動によって自衛隊や自衛官が虐げられるようなことがあってはならないことは自明の理です。
今回の騒動について、中谷元防衛相が8月8日午前の記者会見で「現地で市民の方々との間でやりとりがあったと承知している。詳細な事実確認を進めている」と述べていますが、本稿を執筆している時点において、政府と自衛隊が「どのような見解を持ち、どのように対処するのか」という方針は未だ明らかにされていません(注16)。
前述したように、8月19日に比嘉警備隊長が「連絡会」に対して「威圧的だと捉えられたこと」について限定的に謝罪しましたが、彼らは比嘉警備隊長の姿勢を「開き直りだ」と断じて謝罪とは認めておらず、「法的な措置を含めて検討する」とほのめかしています。
今後さらに比嘉警備隊長に対する何らかの処分や処罰を求めるなど理不尽な要求を突き付けてくることも想定しておかなければならないように思えます。
この度の騒動において責められるべきは、反戦平和活動家たちの挑発に乗せられてしまい、部下を守るために行動した隊長ではなく、常識(コモンセンス)からかけ離れた抗議活動をする反戦平和活動家たちであることは火を見るよりも明らかです。
政府や自衛隊が、反戦平和活動家たちの理不尽な要求に屈して、正当な理由なく比嘉警備隊長を処分したり、処罰するようなことがあってはなりません。
政府と自衛隊に対して、若い隊員達を守った隊長を守ることを望みます。
——
(注1) 「許可を取ってこい」陸自隊長が市民を恫喝 宮古島徒歩訓練中、許可不要の場所で【動画あり】 | 沖縄タイムス+プラス
(注2) 徒歩訓練中止求める 宮古 陸自に市民ら抗議 | 沖縄タイムス+プラス
(注3) 宮古島市長、陸自の公道訓練に理解示す 事前の説明を要望 沖縄 – 琉球新報デジタル
(注4) 陸自の徒歩訓練「今後も」 宮古島駐屯地司令が明言 沖縄 – 琉球新報デジタル
(注5) 【識者談話】陸自の恫喝行為、市民の「表現の自由」侵害 山田健太氏(専修大教授) – 琉球新報デジタル
(注6) <社説>宮古陸自市民どう喝 非を認め直ちに謝罪を – 琉球新報デジタル
(注7) [社説]陸自隊長が市民どう喝 この言動は行き過ぎだ | 社説 | 沖縄タイムス+プラス
(注8) 陸自、市民への恫喝は「適切だった」 大音声による抗議を制止と説明 市民は反発「声量の注意はなかった」【動画あり】 | 沖縄タイムス+プラス
(注9) 陸自隊長による恫喝 宮古島の市民が謝罪を求め駐屯地へ 休暇中と言われ、後日面談を要望「出向いて謝るべき」 | 沖縄タイムス+プラス
(注10) 陸自宮古島司令が限定的に謝罪 「威圧的なら本意ではない」 市民は法的措置も検討へ | 沖縄タイムス+プラス
(注11) 「ホテルあるだろ、ホテル!」「市民のものじゃない」 宮古島・陸自隊長と市民のやりとり
(注12) 【藤原昌樹】またもや「沖縄の自衛隊差別」を助長する在沖マスメディア ―なぜ、彼らは自衛隊を目の敵にするのか― | 表現者クライテリオン
(注13) 【藤原昌樹】わたしたちは沖縄人か、日本人か -大規模世論調査に見る沖縄人のアイデンティティと世代間ギャップ- | 表現者クライテリオン
(注14) メルレ祐子「陸上自衛隊宮古島駐屯地の隊員達を身体を張って守った比嘉司令の勇気」『八重山日報』2025年8月12日
(注15) 小畑敏「現場指揮官に見る指導者の条件」
(注16) 中谷防衛相「市民とのやりとりあったと承知」 宮古島陸自トップの「恫喝」問題に言及 | 沖縄タイムス+プラス
(藤原昌樹)
<編集部よりお知らせ1>
クライテリオン叢書第5弾、『敗戦とトラウマ 次こそ「正しく」戦えるか』発売中です。
お読みくださった方、ご感想等、AmazonレビューやSNS等で発信していただけると大変励みになります。
よろしくお願いいたします。
|
|
敗戦とトラウマ |
執筆者 :
CATEGORY :
NEW
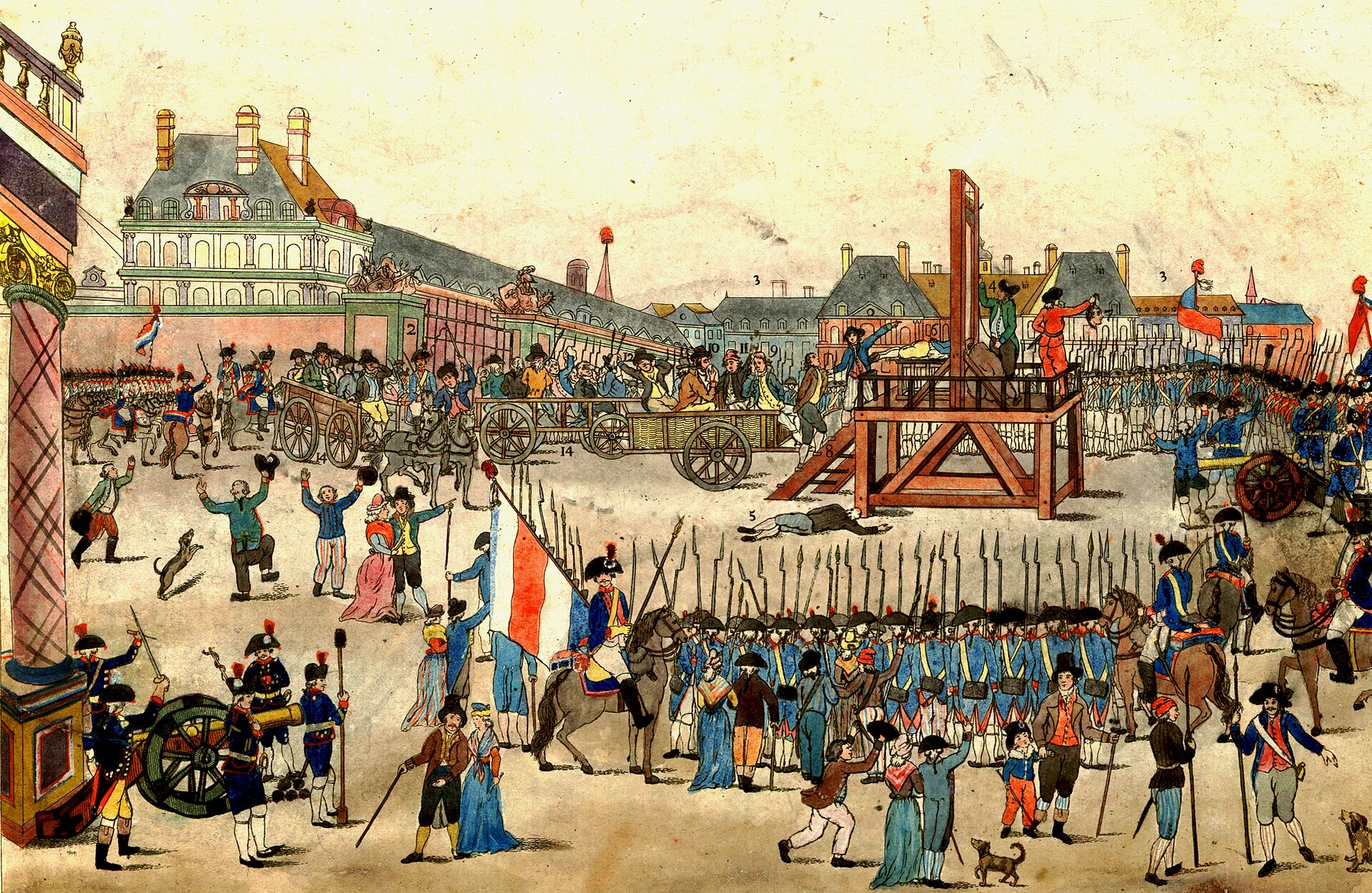
2026.02.20
NEW

2026.02.19
NEW

2026.02.18
NEW
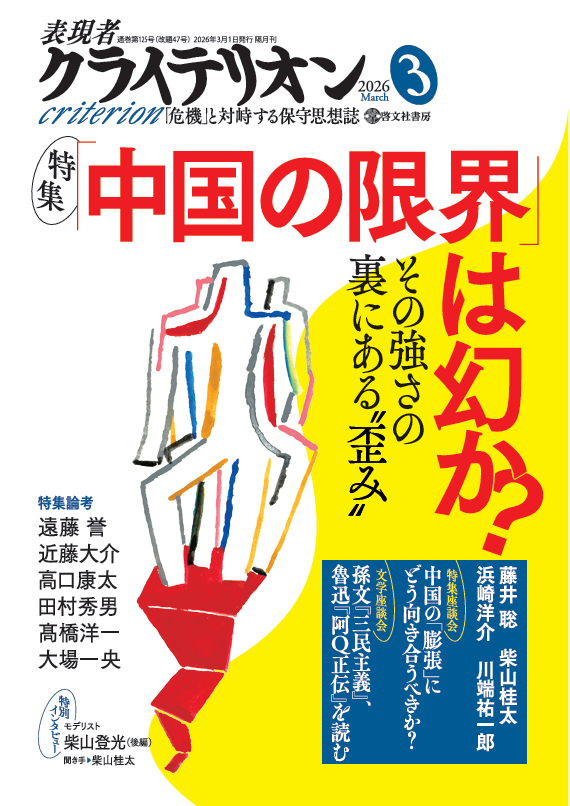
2026.02.16
NEW
.png)
2026.02.16
NEW
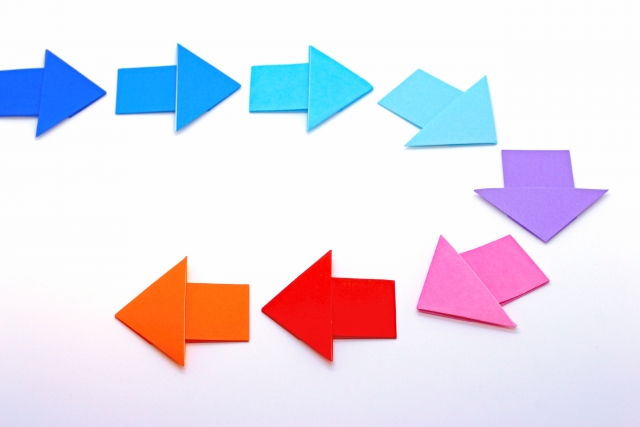
2026.02.16

2026.02.19
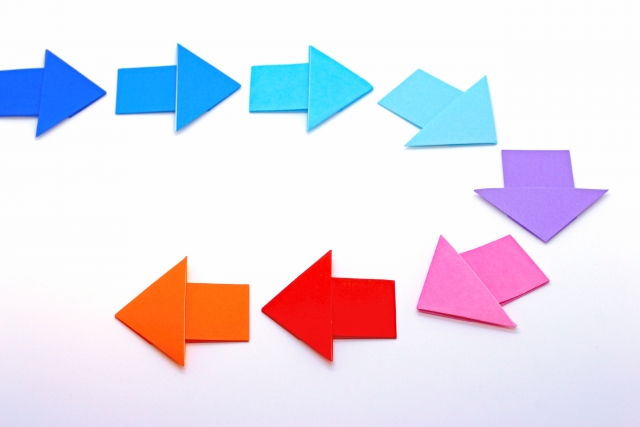
2026.02.16
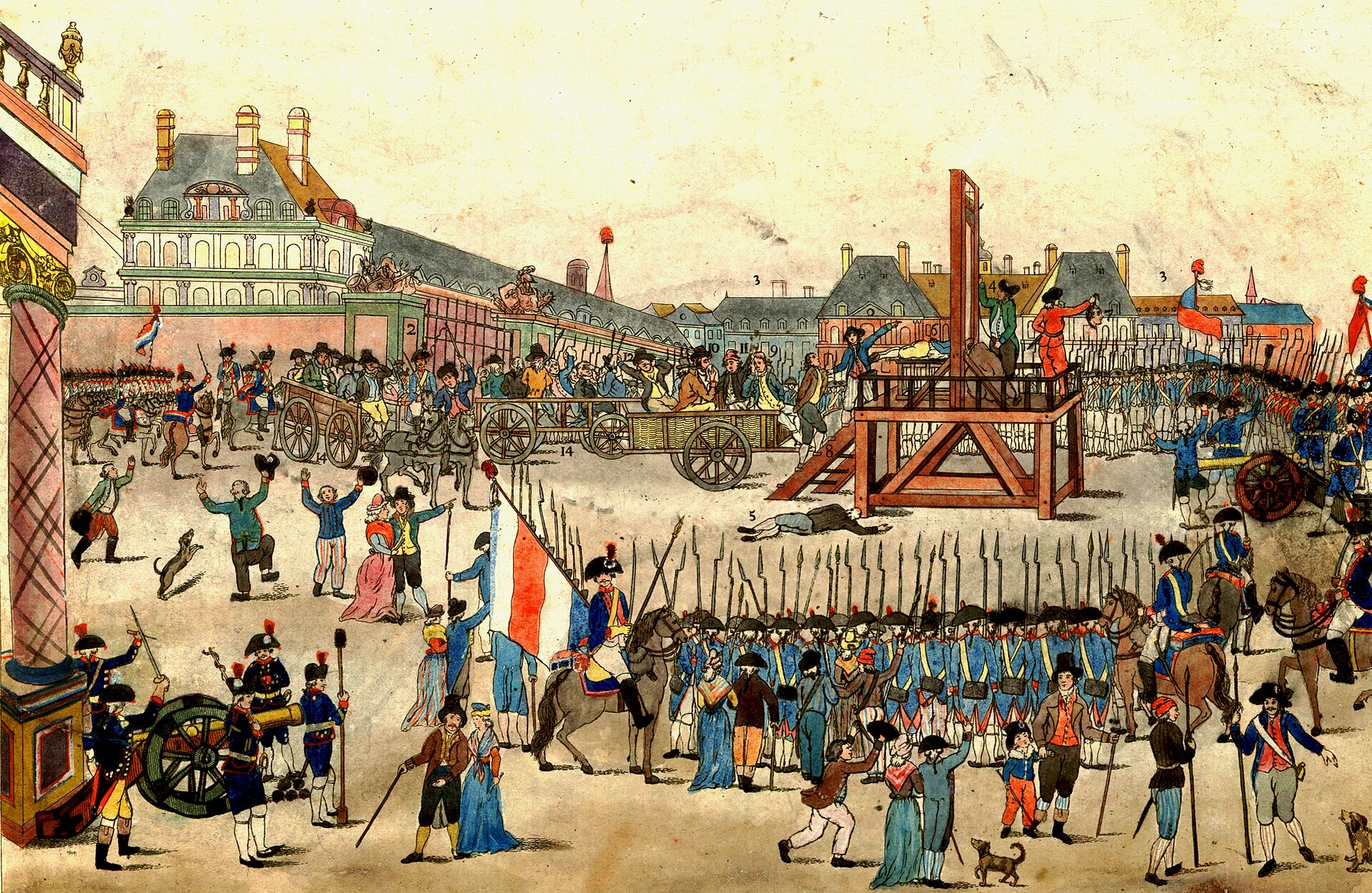
2026.02.20
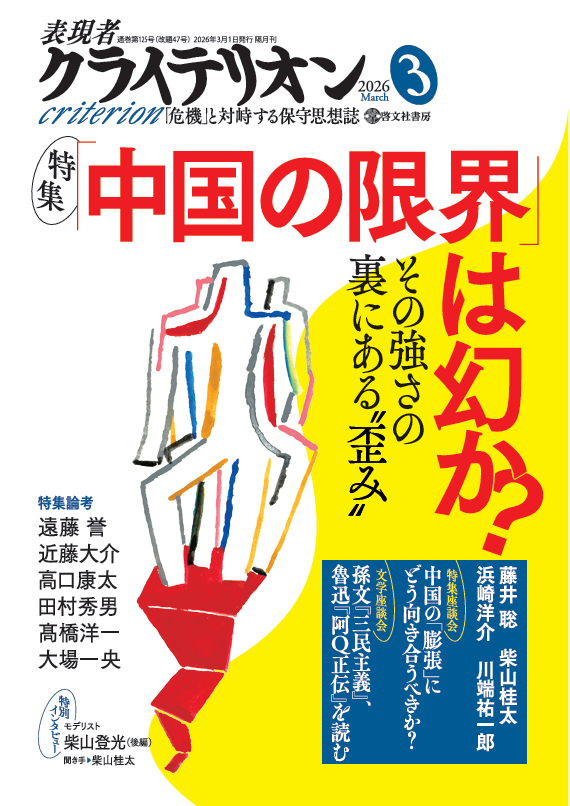
2026.02.16

2026.02.11
.png)
2026.02.16
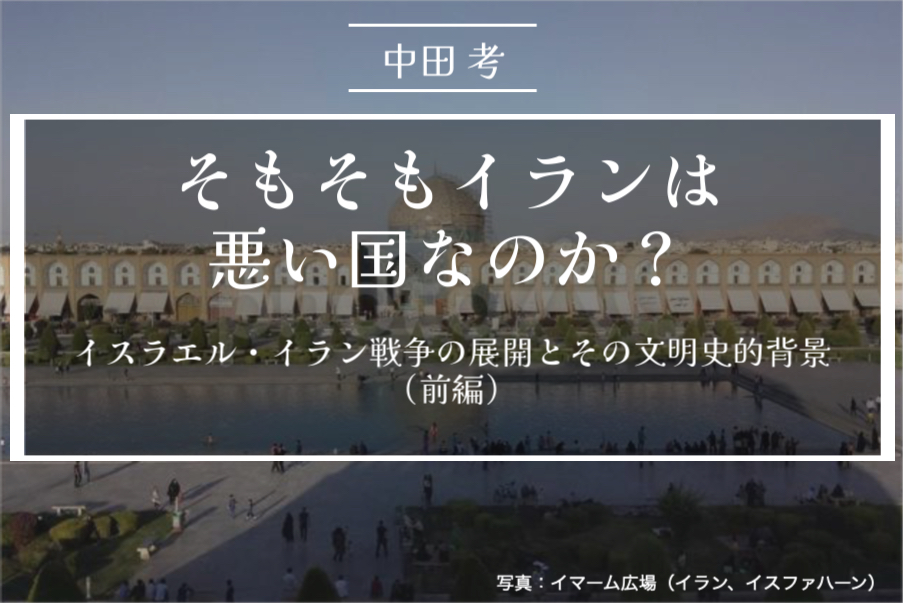
2025.06.24

2026.02.13
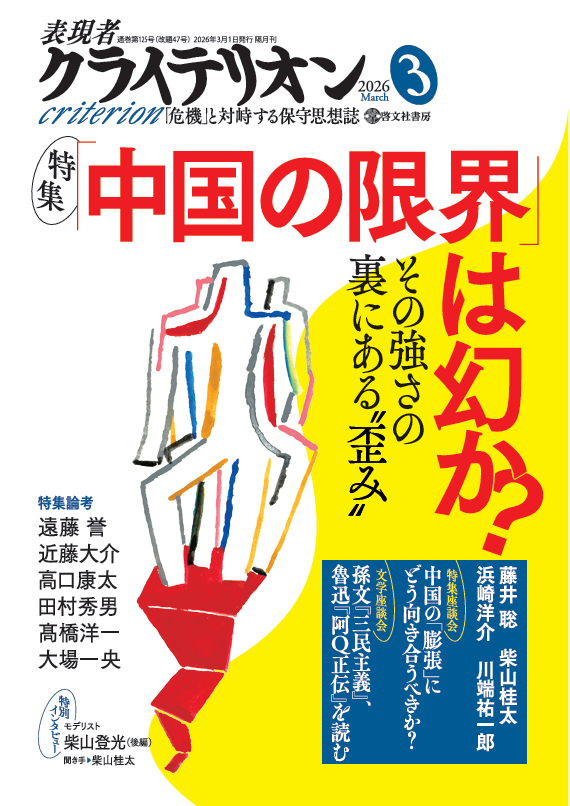
2026.02.16

2026.02.12