本日は10/16発売の最新号『表現者クライテリオン 11月号 この国は「移民」に耐えられるのか?』より、巻頭コラム「鳥兜」をお送りいたします。
移民先進国の欧州の惨状をレポートした『西洋の自死──移民・アイデンティティ・イスラム』 (原著二〇一七年)のなかで、ダグラス・マレーは、その「自死」を呼び寄せるまでに過激化したリベラリズムに身を任せてしまった欧州について、その病根を二つ指摘していた。
一つは、日本人にも身に覚えがあるところの「歴史的罪悪感」である。要するに、西洋の植民地支配、帝国主義的拡張、ホロコーストを引き起こしたユダヤ人差別などに対する欧州自身の歴史的自己嫌悪である。その罪悪感によって、自分自身に自信が持てなくなった西洋人は、移民の受け入れを拒むことができなくなってしまったと言うのだ。
そして、もう一つの病根が──こちらの方がより根が深い問題なのだが ─「普遍的人権」「寛容」「多様性」などのリベラリズムを価値とする「西洋啓蒙思想」の問題である。
啓蒙思想の問題は、「リベラリズムは失敗した。 〔…〕 成功したために失敗した」(P・J・デニーン『リベラリズムはなぜ失敗したのか』) と語る、アメリカの「ポスト・リベラル右派」の議論とも相即しているが、要するに、それは、そのイデオロギーを純化すればするほど、必ず「失敗」するという「リベラリズムの逆説」についての認識である。
たとえば、リベラル(Liberal)という言葉が、その政治的意味を帯びはじめるのは「新プロテスタンティズム」 (特に、洗礼主義などのピューリタニズム) が登場する十七世紀以降のことだと言われるが、それはまさに、リベラリズムが、カトリックと結んだ専制国家から、個人の「信仰の自由」を守ろうとする政治的主張から生まれたことを示している。要するに、その台頭ズムとは、「~からの自由(消極的自由) 」 (アイザイア・バーリン)を理論化する態度として現れていたということである。
だが、そこにこそ、リベラリズムの逆説と、その頽廃の芽も孕まれていた。はじめ、カトリックからの自由を唱えていたリベラリズムは(十七世紀/ピューリタン革命) 、次第に「伝統」からの自由を唱えはじめ(十八世紀/フランス革命) 、ついには、「信仰」からの自由まで唱えはじめるのである (十九世紀/社会主義と共産主義)。
しかし、「信仰のための自由」が「信仰からの自由」に反転してしまえば、私たちがその「自由」を使って守るべき価値 (その信仰と生き方) を失ってしまうのは必然だろう。自己目的化された「自由」が導くのは、「価値判断は誤りであるという価値判断」、あるいは、他者 (移民) に無限に自己を譲り続ける「実存的ニヒリズム」でしかない。
これは、移民大国への道を進みつつある日本も他人事ではないだろう。にもかかわらず、リベラルは、「神はいない、思い悩むのはやめて、人生を楽しもう」 (『西洋の自死』) と語りながら、神なきエゴイストの主張を「人権」の名の下に擁護し、他者に譲り続ける自己喪失を「寛容」と言い換え、秩序なき喧騒を「多様性」と呼び変えながら、その実、人が「安価な労働力(モノ) 」として扱われることに異論を差し挟もうとはしないのである。
おそらく、私たちが「実存的ニヒリズム」に陥るのか、それとも、その「人格」を守ることができるのか、それを分けるクリティカル・ポイントは、私たちのなかに、「安価な生活」と「幸福な生活」とを見分ける力が残っているのか否かにある。アリストテレスによれば、「幸福」を作り出せるのは「よい人間」だが、その「よい人間」は「よい共同体」からしか生まれはしないのだ。その重い事実を日本人は忘れるべきではない。
<編集部よりお知らせ>
最新刊、『表現者クライテリオン2025年11月号 この国は「移民」に耐えられるのか?ー脱・移民の思想』、好評発売中!
よりお得なクライテリオン・サポーターズ(年間購読)のお申し込みはこちらから!サポーターズに入ると毎号発売日までにお届けし、お得な特典も付いてきます!。
サポーターズPremiumにお入りいただくと毎週、「今週の雑談」をお届け。
居酒屋で隣の席に居合わせたかのように、ゆったりとした雰囲気ながら、本質的で高度な会話をお聞きいただけます。
執筆者 :
NEW

2026.01.23
NEW

2026.01.23
NEW

2026.01.22
NEW

2026.01.20
NEW

2026.01.18

2026.01.16

2026.01.18
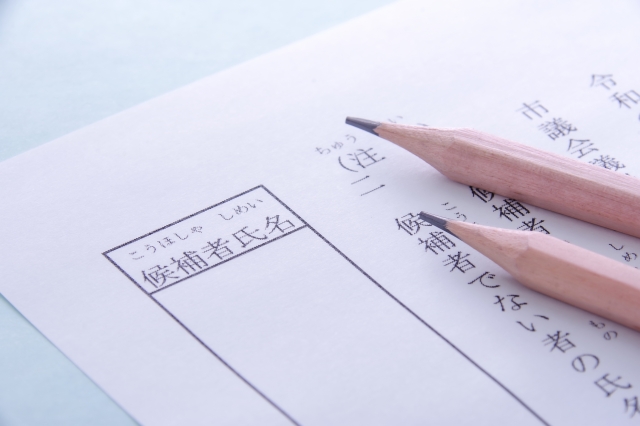
2026.01.13

2026.01.20

2026.01.16

2024.08.11

2026.01.22

2026.01.15

2018.09.06

2026.01.23

2026.01.23