私たちの「からっぽ」を 乗り越えるために
戦後日本人試論 岸田文雄首相の顔に象徴されるところの「からっぽ」……。それはどのような経 験に由来し、どのような選択の積み重ねによって現われ出たものなのか。その経 緯を振り返りつつ、私たちの顔に張り付いた「仮面」を振り捨てる方途を考える。
Ⅰ 盲人もし盲人を導かば穴に落ちん ──依存症国家ニッポンの今
五十年以上も前に、すでに三島由紀夫は書いていた、 「このまま行ったら『日本』はなくなってしまうのではないかという感を日ましに深くする。日本はなくなって、その代わりに、無機的な、からっぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜け目がない、或る経済的大国が極東の一角に残るのであろう」(「果たし得ていない約束」昭和四十五年) と。
あの岸田文雄首相の凡庸な顔を見ていると、三島の予言の正しさを感じる。
三島が言う「日本」とは、一言で言えば、それ固有の生き方を持った文化であり、その柔軟性と一貫性によって、自らの強度を高めようと努力してきた有機体である。が、果たして、岸田政権のなかに、何かしらの有機性を思わせる全体的な命の手触りは存在しているのだろうか。
自民党総裁選で「所得倍増」(賃金倍増)を掲げながら、総裁選が終わってしまえば、いつの間にやら、それを「資産所得の倍増」へと誤魔化し、さらには、そんな言葉も忘れた頃に、「異次元の少子化対策」を大義名分に、コストプッシュインフレ下での増税をちらつかせるという支離滅裂ぶり。要するに、自民党に向けては「所得倍増」の仮面を被り、国民に向けては「異次元の少子化対策」の仮面を被り、財務省に向けては「増税」という名の仮面を被っているというだけのことにすぎないのだろうが、そのなりふり構わぬ八方美人ぶりこそが、岸田文雄の「聞く力」だったのだということが改めて分かる。
もちろん、岸田政権の「統合失調」ぶりは、経済政策に限らない。
過去には、SARSやMERSなどと同じ感染症二類指定にコロナを留め置きながら、訪日外国人を受け入れるという何がしたいのか分からない判断もあったが、さらに今回、過去最高の死亡者数を記録している最中での感染症五類指定(インフルエンザレベル)への移行は、世間の空気を読むことしかできない岸田文雄政権の弱さを如実に示している。
しかし、今回のコロナ騒動で目立ったのは、世間の空気に振り回される政権の優柔不断ぶり以上に、政府の指針なしには何も判断できない日本国民のあなた任せの生き方でもあった。たとえば、「個人の主体的判断を尊重する」というマスクのルールに関して、日本人は、「主体的判断」どころか、自分の本音を隠してもなお政府や専門家の「推奨」に従い続けるという依存性を見せたのである。政府は世間や専門家の顔色を窺って政策を決め、世間は政府や専門家の方針に従って自らの振舞を決め、肝腎の専門家は閉じた業界の権威にのみ従って判断を定めていく……、この、誰もが「主体的判断」を見失ったかのような悪循環のサイクルのなかに日本があるのだとすれば、それこそ日本は、「盲人もし盲人を導かば穴に落ちん」という聖書の警句そのままの状況に嵌り込んでいると言って差し支えあるまい。
なるほど、他者への「配慮」や「気遣い」は確かに日本人の美徳である。が、それも行きすぎれば他者の顔色を窺うだけの「事なかれ主義」や「臆病」へと堕していく。しかし、それなら、日本人の「配慮」は、いかにして「臆病」へと退行していったのか。日本人は、いかにして、その「主体的判断」を見失うほどの自己喪失に見舞われることになったのか。
Ⅱ 日本人が「死んでしまった」ようになるまで ──日本精神分析
日本人の自己喪失の直接の原因は、言うまでもなく、戦後七十八年の時間のなかで、日本人がすっかりアメリカに飼いならされてしまったことにある。その結果として、冷戦が終結してもなお日本人は、「パックス・アメリカーナ」(アメリカの平和)の夢を貪り続け、「グローバリズム」の毒を毒とも感じられないほどに生命力を鈍らせてしまったのである。
だから、その依存症の実態は、もしかすると「パックス・アメリカーナ」の恩恵に浴すことの少なかった国の方がより正確に見えているのかもしれない。たとえば、イスラエルの哲学者・政治理論家のヨラム・ハゾニーは、西側諸国の退行ぶりを次のように指摘していた。
地面から噴出する石油のおかげでサウジアラビアが何の苦労もせずに富を手に入れているように、自分たちの安全を得るために力を尽くさなくてもアメリカが安全を与えてくれるならば、なぜネイションの独立と自決の原則を守る必要があるのだろうか?
ヨーロッパの人々は、アメリカの気前の良い行為のおかげで存在し、依存状態に陥っているにすぎない。彼らは、独立した国民国家の解体によって世界平和への秘訣を見つけたというアデナウアーの主張を嬉々として繰り返し、自分たちを永久に子どものままにしている。〔中略〕これこそ帝国のやり方だ。帝国は、独立の放棄と引き換えに、平和を提供する。そのなかには、独立したネイションとしての思考力、独立したネイションの生活にふさわしい成熟した政策を考案し実行する能力の放棄も含まれている。─『ナショナリズムの美徳』庭田ようこ訳、〔 〕内引用者、以下同じ
これは、もちろん「“戦争は遠い過去のこと”にしたがっている」ヨーロッパ人、あるいは、もはや「武器を持って戦わない」ヨーロッパ人(エマニュエル・トッド『第三次世界大戦はもう始まっている』)についての言葉なのだが、その本質は日本人についても当て嵌まろう。
が、日本人の依存症には、それに加えて特殊日本的な事情も存在している。それは、日本人が、明治維新と敗戦という二つの切断を自らの「外からの力」として経験したことである。
かつて石原莞爾は、東京裁判で尋問された際、「もし日本の近代史を全部裁く、その責任者を追及するというなら、まずペリーを連れてくるのが先決だ」(半藤一利『あの戦争と日本人』)と言ったというが、日本の近代化とその後の拡張政策を導いたのは、まさしくぺリー・ショックという名の外傷体験の影響だったと言っていいだろう。要するに、十九世紀末の帝国主義に直面した日本人は、自国の自主独立を守ることのできる唯一の方法を、日本の西洋化=帝国主義化、つまり、自国の伝統の大きな切断(明治維新)に見出したということである。
もちろん、それを成功させるためには、幕末に生み出された尊皇攘夷思想を尊皇倒幕思想へ、そして、それをさらに文明開化思想へと転換していくだけの大きなエネルギーが──馬関戦争・薩英戦争の敗北における薩長の屈辱感が──必要だった。が、皮肉にも、最初「和魂洋才」で始まったはずの維新運動は、その屈辱の大きさに比例するようにして、次第に「洋才」の仮面が、素面としての「和魂」を食い尽くすという形で展開していったのである。
かくして、厚化粧に慣れた女が、自分の素顔を見失ってしまうように、近代日本人もまた、「文明開化」の裏に隠した自分の素顔を見失ってしまうことになるのだった。が、そんな「文明開化の論理」に覆われ切った大正末期から昭和初期、日本人は、関東大震災と昭和恐慌という二つのカタストロフィー=故郷喪失を経験することになる。そして、その不安感から日本人は、一転して家郷への道を探しはじめることになるのだが、しかし、その帰省先で見出したものは、「既に昔の面影はなく、軒は朽ち、庭は荒れ、日本的なる何物の形見さえなく、すべてが失われている」(萩原朔太郎「日本への回帰」昭和十二年)という現実だった。果たして、その絶望が呼び寄せたものこそ、国体明徴運動や東亜新秩序や大東亜共栄圏といった新たな尊皇攘夷思想、つまり、ここではないどこかへの夢だったのである。
けれども、日本人の自己喪失において、近代化以上に決定的だったのは、その文明開化に対する反動として戦われた大東亜戦争によって、日本人が完膚なきまでに打ちのめされてしまったという事実の方かもしれない。それ以降、日本人にとって西洋近代文明に挑む姿勢は禁忌とされ、アメリカに対する過剰適応だけが、つまり、「自発的隷従」(エティエンヌ・ド・ラ・ボエシ)の姿勢だけが価値とされることになってしまうのだ。そして、そのとき他者に対して被られた仮面が、ほかならぬ、「戦後民主主義」と「平和主義」という偽善のマスクだったというわけである。
ただし注意したいのは、そこで被られた仮面が、素面を絶滅させるまでにぶ厚い仮面であったがゆえに、一度でも本気で信じられたことのない「戦後民主主義」や「平和主義」という言葉は、しかし、決して否定もされなかったという事実である。そして、その証拠こそが、「不義の子」(小幡敏『「愛国」としての「反日」』)としての自衛隊の存在にほかなるまい。それが噓と分かりながらも(だから自衛隊は存在する)、しかし、なお打ち捨てることのできない「平和主義」の仮面(だから自衛隊は軍ではない)……。
だが、それなら、戦後日本人の本音はどこにあるのだろうか? いや、その本音そのものの喪失こそが、自己喪失の真の意味であり、あの岸田文雄の顔に象徴されるところの「からっぽ」なのだとすれば、私たちの闇は想像以上に深いと言うべきなのかもしれない。
たとえば、現象学的精神病理学の草分けの一人であるR・D・レインは、そのように一人歩きしていく仮面(偽自己)の病理を指して、「統合失調気質の自己」を疑っていた。
このような統合失調気質の「自己」は、多かれ少なかれ非肉体化されているのが普通である。〔中略〕この自己はキェルケゴールのいう「閉塞」状況に落ちこむ。そういう人の行動は自分の自己の表現としては感じられない。〔患者である〕デイヴィッドが「性格」と呼び、私が偽自己─体系と名付けることにした外面的行動〔仮面〕というものは、自己から遊離し、なかば自律的となる。偽りの自己あるいは偽りの自己たちのすることには自己は関わりあいがないように感じられ、それ、あるいはそれらのすることは、ますます偽りで無益なものに感じられてくるのである。一方自己はそれ自身に閉じこもり、みずからを「真の」自己、ペルソナを偽りの自己とみなすのである。そのような人は無意味性、自発性の欠如などに不満をもらすが、彼自身で自発性の欠如を育て、それによって無意味感を倍加させているのかもしれない。──『引き裂かれた自己──狂気の現象学』天野衛訳
そして、レインの言葉において注意すべきなのは、「初めは自己に対する破壊的な侵犯〔外圧〕を防ぐための防壁として考え出されたもの〔仮面〕が、自己にとって脱け出すことのできない牢獄の壁」となるという指摘だろう。
だからこそ、「壁」に閉じ込められた統合失調気質の〈自己=精神〉は、いつまでたっても外界の他者と生命感をもって交わることができないのであり、その妄想のなかで己の精神を「非肉体化」(非現実化)していってしまうのであり、ついには、「無意味性」のなかに呑み込まれ、死んでしまったようになるのである。
<続きは本誌でお読みください>
『表現者クライテリオン2023年5月号』【特集】「岸田文雄」はニッポンジンの象徴である ”依存症”のなれの果て より
岸田首相の批判を通じて、日本人の”依存症”を見つめた本特集。是非、本誌をお手にお取りください!
創刊5周年記念シンポジウム開催が決定!
浜崎先生にももちろんご登壇いただきます!
第一部では、自己喪失(故郷喪失)におちいった日本人に必要な処方箋とは何か徹底議論します。

7月1日(土)14:30〜17:50@新宿
是非お申し込みください!
https://the-criterion.jp/symposium/230701-2/
執筆者 :
CATEGORY :
NEW

2026.02.12
NEW

2026.02.11
NEW

2026.02.09
NEW

2026.02.07
NEW

2026.02.06

2026.02.05

2026.02.09

2026.02.06

2026.02.07

2026.02.05

2026.02.11

2024.08.11

2026.01.20

2026.02.12
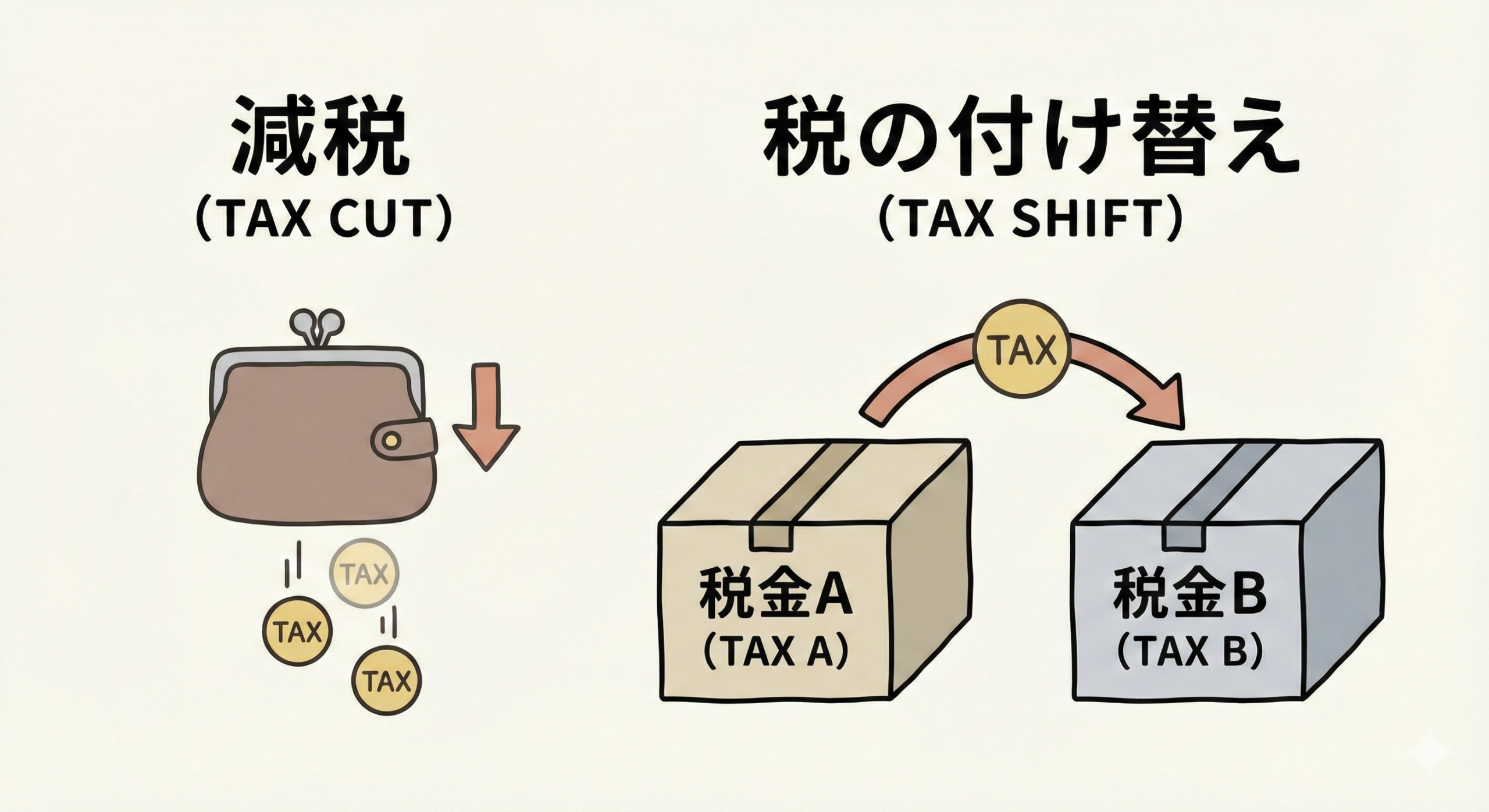
2026.01.18

2018.09.06