最新刊、『表現者クライテリオン2024年11月号 [特集]反欧米論「アジアの新世紀に向けて」』、好評発売中!
本書の購入はこちらから!
よりお得な年間購読(クライテリオン・サポーターズ)のお申し込みはこちらから!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
伊豆・下田公園の開国記念碑に刻まれている「マシュー・ペリーの言葉」は、ダグラス・マッカーサーが選んだ一文である。第二次大戦にアメリカ海軍の戦史編纂担当者として従軍した歴史学者サミュエル・E・モリソンは、著書『伝記ペリー提督の日本開国』(原著1967)で何回かマッカーサーに触れているが、日本でも「開国」をキーワードにしてペリーとマッカーサーを結びつけた言及は多い。多くの戦後生まれの世代にとって「開国」はポジティブなイメージをもつ言葉であり、一度目の開国は近代、二度目の開国は民主主義の黎明を意味した。学校でもそう教えられたし、新聞にもそう書いてあった。戦前世代のなかでも進歩的知識人と呼ばれる人たちは、「封建的な価値観から個人主義や自由主義へ進化」しなければならないと主張した。終戦後に生まれた子供たちが大人になった1970年代には、民主主義や個人主義や自由主義はほとんど「絶対的な善」になっていて、異論を挟むには相当な勇気が必要になっていた。
マッカーサーがペリーを意識していたのは事実である。日本の降伏文書調印式が行われた戦艦ミズーリの艦上の後甲板に飾られていた星条旗は、この日のためにわざわざ本国から取り寄せた「サスケハナ号のマストに掲げられていた星条旗」であった。しかし、ペリーとマッカーサーは、日本に関わったこと以外には、ほとんど共通項がない。ペリーは海軍将校であったが、陸軍のマッカーサーは海軍が嫌いだったという。ペリーは民主党支持者で、マッカーサーは共和党支持者だった。ペリーが東インド艦隊の長官になったのは、地中海や大西洋の任務に就くことを望んでいた彼にとって不本意な命令であったが、マッカーサーには日本征服の強烈な意思があった。両人が同世代人だったら「仲良し」にはなれなかったかもしれない。
父親の代からフィリピンと関係が深かったマッカーサーが最初に青年将校としてフィリピンに赴任したのは1903年で、日露戦争の前だった。彼は、インドから日本列島に連なるアジアの島嶼部の中心にあるフィリピン群島を、太平洋の重要な要として捉え、「アメリカの運命はアジアおよびその周辺の島々と分かち難くつながっている」ことを悟ったと言っている。彼は、約1世紀前にアメリカ海軍が着手した「日本開国の事業」を、自らが完成させるという意欲をもっていた。おそらく「ペリーの意思」を継ぐ者としての自負心があったのだろう。彼が考えていた「日本開国の事業」や「ペリーの意思」が、果たして当時の政府やペリー本人の意思なのかはわからない。寧ろ、彼独自の「使命感」があったようにも思われる。
東アジア艦隊の任務には、中国における商業権益とキリスト教宣教師の布教活動を保護することが含まれていた。ペリー派遣での江戸幕府との交渉の目的は開港や居留地を含む通商問題であって、フィルモア大統領の親書には次のように書かれている。
「私はペリー提督に、次のことを確信するよう命じている。すなわち、私は陛下と陛下の政府とに対し深甚なる親愛の情を抱いており、また私が提督を日本に派遣した目的は、合衆国と日本が友好を結び、相互に商業上の交際をなすべきことを提案するためにほかならない。合衆国の憲法および諸法律は、他の諸国民の宗教的あるいは政治的問題に干渉することをすべて禁じている。私はとくに、陛下の国土の安寧を乱すような行動はいっさい慎むよう、ペリー提督に訓令している。」
開港に関しては、薪炭・食糧・水の補給港、暴風雨等の際のアメリカ捕鯨船や商業船の避難港としての使用許可も要求している。しかし、日本に関する事前の入念な調査もあって、宗教の布教活動には言及していない。あくまでも「対等な文明国同士」の扱いであるが、大砲を積んだ軍艦を連ねてやって来たこと自体が威圧であったことに変わりはない。ペリーは、日本との条約締結のあと、琉球王国との協約に署名して、それを以て「日本との交渉の終了」とした。アメリカでは、日本・琉球との通商交渉の成功はアメリカ海軍がアジアで勝ち取った最初の「勝利」だと捉えられた。日本における砲艦外交の無血勝利であって、議会は彼を賞賛し「軍功(成果)」に対する報酬を議決した。
まだ日本が元気だった頃、アメリカの友人のたちが日本に来たとき、必ず話題になったのがペリーのことだった。彼らに大した知識はなく、「ペリーが上陸したのはヨコハマか?」といった類の質問であったが、ペリーが日本を開国させたということが、アメリカ人にとって「誇り」のように見受けられた。一般のアメリカ人は「ペリーってだれ?」であるが、知識人がペリーを知っていたのは多分にモリソンの影響があったと思われ、マッカーサーとの関連で、ペリーの時代から日本とフィリピンが「アメリカのフロンティア」だと捉えていたような気がする。
議会によって栄誉を与えられたペリーはいろいろな商業団体からも感謝状を贈られた。彼はそれに応えて「この強大な帝国(日本)を国際社会の一員にし、さらにその上これをわれわれの宗教の恩恵下におく事業は、まだほんの始まったばかりである」と述べている。ここで、私がひっかかるのは、「われわれの宗教の恩恵下におく事業」という部分である。私たちの歴史では、開国は政治的・経済的な問題であるが、アメリカ合衆国にとってはそれだけでなく「宗教的な事業」であったということだろうか。ペリーにはその「使命感」があったのだろうか。
プロテスタントは「教会とカネの問題」を発端として生まれた。カトリック教会の資金調達手段、カネで罪が贖えるという「免罪符」に怒った若い神学者のルターが、長い批判文を教会の扉に打ち付けたのは1517年だった。貼り紙に集まった人々の中でラテン語の文章を読める者は僅かだっただろう。それにも拘らず、これがあっという間に広まったのは、批判文を印刷した人々がいたからである。既に活版印刷が始まってから半世紀経っていた。
プロテスタントは印刷技術なしでは語れない。「ひとつの発明が決定的な影響を与えたという点では、宗教改革に与えた印刷技術の影響を凌ぐものはない」と言われる。各地の少数のラテン語を読める者が、行商人によって遠隔地まで運ばれたルターの告発文を読んだ。当時は本や冊子の種類が少なかった。選べる本が他になければ、ルターの小冊子は独占市場を得たようなものだった。どうも16世紀の聖書セールスマンたちは、強引な販売法で商品や聖書を売り歩いたらしい。いつの世にも抜け目のない商人はいる。告発文の冊子も、多くは買い手が望んだというよりも「押し売り」だったのかもしれないが、カトリック教会に批判的な人々にとっては刺激的な内容だった。こうして伝わったラテン語の告発文は各地で「俗語」に翻訳され、瞬く間にヨーロッパ中に広まった。
印刷による情報の波及の速さというだけでなく、プロテスタントの教義そのものが聖書という印刷物なしではありえなかった。プロテスタントでは、神の言葉は聖書にすべて書かれているのだから、司祭によって与えられるのではなく、それぞれの信者が聖書を読んで解釈すべきであるという。信者は一人ひとりが司祭なのだという「万人司祭」の革命的な思想である。グーテンベルクが最初に印刷したのはラテン語の聖書であったが、発行部数は少なく高価なものだった。しかし、ルターの時代には印刷技術も進み印刷業者も増えていた。各地でそれぞれ俗語に翻訳された聖書が普及し、徐々に人々が自分の聖書を持つことが出来るようになった。
聖書の「個人の解釈」が認められるということは、聖書という印刷物が手許にあることが前提になる。その上で、「真実が何であるかを決めるのは個人」であり、解釈も「個人の自由」を認めるということである。自由主義と個人主義は決定的に「正しい在り方」となった。(これについての考察にはもっと複雑な要素があるのだが、紙幅の関係もあり、また別の機会に言及したい。)
イギリスがカトリック教会と決別したのは、ヘンリー8世の離婚問題が原因だということはよく知られている。英国国教会は、カトリックに反旗を翻したという点では「プロテスタント」であるが、ルターのような潔癖な神学論争から生じたものではなかったため、国家に管理され、教会の儀式や司祭の権威も保たれ、カトリックに近いところがある。プロテスタントの信者たちの間で、英国国教会が独裁的だと言って改革を求める運動が起こり、その中でも「急進派」の信徒は「ピューリタン」と呼ばれた。ピューリタンは「信仰に純粋な者」と言われるが、当時は「バカ正直な奴ら」という蔑称だった。彼らは不屈の熱意をもって生活そのものを信仰に捧げる過激な「カルト集団」であった。
北部ヨーロッパのプロテスタント地域の識字率が上がったのは、聖書を読むためである。イギリスではジェームズ1世の勅命により、1611年に「欽定訳聖書」が登場した。この英語版聖書が出版された一世紀後には、イギリスの識字率が3倍になったという。
コロンブス以来、スペインが南米の銀を独占し、他国も競って金・銀の鉱脈を探した。北米にもエルドラドを夢見て探検家やはぐれ者が海を渡ったが、多くは遭難して、新大陸に辿り着いた者たちも黄金郷を見つけることはできなかった。それでも一攫千金を夢見た人々は次々に新大陸に渡り、バージニアの入植地を建設する。後に英国国教会の最高指導者でもあるジェームズ1世がアメリカに植民地を開設する勅許を出した頃には、既に「欽定訳聖書」の作成が進められていて、植民地開設には福音の伝道も目的になった。
南部バージニアへの入植から一世紀あまり経ったその頃、ゴールドラッシュとは別の集団がイギリスから北部の海岸に押し寄せるようになった。新大陸に本気で「神の国」を建設しようと大西洋を渡って来たピューリタンたちである。「ピルグリム・ファーザーズ」と呼ばれるピューリタンたちが1616年に出航したときは「欽定訳聖書」が出版されたばかりで、ルターの告発文から僅か100年しか経っていなかった。反体制派として差別されていた急進派のピューリタンは、「腐敗した旧大陸」を捨てて新たな地で信仰の生活を送るために、熱狂と興奮のなかで無謀な航海に船出した。
この頃のプロテスタントの主流はルターの次の世代のカルヴァンによる改革派の思想だった。カルヴァン主義の大きな特徴は「天国に行ける者は神によって予め決められていて、人間がいくら努力しても変えられないものだ」という「予定説」にある。神の決定に対して抗ったりお願いしたりすることは、人間が神に「命じて」神の気持ちを「動かそうとする」不遜な考えである。しかし、決定済みで変更不可というのは身も蓋もない話である。救いは、各々が勤勉や禁欲によって「神に選ばれていることを感じ取ることができる」ということだった。自分が選ばれているという「霊感」を得るために、人々は労働に励み品行方正な暮らしをして、ひたすら「確証を感じ取る」ことを待つのである。神に選ばれているという「スピリチュアルな実感」を得ようと熱心に働いた結果としての現実の収入も「満足感を伴う証拠」と考えられた。金儲けも巨額な資産も「神に選ばれているという確信」として肯定された。(教義の解釈などというものは、案外、「後付け」なのかもしれない。)
このような「個人の霊感」は、他人にはわからない自分だけの感覚であって、誰かと共有するものではない。自分だけの体験という狭い視野での「幻想」であり、自分が実感すれば、それが「正しい」という独善に陥る。あくまでも感覚であるから、客観的証拠が得られない。こうして徹底的な個人主義がアメリカを形成していった。
ペリーの祖先がアメリカに渡ったのは1639年頃と言われている。コッド岬のサンドウィッチという寒村に上陸し、のちにロード・アイランドのナラガンセットというインディアンの開墾した肥沃な土地に移住する。港町ニューポートの近くである。
ペリー一族はクエーカー教徒だった。イギリス本国で差別や迫害を受けていたのはピューリタンだけでなく、新教徒のバプティスト派やクエーカー教徒も同様で、彼らも新大陸に渡った。しかし、新大陸ではピューリタンが主流派になり、規模の小さなクエーカー教徒を迫害したのである。親から虐待を受けた子供は、大人になってから自分の子供を虐待することがあるというが、嘗て迫害された者が加害者側に回ることはよくある話である。ヨーロッパで迫害され続けホロコーストの記憶を持つイスラエルが、ハマスとの戦争で容赦ない攻撃をするのにも同様な背景がありそうである。
クエーカー教徒は、一人ひとりが神と直接交信できると信じているという。神との交信はカトリックにもあって、幻視やエクスタシーと言われ、一種のトランス状態になる。こうした「狂信的な反知性主義」がありながら、クエーカー教徒は、民主主義、平和主義、寛容性、フェミニズムなどに則って市民秩序を守ることで、合理的な人々に見られるという。この辺りは日本人には、理解が難しいところである。
海の仕事に関わったのは、マシューの父親クリストファー・ペリーだった。彼は、私掠船に乗り込んだ。イギリスでもスペインでもそうであったが、国家の海軍が建設されるまでは、海上貿易の攻防は私掠船が引き受けていた。アメリカ合衆国海軍の正規軍は、ヨーロッパ各国の海軍に比べてまだまだ弱体で、海域や貿易を護るには私掠船が必要だった。父親は、このころクエーカー教徒から、もっと国教会に近い保守系のアングリカン(聖公会)に改宗している。
この頃、イギリス国内法で黒人奴隷の売買禁止令が成立する。勿論、人道上の議論もあったが、あれだけせっせと奴隷貿易に勤しんだイギリスが禁止令を出したのは、奴隷の需要が減少したからである。西インド諸島の砂糖栽培では安価な労働力として黒人奴隷が使われていた。しかし、ナポレオンの大陸封鎖令により、ヨーロッパ大陸で砂糖が売れなくなってしまったのだ。また、産業革命で機械の潤滑油として必要になったパーム油の需要が増え、黒人を西インド諸島にコストをかけて運ぶよりも、アフリカの地で安い賃金労働者としてパーム油生産に従事させようとしたのである。奴隷売買禁止法の成立は、黒人労働力をどのように利用するかという「採算性」を考えた結果でもあった。
アメリカで黒人奴隷に早くから反対していたのは、クエーカー教徒であった。彼らの信仰の寛容性や平和主義という教理による。南部では農作業で奴隷が必要であったが、北部では奴隷解放論が始まっていた。それは、黒人奴隷をアフリカに帰還させるという運動になった。彼らを祖国に帰すという計画は人道的な政策に見えるが、現実の「帰還」は、何世代もアメリカに住んでいた黒人をアフリカに「入植」させるという話である。戦後の「イスラエル建国」でユダヤ人をパレスティナの地に「入植」させた発想と同じである。このときは、黒人のなかでリーダー格の者にキリスト教を布教させてアフリカにキリスト教を広めようという狙いがあった。しかし、大昔に出て行ったユダヤ人が戻って来たことでパレスティナが困惑したように、アフリカでも、何世代も前にアメリカに行った黒人の子孫が戻って来て勝手に国を作られたら、現地人には大迷惑である。ペリーは、解放奴隷のアフリカへの搬送という厄介な仕事を命じられた。
赤道直下の海上での長期間の逗留で、船上の海軍兵士たちは気候や風土病に悩まされたが、リベリアという新国家建設だけはうまくいった。詳細は省くが、既に「アメリカ的」になっていた黒人が入植して建設したリベリアは、アメリカが作った国家ともいえる。アメリカやヨーロッパの船主にリベリア船籍の船が多い理由は、このへんにあるのかもしれない。ともあれ、モリソンは、リベリアの国家建設の功労者として、ペリーを高く評価している。
ペリーの「われわれの宗教の恩恵下におく事業」が何を意味したのかはわからない。開国当時に宗教の押し付けはしなくても、自由な人の往来には宣教師も含まれる。宗教そのものの布教ではなくても、ピューリタンにとっての「善」である「個人主義」や「自由主義」を広めることが、「信仰の自由の時代」における彼らのMission になったらしい。ペリーにはマッカーサーほどの強烈な意識はなかったと思われるが、アメリカに存在する潜在意識としての使命感はあったのかもしれないし、それは、ピューリタン国家として、ことさら意識するまでもない「普通の態度」なのかもしれない。
彼らのMission は、その地の文化・思想を入れ替えることを躊躇しない。「正しい行い」なのだから、躊躇する必要はない。けれども、敗戦によって抵抗できなかったことを考慮しても、戦後になってそれを自ら受け入れたのは日本人のほうではなかったか。直前の軍国主義の時代しか体験していなかった世代にとって、軍部の締め付けからの解放は「ありがたかった」だろう。「個人主義」や「自由主義」が輝いて見えたかもしれない。しかし、個人が体験できる「時間」は、日本の長い歴史のほんの一瞬である。戦争の時代のずっと以前から「日本の歴史」はあった。「戦前」は軍国主義の時代も含まれるが、軍国主義とイコールではない。
マッカーサーが禁じたのは、軍国主義的なことだけではなかった。寧ろ、政治であろうが制度であろうが、日本に伝統的にあるものは何もかもを消し去って、自分たちの思想に入れ替えようとしたように見える。これは宗教的使命感に近い。私たちは「改宗」してしまったのだろうか。雨霰のような焼夷弾や原爆の恐怖を体験していない戦後世代には、何も言う資格がないかもしれない。ただ、個人の体験だけがすべてではない。何世代も前から紡いできた歴史を学ぶことで視野を広げて、失ったものを問い直す必要はあるだろう。
『ペリー提督 日本遠征記』M.C.ペリー著 宮崎壽子監訳 /角川ソフィア文庫 2014
『ペリー提督の機密報告書』今津浩一著 /ハイデンス 2007
『アメリカのデモクラシー』トクヴィル著 松本礼二訳 /岩波文庫 2005
『ファンタジーランド 狂気と幻想のアメリカ500年史』カート・アンダーセン著 山田美明・山田文訳 /東洋経済新報社 2019
『反知性主義』森本あんり著 /新潮選書 2015
『ペリーは、なぜ日本に来たか』曾村保信著 /新潮選書 1987
『印刷革命』E.L.アイゼンステイン著 別宮貞徳訳 /みすず書房 1987
橋本由美
<編集部よりお知らせ>
最新号『表現者クライテリオン2024年11月号』が好評発売中!是非ご一読ください。
本書の購入はこちらから!
よりお得な年間購読(クライテリオン・サポーターズ)のお申し込みはこちらから!サポーターズに入ると毎号発売日までにお届けし、お得な特典も付いてきます!。
サポーターズPremiumにお入りいただくと毎週、「今週の雑談」をお届け。
居酒屋で隣の席に居合わせたかのように、ゆったりとした雰囲気ながら、本質的で高度な会話をお聞きいただけます。
執筆者 :
CATEGORY :
NEW

2026.02.16
NEW
.png)
2026.02.16
NEW
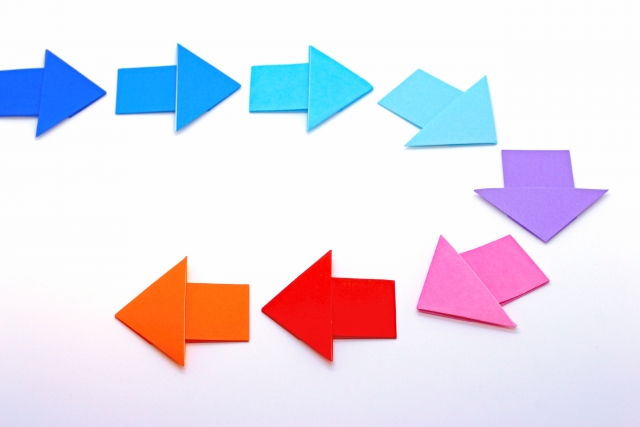
2026.02.16
NEW

2026.02.16
NEW

2026.02.13
NEW

2026.02.12

2026.02.12

2026.02.11

2026.02.13

2026.02.09

2024.08.11

2026.02.16

2022.10.25

2026.01.20
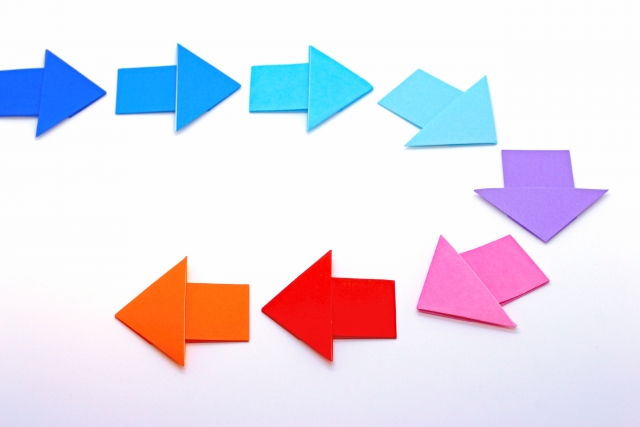
2026.02.16

2018.03.02