本日は8/16発売の最新号『表現者クライテリオン 9月号 財務省は敵か味方か?』より、特集インタビューの一部をお送りいたします。
本誌の詳細はこちらから

柴山▼ 今回の特集は「財務省は国民の敵か味方か」という刺激的なテーマとなっています。もちろん、財務省は国民の味方であるべきであり、職員もその意識で働いていると思います。
しかし、最近は「財務省解体デモ」が行われて話題になったり、増税に向けた空気づくりに国民が強く反発したりと、国民の側が財務省を味方と感じていないと思われる場面も増えてきているように感じます。
そういう状況を考える上でも、まずは現在の日本で財務省がどれくらいの権力を持っているのかを客観的に把握しておくことが重要です。そこで今回は、安倍政権で内閣官房参与を務め、予算編成をめぐって財務省と激しく対峙した経験をお持ちの藤井聡さん──いつもは本誌編集長としてインタビューをする側ですが、今回はインタビューされる側に回ってもらって──にお話を伺いたいと思います。
一般的な理解として、昭和時代に比べて現在の財務省の権力は弱くなっているのではないか、という見方があります。実際、平成の省庁再編で大蔵省が財務省に改組された時、権限が大きく縮小されました。例えば金融監督部門は金融庁に分離されましたし、その少し前(一九九七年)には日銀法が改正され、日銀の独立性が確保されました。また、予算編成においても政治主導・官邸主導の流れが強まり、経済財政諮問会議のような会議体が設けられて、「骨太の方針」を策定してから予算編成を行うようになっています。
以上を踏まえて、現在はかつての最強官庁の面影はないのではないか、との見方もあるように思うのですが、実際に政府の中枢に近いところからご覧になって、その見方は正しいと言えるのでしょうか。
藤井▼ 一般の方は官邸や永田町でどういう議論があり、どういうプロセスで物事が決まっているのかを知る機会があまりないでしょうから、「財務省が日本を支配している」という言説を陰謀論のように扱っている方も多いと思います。しかし、二〇一二年から二〇一八年までの六年間、安倍内閣の内閣官房参与として仕事をして、そのプロセスに参与して観察してきた立場から申し上げると、公平に申し上げて、「財務省支配」と言い得る権力構造は実際にあると認めざるを得ないと思います。
まず、財務省の権力はどこにあるかということからお話しします。日本には農水省や国交省、防衛省、文科省などの省庁があり、それぞれの行政の取り組みは各省庁や大臣、政治家らが決めているかのように思われていますが、実際には予算がないと動きません。例えばインフラを整備するにしても防衛装備品を買うにしても、予算がなければ当然できないわけです。新しい制度を運用するにも人がいるのであり、そのためには人件費や事務所経費が絶対にかかります。つまり、政治・行政の具体的な中身はすべて予算の裏付けがなければならず、したがって政治にとって予算は極めて根幹的な意味を持つという事実をまずは理解していただきたいと思います。
だから日本の政体においては、国民主権の下、国権の最高機関である国会で予算を審議し、政治・行政の内容を決めることになっているわけです。
柴山▼ 本来なら、国民の代表者である国会と、国会から指名される総理大臣が、大きな権力を持って予算を差配できるはず、ということですね。
藤井▼ そうです。建前上はそうなっているわけです。しかしそれはあくまでも建前。現実は全く異なっており、具体的にどうやって予算の内容が決められるかというと、毎年六月に「骨太の方針」を閣議決定し、政府から予算案が提示されて国会で議論し、最終的に決議するという流れになっています。この「骨太の方針」について審議するのが経済財政諮問会議であり、総理大臣や財務大臣、官房長官、総務大臣、経産大臣といった主要閣僚に加え、「民間議員」として学界と財界から二名ずつ参加しています。
このように国会とは別の官邸主催の会議で決められているのですが、その方針案の事務局をやり、そのたたき台を作っているのが財務省というわけです。正確にいうと内閣官房で案が作られているのですが、内閣官房には財務省の人間が必ず出向していて、財務省と綿密に連携しています。ですから、経済財政諮問会議のメンバーが何を言っても、財務省が認めない限り「骨太の方針」には意見を反映できないわけで、これによって財務省は非常に大きな力を持つことができます。
ここで重要なワードの一つが「財政規律」であり、「プライマリーバランス(PB)黒字化を目指します」という文言が「骨太の方針」に記載されます。それ以外にも、例えば「社会保障費は単年度で五〇〇〇億円まで、その他の費用は三年で一〇〇〇億円(つまり単年度で三三三億円)までしか増やさない」ということが、引用の引用の引用のようにしてひっそりと書かれているんですが、それを密かに挿入した張本人こそが、財務省なんです。
藤井▼ さて、一旦PB規律が骨太に記載されれば、それは絶大な拘束力を持つことになります。例えばPB黒字化を今後五年で達成する目標を立てて、初年度の赤字が一〇兆円だとすると、次の年は八兆円、その次は六兆円、さらに四兆円、二兆円、そしてゼロというように圧縮していくことになります。この縛りがものすごく強く、実際の予算を見てみると綺麗に目標通りになっているんです。つまり財務省がPB規律を骨太に書き込み、その骨太の方針通りに、財務省が予算規模を完全にコントロールしてしまうわけです。
もちろん国会審議はしますが、財務省が決めた額の中で議論をしますから、当然ながらその額を超えることはできない。というわけで、どこかに橋を架けようとしても「当初の額を超えるからダメだ」ということになるんです。
柴山▼ PB目標を設定する際には税収予測をするはずですが、実際の税収は予測とはズレますよね。つまり、税収の変動によってPBの達成状況も変わってくると思うのですが、そこはどうなっているのでしょうか。
<編集部からのお知らせ>
皆さん、こんにちは。
表現者クライテリオン事務局です。
クライテリオン叢書第5弾、『敗戦とトラウマ 次こそ「正しく」戦えるか』、書店・Amazon等で公表発売中!
|
|
敗戦とトラウマ |
執筆者 :
NEW

2026.02.27
NEW

2026.02.26
NEW

2026.02.26
NEW

2026.02.24
NEW
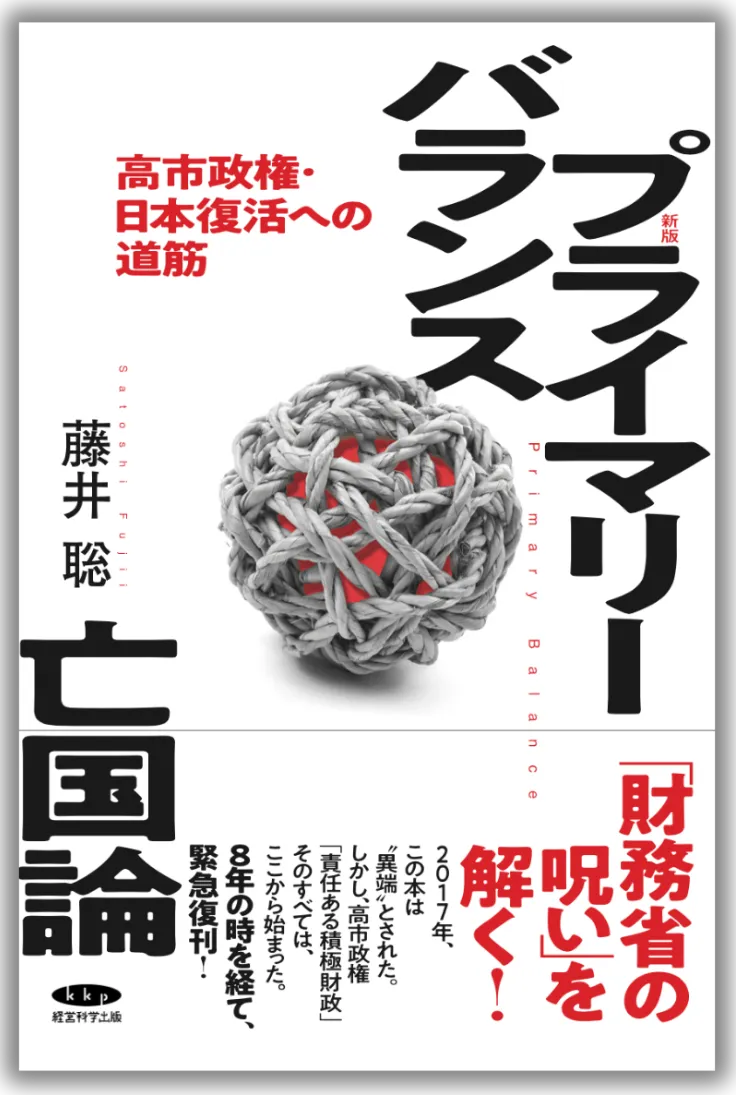
2026.02.23
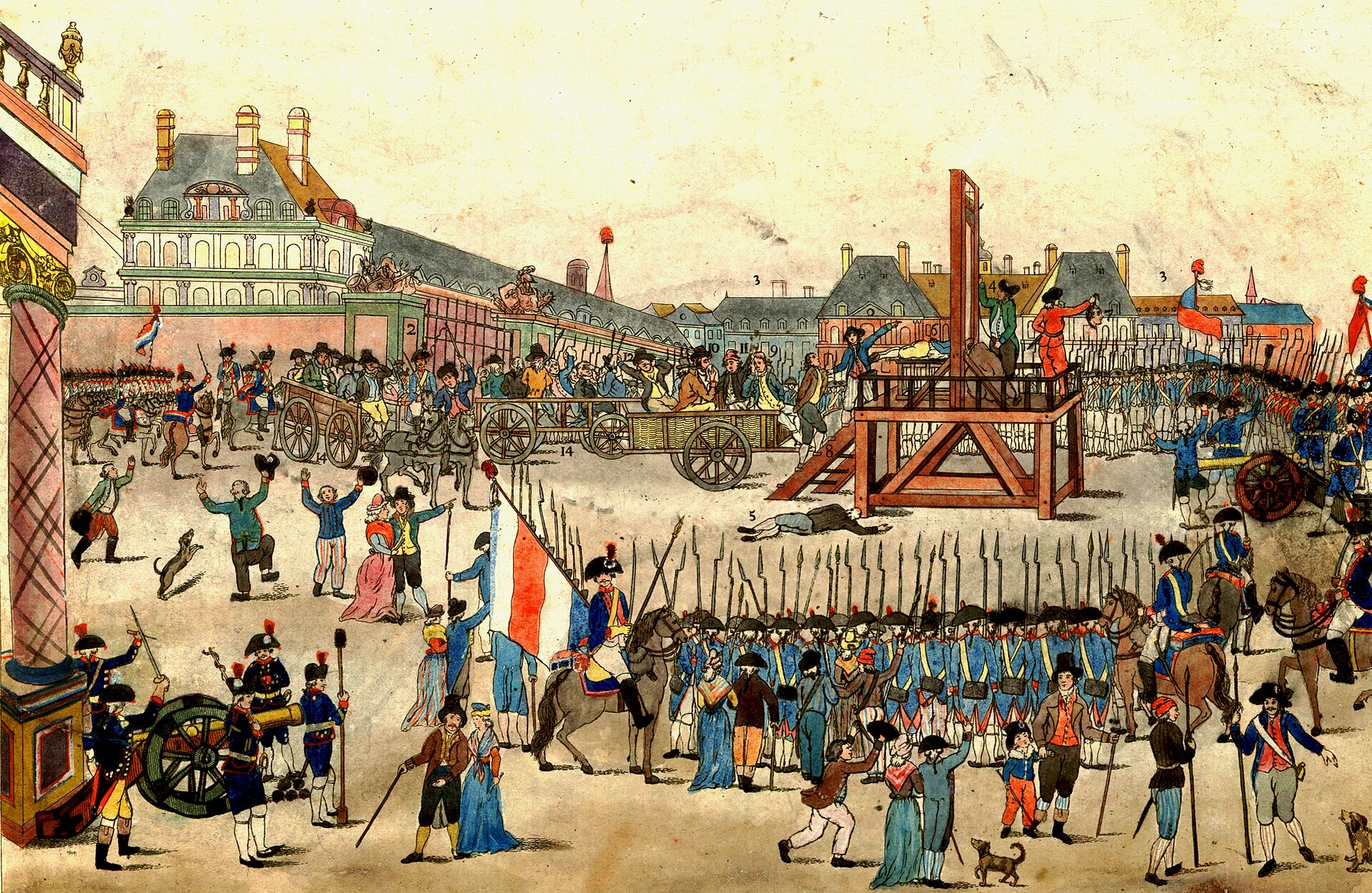
2026.02.20

2021.06.23

2021.06.22
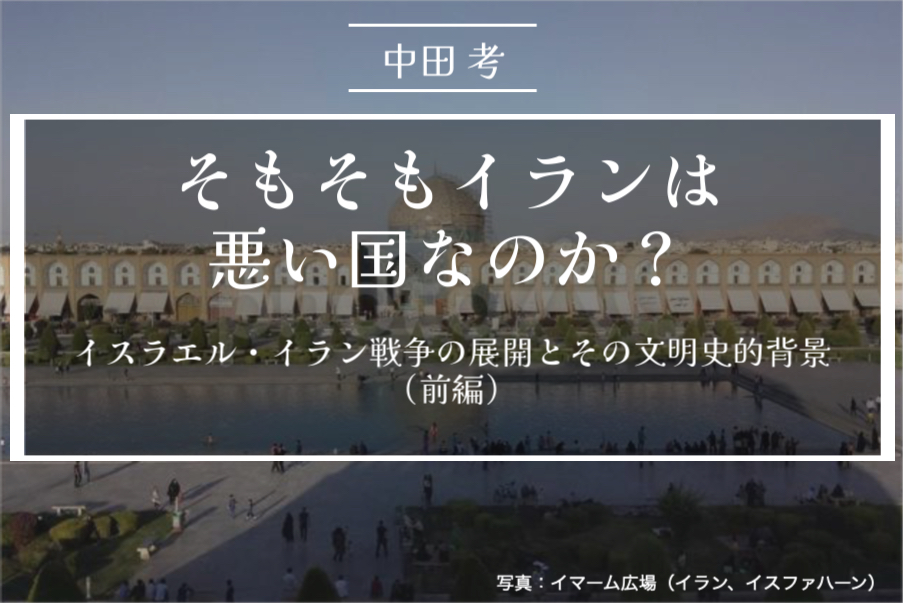
2025.06.24
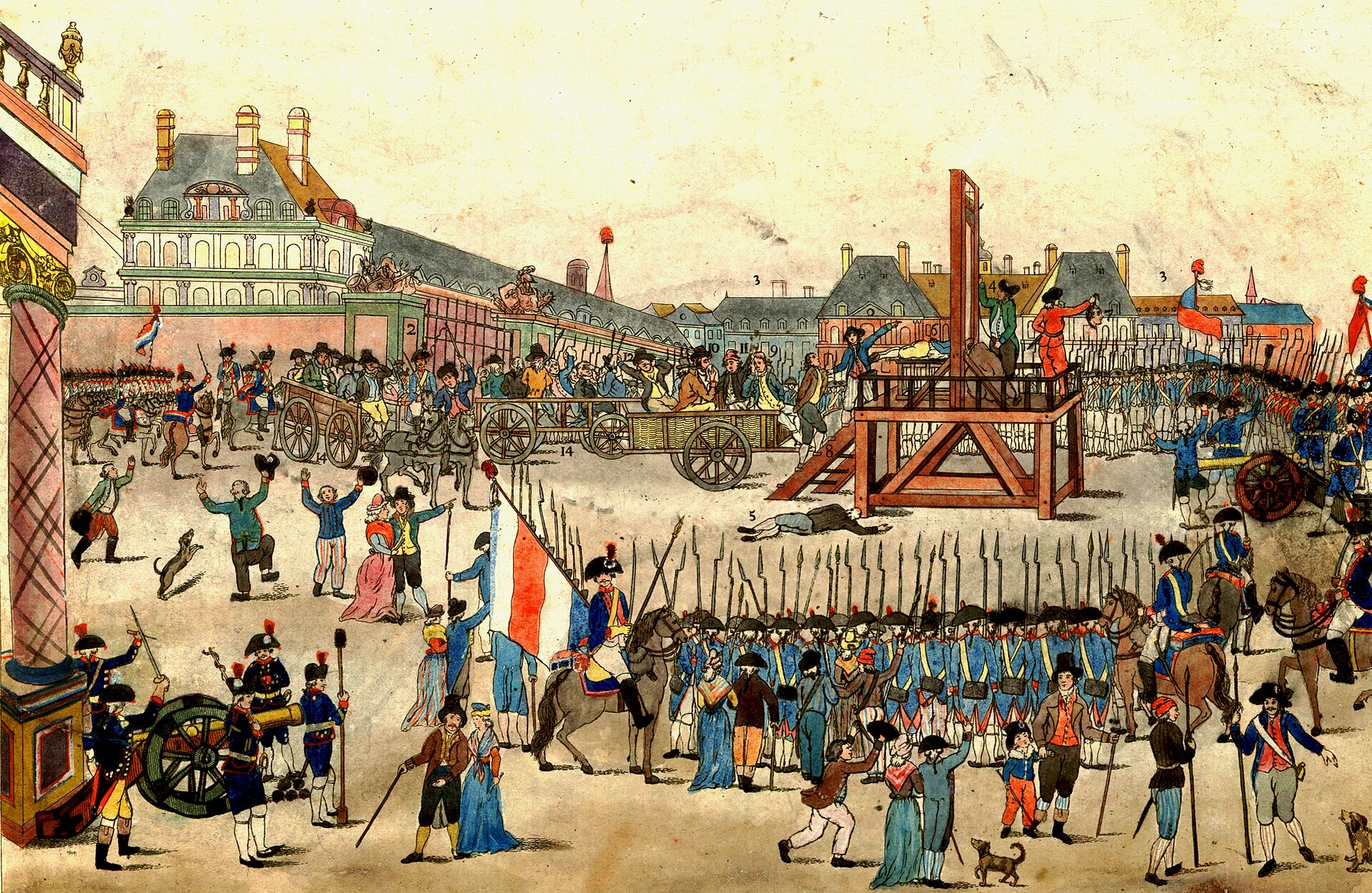
2026.02.20
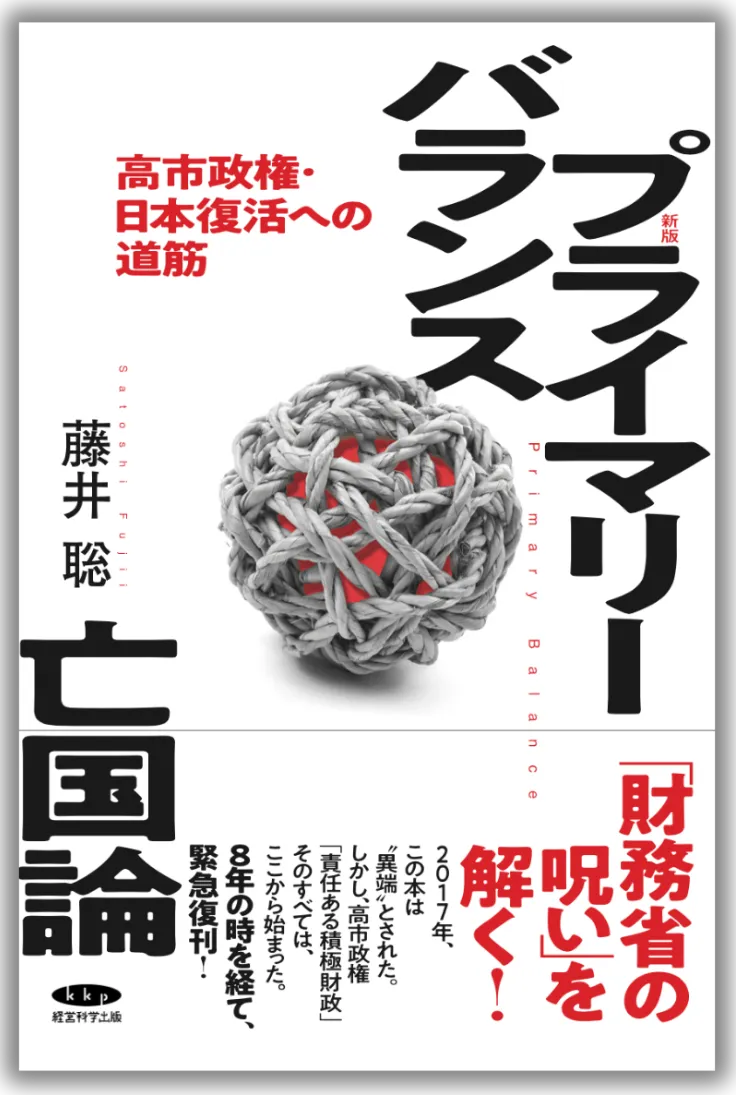
2026.02.23

2026.02.27

2026.02.26
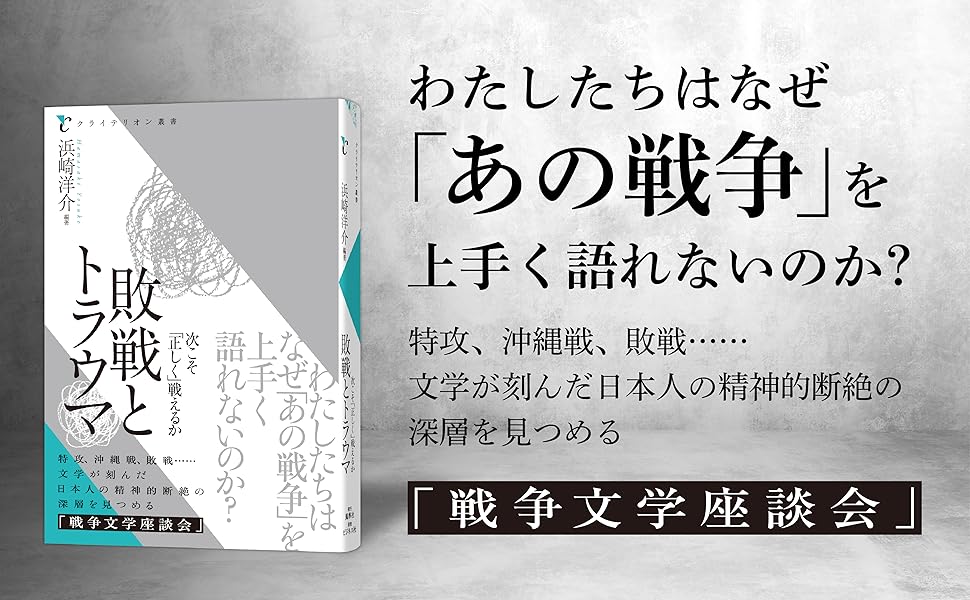
2025.08.01

2026.02.19
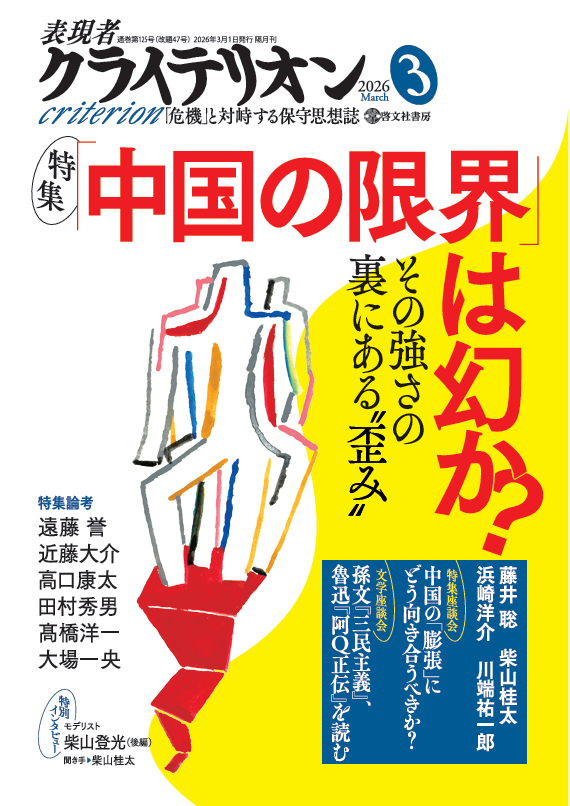
2026.02.16