第一次トランプ政権の国防副次官補として合衆国の国防戦略(NDS)策定で頭角を現したエルブリッジ・A・コルビーは、非営利の戦略シンクタンク『マラソン・イニシアティブ』の共同代表であり、現政権では国防次官を務めている。1979年生まれで現在45歳のコルビーは次世代を担う若手閣僚の一人で、28年の次期政権が共和党になれば重要ポストに任命されるだろう。日本は、対中国戦略を最重視する彼の戦略を検討しておく必要がある。コルビーの戦略は著書『The Strategy of Denial(拒否戦略)』(2021)に詳しい。
ミアシャイマーは、冷戦後のアメリカの外交政策をリベラリズム・ナショナリズム・リアリズムの3つの関係から考察しているが、コルビーの立場は保守的なリアリズムといえる。冷戦期から2000年代初めにかけてのアメリカ優位の立場ではなく、減退期にあるアメリカの現実を認め、中国がアメリカの地域覇権を侵食しつつあるという緊迫した危機感を持っている。彼は、保守的なナショナリストでもあるから、あくまでもアメリカの利益に沿った戦略であるが、本来、国家というのは自国第一なものであって、そこは当然である。従って、日本が彼の戦略のすべてを受容できるわけではないが、その土台となる現実の把握と分析には鋭いものがあり、日本としては真剣に考察する価値がある。
古典的地政学のH.J.マッキンダー(1861-1947・英)が提示した大陸国家と海洋国家という概念は、いまでも生きている。第一次世界大戦後の1919年に発表された『デモクラシーの理想と現実』は、彼の戦略思想の集大成で、「マッキンダーの地政学」としてその後の地政学の基本となった。マッキンダーは、ユーラシア大陸とアフリカ大陸を世界島と呼んで、第一次世界大戦を「ユーラシア大陸の心臓部(ハートランド)を支配しようとする大陸勢力(ランド・パワー)に対して、それを阻止しようとする半島や島嶼国の周縁部(リムランド)による海洋勢力(シー・パワー)との闘争である」と見做した。海上交通と貿易によって維持される自国の運命を強く認識したのは、既にイギリス一国では世界に君臨できない時代になっていたからでもある。大陸内部の新興勢力であるドイツとロシアに対抗するために、ユーラシア大陸を取り囲む海洋勢力の協力体制の重要性が顕在化していた時代であり、彼の理論はこの時代の要求から生まれたものと言える。海洋国家同士の協力を目的とした日英同盟(1902)は、その先駆けだった。
当時、既に帆船の時代が終わり、資源や工業製品を大量輸送できる船舶が航行するようになっていて、内陸部から膨張して富を独占しようとする大陸国家に対して、富を移動・分散させアービトラージによる利益を得ようとする海洋国家が衝突するようになった。大陸の周縁部(リムランド)は、覇権を取る上で地政学的に重要な地域になった。地政学上、アメリカ合衆国もユーラシアからかなり離れた沖合の島嶼国と見做され、海洋国家のひとつである。アメリカは、第二次大戦後に太平洋の海上覇権による「安全な地理経済圏」を構築するために、ユーラシアの周縁部である韓国・日本・台湾・フィリピンを勢力下に置いた。
21世紀に最も富が集中するのが東アジアからインドに至る地域で、コルビーは「アジアはパワーの集積地」と言う。この地域の80年代のGDPは世界の15%だったが、現在は約40%を占め、ますます集中度を高めている。ヨーロッパのGDPは、現在20%弱まで落ち込み今後も衰退が予測され、いずれはほとんどゼロに近くなるという。パワーの集積地を制する者がこの地域の覇権を握る。一世代前の戦略家の時代と異なるのは、アジア地域が経済の中心になったという点にある。アジア地域に比べれば、ヨーロッパも中東もオセアニアもパワーに乏しく、アフリカと南米は取るに足らないと、コルビーは言う。
パワーの集積地を制すれば、世界に影響力を持つことも可能になる。既に一帯一路によってユーラシアで優位に立つ大陸国家の中国は、アメリカを西太平洋から追い出して、完全な地域覇権国になることを狙っている。台湾を領有し、次に狙うのはフィリピンであろうと言い、いずれは韓国も日本も影響下に置くことを考えている、というのがコルビーの分析である。彼には、世界で最も富を生み出すリムランドの覇権を中国に握らせてはいけないという危機意識がある。いま、アジアは、次世代の覇権を巡る主戦場なのである。
アメリカの衰退は、あらゆるデータに表れている。金融やサービス産業を含むGDPではなく、購買力平価(PPP)で比較すると、2024年のアメリカのPPPが28兆7810ドルであるのに対して、中国は35兆2910ドルである。市場規模ではアメリカのほうが大きいが、経済力では中国のほうが大きいということになる。
2022年の両国の電力の発電総量はアメリカが4291.95TWhであるのに対して、中国は8881.87TWhでアメリカの倍以上、世界第一位である。2023年の国連貿易開発会議のデータによれば、中国の造船総トン数はアメリカの500倍である。アメリカにはもう造船能力がない。世界の海を航行しているのは、ほとんどが中国製の船舶である。今年5月のインドとパキスタンの空中戦では、パキスタン軍の中国製戦闘機がインドのフランス製戦闘機を撃墜して圧倒し、アメリカの核施設攻撃を受けたイランが中国製ハイテク兵器に注目している。
アメリカがグローバリゼーションによって脱工業化を図り金融資産の増加に踊っている間に、アメリカの製造業は悲惨なまでに壊滅した。いま、アメリカが中国に対してできることは「制裁」しかなくなっている。しかも、中国は「制裁」を受けるたびに、それをバネにしてハードルをクリアする。AIチップの禁輸とトランプ関税で、中国国内の半導体産業は多忙になり、27年までに中国のAI半導体の82%が中国製になると予測されていて、エヌビディアのシェアを既に奪っているという。中国にとってTSMCが必要なくなる日が来るかもしれない。
80年代から40年に及ぶアメリカの製造業と技術者の空洞化は悲惨な状況で、工場をアメリカに持って来れば回復するというものではない。雇用が増えても、ウェイトレスや清掃員を職業訓練してどうにかなるものではないし、嘗て産業を支えた熟練工はリタイアしている。これからの工場は自動化されて、雇用そのものにもかつての需要はない。いまや、船舶もドローンも新エネルギー産業も宇宙産業も、アメリカはすべて中国の後背を期している。
バイデン政権までの民主党には、危機感が希薄だった。製造業とかけ離れたロースクール卒業生が金儲けに精を出し、ジェンダーや人種やアイデンティティの問題を作り出して国民をバラバラにしただけだった。軍需産業と結びついたネオコンは自国の衰退の深刻さに気付かず、ウクライナ戦争の導火線に火をつけた。初めのうちは日和見をしていた中国は、いまではロシアを援助して延命させることで、アメリカをウクライナに貼り付けて離さないようにしている。アメリカの兵力を東アジアに集中させないためである。すべて他国のせいではない。アメリカの自滅である。
トランプ政権が危機感を持っていることは確かだが、ただ、中国の覇権は関税や制裁で解決する問題ではない。中国には資源も生産力も市場も、アメリカに比べればまだ安価な労働力もあり、頭脳もある。共和党内部のことはまったくわからないが、少なくともニュー・ライトと呼ばれる若手政治家たちは現実を直視していて、自分たちの未来を賭けて動き出しているように見える。
オフショア・バランシングは「沖合(オフショア)から、バランサーとして、ユーラシアの勢力均衡を図る」というイギリスやアメリカの外交政策であり、自分以外の他国が覇権を取るのを阻止するための戦略のひとつである。アメリカの場合には、自国にとって好ましい均衡を破ろうとする国家が現れた場合に、直接介入という手段だけでなく、リスクとコストを計算して周辺国を利用して抑制する方法、最終的には引きこもってしまうことまで様々なケースを選ぶことができ、論客によってオフショア・バランシングの考え方も違う。アメリカは大西洋と太平洋という2つの大洋によって自国の安全を確保されているために、巨大なリスクとコストが見込まれれば孤立することも可能で、大陸国家よりも変化に富んだ作戦を選択できる。
オフショア・バランシングの典型的な例が「バックパッシング」である。この場合、地域国家は軍備増強を要求されるが、孤立主義が採択された場合にも、地域国家は自立のための軍備が急務になる。覇権国にとってリスクとコストを如何に減少させるかは、常に基本的な課題であるが、自国の衰退が確実になれば、その要求は格段に強くなる。オフショアによる封じ込めがうまくいかないと判断すれば、アメリカは戦闘を回避することもできるが、そうなれば逃げ場のない地域国は大きな危険に直面する。
着々と軍備を増強している中国は「平和的な台頭ができない」と考える戦略家が多く、現に何年も前から南シナ海を基地化していることが、武力行使を否定していないことを示しているという。一国で中国と対抗できるだけの力がない地域国家をどう扱うかは、戦略家によって異なる。クリストファー・レインのように台湾や尖閣諸島や南シナ海はアメリカにとって戦略的価値はないと断言して、米軍基地も撤退すべきだという意見や、地域国家の軍事的負担を増大させることで地域のバランスを取るべきだという者もいる。
近年、その多くが、日本や韓国の核武装を容認する発言をしていて、中国との直接軍事衝突を避けようという意思は明確である。イージス・システムではリスクとコストが大き過ぎて、もう太刀打ちできなくなっているということなのかもしれないし、それだけアメリカの衰退が激しいということでもある。「核の不均衡」が核攻撃を招くというのはエマニュエル・トッドで、広島と長崎の時点ではアメリカだけが核を持っていたために実行が可能だったが、それ以降、ソ連や中国などが核を保有するようになってからは、報復を恐れて実行されていない。ミアシャイマーなど少なからぬリアリストたちは、「核不拡散」は核の不均衡によって核保有国の優位を保つためであり、核抑止を機能させるには「核拡散」のほうが効果的だという逆説的な見解を述べている。
コルビーの戦略もオフショア・バランシングである。まず、アメリカの限られたリソースを行使するのに、優先順位をつけるべきだという。ヨーロッパや中東にコストをかけるべきではなく、中国の覇権拡大を阻止することに集中すべきだと強調する。アジアは経済と利益の集積地であり、このエリアで中国に軍事的占領をさせれば、地域のバランスが崩れて中国の覇権を許してしまう。これを阻止するためには「反覇権連合」を作る必要がある。「覇権に反対する国家」ならば、国家の体制や主義や宗教を問わない。自由主義国家であろうと共産主義国家であろうと独裁的であろうとイスラム国家であろうと、「中国に支配されたくない」という意思を持つ国の強固な協力が抑止になるという。
彼の主張は、最終的に中国に勝利することが目的ではなく、中国の覇権を阻止してバランスを維持することが目的で、中国の体制を変えようとするものではない。「自由と民主主義を守る」という思想的価値観を押し付けるのではなく、地域のバランスを崩さないことが最優先で、国家の体制や宗教を変更させる必要はない。ここが民主党と異なる点である。彼は、体制が変わっても、中国は覇権を狙うだろうと見ている。
中国は、「反覇権連合」を崩そうとして、サラミ戦術で弱い部分を狙って来る。その最初の標的が台湾だという。直接的な軍事侵攻や占領を実行できなければ、中国はこの地域の覇権を達成できないだろうと考えている。だからこそ、「軍事衝突」を避けなければならない。戦闘を避けるために「中国の覇権を拒否する」意思を明確にすべきだというのが「拒否戦略」である。「冷戦期のバランス」を再現すべきだということかもしれない。
コルビーが何度も強調するのが「人間の意思を強制的に変えさせることができる手段は、顔に銃を突きつけたときだけだ」ということである。恐怖は侮れない情熱なのだ。そして、繰り返すのが「軍事衝突を避けなければいけない」ということである。軍事衝突を避けるには、軍備増強によって相手にリスクの恐怖を与えることが必要だというのが、彼の主張である。平和の追求は政府の義務であるが、他国の脅威が迫っているときは、「一時的に平和を放棄しても、国民の利益と安全を守ることを優先する」のが、寧ろ「道徳的」だという。今後、アメリカは日本や同盟国に防衛予算の増額を求めるだろう。日本の海岸線に敵が到達した時点で、勝負は決まる。地域国家は、決して敵を上陸させてはいけないという。上陸したときには、すでにバランスは崩れているのだ。専守防衛の限界である。
コルビーは、1986年からの6年間の少年時代を東京で過ごしている。短期間、香港にも住んだことがある。他の政治家よりも肌感覚でアジアを知っているだろう。それでも、彼は愛国者のアメリカ人であるから、バランスを保つことに失敗したときには日本から米軍基地を撤退させることも視野に入れている。
コルビーの戦略は、今後アメリカで採用される可能性が高い。日本にとっては、アメリカ支配からの脱却のチャンスでもあるが、何の準備もなければ、これ以上危険なことはない。アメリカのオフショア・バランシングに翻弄されることなく、自分たちの立場で「思考」しなくてはいけない。自ら思考しなければ「自立」はない。
リアリストたちの予測の根拠に、いくつかの興味深い分析がある。そのひとつは、権威国家のリーダーの年齢が行動を起こす上で大きな要因になるということだ。プーチンが決断したのは、戦闘を継続できる集中力や体力を失う前であることが必須条件だったと、エマニュエル・トッドは見ている。コルビーも習近平の年齢が、台湾に何らかの行動を起こすのに関係するだろうと言う。リーダーに権力が集中する体制では、人間としての「生物的限界」が大きな要因になる。
もうひとつは、権威主義的で攻撃的な国家では、国力のピークを過ぎた時期が最も危険だという点である。ロシアは人口減少期に入った時期であるし、中国は経済成長のピークを越え出生率も減少に転じたところである。人口動態と経済発展はリンクしている。決断は、まだ余力のあるこの時期を逸するとチャンスを失うというギリギリの時点で下される。1939年のドイツも「機会の窓」が閉じつつあるタイミングだった。
戦争は冷徹な戦略によって遂行される。その結果は多くの犠牲者と被害を意味している。為政者は被害や犠牲を見つめるだけでなく、そこに至らないための「冷徹」なシミュレーションを行わなければならない。「冷徹な思考」が国民を救うこともある。感情や同情や善意では敵を防げないのが現実である。
橋本由美
『拒否戦略 中国派遣阻止への米国の防衛戦略』 エルブリッジ・A・コルビー著 塚本勝也・押手順一訳/ 日本経済新聞出版 2021
『アジア・ファースト 新・アメリカの軍事戦略』 エルブリッジ・A・コルビー著 奧山真司訳/ 文春新書 2024
『大国政治の悲劇』ジョン・J・ミアシャイマー著 奥山真司訳 /五月書房新社 2017
『リベラリズムという妄想』ジョン・J・ミアシャイマー著 新田享子訳 伊藤貫解説 /経営科学出版 2024
『マッキンダーの地政学 デモクラシーの理想と現実』 H・J・マッキンダー著 曾村保信訳/ 原書房 2008
『米中新産業WAR』遠藤誉著/ ビジネス社 2025
トランプ「半導体に100%の関税」 追い上げる中国製半導体 | 中国問題グローバル研究所
<編集部からのお知らせ1>
8/16発売の最新号『表現者クライテリオン 9月号 財務省は敵か味方か?』 好評発売中!
本誌の詳細はこちらから

<編集部からのお知らせ2>
クライテリオン叢書第5弾、『敗戦とトラウマ 次こそ「正しく」戦えるか』、書店・Amazon等で公表発売中!
|
|
敗戦とトラウマ |
執筆者 :
CATEGORY :
NEW

2026.02.27
NEW

2026.02.26
NEW

2026.02.26
NEW

2026.02.24
NEW
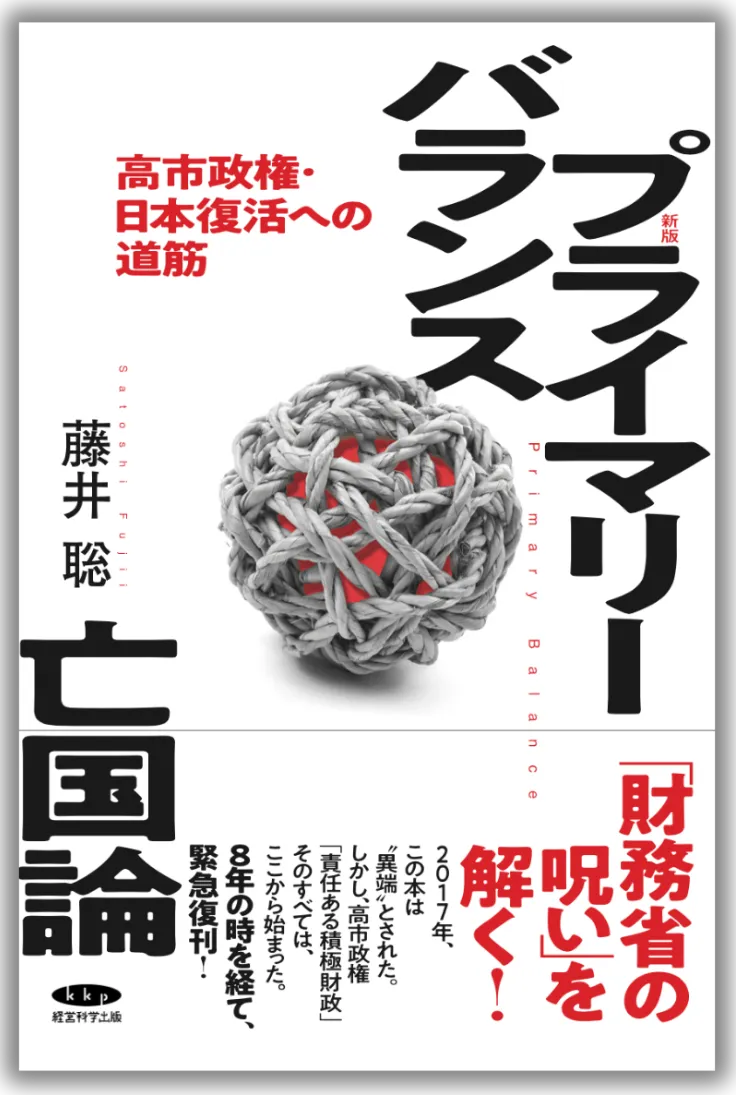
2026.02.23
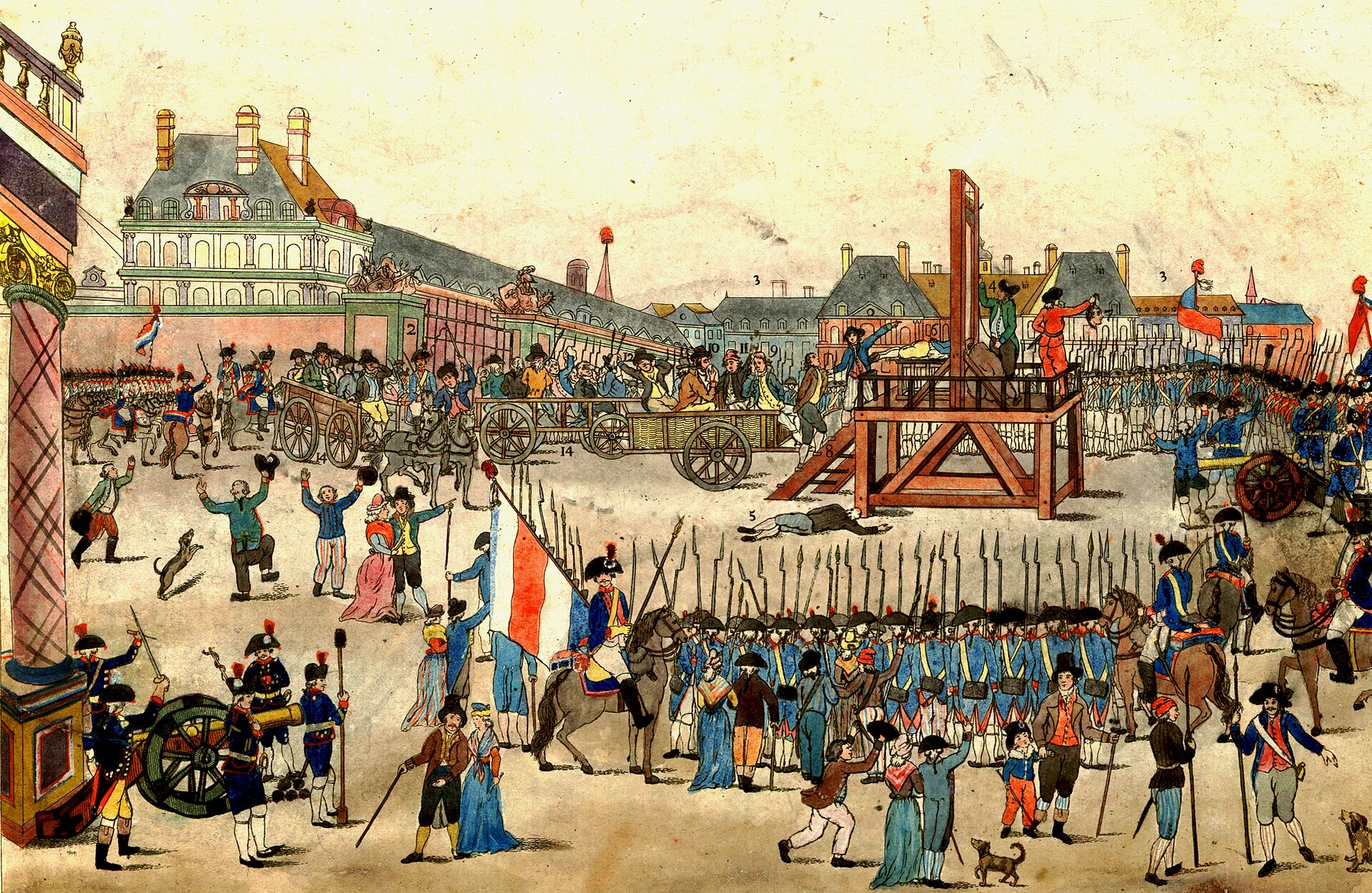
2026.02.20
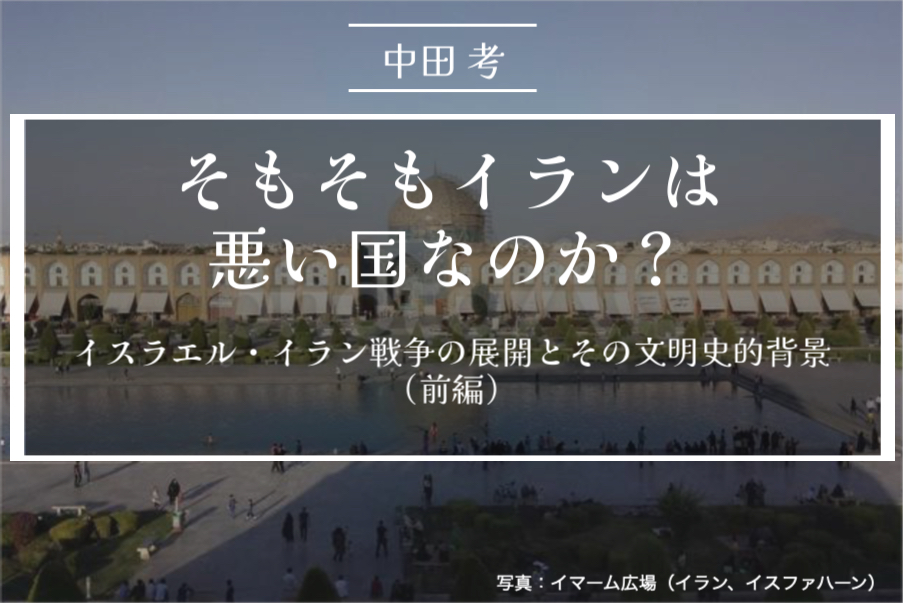
2025.06.24

2021.06.23

2021.06.22
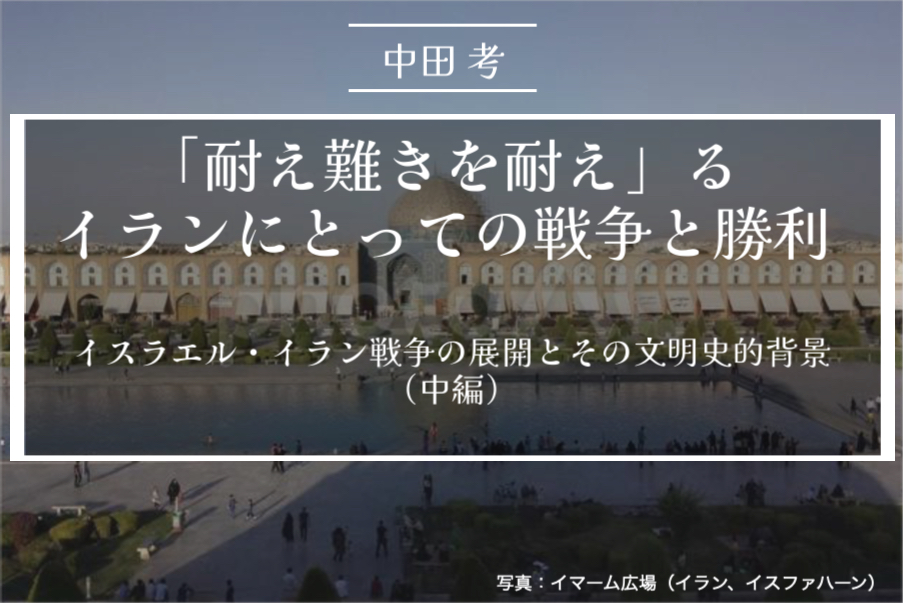
2025.07.07
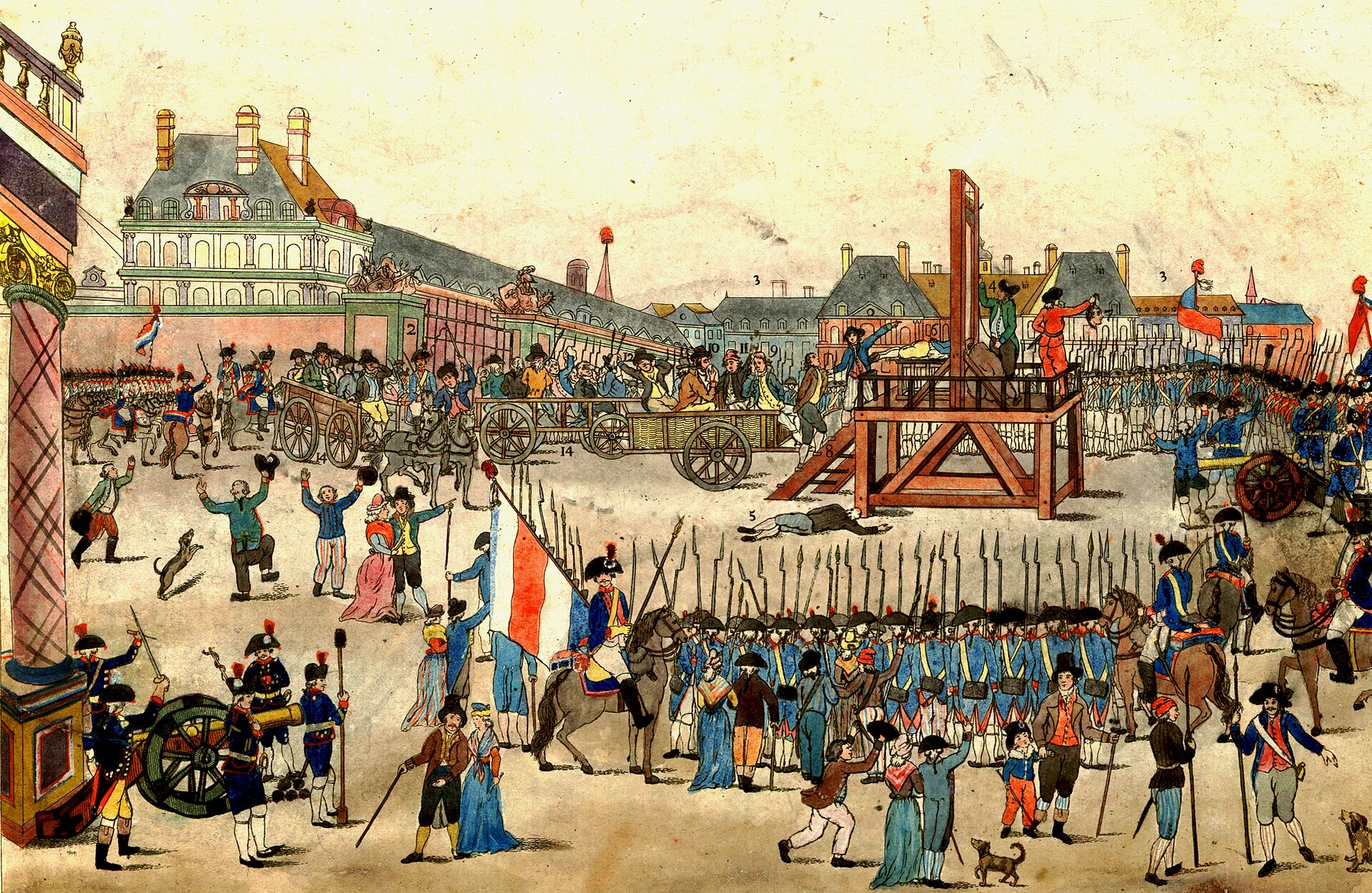
2026.02.20

2025.07.09
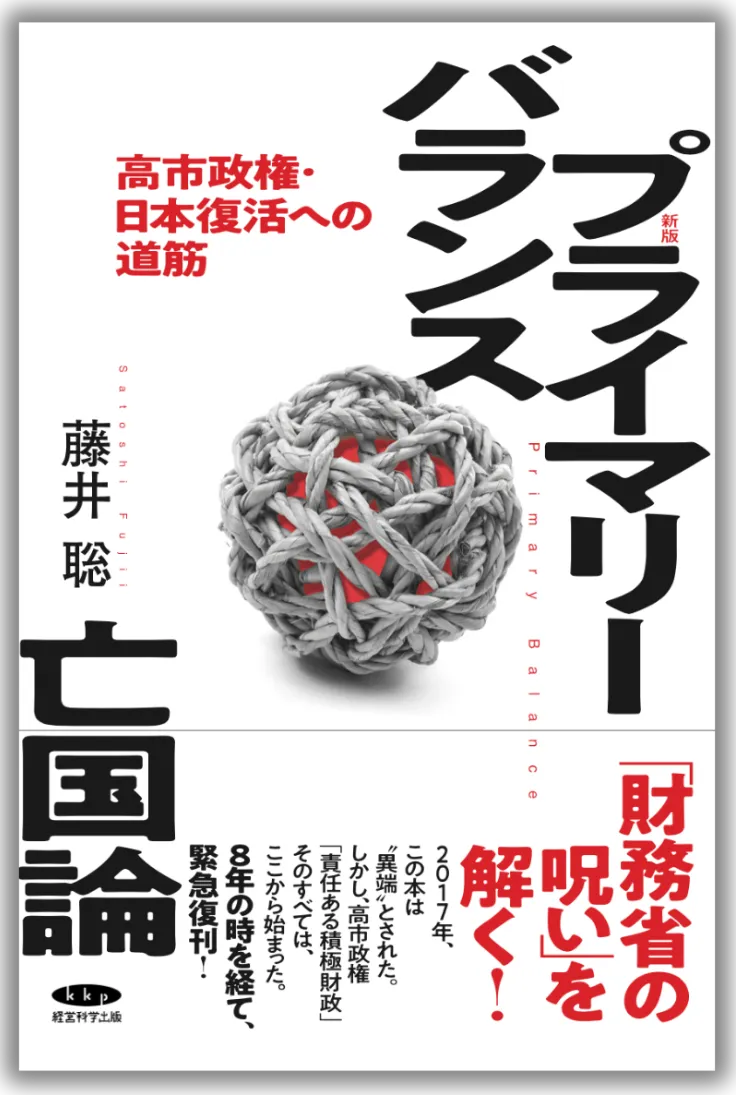
2026.02.23

2026.02.27

2026.02.26
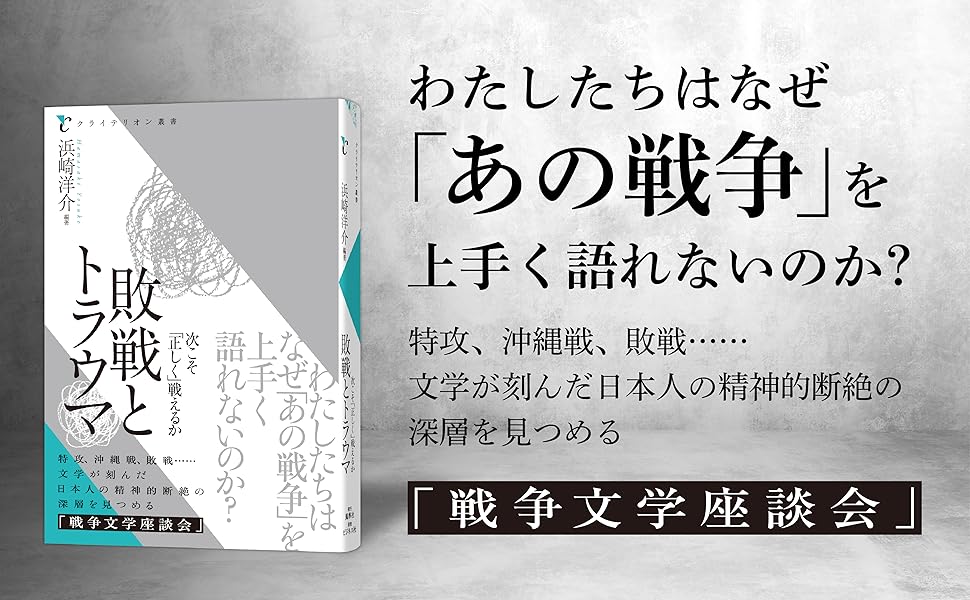
2025.08.01