江藤淳という難問
平成という時代を終えた今、江藤淳という人物をどのように評価すべきなのか。 『夏目漱石』の批評から始まり、保守言論人として「戦後」という時代に対する違和感を全身でもって表現してきたこの文芸批評家を浩瀚な評伝は生き生きと描き出した。 江藤の自殺の数時間前に直接本人から原稿を受け取った著者渾身の作である。
江藤の歴史や国家の問題への向き合い方は、自己の外なるものとしての「政治」的なものへの向き合い方であると同時に、江藤淳その人の内部に巣食う深い「故郷喪失」を克服する道でもあった。江藤は幼くして「母」を失い、唯一の「故郷」でもあり亡き母の記憶が残る「胎内」でもあった「百人町の家」を空襲で無くした。そして最後にはその「母」の分身でもある「妻」をも失うことになる彼の批評は、まさに生涯を通じた「故郷喪失」を埋めるための自己内対話でもあったのだ。江藤がアメリカで古典を読むなかで再発見した「日本」も、もはやそれは「戦後」の日本ではない。
彼が幼少時代に五感で感じた、記憶のなかの母とあの百人町の家のある「日本」である。記憶のなかのあるべき故郷の姿と現実の姿(「日本という疵ついた作品」)との間で引き裂かれた江藤にとって、「戦後」とは「悲しみ」の時代なのである。「戦後」を克服するとは、これら「故郷喪失」の「深い癒しがたい悲しみ」を乗り越え、癒すことなのであった。『成熟と喪失』における「母」の存在への探求や勝海舟や西郷隆盛を巡る「歴史」との対論、そして戦後体制(憲法、検閲)批判もこうした失われた故郷への「再訪」を果たそうとする試みだったとも言えるだろう。
彼が懐古する幕末、明治、大正、昭和へと続く近代日本の記憶も物語も、もしかすると敗戦という「断絶」によってすでに失われてしまった過去であり、我々にとっても「悲しみ」の感情なくしては振り返ることのできない過去なのかもしれない。重要なのはこうした「悲しみ」あるいは「喪失」をまずは受け止める姿勢なのだろう。惨憺たる故郷の現状から目を背け、過ぎ去った時代の栄光や華やかなりし時代の記憶に自己の本来性を求めて一体化を図るロマン主義的な誘惑、そこから江藤は逃れることはできなかった。
失われた過去が幼少期に体験した母や祖父の記憶と結びついた過去でもあったからであろう。しかし目を背けても、この「悲しみ」は決して癒されることなく存在し続ける。すでに「戦後」に養われた我々にとって、そこ(戦前)にあるのはもはや「故郷」ではなく「異郷」なのかもしれないのだから。「戦後」という現状の単なる否定ではなく、そのなかに過去からの「連続」を積極的に見出していく智慧はむしろ「故郷喪失」の苦悩に徹するなかでこそ生じてくるのではないか。「戦前」と「戦後」の狭間で苦しんだ知識人、江藤淳はただ甦らせるだけで終えてはならない、むしろ乗り越えていかねばならない令和時代の課題の一つなのであろう。
岡崎祐貴 (『表現者クライテリオン』2019年9月号より)
ご購入はこちらから
執筆者 :
CATEGORY :
NEW

2026.02.07
NEW

2026.02.06
NEW

2026.02.05

2026.01.30

2026.01.30

2026.01.29

2026.02.05
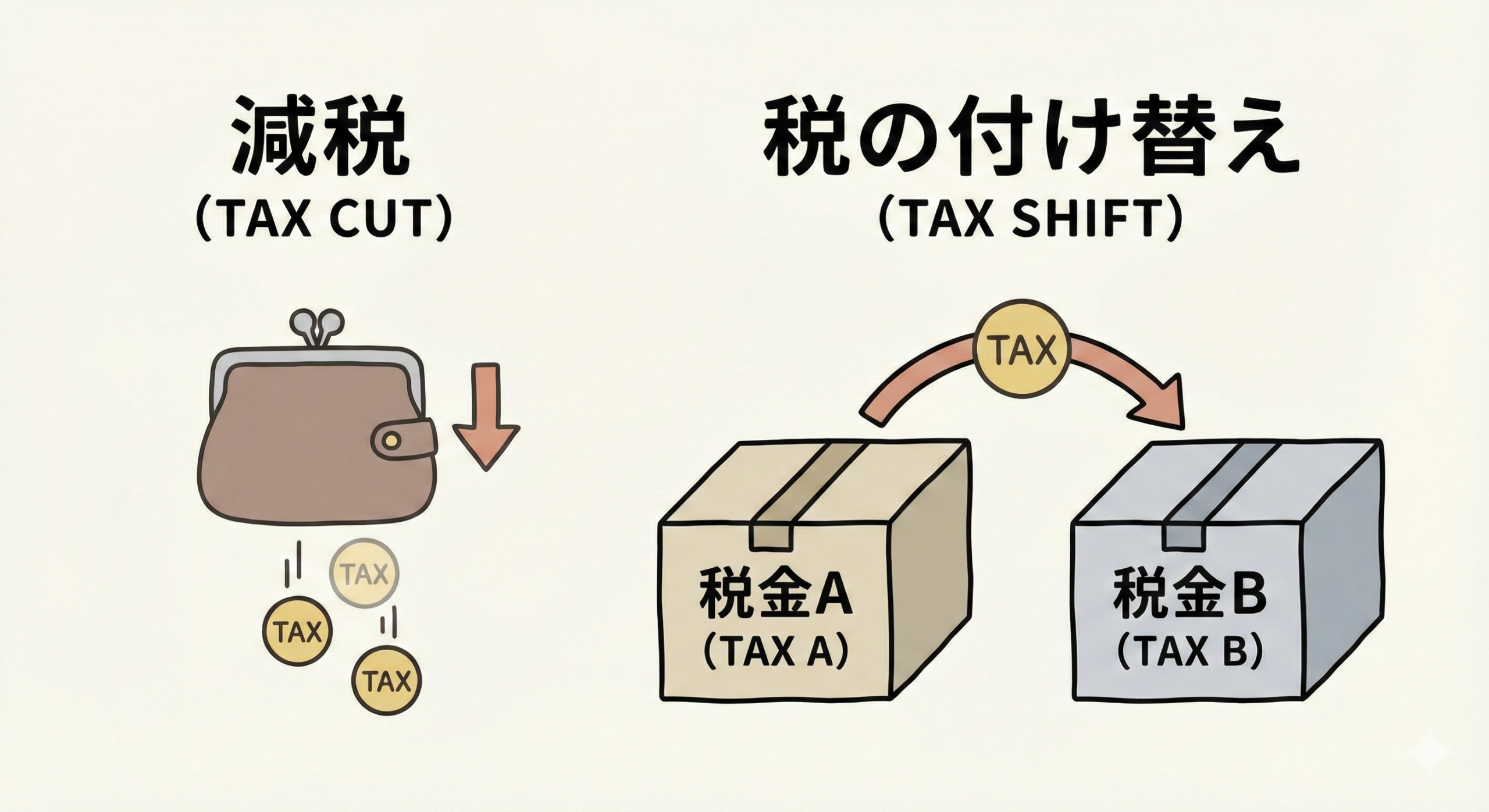
2026.01.18

2024.08.11

2026.01.20

2026.02.06

2026.01.30

2018.04.06

2026.01.30

2018.09.06

2020.07.06
コメント
江藤淳についての個人的な記憶を以下に述べる。
若い頃図書館で見つけて
途中まで読んだあまりにも長い評論「漱石とその時代」と
その後三島由紀夫の「金閣寺」の対談で
文芸批評の神様と恐れられた小林秀雄との
やりとりが印象に残った関係で
彼の戦後の文芸評論の後継者と目された
その人はどうゆう人なのかと思っていた。
そうしたら、今度はきちんとした身なりの
国立大学教官として
NHKの公論解説で一般大衆の前に出てきた。
そして最後は妻の後を追って終焉し
かつての文学者が辿ったと同じ印象に帰ってきた。
誰かも言っていたが処女作「漱石とその時代」は
学者的考証の塊で異常に長い作品だが
内容的に「未完」であった
この近代と格闘した複雑な精神満載の国民作家の評論を
仕上げて欲しかった思いが強い。