高校の世界史で習うレコンキスタは、8世紀からイスラム勢力が支配していたイベリア半島をキリスト教勢力が復権するまでの国土回復運動のことを指していて、抗争は1492年のグラナダ陥落で終結した。しかし、当時の国家は、現在の国家とは違う。イベリア半島北部にあったいくつもの弱小なキリスト教国は、それぞれが豊かな南部のイスラム勢力と共存したり妥協したり争ったりしていて、イスラム勢力に団結して立ち向かっていたわけではない。西欧のキリスト教王国と連携して、イスラム勢力下にあった豊かな土地を奪おうと軍事化していく過程で、レコンキスタ(Reconquista = reconquest)が宗教対立のイデオロギーとなっていったようである。キリスト教徒が団結してイスラム勢力に立ち向かい「キリスト教国家」を復興したという物語は、スペイン王国の正当性を表すために脚色されていったもので、20世紀のスペイン内戦でもイデオロギーとして利用された。
近年、現在の境界線を不服とする国家が、嘗ての歴史や物語を根拠に、過去に失った勢力圏を回復しようとする動きが各地で見られる。世界で見られる対立は、広い意味でのレコンキスタと言えなくもない。大陸にある国々は、長い年月の間に何度も近隣諸国と戦い、ときには大帝国に呑まれ、その都度、領土が増減したり、国境が書き換えられたり、国そのものを失ったりした。いまのレコンキスタでは、いつの時代の領土を回復しようとするのか、それぞれの言い分はいろいろだが、大国は自国の最盛期の領土を想定することが多い。最も栄華を誇った時代の過去へのノスタルジアも漂う。
レコンキスタというのは、厄介な国家感情である「喪失感」を伴う。「所有していない」という事実でも、初めから所有していないときと、所有していたものを失ったときでは、まったく違う感情を呼び起こす。失ったときには「痛み」を強く感じるのである。恋をしたことがないときには当たり前だった単身生活も、恋人を失って独りになった時には、単身であることに「喪失感」が生じる。子供を失った夫婦やペットロスも同じで、初めからいなかった場合にはない「喪失感」が漂うようになる。
持っているはずのものを、いまは失ってしまったというだけならば、寂寥を帯びた自己憐憫で済むが、「誰かに奪われて」喪失した場合は、奪った相手を憎悪するルサンチマンとなる。為政者は、何百年も前の争いの結果であっても、「あの土地は、もともと自分たちの土地だった」という意識を国民に植え付けることで、「喪失感」を作り出して煽ることができる。自分が生まれる幾世代も前の遠い昔のことであっても、国家の喪失感はナショナリズムに訴える効果がある。
約2500年に亘って強烈な喪失感を持ち続けたユダヤ人が、20世紀になって祖先の地にイスラエルを再建したのもレコンキスタと言えるだろう。ダビデが古代イスラエル国家を建設したとき、そこには他の民族が住んでいて、その土地の民族の神ではなく、自分たちの神の啓示によって土地を奪った。2500年も経ってから戻ってきたときにも、そこには他の民族が住んでいて、当然ながら争いが起こる。イスラエルのレコンキスタの成就は、他民族の新たな憎悪とレコンキスタを生んだ。
オスマントルコ帝国は、13世紀から勢力を伸ばし、16世紀にはエジプトからシリア地方、バルカン半島に至る広大な地域を勢力下に置いた。いまのところトルコ共和国は往時の図版を自国の領土と主張するような無謀なことはしていない。しかし、もし、アナトリアを侵食されたら彼らはレコンキスタを起こすだろう。
プーチンにとって、ソ連崩壊後の勢力圏の喪失は耐え難い屈辱だったはずだ。それでも、ワルシャワ条約機構下にあった東ヨーロッパ諸国が次々とNATOに加盟していくのは、(自国の衰退を突き付けられることであっても)ヨーロッパへの回帰として黙認するしかなかったのではないだろうか。しかし、2008年のブカレスト合意がグルジアとウクライナを将来NATOに加盟させることを承認したのは、プーチンの忍耐の限界を超える決定だった。プーチンが発し続けた警告は無視された。アメリカやNATOはロシアを衰退する国家として見下していたとも言える。ウクライナ戦争は、プーチンの生涯とロシアの威信を賭けたレコンキスタである。
日本人に、大日本帝国の勢力圏だった朝鮮半島や台湾やパラオ諸島を「回復」しようという意思は全くない。日本の最大図版であっても、日本人はそれらが自分たちの固有の領土だとは考えていない。しかし、北方領土や沖縄となると話は違う。中国は、以前から琉球が中国に属すると主張していたが、最近、その声が大きくなっていて世界中に帰属の正当性を発信している。中国にとって、琉球は台湾と同じくレコンキスタの対象であるという主張である。
中国には「国恥地図」というものがある。ここからは、譚璐美の著書『中国「国恥地図」の謎を解く』によって、話を進める。著者は、香港返還直後に耳にした「国恥地図」というものをネット上で検索して、その画像に驚くと同時に興味を持ち、後日、本格的な調査をして、結果を一冊の本にまとめた。(著者が見たネット上の地図の画像は既に削除されているという。)戦前の日本の出版社との関係など、興味深い事実を丹念に調べ上げているが、ここではすべて割愛して、「国恥地図」が作られた意図と地図上で扱われた範囲について見ていくことにする。
返還直前の香港で『近代中国 百年国恥地図』という人民出版社刊行の小冊子がブームになっていた。人民出版社は中国政府直営の出版社と言っていい。政府公認の冊子ということである。この時期に出版されたというのは、香港が「奪われていた」ことに関係があるのだろう。序文にはアヘン戦争に始まる国家の恥辱が綴られ、中でも日本から受けた屈辱と、日本の政治家が「ひとつの中国」を認めず、台湾を支持していることが糾弾されている。
この小冊子が扱っている「国恥地図」が初めて作成されたのは中華民国時代である。1929年、蒋介石の国民政府が「革命記念日」を制定したとき、同時に6つの「国恥記念日」を制定した。アヘン戦争後の南京条約や義和団事件後の北京議定書、日本の二十一か条の要求などの締結日が含まれる。その後、上海事変や満州事変も追加され、1930年には8つの「国恥記念日」となった。現在の中国では法的な記念日ではないが、その日には各地で記念行事が開催されている。「国恥」という言葉は、1915年の二十一か条要求のときに現れたのが最初で、8つの国恥記念日のうち、6つが日本に関係している。「国恥」とは、日本への敵意が反映された言葉であることがわかる。
『近代中国 百年国恥地図』という冊子は、愛国主義教育のために作成されたものだった。著者は、この冊子に載った地図の実物を見たいと調査を始め、その過程で、嘗て「国恥地図」が小学校の教科書に載っていたことを知る。「国恥地図」では、現在の国境を黒、「本来の境界」を赤で示している。教科書の発行年によって多少異なる場合があるが、それにしても現在の国境に比べて、彼らが赤線で認定している「本来」の領域は異常なほど広範である。

1933年(昭和8年)の世界輿地學社「小學適用本國新地圖」(Wikipedia)
赤線で示された領域は、北から時計回りに、黒竜江以北のシベリア南部、沿海州、樺太、朝鮮半島、東シナ海、琉球列島、台湾、南シナ海、ベトナム・カンボジアからマレー半島を含むミャンマーまでの東南アジア半島部の全域、チベット、ブータン、ネパール、カザフスタンまでのスタン5か国、北上して、ロシア南部からモンゴルに至る広大な地域のすべてを含む。カザフスタンや沿海州や黒竜江北岸などのロシアの勢力圏も含まれていて、いまは反米で協調をしていても、嘗てのように、いずれ二国間の国境紛争になる可能性がある地域である。黒竜江(アムール川)北部にはロシア人の人口は少なく、すでに中国資本が入り込んで侵食しているらしい。
「国恥地図」に赤線で囲まれた領域は、清王朝の最盛期に、朝貢国を含めた「清が世界だと認識していた」範囲である。認識できる世界を勝手に領地だと決め込んでいた清王朝時代の最大図版を「回復」するというのはレコンキスタではないだろう。清王朝にとっては満州が本来の国土であり、漢民族にとっては「中原」が本来の国土である。中原を占領されたなら、そこを取り返そうとするのは、中国にとって立派な国土回復運動である。しかし、マレー半島やシャム王国やビルマ王国、キルギスのトルキスタンの人々は、自分たちが「清」の国民だと思っていただろうか。スタン地域や東南アジアは、中国から奪われた土地ではなく、現在そこを支配していないからと言って「国恥」になるような話ではない。
著者の調査によれば、「国恥地図」のベースマップ(基本になっている地形図)は日本人の作図技術によるものだという。中国に世界地図をもたらしたのは、マテオ・リッチだった。それまでの中国古来の地図と異なり五大陸を描いたもので、中国中心の世界観に打撃を与えたという。その後、康煕・擁正・乾隆の時代には地図の制作に資金が投じられ、「皇輿全覧図」という初の実測図が作られた。しかし、この地図は密かに西洋に持ち出され、アヘン戦争に利用された。これに危機感を持った清朝政府は、以後、測量と地図製作を全面的に禁止し、製図技術が衰退してしまった。
日清戦争や義和団事件の敗北で近代化の重要性を痛感した中国では、日本への留学生が増えた。同時に、上海では「日本ブーム」が起きて、日本の近代化に学ぶために、多くの日本の出版物が漢訳された。日本で使われていた教科書も翻訳され、親が子供の教育用に購入したためベストセラーになっていたという。このとき、中国の地図の作成に携わったのが日本人で、京都大学地理学教室の創始者・小川琢治博士と共に地図の共同制作を行ったことのある木崎盛政という製図技術の第一人者だった。彼は上海に渡り、上海商務印書館の依頼で「大清帝国全図」を作成した。光緒三十一年、1905年の発行である。
この地図では、中国の南限が「香港」になっていて、これについて、譚璐美は次のように書いている。「中国領の『南限』は、現代の中国政府が取る強硬な姿勢に大いに関わる話だ。それがこの『大清帝国全図』には、南シナ海が一切描かれておらず、1905年の段階では、南シナ海は中国領だとは認識していなかったことを示唆している。」また、「国恥キャンペーン」が始まった直後の1929年発行と思われる上海中央輿地学社の「中華国恥地図」は、図面最下部ぎりぎりのところに海南島が描かれている。このことから、譚璐美は、1929年ごろの認識では、中国領土の南限が海南島だったのではないかと述べている。「国恥地図」の中国の領土領海がだんだん広がって、2007年頃から急に「南沙諸島は二千年来、中国の領土だった」と言い始めたのだという。
著者によれば、同志社大学の村田雄二郎教授は「中国が主権や領土について考え始めたのは1880年以降のことだった」と述べている。アヘン戦争で香港を割譲されたときには、現代の感覚とは異なり、中国はそれほど深刻な問題だと考えていなかったのではないかと言う。清王朝の繁栄期に人口が増加したが、19世紀から20世紀初頭にかけて断続的に飢饉が発生して大衆の貧困化が激しくなり、太平天国の大混乱を招くような国内要因があったことも、主権や領土の重要性についてについて考える余裕を与えなかった可能性がある。
更に、両者の領土認識の違いを考慮しなければいけない。これは、インドがベンガル地方の徴税権をイギリス東インド会社に褒賞として与えたことが植民地化の原因になったことに似ている。非西洋世界には、国土や国境に関して、西洋の領土や主権の概念とはまったく異なる認識があったことは間違いない。近代の領土や主権の概念は、西洋においてさえも17世紀末になってからようやく共通認識になったものである。近代化以前の異なる文明間の交渉で、領土に対する認識のずれがあっても互いに気がつかないということはありえる。
中国には、古代からの朝貢による勢力圏の認識と近代の国境認識とのずれも、未だに「感覚」として残っているのかもしれない。嘗ての朝貢の記憶、現代の制度、国恥意識、それらが曖昧に混ざり合い、意図的にナショナリズムの醸成に政治利用されているとも言える。小学生のころから「国恥地図」を叩き込まれた世代の国民は、「失地」の屈辱意識を刷り込まれ、ルサンチマン感情のスローガンである「中国民族の偉大な復興」という「中国の夢」の実現のために、レコンキスタを肯定するようになる。
あるいは、西洋が勝手に決めたルールである国際法などは無視しても構わないと考えているかもしれない。中国には何千年も前からの歴史観や独自のルールがあるという自信が垣間見える。中国は、プーチンがロシアの歴史観によって行動するのを否定しない。西洋でさえ、トランプが現行制度を無視して「俺さまルール」で世界を変えようとしているではないか。中国が、自国の制度や歴史観を優先して何が悪い……。むしろ、アメリカが脱退した国際機関を利用して、世界を中国ルールに変えていこうという意図が感じられる。
中国が、いま最も「失地回復」に力を注いでいるのが「台湾」である。南シナ海を領有化して台湾を併合したとしたら、東シナ海・琉球列島の領有も主張するかもしれない。そうすれば、第一次列島線の完全な破壊が達成され、日本列島を孤立させることができる。
「国恥地図」に琉球列島が含まれていることには警戒を要する。中国では教科書や「国恥地図」で、琉球列島は「沖縄県」ではなく奪われた国土だと、教育しているのである。国民への教育だけでなく、福建省には「琉球館」を建て、「琉球地位未定論」を世界に発信し続けて、琉球列島が本来は中国領で「失地」であると主張している。既に尖閣の周辺では建造物の建設に着手している。彼らは琉球列島領有のためにはどんな理由でも「作って」しまうだろう。中国の言い分を馬鹿馬鹿しいと笑って聞き流すのは危ない。
台湾に好意的な態度を示している高市総理の内閣である限り、中国が日本に対して攻撃的な態度を収めることはなく、寧ろ、今後、何か中国を刺激するようなことがあれば、一層強硬な姿勢をとるようになるだろう。国力で日本を凌いだという自信を持ったいま、「日中友好」を装う必要はなくなった。何ごとも責任は日本に転嫁される。中国に関係する事項や言動はどんなに些細なことでも慎重さが求められる。中国の本気度を疑わないほうがいい。
『中国「国恥地図」の謎を解く』譚璐美著 /新潮新書 2021
『世界史年表・地図』亀井高孝・三上次男・林健太郎・堀米庸三 編 /吉川弘文館 1995 (2022年版)
『「再征服」はなぜ八百年かかったのか』黒田祐我著 /NHK出版(世界史のリテラシー)2025
橋本由美
2月16日に『表現者クライテリオン2026年3月号』が発売となります。
今回の特集は、
「『中国の限界』は幻か?──その強さの裏にある“歪み”」
まやかしの「崩壊論」や「万能論」から距離を置き、経済、社会、地政学、思想、文明的に中国という国の本質とその限界を徹底的に論じました。
ぜひ、ご一読ください。
|
|
2026年3月号 |
執筆者 :
CATEGORY :
NEW

2026.02.06
NEW

2026.02.05
NEW

2026.01.30
NEW

2026.01.30

2026.01.29

2026.01.23
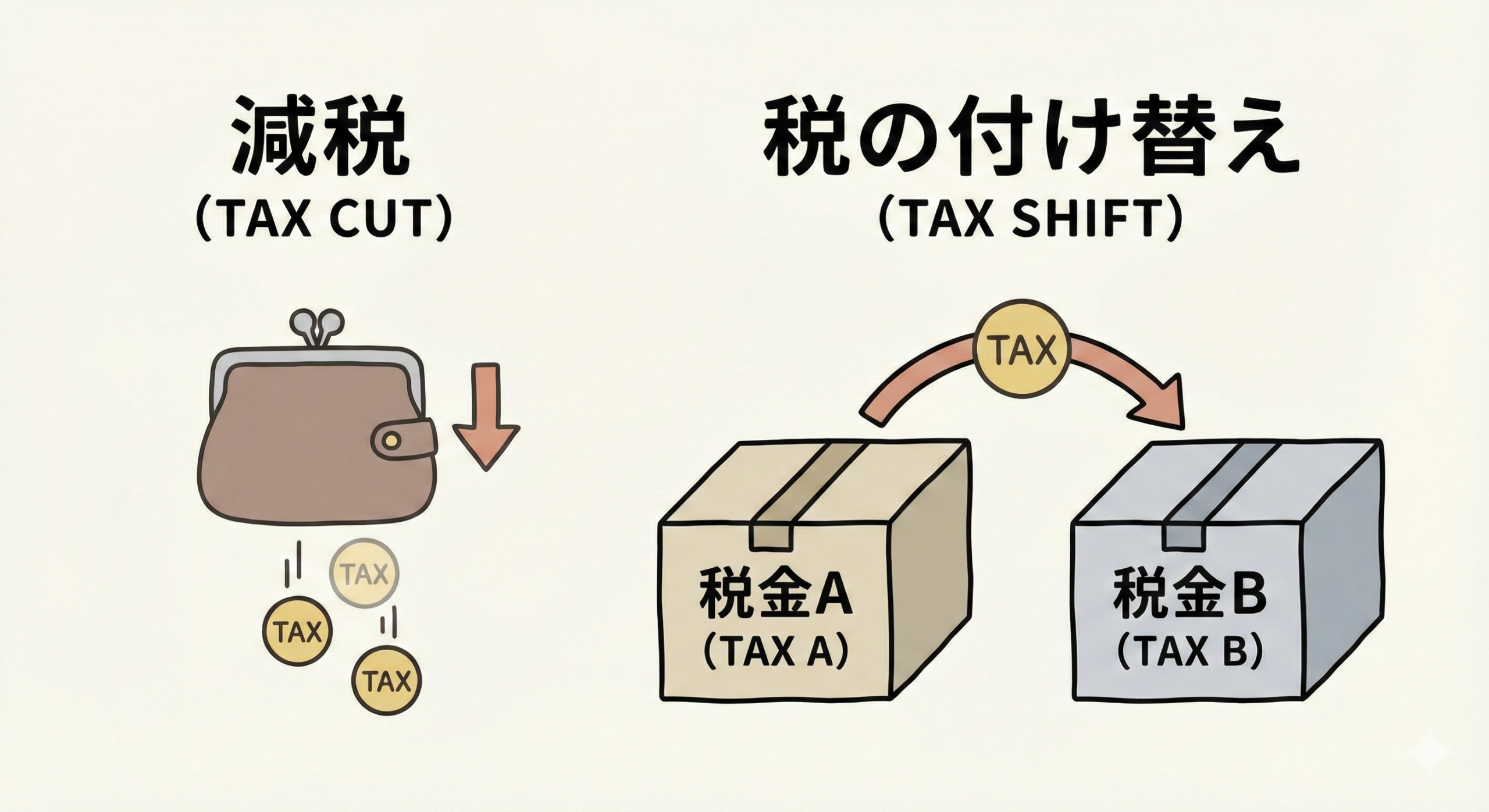
2026.01.18

2026.01.20

2026.02.05

2024.08.11

2026.01.30

2026.01.30

2018.04.06

2018.09.06

2018.03.02

2026.01.22