いつもお世話になっております。『表現者クライテリオン』事務局です。
本日は、先日の衆議院総選挙の結果を受け、2025年12月16日発売の『表現者クライテリオン 1月号 『高市現象』の正体』より、柴山桂太先生の特集論考「戦略的介入主義の時代―高市現象が示す日本政治の転換」を特別に全文公開いたします。
本論考は総選挙前に執筆されたものですが、本稿の中で柴山先生が指摘した「高市支持の中核は都市部にある」という分析は、選挙で示された結果とも符合しており、今回の選挙を振り返る上でもぜひご一読ください。
「なぜ今、高市なのか」――
誰もが驚いたこの結果の背景には何があるのか?『表現者クライテリオン 1月号』では、この事態を「高市現象の正体」として分析。日本、そして世界の、ここから始まる「大転換」を見据えつつ、多角的に論じています。
新政権の行方と、日本社会の構造的転換を深く読み解く「規準(クライテリオン)」として、ぜひご覧ください。
柴山 桂太
片や大都市の生活不安、片や地方の産業衰退。二つの課題に応えるには効果的な政府介入と、総合的な投資政策が必要だ。
高市現象は、世界各地で起きている新たな政治潮流が、いよいよ日本にも到来したことを物語っている。二〇一六年のブレグジット(英EU離脱)やトランプ一期目の選出からおよそ十年で、その波が日本にも到来したことになる。とはいえ、細部に目を向ければ、トランプ現象と高市現象の間には無視できない違いもある。
英米を皮切りに始まった今の潮流は、さしあたりグローバル化への反動と理解することができるだろう。冷戦終結後に本格化した自由貿易の流れは、輸送通信分野での技術進歩と結びついて、世界経済に劇的な変化をもたらすことになった。これまで「北」に集中していた生産拠点は人件費の安い「南」の国々へと拡散した。商品の多様化や価格の下落で先進国の消費者は恩恵を受けたが、国内の産業構造の急速な変化で、大多数の労働者が所得の停滞を余儀なくされることになった。
特に深刻な打撃を受けたのが地方である。生産拠点の海外移転によって産業は空洞化、若年層の都市部への流出が進んだ。税収の減少は地方財政を圧迫し、交通、医療、教育といった生活インフラは徐々に痩せ細っていった。こうした地方の不満と閉塞感がトランプ現象を準備することになった。二〇一六年や二〇二四年の大統領選挙の結果を見ても、地方ほどトランプ支持が高く、大都市ほど反トランプの傾向が顕著である。「アメリカを再び偉大にする」として高関税を課し、製造業の生産拠点を強引に米国国内に回帰させる政策は、専門家からその実効性が強く疑問視されているにもかかわらず、地方において根強い支持を集めている――政策そのものに期待しているというよりも、長年、政治エリートから「見捨てられてきた」と感じてきた人々にとって、初めて自分たちの側に立つ政治指導者が現れたと受け止められているのである。イギリスのブレグジットも、ロンドンのような大都市はEU「残留」支持者が多かったのに対し、産業の衰退が著しい地方ではEU「離脱」に投票する傾向が見られた。その意味で、ブレグジットやトランプ現象には、グローバル化に対する「地方の反乱」という側面がある。
高市現象はどうか。新聞各社が就任直後に実施した支持率調査で、七割から八割近くが支持と答える首相が登場するのは、久しぶりのことと言ってよい。ただし日本の場合、高市支持が強いのは地方よりも都市部である。二〇二四年の自民党総裁選での党員・党友票を見ると、石破氏が地方票で優位に立ったのに対し、高市氏は東京、愛知、大阪などの大都市で支持される傾向にあった。今回(二〇二五年)の総裁選でも、東京や愛知、また関西圏(高市氏のお膝元なので当然かもしれないが)では高市支持がはっきり出る一方で、地方では票が分散し、石破政権の継承色が強い小泉氏が最多得票となっているところも一一県あった。高い支持率から見て、高市人気は今や全国的な現象となっていると推測できるが、自民党員の声に限ってみれば、高市現象は大都市圏とその周辺で際立っているのである。
これは、グローバル化の弊害が日本では、とりわけ都市部で意識され始めている、ということなのであろう。訪日外国人観光客が押し寄せることで地元住民の生活が掻き乱される「オーバーツーリズム」は、東京や大阪、京都などで顕著である。特に京都では観光地の混雑が限界を超えており、もうこれ以上来ないでくれとの声が上がり始めているが、一方で、地方を見れば、外国人観光客の誘致にまだまだ熱を入れているところが少なくない。
外国人投資家がマンションや不動産を高値で買い占めているとされる問題も、住宅価格の高騰が続く東京では一刻も早い規制を求める声が多いが、地価の低迷が続く地方では、それほどの切迫感は見られない。経済安全保障についても、大企業の本社機能が集中している大都市ほど、サプライチェーン(供給網)の強靱化が重要な政策課題として意識されている。逆に地方では人手不足の方が深刻な問題となっており、農業だけでなく製造業やサービス業の現場でも、外国人労働者の活用範囲の拡大を要望する声が大きくなっている。
ここにトランプ現象と高市現象の無視できない違いがある、というのが私の見立てである。アメリカの場合、ラストベルト(錆びついた地帯)を中心に、製造業の空洞化で良質な雇用が失われ、軍事産業の基盤さえ揺らいでいると危機感を募らせる地方の保守層が、トランプ人気を支えている。そのためトランプ大統領の政策は、地方の製造業再生を重視している反面、大都市に厳しい――正確に言うと、トランプ氏自身もその一人である大都市の超富裕層は減税政策などで優遇されるが、移民労働者を多く含む都市部の中下位層には冷淡な態度を取っている。
日本では、高市支持の中核にいるのは大都市の保守層である。住宅費や教育費が高い大都市では、所得水準が高い中上位層でも生活の豊かさを実感できない。サプライチェーンの混乱や地政学的リスクが、大企業のホワイトカラー層の将来不安を高めている。また、最初は地方にやってくる外国人労働者も、やがて同胞が多く働き口も多様な大都市へと移り住んでいくため、大都市の周辺に移民コミュニティが形成されやすく、そのことへの文化的反発も生じやすい。高市首相が掲げる経済安全保障政策や外国人政策が支持される土壌は、日本の場合、都市部の方にあるのだ。
この違いは、これからトランプ政権や高市政権が直面する困難を予想する上でも重要である。アメリカでは、反トランプの狼煙は大都市から上がってくることになるだろう。実際、十一月のニューヨーク市長選挙では、急進左派のマムダニ氏が勝利した。保育の無償化や家賃の凍結、市営食料品店の開店など中下層向けの政策を掲げる一方で、不動産の空室税や富裕層増税など、明確な再分配志向を打ち出す民主社会主義者である。このようにアメリカでは、これから大都市が反トランプの最前線となり、やがてその波が地方にも波及していく局面を迎えるかもしれない。
日本の場合、高市政権はまだ発足したばかりであるため、この先に起こることを予測するのは難しい。ただ、これまで述べてきたことを踏まえるなら、地方の支持を広げていくことが安定政権への鍵となるだろう。日本でも、製造業の海外移転で地方経済は大きな打撃を受けている。それでも英米型の「地方の反乱」が起きないのは、東京などの大都市が人口を無際限に吸い上げてきた結果、「反乱」を組織する政治的エネルギーさえ枯渇してしまったのだと思われる。一方に都市部の生活不安があり、他方に地方の人口減少や産業衰退の如何ともしがたい現実がある。この二つの課題に応えるには、高市首相が公約とする「危機管理投資」を地方への投資と結びつけて、経済安全保障と地方再生を同時に進めていくしかない。
そのために必要となるのが、積極財政への転換である。というのも、従来のように財政に厳しい制約を課したままでは、地方への投資が都市からの「持ち出し」として理解され、都市部の不満を増大させかねないからである。都市部のサラリーマン層の手取りを増やしつつ、地方への投資を拡大して国家全体の経済安全保障を強固なものにしていく。地方での産業や雇用の受け皿が拡大すれば、人口集中の緩和や生活コストの安定という形で、都市の利益にもなる。そのための国家の積極的な投資政策と、その意義を国民に明確に伝える政治的メッセージが求められている。
これは単純な反グローバル化ではない。行きすぎた市場依存や海外依存への反省から、政府の力を適切に用いて、資源や人口を国内に再配置していく是正の取り組みである。いま世界各国で始まりつつある、こうした再編の動きを前号(巻末オピニオン「国家主義(ステイティズム)の時代 単なる反グローバリズムの先にあるもの」)では「国家主義(ステイティズム)」と呼んだ。しかし、国家主義という言葉は手垢が付きすぎており、市民的自由を犠牲にしても国家目標が優先される時代錯誤の体制を想起させるため、ここで新たに「戦略的介入主義」と呼び直しておきたい。
戦略的介入主義とは、国家の安全や経済社会の持続性に関わる分野に限って、政府が選択的に介入し、市場の偏りや外部依存を反映していこうとする立場である。それは何かまったく新しい理念を指しているわけではなく、この十年ほどの間に、世界の主要国で現実に進みつつある政策転換である。
転換の徴候が見え始めたのは、二〇一五年の前後である。この頃から、ロシアや中国が、アメリカ中心の国際秩序に対して、より明確な挑戦を始めた。ロシアはクリミアを併合し、後のウクライナ侵攻へつながる動きが加速した。中国は一帯一路構想を打ち出すのみならず、「中国製造2025」でアメリカの先端技術分野に追いつくという産業政策の大目標を掲げた。冷戦終結後のグローバル化で、経済的な相互依存は国際平和を強固にするというリベラル派の楽観的な幻想は打ち砕かれ、むしろ相互依存がリスクや脆弱性を生み出すという現実的な認識へと急転換したのである。
また二〇一五年前後は、産業政策が国際的に再評価され始めた時期である。新自由主義の時代には、政府の産業政策は市場を歪める介入として否定的に扱われていた。しかし中国の台頭は、こうした議論を根底から揺さぶった。国の「成功」は明らかに、経済自由主義のみに基づくものではないからである。一方で、一九九〇年代以後のアメリカで起きた新技術の開花も、個別企業のイノベーションの成果という以上に、政府による軍事投資や科学技術投資の成果であるとするM・マッツカートの研究(『企業家としての国家』)も、各国の政策担当者に強い影響を及ぼした。
現実政治も変化し始める。二〇一六年の大統領選で勝利し、翌年に発足したトランプ政権は、保護関税の強化や製造業回帰を前面に掲げ、WTOの自由貿易ルールを無視する姿勢を明確にした。バイデン政権も半導体への補助金政策などの巨額の財政拡大で、戦略的産業の国内回帰を制度化した。その後の第二期トランプ政権は、一期目を上回る高関税と、日欧韓から巨額の対米投資を引き出すディールを半ば強引に取りまとめた。トランプ、バイデン両陣営の対立は激しく、また関税と補助金というように政策手段も異なるが、政府介入による国内生産体制の再構築と、対中依存度の低減は国家戦略として継続されている。
欧州でも、グローバル化が安全保障上の脆弱性や、域内の産業基盤の弱体化をもたらしたという反省から、「開かれた戦略的自律」を新たな柱と掲げるようになった。自由貿易と国際協調を基本路線として維持しつつも、エネルギー、半導体、重要鉱物といった戦略分野では、特定の国への過度な依存を減らし、域内生産や調達先の多様化によって自立性を高めるという考え方である。中国との関係については、フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長が「デカップリング(切り離し)ではなくデリスキング(リスク低減)」を宣言し、リスクの高い分野の依存度を計画的に下げていく方針を明確にしている。
サッチャー・レーガン改革が新自由主義時代の始まりだとすれば、二〇一五年頃から始まっているのは、新自由主義から戦略的介入主義への転換である、と理解しておきたい。重要なのは、こうした政策転換が、安全保障の強化という国家理性に基づいて行われているだけでなく、先進地域で没落が進む中間層の再生という課題にも答えようとしているという点である。
「K字型経済」とも呼ばれるように、一部の上位層の所得、特に資本所得が急速に伸びる一方で、中間層以下の実質所得は下降し、インフレによる生活費の上昇に追いつかなくなっている。住宅価格の高騰や教育費の負担増、移民流入によるアイデンティティの揺らぎなどが重なり、中間層から生活の安定が急速に失われた。地方では製造業の衰退、都心部では過密と生活費高騰という形で、異なる形の不満が蓄積し、その政治的反動がトランプ現象や急進左派の躍進という形で現れてきたのが、この十年の政治動向であった。
このような状況にあっては、成長戦略や財政規律をめぐる従来型の議論では、社会の不安定化という現実に対処できない。経済の脆弱な部分に政府が選択的に介入し、産業や雇用の基盤を再構築することは、安全保障上の要請であると同時に、民主主義の安定を回復するためにも不可欠な政策課題となっているのである。
経済安全保障相を務め、積極財政にも理解を示してきた高市首相が、必要な政策転換を主導する上で、ふさわしい政治家の一人であるのは間違いない。ただ、日本の戦略的介入主義が高市政権から始まる、というわけではない。実際、「経済安全保障推進法」が制定され、重要物資の供給網強靱化や基幹インフラの安全性確保、先端技術の育成といった枠組みが制度的に整えられたのは岸田政権期であり、高市氏はこの時の経済安保相であった。また地方創生は、実効性のある政策にはほとんどつながらなかったとはいえ、石破前首相が強くこだわったテーマであった。日本でもこの十年で新自由主義からの政策転換は、少しずつではあったが進んでいた。ただし、経済安全保障と地方の産業再生の双方は結びつけられては論じられていなかったし、踏み込んだ政策を行うための財源の壁にも直面していた。しかし今は、野党にも積極財政を主張する政党が増えてきたこともあって、状況は好転しつつあるように見える。
高市政権に求められているのは、こうした政策課題を組み合わせて総合的な投資政策を実施していくことにある。それは都市部の不安や不満を宥めるものであると同時に、衰退が続く地方に未来への希望を持たせるものでなければならない。自由主義経済の原則を守りつつも、脆弱性の高い部分に戦略的に働きかける必要があり、場合によっては国境の壁を部分的に高めるような保護的措置も選択肢に入ってくる――例えばこの先、世界的な景気後退によって各国が生き残りをかけたダンピング競争に入った場合には、国内の生産者を守るために躊躇なく関税を引き上げる判断が求められる局面も出てくるだろう。
これは政府介入の範囲や規模の拡大という意味で国家主義的である。しかし同時に、国家の安全保障が強化されることで社会が安定し、個々の活力が高まるという意味では、自由主義的でもある。国家と市場の関係は、時代の転換とともに常に再検討され、その境界線は引き直されてきた。そう考えるなら、これから本格化する戦略的介入主義の時代とは、各国が各様に、新しい時代にふさわしい自由主義の形を模索していく時代であると言うこともできるはずである。
今回の衆院選の結果の背後にある思想的構造を理解するために、
ぜひ特集の全容をお読みください。
【特集座談会】
【特集インタビュー】
【特集論考】
「責任ある積極財政」を掲げる自民・維新連立による「高市政権」が誕生した。この政権誕生を予期できた者はほんの数年前までは「皆無」であり、国会の権力構造を考えれば高市政権は「絶対無理」と言い得る幻の如きものだった。にも関わらず高市政権が現実に誕生したのは偏に国民がそれを希求したからだ。
結果、高市政権は極めて高い支持率で滑り出したのだが、この「高市現象」とでも言うべき社会現象は、財務省解体デモやオールドメディア批判の全国的広がり、近年の国政選挙における参政党や国民民主党の躍進の流れにあると共に、世界的に広がる「反移民運動」の潮流とも軌を一にしている。しかも21世紀に入ってからのブレグジットやトランプ大統領の誕生、欧州各国の保守政党の躍進とも通底する。
かくしてこの「高市現象」は日本、そして世界の「大転換」を暗示する重大な意味を持ち得るのではないかとの思想的予感の下、本誌では日本と世界の未来を占うべく、政治家「高市早苗」と日本国民の集合的無意識の双方を見据えつつ「高市現象の正体」を多面的に論ずることとした。
表現者クライテリオン編集長 藤井 聡
執筆者 :
NEW
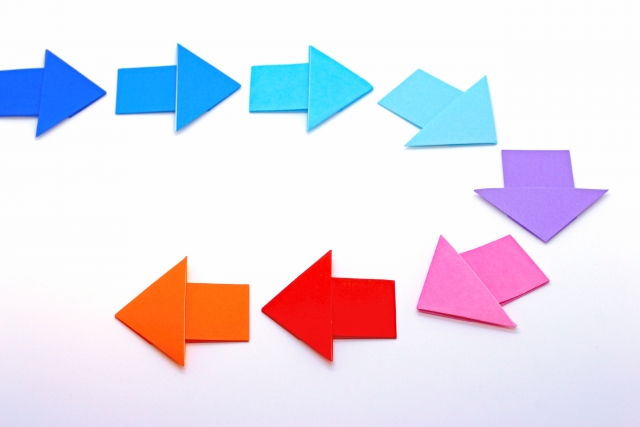
2026.02.16
NEW

2026.02.16
NEW

2026.02.13
NEW

2026.02.12
NEW

2026.02.11
NEW

2026.02.09

2026.02.09

2026.02.12

2026.02.11

2026.02.13

2024.08.11

2026.01.20

2026.02.06

2022.10.25

2018.03.02

2023.10.12