こんにちは、浜崎洋介です。
今日は、表現者塾の塾生の方から頂いた、「文化とは何か」という質問――より正確に言えば、「文化を感ずる肌感覚とはどのような感覚なのか」という質問――に答えてみようと思います。
というのも、それを問い直すことは、質問者の方自身が、「日本人の精神的土壌を立て直す第一歩ではなかろうか」と言うように、たしかに、「保守思想」を原理的に考え直すことに繋がるのと同時に、今、目の前にある「コロナ自粛の空気」の異様さを、ひいては、その文化破壊の様相を浮かび上がらせることにも繋がって来るように思われるからです。メルマガという場で、どこまで答えられるか分かりませんが、できるだけ丁寧に議論していきたいと思います。(いつもののように、質問の全文は、文末に示しておきます)。
まず初めに、20世紀の言語哲学者ウィトゲンシュタインによる示唆的な言葉、人間の「理解」という行為をめぐって書かれた次のような一節を挙げておきます。
「『そう言い終わってから彼は、前の日のように彼女のもとを立ち去った。』―私はこの文を理解するか? 私はそれを、ある報告の中で聞いた時のように理解するか? もしここでこの文が孤立しているのなら、何のことかわからないと私は言うだろう。それなのに私は、この文をどのように使えばよいのかはわかるだろう。私は、この文が使われる文脈すら考え出せるだろう。(これらの言葉からは、よく知られた一群の小道があらゆる方向へと延びている。)」『哲学探究』1部525節―鬼界彰夫訳
あるいは、この「理解するか?」という言葉を「味わうか?」という言葉に言い換えた方が、「文化」の議論には接続しやすいかもしれません。が、いずれにしろ、この一節でウィトゲンシュタインが問うているのは、あるモノやコトを理解する(味わう)ために、私たちが引き受けている条件とは、どのようなものなのかということです。
ウィトゲンシュタインも言うように、たしかに、「そう言い終わってから彼は、前の日のように彼女のもとを立ち去った」という文は、それだけを読んでも何を言っているかが全く分かりません。が、この文が置かれた状況(コンテキスト=小道)を想像してみるとどうでしょう。上司の男が部下の女に何かを指示して立ち去っていく状況、あるいは、片思いの男が女に告白して立ち去っていく状況、はたまた、孤独なテロリストの男が、ときの権力者である女政治家の選挙ポスターに向かって何かを吐き捨てて立ち去っていく状況……。その背景を想像するだけで、「そう言い終わってから彼は、前の日のように彼女のもとを立ち去った。」という一文は、急に色づいて見えはじめます。
つまり、ウィトゲンシュタインが示唆しているのは、あるモノやコトが〈理解できている=味わえている〉のは、そのモノやコトの属性のみならず、それが置かれた文脈が作用している限りだということです。言い換えれば、あるモノ(図)の理解や味わいは、そのモノ自体(図)が原因なのではなく、そのモノ(図)と、それが置かれたコンテキスト=文脈(地)との関係から来るのだということです。そして、その関係を脈絡づけている流れ、要するに、無限に多様なコンテキストから、適切なコンテキストを切り出し、そのモノを脈絡づける「生活形式」、それを私たちは「文化」と呼んでいるのではないかということです。
あるいは、これとよく似た話として、私は、よく「塩」の例を持ち出します。
たとえば、「台所(という地)」に「塩(という図)」が置かれている場合、私たちは、それを難なく理解し、使用し、また安心して味わうことができるでしょう。が、「塩」が「郵便受け」にあった場合はどうでしょうか。おそらく、その不気味さに、私たちはおそるおそる手を伸ばし、「これは塩なのか? もしかすると、塩に見せかけた毒ではないのか?」などと疑いながら、ある場合には、ちょっと舐めてから、それが「塩」であることを確認するかもしれません。しかし、そうなると、もはや、その行為は「毒味」のようなものとなってしまい、私たちは、その「塩」を十分に理解する(味わう)ことはできないでしょう。
その点、質問者の方が言うように、我流で点てた抹茶が「どこか隙があり、すかすかな感じの味で、重み」がないのに比べて、「裏千家の茶室」で、「先生の点てる抹茶の味は温かみがあり、味の重みのようなものを感じ」たというのも理由のないことではありません。
おそらく、その差は、「抹茶」そのものの味から来ていると言うより、すでに質問者の方が自覚されているように、「茶道特有の所作・振る舞い」、「茶室の室温や湿度」など、目の前の「抹茶」を取り囲む様々な文脈から齎された差ではないのかということです(さらに言えば、和歌や、俳句や、私小説など、日本の文学は、その〈文脈=地〉がなければ理解できないものの代表格であり、その享受者は高い文脈把握能力が要求されますが、その意味で言えば、「文化の洗練」とは、まさしく、この図と地の関係を複雑化していくことだと言ってもいいのかもしれません――それゆえ、ときに「文化」は、その文脈を読める人と、読めない人とを区別する≒階層化する装置としても機能することもあります。)
しかし、それは逆に言えば、その文脈把握能力を失ってしまった場合、私たちは、目の前に置かれたモノやコトに対する理解(味わい)を失ってしまうのだということでもあります。
それについて、たとえば、現象学的精神病理学の開拓者の一人であるブランケンブルクは、統合失調症患者の性格の一つとして、極度の文脈把握能力(自明性)の喪失を指摘しつつ、そのとき失われる「Haben」(Have=所有)の感覚について、次のように書いていました。
「このHabenという(助)動詞には、所有の意味と完了時制の意味が同時に含まれている。だれもが《〔すでに〕いとも簡単に所有している》ところの、事物に対する自明な関係は、過去へ向かっての連続性(Kontinuität nach rückwärts)ということと自己の所有(Selbstbesitz)ということを同時に意味している」(『自明性の喪失―分裂病の現象学』木村敏・岡本進・島弘嗣訳、みすず書房)
ここで、ブランケンブルクが指摘しているのは、たとえば英語のhaveが「持つ」という動詞であると同時に、完了形の助動詞(過去と現在との関係を表す助動詞)でもあるということからも分かるように、人々の自明な経験が、「過去との連続性」を「持つ」ことによって成り立っているという人間的事実です。もし、「過去」の文脈(地)を持てなくなってしまえば、私たちは、郵便受けの中に突然「塩」を見つけてしまった人間のように、あるいは、未知のウィルスに怯える現代人のように、そして、あのブランケンブルクが症例として挙げていたアンネ・ラウのように、眼前のモノに目を釘づけにされてしまうばかりで、そのモノを理解するための「余裕」や「現実感」(自明性)を失ってしまうのだということです。
いや、さらに言えば、この「have」の感覚は、私たちが音楽を楽しむ際の経験を想い出したほうが納得し易いかもしれない。たとえば、一つの音楽が奏でられたとき、私たちは、過去へと流れ去って行く音を聞きながら、しかし、その過去を「持つ」ことによって、それぞれの音を一つの流れ=メロディへと統合しています。さもないと音楽は、聞いたそばから、単なる音(物理現象)へと分解されてしまい、私たちは、それを一つの「流れ」として味わうことができません。つまり、「ド・レ・ミ」の中にある「ミ」は、すでに「ド」と「レ」を引き受けている限りで、単なる「ミ」とは質が違うのだということです。
そして、それが納得できれば、「伝統」について福田恆存が語った次のような言葉も、決して大袈裟には聞こえてこないはずです。福田は言います、「文化とは生き方であります。適応異常や狂気から人を守る術であり、智慧であります。〔…中略…〕文化がなければ、私たちは生きられないのだといふことを自覚していただきたい。狂気と異常から身を守るために、それがどうしても必要なのです」(「伝統にたいする心構」昭和三十五年)と。
では、最後の問いとして、それなら「文化」を育ててきたものとは一体何なのでしょうか。それこそは「歴史」なのだと言いたいところですが、しかし、そう言うと、ほとんど同語反復になってしまうので、ここでは、少し視点を変えてみましょう。すると、先の問いは、次のように言い換えられることが分かります。すなわち、「人間の文脈力を育ててきたものとは一体何なのか」と。
というのも、これまで見てきたように、まさに「文化」とは、目の前のモノやコトを理解するために私たちが作り出してきた「一群の小道」、つまり、図と地の関係を読み、その関係=文脈を作っていく能力そのものの異名だからです。
しかし、それなら、答えは明らかでしょう。おそらく、人と人との「あいだ」を取り持ってきた「社交」、それこそが、私たちの「文化」を育ててきたものの基盤にあるものなのです(そもそも、「お茶」も「短歌」も「俳句」も全て、「社交」するための方法=道具として見出されていたことを想い出してください)。
では、なぜ「社交」が〈文脈力=文化力〉を育てることになるのか?
それは、「社交」こそが、人と人との「あいだ」にある流れを感じ取り、そこに一つの文脈を生成させていくゲーム、言い換えれば、他者を受け入れ、言葉を交換し、それに基づいて、私たちの「理解の仕方」を育てていく営み(礼儀・作法の育成)――だからです。
たとえば、「そう言い終わってから彼は、前の日のように彼女のもとを立ち去った」という一文を想い出してください。その文章について、私が、いくらでも違う文脈を考えられるように、他者もまた、それについて無限に多くの文脈を想像できてしまうのです。とすれば、目の前のモノ・コトについての理解を生成させていくためには、私たちは、一つの文脈に固着しすぎても、また無頓着であってもいけないということになる。まさに、固着と無頓着の「あいだ」でバランスをとりながら――醒めて踊りながら――、その都度〈我と汝〉を取り囲んでいる条件(与えられた土地・歴史・記憶・言葉)を鑑み、それに従って紡がれてきた共通感覚を拾い上げ、互いの文脈を折り合わせていくこと、その長い長い実践の積み重ねの結果として齎されたもの、それこそが「文化」だということです。
しかし、それゆえに、「文化」のない社会は、何でもありのアナーキズム(自由放任)に傾くか、一つの意味に固着し、それを絶対化する権威主義(全体主義)へと傾いていってしまうのです。そして、だからこそ私たちは、「他者」と定期的に集まり、そこで会話をし、固定化した文脈の「こわばり」を揉みほぐし、一つの「図」に対して複数の「地」(解釈)を重ね合わせ、それらを折り合わせていくための「社交」を容易に放棄してはならないのです。というのも、その時間と場所こそが、自然の流れのなかから、その時と処と立場に合った適切な言葉を選び出し、振る舞っていくという「常識」(遊びとしての言語ゲームと、その実感)を、つまり「演戯」としての「文化」を導いてきたものなのだから。
しかし、それなら、やはり他者との「遊び」を抑圧し、「社交」を放棄させ、たった一つの文脈(ゼロ・コロナ!)に人間を縛り付ける「過剰自粛」は――あるいは、社会のリモート化は――私たちの〈文脈把握能力=文化〉を著しく毀損していると言わなければなりません。事実、この一年間のリモート授業で、大学生の社交力=常識力=文化力は間違いなく後退しています(それは、現場で教えている私自身が一番肌身で感じています)。
そして、それはまた、一つの文脈への固着を排し、移動し、また違う文脈へと接続していくという人間的な能力(あるいは柔軟さ)を、つまり、動物から人間を分かち、野蛮人から文明人を区別する「会話」の能力を私たちから奪っていくことにもなるでしょう。
20世紀イギリスの政治哲学者で、保守思想家でもあるマイケル・オークショットは、「人類の会話」について、次のように述べていました。
「会話においては、参加者達は、研究や論争にかかわるのではない。そこには、発見されるべき「真理」も、証明されるべき命題や、めざされるいかなる結論もない。彼らは互いに知識を伝達したり、説得したり、論駁したりすることにたずさわるのではなく、したがって彼らの発話の適切さは、彼らがみな一律の用語法で語るということに依存しているのでもない。彼らは互いに異なっていても、あい入れ得ないわけではない。もちろん、会話が議論の言葉を含んでいてもよいし、論証が話者に禁じられているわけでもない。〔中略〕会話では「事実」は現れるたびごとに、それが生じてきたところの諸可能性の中へともう一度解体されるのであり、「確実性」は、他の「確実性」や懐疑と照らし合わされることによってではなく、また別の系列の諸観念の存在によって点火されることによって、その可燃性が示される。」「人類の会話における詩の言葉」1959年
だからこそ、大した根拠もなく、酒場から、学校から、大学から、職場から「会話」を奪っていく「過剰自粛」は、人間にとって「毒」なのです。ただ、逆に言えば、そんなことも分からないほどに、すでに日本人の「文化力」は地に落ちてしまっているということなのかもしれませんが。
いずれにしろ、この拙文が、質問者の方にとって、「文化とは何か」について考える切っ掛けになれば幸いです。また、表現者塾での「会話」を楽しみにしています。
また、質問者の方からの質問を以下に示しておきます。
先生の皆様が考える「文化」とは何ですか?
また、その「文化」を感ずる肌感覚とはどのような感覚なのでしょうか?
確かに、福田恆存の「伝統にたいする心構」の引用で、
「文化とは生き方であり、適応異常や狂気から人を守る術であり、智慧である。一朝一夕に出来るものではない。」
と書いてあります。
私は趣味で「抹茶」を点てます。
しかし、流派には属していないので、ある意味”我流”です。そこで、流派に属する先生の点てる抹茶と自分の点てる抹茶の何が違うのかを確かめるべく、ある茶室を訪ねました。
そこは裏千家の茶室でしたが、先生の点てる抹茶の味は温かみがあり、味の”重み”のようなものを感じました。しかし、私が点てた抹茶はどこか隙があり、”すかすかな感じ”の味で、重みがありませんでした。そこで私が思ったのは、茶道特有の所作・振る舞いから、茶室の室温や湿度など、科学的に測定できない「経験値的な肌感覚」の違いが、味の違いとして現れたのではないかと思いました。
そうした、土地環境の中で培われ築き上げられた「経験値的な肌感覚」が”形”として現れるのが「文化」なのでしょうか?
「和歌」についても思うことがあります。
短歌は個人の想いを歌にする。つまり、個人が出発点と言われます。和歌は「自然の中にいる貴方と私」。つまり、自然と私とのやりとり、または、自然の中で起こる人間模様を誰もが共感できるよう、価値観を共有する。そうした「決まり事」を守った上で想いを歌にする。その現れた歌そのものが「文化」となっていくのでしょうか?
分かりにくい文章かもしれませんが、文化というものを感ずる肌感覚について知りたく、質問させて頂きました。
そうした肌感覚を日本人に共有するには、そうした感覚を持っており、それを身体感覚で説明していく事が、日本人の精神的土壌を立て直す第一歩ではなかろうかと考えるからであります。
メルマガの記事でも構いませんので、ご回答頂けたらと思います。
2月16日に発売になった『表現者クライテリオン』の最新号(3月号)では、「抗中論―超大国へのレジスタンス」と題した特集を企画していますが、第二特集として「コロナが導く社会崩壊」も企画しています。以上のメルマガの内容を、より詳しく具体的に吟味したいと言う方は、是非、『表現者クライテリオン』の最新号を、お求めいただければと思います。
『表現者クライテリオン』2021年3月号発売中!
本誌はその他、人と社会のあらゆる問題を様々なテーマに沿ってお届け。毎回読み応え抜群です!
気になった方はぜひ以下から本誌を購入してみてください!
『表現者クライテリオン』2021年3月号
「抗中論 超大国へのレジスタンス」
https://the-criterion.jp/backnumber/95_202103/
メールマガジンではいち早く記事更新やイベント情報をお届け!
無料で購読できます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メルマガのバックナンバーはこちらで閲覧頂けます。
https://the-criterion.jp/category/mail-magazine/
雑誌『表現者クライテリオン』の定期購読はこちらから。
https://the-criterion.jp/subscription/
Twitter公式アカウントはこちらです。フォローお願いします。
https://twitter.com/h_criterion
その他『表現者クライテリオン』関連の情報は、下記サイトにて。
https://the-criterion.jp
ご感想&質問&お問合せ(『表現者クライテリオン』編集部)
info@the-criterion.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
執筆者 :
CATEGORY :
NEW

2025.06.27
NEW

2025.06.26

2025.06.24
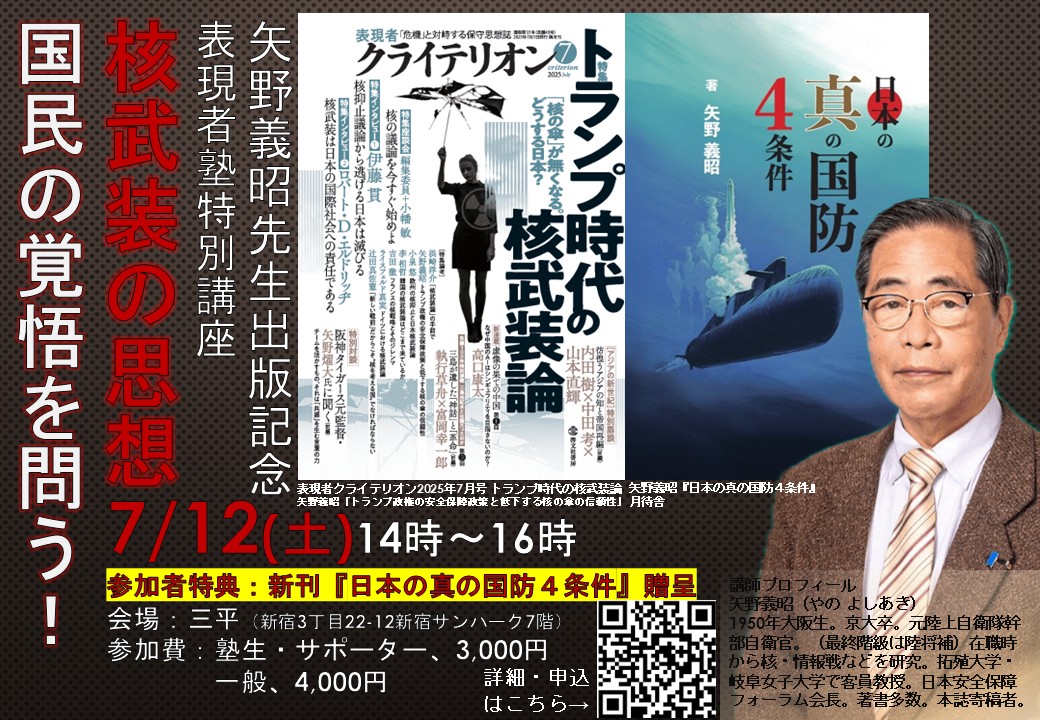
2025.06.24
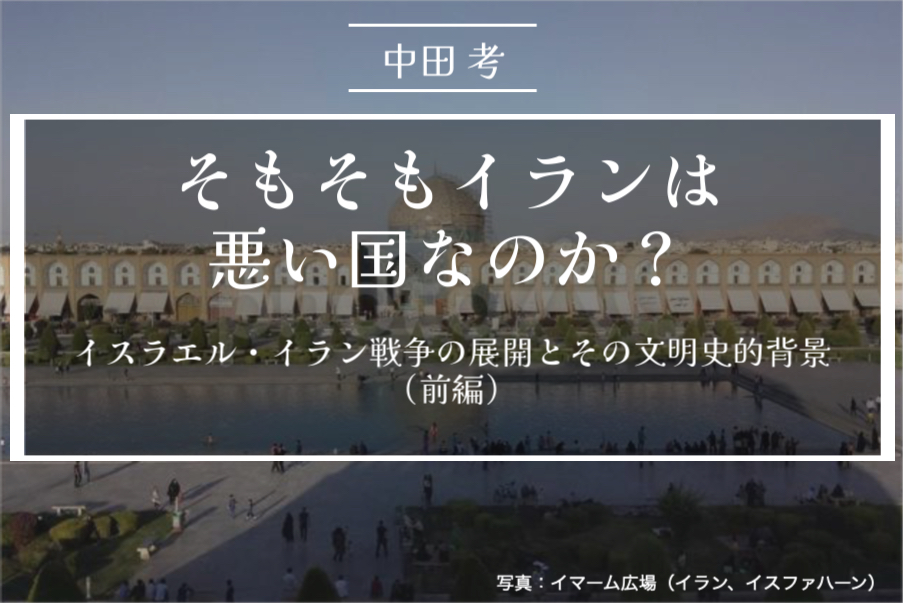
2025.06.24
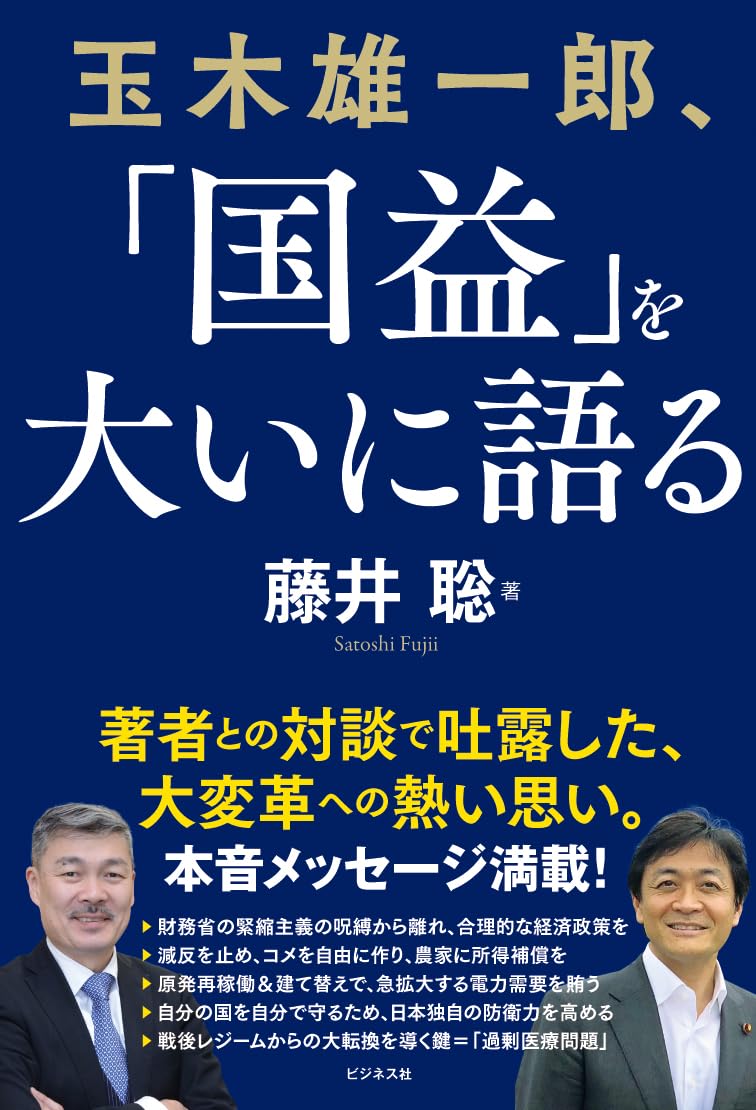
2025.06.21
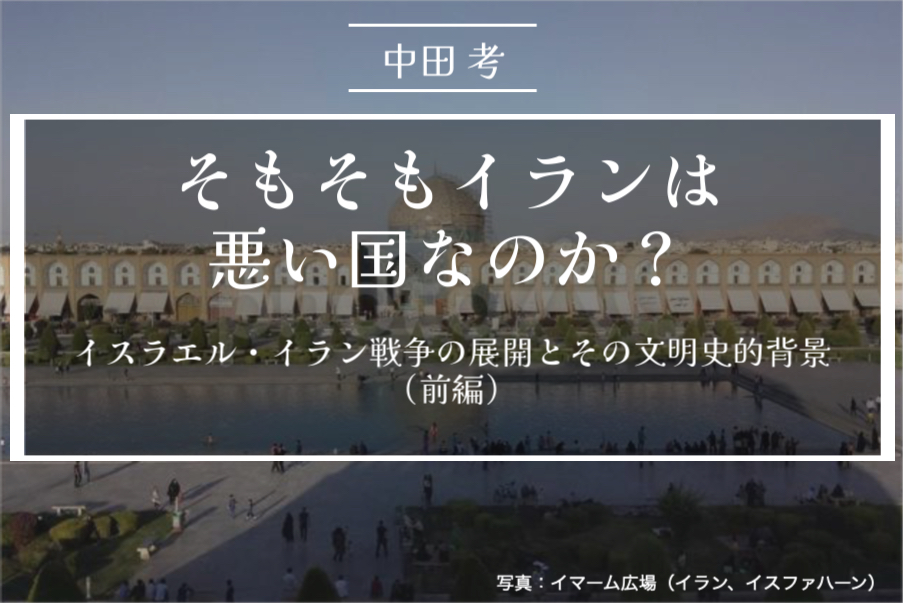
2025.06.24

2025.06.26

2024.08.11

2025.06.27

2024.07.13
.jpg)
2025.06.03

2025.06.20
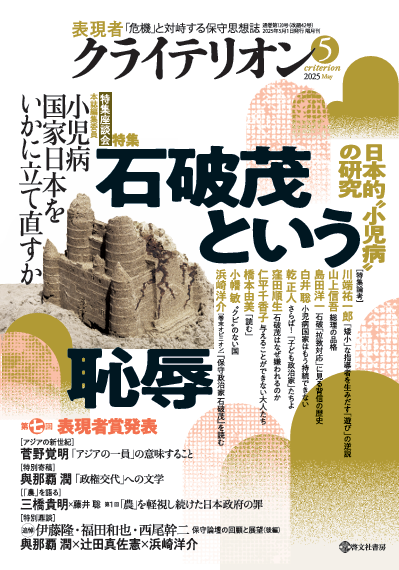
2025.04.21
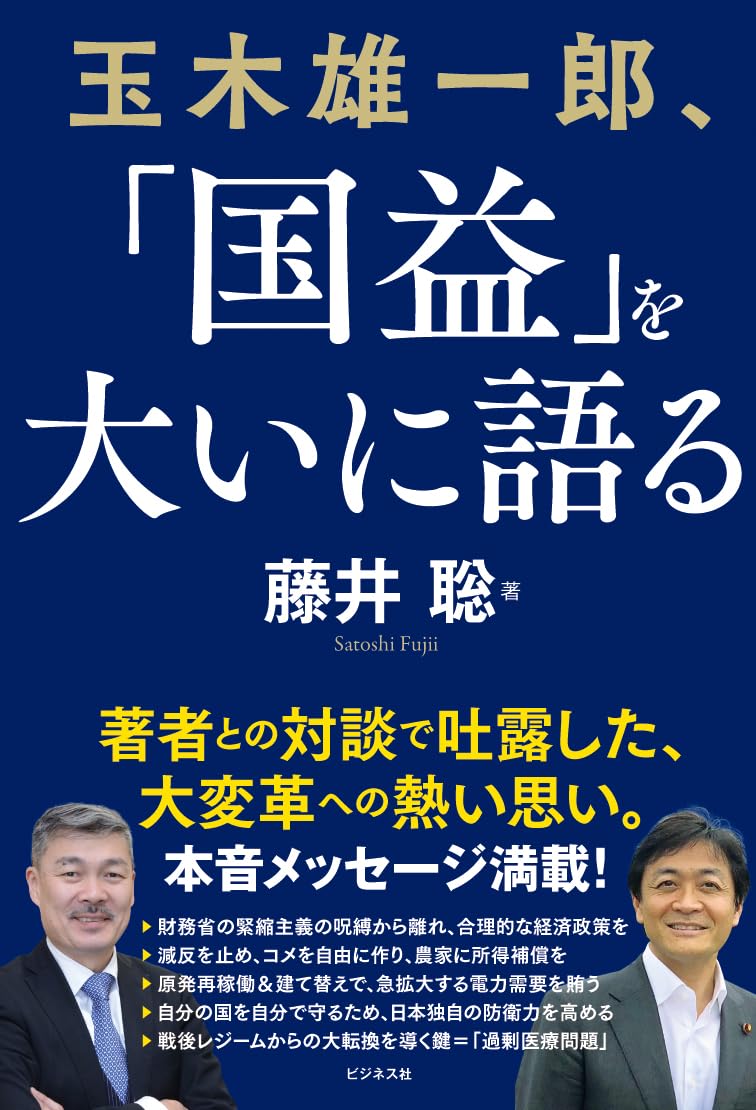
2025.06.21

2025.06.24
コメント
文化とは、文明でないもの。
日本文明、あったかな?
クラシック音楽は、0.1秒先の未来をも予測する。まあ、つまり、タイミングです。
しかし、メロディーでもない、伴奏、リズムでもない、なんでしょか、説明はいらない、音楽だから。
和歌か俳句の季語は、客観的なもの。
文芸と芸術、美
違うな。
わたくしの中での文化に値する結論は【自然と皇室と我々民族】の三位一体である純粋な伝統だから、総じて【歴史】ですね。
そして正確には先の大戦後の沖縄返還された時期までは、何とか日本文化は脈々と明確に存在していたのですが、三島事件を境にした頃から、オイルショックとロッキード事件とで急激に社会の対立から社会環境が、キッパリと変貌を遂げてしまいましたから、三島由紀夫を強烈に非難した中曽根康弘政権を強烈に非難するのです。
そして政治では、三木武夫政権と新自由クラブが画策されまして、それに伴い報道の規制がかなり緩くなり、さらにバカげた経済主義と学歴主義とで日本文化が結構毀損されまして、バブル景気が到来した挙げ句に民族の分断工作が始まり、いつしか純粋な部分が失われました。
ちなみに先頃、浜崎先生が桜の討論番組の中で文化を衰退させた世代の戯けの加瀬英明に、理不尽な説教を受けていたのを拝見していて、私自身も内蔵が破裂する程めちゃくちゃに激怒していましたよ。
それから私は、基本バランスを取ることは【純粋】を欠く事なので好んでいませんし、恐らくは創設者の西部先生も同じような考え方だと認識しておりますし、浜崎先生にも同じ香りが漂っておりますから先生には多いに期待いたしております。
浜崎さんの自分語り動画を拝見しました。子供の頃に転校を繰り返した故郷喪失者との事で、大変なご苦労をされたと思います。福音書を読んだ事があるなら分かると思いますが、マタイの福音書10章に『売られているスズメの一羽でさえも天の父のお許しが無ければ地に落ちる事は無い』と書かれています。この聖書の一節は、この世界には『運命』と呼ぶべきものが存在している事を示しています。
神が浜崎さんに与えた(または与えている)運命は過酷としか言いようがありませんが、必ず良い終わりが待っていますので、どうか神を嫌いにならないでください。
浜崎先生いつも応援してます。
しかしながら浜崎先生の書かれる教養の類のお話になると、今の日本社会の誰も興味を持っていないかの様な雰囲気になります。日本国民はお金や経済の話ですと、浅ましい根性を出して論戦にもならない「俺にもよこせ感」を「俺が俺が」と言って丸出しにするのですが、恐らく浜崎先生が書いてる文章の意味すら解らない人が増えたのではないでしょうか?
または、何が書いてあるのかが解らない、といったところまで日本人が劣化したことなのでしょうか。
日本人なので日本語の文章の文字を追うことは出来ても、文字を追うだけで精一杯なのかもしれません。いや、そこまではないだろう、と疑いつつも実際そうなのかもとの思いが交錯します。
恐らく単純化されたものや、お金にしか関心を示さないその現象を何度となく目にするだけで、日本の文化レベルはただ目の前の損得勘定しか出来ないまでに相当低くなったと感じています。
ミクロの経済政策のAがいい、いやBにすべきだという議題に血眼を上げるクズばかり。そんなことは現実を見ていればAかBのどっちが誰にとって有利か?など直ぐに判ることでして、そのことについて、国民一人一人が人生を賭ける様に真剣に考えなきゃならないことでしょうか。
音楽もお金に変えられてしまったと思うのですが、エイベックスは以前から商業主義だと思っていました。そしてこのコロナ禍で日本市場に期待せず、日本人に中国語をマスターさせ、中国市場でそのグループを売り出してます。私はそういったことを見るにつけ、もう音楽とは何ぞや?ということすら解ってない人達が生み出すコンテンツに、共感したり期待をすることもなくなりました。
文化レベルの低い国民は、メェメェ草をはみながら次の草は何処にあるのかな?だけを考え勝手にやってくれ、と思います。
保守は何も阻止出来ませんが、例えば軸がある人が出来ることといえば、流行り物に流されず自分の生き方を持つことくらいでしょうと私は思います。
しゃぼん玉というドラマが91年頃にあったんですけども、日本の文化レベルはあの頃よりさらに後退したと明らかに思います。
私は浜崎先生の様な教養のある文章は書けませんので、ドラマの主役の長渕剛の様に「退け、オラ、俺が通るんだ」と言い、そして社交という様に仲間に「飯食いに行って笑い飛ばそうぜ」ということでしか自分の生き方を表現出来ませんし、それしか自分を現実に繋ぎ止める術を知らないです。逆に言えばそれしか知らなくても、しゃぼん玉の様に命が消える時までは、自分一人くらい生きるだけなら生きて行けると思ってます。
どうせ日本人は自粛論者にしろ経済論者にしろ、「退け、オラ」と言われたら金を置いて逃げるでしょう。実際日本政府は米国など諸外国にそうして来て、現に今も尖閣問題などでそうしてます。
なので意識高い系になったつもりの人や、メディアがポリコレ棒を振り回そうが、馬鹿が馬鹿な法を作って、国民がそれに乗って「違う」と私に言ってみても、私は「違わねぇよ、退け、オラ、俺が通るんだ」で済みますんで。何でもかんでもその様な態度を取るわけでも、その様な言い方をするわけではありませんけど、いつも自分の生き方を中心に物事を考え対処しようとしている自分がいます。
それしか出来ないそれが私自身の最後の砦であり、私が教わった文化であり、生き方でもあると思ってます。
矢島 鉄平=長渕剛
【「権力者に向かって」
俺の親父を殺したのはお前だ。俺の友人の浅倉を殺したのはお前だ。他の友人を殺したのもお前だ。
聞いてんのか菅!
どれだけ、どれだけ人を殺せばテメェの野心は満足できるんだ。
聞いてんのか菅!
何でこうも、何でこうも日本人同士いがみ合わなきゃなんねぇんだ。
褒めること何一つなく、貶すこと限りなく、足を引っ張るだけの日本人をどうしてお前は作るんだ!
何が復興だ!何が繁栄だ!キサマの手でどれだけの人が傷付き、どれだけの人の命が絶たれたかキサマには解ってんだろう。
聞いてんのか菅!
「自分に野次を飛ばす日本国民に対して」
おう、日本国民、お前だよお前、もう一度言ってみろこの野郎。ふざけんじゃねぇよ。テメェらいつもそうやって高見の見物かよ、何かあった時だけ国が悪いだの政治が悪いだの税金が高いだの抜かしとるクセに、新宿都庁がぶっ建ちゃあ、腑抜けた面してカメラぶら下げて、間抜けな面してピースサインの記念撮影か!
それが日本国民かこの野郎!
うるせぇ、この野郎!
何だこの野郎!
「権力者に向けて」
46年前、あの戦争で死んでいった人々は、こんな見せかけの豊かさを築く為に、その犠牲となる為にただ死んで行っただけなのか。
焼け跡から復興する為に、俺達の親達は汗水垂らして一生懸命働いた。
働いて、働いて、働いて、やっとテレビが買え、やっと洗濯機が買え、そして小さな兎小屋みたいな、そんな家の中で俺の親父は死んでった。
何が、何が復興ですか!何が繁栄ですか!
「マスメディアに対して」
よう、姉ちゃん、あんたら本当は何が正しくて何が悪いのか位は解っているはずだ。
お前ら幼い頃から人が遊んでる時も勉強し、見たいテレビも見ずに我慢して我慢して一流大学出たはずだ。
そんな学歴社会を戦い抜き、マスメディアに入った当初は真実を報道しようと正義感に駆られて入って来たはずだ。それが何だこのザマは!
歪んだ正義感の上に胡座をかき、こんな嫉妬深い、足を引っ張るだけの日本国民に仕立て上げたのはテメェらマスコミ、ウジ虫共だってことを、しっかり頭の中に叩きこんどけ!いいかこの野郎!馬鹿タレが!
「権力者に向けて」
今の日本の若者を見ろ、人を蹴落とすことしか教えられず、才能の芽は潰され、夢も希望もねぇ、お前らの操り人形じゃないか。
何でこうも真面目に直向きに生きようとする人間が、申し訳なさそうに背中丸めて裏通り歩かなきゃいけないんだ。
何とか言え、菅!
こんなシラけた日本国民のでっち上げた1票1票で、こさえたキサマの意思など糞食らえだ!
俺は騙されんぞ!
キサマの謝りこそ偽善だ、キサマの謝りこそ偽善じゃないのか菅!
機動隊の後ろで見物してる国民の皆さん方よ、さぞかし面白いだろうな。
文句あんなら向かって来い、オラ!
どうしたオラ!
テメェらの、テメェらの無関心な目ん玉で、俺のちぎれた右脚見れるかこの野郎!
俺のちぎれた右脚は、人々の痛みと叫びの象徴だ!
まぁだ、解らんねぇのかキサマら!
例えお前らが腐りきっていたとしても、俺は残った左脚で、この文化レベルの低い日本の土の上を生きてくぞ、生きてくぞ。
退け、オラ、俺が通るんだ、退け、オラ、
…….はあ、疲れたなあw、飯食い行こうか、ええ?なあ。】
日本が過剰自粛を終わらせないなら、過剰自粛が日本を終わらせるだろう。