2023年度の「表現者塾」第6回(9月9日)にオンラインで参加した後、何気なくテレビを点けたところ、昨年放送されたドラマ『ミステリと言う勿れ』の特別編が放送されていました。同タイトルのコミックスを原作とし、ドラマ化や映画化されるほどの人気作品であり、今回の特別編は映画版の公開(9月15日)を記念し、そのプロモーションのために制作されたものだとのことです(注1)。
ドラマの中で、菅田将暉が演じる主人公である久能整(くのうととのう)と青砥刑事(演じるのは筒井道隆)との間で交わされた「真実」と「事実」を巡るやり取りが描かれていました。当該シーンはコミックスの第1巻に収録されている「episode1 容疑者は一人だけ」における一場面であり、ドラマ版においても原作がかなり忠実に再現されています(注2)。
青砥刑事「どれだけ虚言を尽くしても、真実は一つなんだからな」
久能整「真実は一つなんて、そんなドラマみたいなセリフをほんとに言う人がいるなんて」「青砥さん、真実は一つなんかじゃないですよ」
青砥刑事「何を言っている」「真実が2つも3つもあったらおかしいだろうが」
久能整「たとえばAとBがいたとしましょう」「ある時階段でぶつかってBが落ちてケガをした」「Bは日頃からAからいじめを受けていて今回もわざと落とされたと主張する」「ところがAはいじめている認識など全くなく、遊んでいるつもりでいる」「今回もただぶつかったと言っている」「どっちもウソはついていません」「この場合、真実ってなんですか」
青砥刑事「そりゃAはいじめてないんだからBの思い込みだけで、ただぶつかって落ちた事故だろう」
久能整「いじめていないというのはAが思っているだけです」「その点Bの思い込みと同じです」「人は主観でしかものをみられない」「それが正しいとしか言えない」「ここに一部始終を目撃した人がいたとして、更に違う印象を持つかもしれない」「神のような第三者がいないと見きわめられないんですよ」
青砥刑事「それは屁理屈というものだろう」
久能整「だから戦争や紛争で敵同士でしたことされたことが食い違う」「どちらもウソをついてなくても話をもってなくても必ず食い違う」「AにはAの真実がすべてで、BにはBの真実がすべてだ」
「真実は一つじゃない」「2つや3つでもない」「真実は人の数だけあるんですよ」「でも事実は一つです。起こったことは」「この場合AとBがぶつかってBがけがをしたということです」「警察が調べるのはそこです」「人の真実なんかじゃない」「真実とかいうあやふやなものにとらわれるから、冤罪事件を起こすのでは」
青砥刑事「おまえは一体、なんの話をしているんだ」
恐らく、多くの人が、久能整が言っていることを「もっともなこと」だと思い、青砥刑事のことを「『事実』と『真実』の違い」(注3)をわかっておらず、先入観に囚われて、自らの主観を客観的な事実だと思い込んでいる愚か者だと思うのではないでしょうか。しかしながら、私たちが青砥刑事を愚か者と看做しうるのは、読者もしくは観客という(久能が言う)「神のような第三者」の立ち位置から物語の全体を俯瞰的に眺めることができるからであるに過ぎません。
私たちには先見的に「事実」を知ることなどできるはずがなく、自分から見える「真実」を文字通りの「真実(ここで言われている事実に近い)」であると看做さざるを得ないのです。もし私たちが久能や青砥刑事と同じく物語の登場人物の一人であるとするならば、神ならざる人間である私たちにとって―久能が青砥刑事に求めるように―自らの主観や先入観に囚われずに「事実」に対峙することなど到底不可能なことであり、青砥刑事を馬鹿にすることなどできないに違いありません。
「真実は人の数だけある」と喝破する久能が青砥刑事に対して「事実のみを調べよ」と求めるのは、まさに彼自身が言う「神のような第三者」の立ち位置から物事を俯瞰的に眺め、人それぞれの「真実」を横断し、さらには自分自身の主観や先入観に基づく「真実」からも自由に「事実」に向き合うという、凡そ私たちにとって不可能なことを求めているのに等しいと言えるのではないでしょうか。
まったく身に覚えのない事件に巻き込まれて犯人に仕立て上げられそうになって取り調べを受けているという境遇には同情を禁じ得ませんが、どちらかと言えば、主人公である久能よりも、自らの「真実」が「事実」であると信じて与えられた職務に愚直に取り組む青砥刑事の方に親近感を覚えてしまいます。
久能整と青砥刑事のやり取りを見て、映画『羅生門』(1950年)を思い出しました。日本国内のみならず、海外でもよく知られている有名な作品であり、改めて説明する必要もないと思われますが、黒澤明監督の代表作の1つである『羅生門』は、芥川龍之介の短編「藪の中」を原作とし、タイトルや設定などは同じく芥川の短編「羅生門」を元にしており、第12回ヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞、第24回アカデミー賞で名誉外国語映画賞(現在の国際長編映画賞)を受賞しています(注4)。
映画『羅生門』で描かれるのは、戦や地震、竜巻、火事、飢饉といった災いが続き、盗賊の群れが都を荒らしまわり、虫けらのように人が死に、殺される末世の平安時代を舞台に、ある藪の中で起こった殺人と強姦という事件を巡る物語であり、原作である「藪の中」との間でいくつかの異なる点があります(注5)。
「藪の中」では、検非違使に尋問された4人の証人達の証言と3人の当事者の告白が羅列される形で記されており、それぞれが矛盾し錯綜しているため、結局、最後まで事件の「真相」が明らかにされないままに物語が終わってしまいます。この作品から「藪の中」という言葉―関係者の証言が食い違うことなどによって真相が不分明になるという意味―が生まれたことがよく知られています。
その一方、『羅生門』では、杣売り(山林に植樹されて成長した樹木を伐採して売りさばく職業の人)と旅法師と下人の3人が雨宿りのために羅生門に居合わせることになり、事件の参考人として検非違使庁の庭で取り調べを受け、証言をした杣売り(「藪の中」では木樵り)が事件について旅法師と下人に語り聞かせる形が取られ、後述するように、杣売りが本当に「事実」を語っているのか否かについて疑念が残るのですが、杣売りが目撃したことが「事実」であるとして描かれています。
盗賊・多襄丸(三船敏郎)の白状
多襄丸は、山で侍夫婦(金沢武弘と妻の真砂)を見かけた際に真砂の顔を見て欲情し、金沢を騙して捕縛した上で、真砂を手籠めにしたことを語ります。その後、真砂が多襄丸と金沢の2人に決闘することを求め、生き残った方の妻になりたいと申し出たことから、多襄丸は(もともと殺すつもりはなかったが)正々堂々と闘い、激闘の末に金沢を倒します。2人が闘っている間に真砂は逃げてしまっており、現場から無くなった、真砂が持っていた高価な螺鈿の短刀の行方については知らないと証言します。
妻・真砂(京マチ子)の懺悔
真砂は、多襄丸が自分を手籠めにした後、金沢を殺さずに立ち去ったと話します。真砂は縛られている夫にすがりつき、辱められてしまった自らを殺すように懇願しますが、眼前で男に身体を許した妻を受け入れることができない金沢が自分を見る冷たい軽蔑の眼差しに耐えられなくなり、そのまま気を失ってしまったと語ります。その後、目が覚めると夫の胸に短刀が刺さって死んでおり、自分は後を追って死のうと試みたが死にきれなかったと証言します。
侍・金沢武弘(森雅之)の物語
巫女の口を借りて、殺された金沢の霊が語ります。金沢の霊曰く、真砂は多襄丸に凌辱された後、縛られている夫を前に、自分を手籠めにした多襄丸に「何処へでも連れて行ってください」と頼み、さらには「(一緒に行くためには)あの人を殺してください」と金沢を殺すよう求めますが、多襄丸は真砂の浅ましい振る舞いに呆れ果て、金沢に「女を殺すか助けるかは夫のお前が決めて良い」と申し出ます。それを聞いた真砂は逃げ去り、多襄丸も姿を消し、1人残された自分は無念のあまり、妻の短刀で自害したと語ります。そして、短刀については、自分が死んだ後に何者かが現れ、短刀を引き抜いたが、それが誰かは分からないと証言します。
目撃者・杣売り(志村喬)の証言
それぞれ食い違う多襄丸、真砂、金沢の言い分を話し終えた杣売りは「3人とも嘘をついている」と言い、検非違使の取り調べの場では巻き込まれることを恐れて黙っていたが、実は事件の一部始終を目撃しており、自分が見た「事実」を語り始めます。
杣売りによれば、真砂を手籠めにした後、彼女に惚れてしまった多襄丸は自分の妻になることを懇願しますが、真砂は女の身である自分が決めるのではなく、男である多襄丸と金沢が闘って決着をつけることを求めます。ところが、金沢は辱めを受けた真砂のために命を懸けることを拒み、真砂に対して武士の妻として自害するように迫り、その一方で、多襄丸も真砂を置き去りにして、その場を後にしようとします。あまりにも自分勝手な男たちの振る舞いに、それまで泣き崩れていた真砂は立ち上がって哄笑し、金沢と多襄丸の2人を罵り、闘うように嗾けます。戦に慣れない2人はへっぴり腰で無様に斬り合い、ようやく多襄丸が金沢を倒すに至りますが、自らが仕向けたことの成り行きに動揺した真砂は逃げ出し、人を殺めたばかりで動転している多襄丸は真砂を追うことができず、その場を立ち去ります。
以上が、事件の当事者である多襄丸、真砂、金沢と目撃者である杣売りが語った内容の概要となりますが、当事者3人それぞれの言い分には自分を美化したいという思いや虚栄心からの嘘が含まれており、互いに矛盾しています(注6)。
多襄丸が白状した内容からは、彼自身が猛者ぶりで都にその名を轟かせていることを誇らしく思っており、真砂に頭を下げて妻になるように懇願したことや金沢との決闘における臆病で無様な姿が白日の下に晒されることを厭うていることが窺がえます。
真砂は、あくまで自分が最大の被害者であるとして同情を集め、夫の情けない振る舞いに対して、恥辱を受けて自害しようとする武士の妻としての潔さを印象づけることを目論み、気がついたら短刀が夫に刺さっていたとして、自らの故意の殺害を否定しています。
金沢は、目の前で妻が辱められ、その妻から多襄丸と決闘することを迫られ、へっぴり腰で闘った上に敗れたことを恥じており、「多襄丸に手籠めにされた真砂が、その多襄丸と連れ添うために、夫である自分を殺すよう求めたことに絶望して自ら命を絶った」と語ることで、自らの武士としての面目を保とうとしています。
さらには、事件の「一部始終を見ていた」という目撃者である杣売りについても、物語の終盤で、下人が羅生門に捨てられていた赤子から着物を剥ぎ取ろうとすることを咎め、下人と言い争う中で、杣売り自身が螺鈿の短刀を盗んでいたことを暴かれることによって、「短刀を盗んだ」という事実を隠蔽して「善意の目撃者」として振る舞う杣売りの証言が、本当に見たままの「事実」を語っているのか否かに疑念が生じてしまいます。
杣売りが語ったことが「事実」であるとするならば、都で勇名を馳せる盗賊・多襄丸の実態はただの女好きの臆病者であり、貞淑な武士の妻であるかと思われた真砂は生きるためには浅ましい振る舞いをも厭わない恥知らずであり、凛とした武士であるかに思えた金沢には死を賭して妻を守るような勇ましさはありません。
物語の中盤で、杣売りが巫女の口を借りて金沢が語ったことも嘘だと言ったことに対して、旅法師(千秋実)が「死んだ人間まで嘘を言うとは考えられない。人間がそんなに罪深いものだとは考えたくない」と嘆き、下人(上田吉二郎)が旅法師に向かって「そりゃあ、お前さんの勝手だが、いったい正しい人間なんてのはいるのかね。みんな自分でそう思っているだけじゃねぇのか。人間というやつは、自分に都合の悪いことは忘れちまうんだ。都合のいい嘘を本当だと思っていやがんだよ。その方が楽だからよ」と語ります。
多襄丸、真砂、金沢の3人が、自分にとって都合の悪いことは忘れて、都合のいい嘘を本当のことだと思い込んでしまっているのかもしれません。それぞれ自分が嘘をついているという意識すらなく、自らにとっての「真実」を語っていて、その「真実」の物語が客観的な「事実」と異なるということに気づいてさえいないのかもしれないのです。
私たちが、多襄丸、真砂、金沢の3人が嘘をついていることを知り、彼らの愚かさや弱さを憐れみ、批判することができるのは、―『ミステリと言う勿れ』の場合と同様に―読者もしくは観客という「神のような第三者」の立ち位置から物語全体を俯瞰的に捉えることができるからであるに過ぎません。
物語の世界を離れ、私たちが生きる現実においては、神ならざる私たちにできることと言えば、自らの主観に基づく「真実」が「事実」―「実際にあった」と多くの人が認める事柄、客観的に認められる事柄―であると思えるように、自分の認識や知識を検証し、自分や世界に誠実であろうと努めることでしかないのではないでしょうか。
2023年9月4日に辺野古の工事に関する裁判において、最高裁が「国の指示は適法である」との判決を言い渡し、沖縄県の敗訴が確定したことを受けて、同日の記者会見で官房長官は「政府としては日米で合意された在日米軍施設や区域の整理、統合、縮小をさらに進めていく必要があると考えている。今後とも地元への丁寧な説明を行いながら普天間飛行場の1日も早い全面返還を実現し、基地負担の軽減を図るため全力で取り組んでいく」と述べ、防衛省は「引き続き、地元の皆さまに丁寧な説明を行いながら、普天間飛行場の1日も早い全面返還を実現するため、辺野古への移設工事を着実に進めていく」とのコメントを発表しています(注7)。
最高裁判決が出たことは1つの区切りであると言えるのかもしれませんが、米軍普天間飛行場の辺野古移設を巡る日本政府と沖縄県との間の対立は深まるばかりであり、両者の間の溝は一向に埋まる気配がありません。
日本政府と沖縄県の法廷闘争の経緯からも明らかな通り、そもそも司法の場で判断されるのは、あくまでも「辺野古埋め立ての承認に関わる政府や県の手続きの違法性あるいは法的な瑕疵の有無」ということであり、最高裁判決も「米軍普天間飛行場の辺野古移設を実現すべきか否か」ということについて判断を下すものではありません。本来であれば、国会など政治の場において「沖縄を含めた日本全体の防衛はどうあるべきか」という「独立国に相応しい防衛・安全保障体制」についての議論を積み重ねることを通して国民の間でコンセンサスを構築しなければならず、それを踏まえた上で「辺野古移設の是非」について政府と沖縄県との徹底的な協議を通して政治的に結論を導き出すべきことであり、そのことを放棄して司法に判断を委ねるということは「政治の堕落」であると断ぜざるを得ません(注8)。
「日米同盟や日米安保体制は永続する」「辺野古移設が唯一の解決策であり、日米合意が成立しているが故に、その合意に反する選択肢を検討する余地はない」ということが、日本政府にとって、そして「米軍普天間飛行場の辺野古移設」を計画通りに推進しようとする政治家や官僚たちにとっての「真実」―決して「事実」ではない―であるのかもしれません。
しかしながら、下記に示すように、既に多くの論者によって「辺野古移設が唯一の解決策である」との日本政府の公式見解―日本政府にとっての「真実」―が、沖縄の「基地問題」にまつわる数多くの嘘話の1つでしかなく、決して「事実」ではないことが明らかにされています(注9)。
「日本の西半分のどこかに、海兵隊が持っている地上の部隊、航空部隊、これを支援する支援部隊の三つの機能が完全に機能するような状態であれば、沖縄でなくても良い」「軍事的には沖縄でなくても良いが、政治的に考えると、沖縄がつまり最適の地域である」
(民主党政権時の森本敏防衛大臣)
「『辺野古が唯一かつベストの案』には大して根拠がない」「辺野古は普天間と比較すると基地機能という面では問題だらけで、少なく見積もっても40~50ぐらいの問題点がある」「辺野古はベストでもなければベターでもない。ワーストである」「『唯一の解決策』ではなく、むしろ数多くの新しい問題を引き起こすことになるほど最悪なものだ」
(ロバート・D・エルドリッヂ)
「(米軍普天間飛行場の移設先について)われわれは沖縄とは言っていない」「基地をどこに配置するかを決めるのは日本政府でなければならない」「(辺野古移設計画については)日本政府が別の場所に配置すると決めれば、私たちの政府はそれを受け入れるだろう」「日本側が沖縄からの米軍撤退を望まず普天間飛行場をはじめとする沖縄の米軍基地駐留の継続を求めていた」
(ウォルター・モンデール元駐日大使)
「普天間飛行場の返還条件について調整がつかなければ、(辺野古に新しい基地ができたとしても)普天間飛行場の返還がなされないことになる」
(2017年6月の参議院防衛委員会における稲田防衛大臣(当時)による答弁)
沖縄の現実(=「事実」)からかけ離れた嘘話でしかないことが明らかにされているにもかかわらず、日本政府が―彼らにとっての「真実」である―「日米同盟や日米安保体制は永続する」「辺野古が唯一の解決策」という嘘話に固執し続け、他の選択肢や可能性を検討しようとしないのは、我が国が米国に従属している現状に甘んじてさえいれば、「独立国家に相応しい安全保障体制の構築」という日本にとって重要ではあるが難しい課題から目を逸らし続けていられる―それが彼らにとって「楽である」―からなのではないでしょうか。
「人間というやつは、自分に都合の悪いことは忘れちまうんだ。都合のいい嘘を本当だと思っていやがんだよ。その方が楽だからよ」と語る『羅生門』の下人の言葉は、(「人間というやつ」を「政府というやつ」に置き換えさえすれば)現在の日本政府に対する批判の言葉として的を射ていると思えてなりません。
一方、沖縄に蔓延る「絶対平和主義」に基づく言説を語る平和主義者達は、「沖縄が地政学的に戦争の問題、軍事の問題から自由になれない場所であり、パブリックには軍事基地から自由になれない可能性が高い」「仮に『沖縄から全ての基地を撤去すること』が実現した場合、そこに生ずる軍事的空白が反って紛争の原因となる可能性が高い」という沖縄が置かれている現実(=「事実」)から目を背け、「沖縄から全ての軍事基地を無くすことさえできれば平和で豊かな島になれる」という非現実的な「夢物語」―彼らにとっての「真実」―に固執し続けていると言えるのではないでしょうか。
「辺野古が唯一の解決策」という嘘話に固執する日本政府も、「沖縄から全ての軍事基地を無くすことさえできれば平和で豊かな島になれる」という非現実的な「夢物語」に執着する平和主義者も、その主張している内容は全く異なりますが、「主観」や「先入観」といった自らにとっての「真実」―決して「事実」ではない―に囚われてしまい、沖縄が置かれている冷厳な現実(=「事実」)に対峙することから逃れようとしているという意味において、「同じ穴の貉」であると看做さざるを得ません。
先にも述べた通り、現実の世界において、神ならざる私たちには、先見的に、もしくは俯瞰的に「事実」を知ることなどできるはずがなく、私たちにできることは、自らにとっての「真実」が「事実」であると信じて生きていくことでしかありません。そして、たとえ私たちに突きつけられる現実(=「事実」)が、私たちにとって都合が悪い、苦難に満ちた厳しいものであるのだとしても、自らの主観に基づく「真実」が客観的な「事実」からかけ離れてしまうことがないように努め、でき得る限り「事実」に即した「真実」の物語を生きていかなければならないのではないでしょうか。
厳しい「事実」から目を背けて「都合の良い嘘」―例えば、日本政府にとっての「辺野古が唯一の解決策」であるという「嘘話」であり、平和主義者にとっての「基地さえ全て撤去すれば平和な島になれる」という「夢物語」である―を作り上げ、その「都合の良い嘘」を自らの「真実」と看做して「楽をする」ことを選んでしまうのであれば、それは真の意味での「解決」などではなく、「現実逃避」であると断ぜざるを得ないのです。
我が国の「防衛・安全保障」をめぐって―あくまでも現時点における私にとっての「真実」であるとしか言えないのですが―いま私たちが為すべきことは、現在の米国に従属している「半独立」の―私たちの生命・財産は守られるのかもしれませんが、我が国の国家としての尊厳が失われていく―状態を甘んじて受け入れ続けることではなく、また、「沖縄から全ての軍事基地を無くすことさえできれば平和で豊かな島になれる」という非現実的な平和主義の「夢物語」に基づく理想郷を目指すことでもないと考えます。
いま私たちに求められているのは、「都合の良い嘘」を「真実」と看做して「楽である」ことを選ぶのではなく、たとえ「楽ではない」厳しい途であるのだとしても、「事実」であると信ずるに足る「真実」に基づいて「独立国家に相応しい防衛・安全保障体制の構築」という目標に向かって着実に歩みを進めていくことなのではないでしょうか。
私たちが『羅生門』の下人に馬鹿にされないようにするためには、そして、私たちの子や孫といった将来世代から批難されないようにするためには、それしか途はないように思えてなりません。
--------------------
(注1)土曜プレミアム・映画公開記念『ミステリと言う勿れ特別編』 – フジテレビ (fujitv.co.jp)
(注2) 田村由美『ミステリと言う勿れ』第1巻、p40~45
(注3)「事実」と「真実」の違いとは – 違いがわかる事典 (chigai-allguide.com)では、「事実は『本当にあった事柄』や『現実に存在する事柄』を、真実は『嘘偽りのないこと』『本当のこと』を意味する。意味は似ているが『事実はひとつで真実は複数ある』と言われるように、事実と真実は異なり、一致しないことの方が多いくらいである。つまり、事実は『実際にあった』と多くの人が認められる事柄、客観的に認められる事柄のことであり、真実は人それぞれが考える本当のこと(事実)であり、客観的なものではなく、主観的なものである」と説明されています。このように真実を「主観的なもの」と看做すこと自体が近代的な価値観に基づく見方であると考えられます。
(注4)羅生門 (1950年の映画) – Wikipedia
(注5)【羅生門(ネタバレ)】芥川龍之介の原作との違いを解説!付け加えられたシーンに込められた監督の意図は?赤ん坊の示すものとは | シネマノーツで映画の解釈をネタバレチェック (cinema-notes.com)及び羅生門 (1950年の映画) – Wikipedia
(注6)黒澤明『羅生門』解説|芥川の名作の先に、黒澤が伝えたかったこと。 (necojara.com)
(注7)辺野古工事めぐる裁判 沖縄県の敗訴確定 最高裁が上告退ける | NHK | 沖縄県
(注8)拙稿「『呪縛』と『幻想』から逃れて」『表現者』66号(2016年5月号)
(注9)拙稿「『沖縄の基地問題』にまつわる嘘話」『表現者クライテリオン』89号(2020年3月号)など。
資料及び参考文献
・田村由美『ミステリと言う勿れ』小学館〈フラワーコミックスアルファ〉第1巻、2018年
ミステリと言う勿れ 1 | 書籍 | 小学館 (shogakukan.co.jp)
『ミステリと言う勿れ』 田村由美 | 「月刊flowers」公式サイト|小学館 (shogakukan.co.jp)
・芥川龍之介「藪の中」「羅生門」『藪の中』講談社文庫、2009年
・拙稿「『呪縛』と『幻想』から逃れて」『表現者』66号(2016年5月号)
・拙稿「『沖縄の基地問題』にまつわる嘘話」『表現者クライテリオン』89号(2020年3月号)
(藤原昌樹)
《編集部より》
「表現者塾」2023年度の後期塾生を募集しています。
特に入会資格などはござませんので、どなたでもご参加いただけます。
9月25日までのお申し込みで最大5,500円OFFでご入会いただけます。
↓↓↓詳しいご案内、ご入会はこちらから↓↓↓
https://the-criterion.jp/lp/hyogenshajuku2023latter/
クライテリオン公式Youtubeチャンネルにて、表現者塾のダイジェスト動画が上がっております。
「第5期第1回 『クライテリオン無き日本の行く末(講師:藤井聡)』」
「第5期第2回 『故郷を忘れた日本人:どうして今文学が必要なのか(講師:仁平千香子)』」
https://www.youtube.com/channel/UCE8qPb4i2vMjLlnRHJXmL1w

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
表現者クライテリオン9月号発売中です。
特集は『インフレは悪くない、悪いのは「低賃金」だ!』。
約2年ぶりとなる「経済」「財政」をテーマにした特集です。
詳細はこちらでご確認ください↓↓
表現者クライテリオン2023年9月号
Amazonでのご購入はこちらから↓↓
Amazonで購入
定期購読にお申し込みいただくと10%オフとなります↓↓
定期購読はこちら!10%OFF!送料無料!
執筆者 :
CATEGORY :
NEW

2025.06.27
NEW

2025.06.26

2025.06.24

2025.06.24

2025.06.24
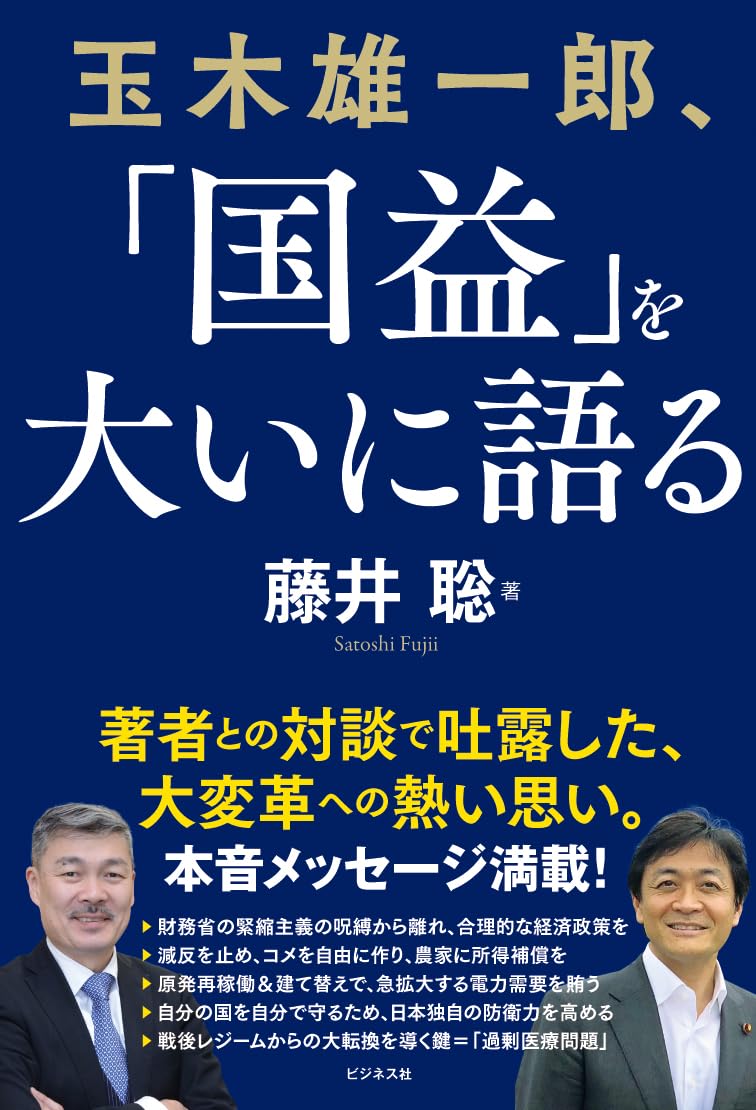
2025.06.21

2025.06.24

2025.06.26

2024.08.11

2025.06.27

2024.07.13
.jpg)
2025.06.03

2025.06.20

2025.04.21
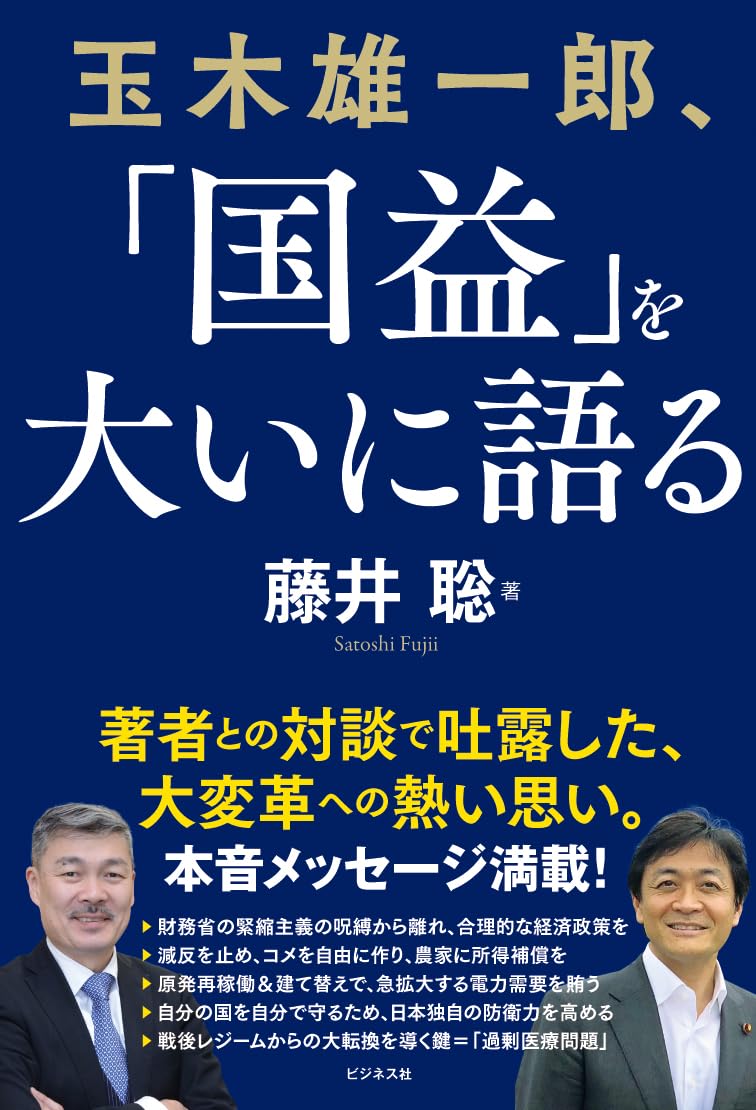
2025.06.21

2025.06.24