最新刊、『表現者クライテリオン2025年3月号 [特集]トランプは”危機”か”好機”か?』、2月15日発売!!
今回は、巻頭コラム「鳥兜」をお送りします。
「サポーターズ」に入会して、最新刊をお得に入手!
昨年12月に米国のオープンAI社が、従来のものより遥かに強力な生成AIモデルを発表したのだが、そのわずか1カ月後にディープシーク(DeepSeek)という中国の新興企業が同程度の性能を持つモデルを発表し、その界隈はにわかに騒然となっている。中国ではこれまでも、アリババやテンセントのような大手企業やムーンショットという新興企業が、オープンAIやグーグルをはじめとする米国企業と互角以上に張り合える高性能なAIモデルを開発してきた。ただ、今回のディープシークが特に大きな話題を呼んでいるのは、西側諸国が持っている「中国企業」のイメージを覆すようなアプローチを採ってうまく行っているためである。
たとえばAI開発の世界では、基礎研究をリードして画期的な方法論を考案するのは米国の研究者で、中国企業はそれを応用した二次的な技術で勝負するのだという漠然としたイメージが持たれていた。米国人の側がそう考えているだけでなく、バイドゥーのような中国企業の経営者もそのように語ってきたのである。ところがディープシークはむしろ、生成AI開発の基礎技術に関して独自の工夫を重ねて成功している。
また、ディープシークは「オープンソース」戦略を採っている点が際立った特徴でもある。オープンソースとは要するに、自社で開発した技術の「中身」をすべて無償で公開するということで、一定のルールに従えばそれを改造して新たな派生的モデルを開発することも可能である。これは、自社技術を秘匿する戦略に舵を切った米国企業とは対照的だ。
米国のオープンAI社は、「人工知能の基礎技術は人類の公共財として公開されるべきだ」という思想を掲げる非営利団体から出発しており、2021年頃までは自社の新技術を「論文」の形で公開するのが当たり前だった。ところがチャットGPTの初期バージョンが成功する前後から、新技術の詳細を公表しなくなっており、この傾向はグーグルについても言える。いまや、米国企業のほうがクローズドで、オープンなのはむしろ中国企業だとすら言える面があるのである。
中国のAI企業に関する欧米メディアの論評を見ていて目立つのは、百年前の日本人に対して向けられた「黄禍論」にも似た、恐れと侮りと驕りが混じり合ったような感情が表れていることだ。たとえばディープシークの技術についても、同社の生成AIモデルが天安門事件について尋ねると口をつぐんでしまうなど、共産党政府の検閲下にあることを批判する声が多く、「権威主義国家の企業」であることを印象づけようと懸命である。
少し極端なところでは、米国企業が開発したAIモデルの「パラメータ」(中核となる重要な数値情報)を中国企業に盗まれないよう、セキュリティを強化しなければならないと説く論者もいる。たしかにセキュリティには気をつけておいて損はないだろうが、その警戒心の背後にあるのは、「中国人には“盗み”以上のことはできないはずだ」という侮りである。現実には、泥棒呼ばわりする欧米人を尻目に、中国では彼らよりも優秀な研究者が育ちつつある。
この現代の黄禍論が裏目に出ている面もある。米国政府は中国に対する高性能なGPU(AIの開発に用いられるコンピュータの部品)の輸出に規制をかけてきたが、ディープシークは貧弱なコンピュータをうまく使って高性能なAIモデルを開発する工夫をしてしまい、結果的に開発コストが大幅に低下して価格破壊を引き起こしている。ディープシークの一件に見るべきなのは、古い「中国企業」のステレオタイプにとらわれたままでは、手痛いしっぺ返しを食らうという戒めである。
<編集部よりお知らせ1>
最新刊、『表現者クライテリオン2025年3月号 [特集]トランプは”危機”か”好機”か?』、好評発売中!
よりお得な年間購読(クライテリオン・サポーターズ)のお申し込みはこちらから!サポーターズに入ると毎号発売日までにお届けし、お得な特典も付いてきます!。
サポーターズPremiumにお入りいただくと毎週、「今週の雑談」をお届け。
居酒屋で隣の席に居合わせたかのように、ゆったりとした雰囲気ながら、本質的で高度な会話をお聞きいただけます。
執筆者 :
NEW
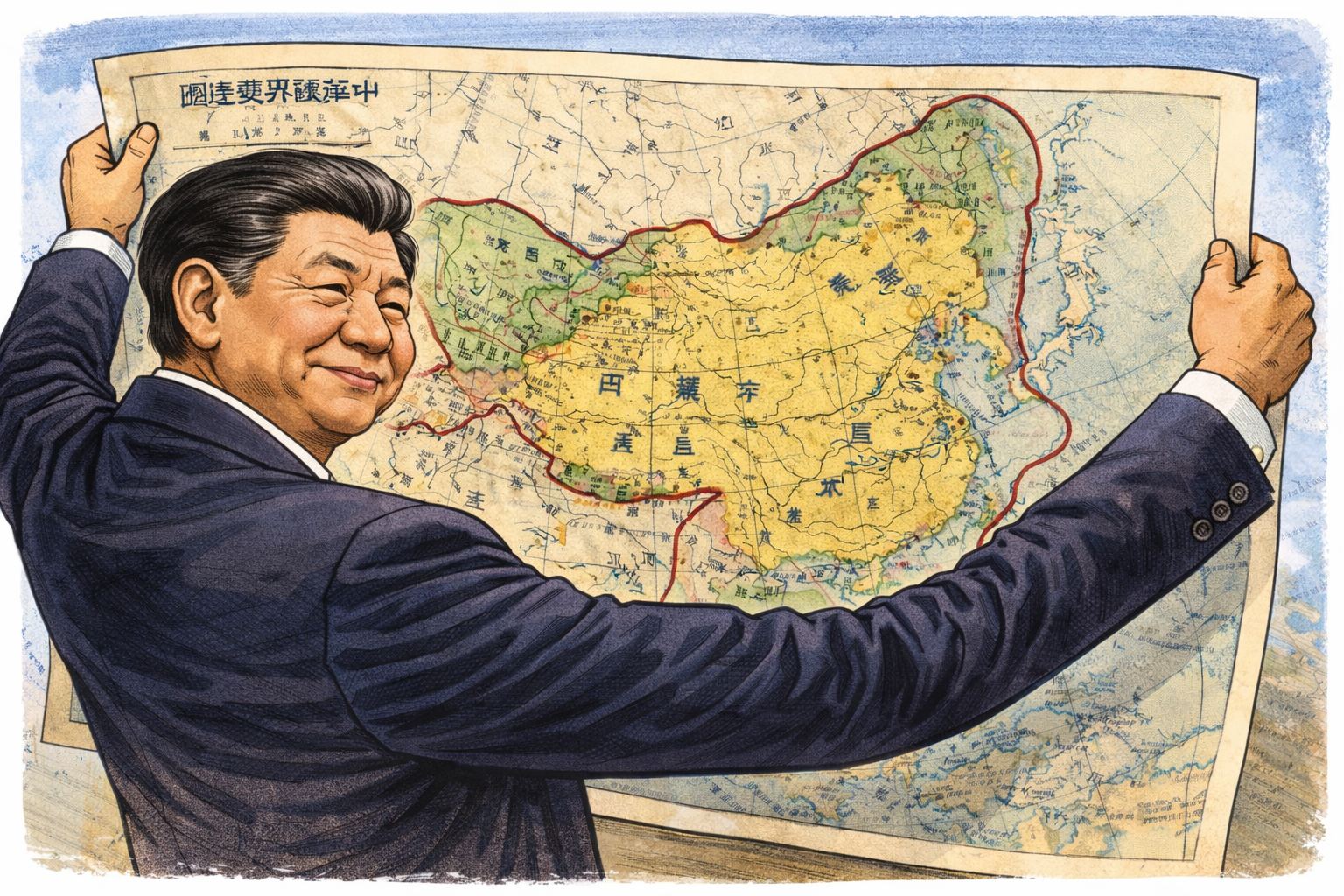
2026.02.06
NEW

2026.02.05
NEW

2026.01.30
NEW

2026.01.30

2026.01.29

2026.01.23

2026.01.18

2026.01.20

2024.08.11

2026.02.05

2026.01.30

2026.01.30

2018.04.06

2018.09.06

2018.03.02

2026.01.22