中川毅氏(立命館大学古気候学研究センター長)のファンである。専門家でもないので「評価する」なんて偉そうなことは言えないが、気候に関することはこのくらいスケールの大きな視野が必要だと思っている。著作を読むのが楽しいので、やはり「ファン」の読者というのが適当だろう。国立科学博物館で発行している『ミルシル』の最新号で久しぶりに中川氏の名前を見つけた。そこで、私たちの歴史に関係のある「農業」について、彼の興味深い話を紹介しようと思う。
今年の夏は本当に暑かった。都会では夜間や早朝でも気温が下がらず、熱中症患者が続出した。多くの人が危機感をもっている。「子供の頃は、こんなに暑くなかった」と誰もが言う。私もそう思う。40℃などという気温は、少し前までは想像もできなかった。しかし、人生100年時代と言われるようになって寿命が延びたとはいえ、日本人の人生はだいたい80年くらいだろう。国によってはもっと短い。人生で経験する範囲は、地球の歴史から見たら「瞬間」である。自分や同世代が経験したことがない現象でも、それが地球にとって「異常」なのかどうかは、本当のところわからない。
私たちは、地球に氷河期があったことを知っている。そして、人類が出現してからも極端に寒い時代があって、現代人が見ている海や川や湖が凍っていたという記録や地質学的な証拠もある。温暖な時代ももちろんあって、同じ地点でも寒い時代と温かい時代では、周りの自然が違っていただろうと推測できる。樹齢1000年以上という屋久杉の年輪からも、温暖期と寒冷期の差がわかる。1000年というのは、人生から見れば相当に長いが、地球の長い歴史から見れば、やはり一瞬である。その1000年という一瞬の間にも、地球の表層では様々な変化があった。つまり、気候というのは変化するのが「普通」なのだ。「定常」の状態がなければ、何が「正常」で何が「異常」なのか、わからない。
人類は自然を粗末に扱っている。山や山林を破壊したり、化学物質で汚染させたり、生物を乱獲したり、やりたい放題である。そのような行為を自重しようという環境意識の高まりは悪いことではない。しかし、いまの環境問題の主流になっている「気候変動」問題で、「気候変動を喰い止めよう」という場合、何が「正常」なのかわからないのに「目的設定」をしていることになる。
温暖化が言われるようになる前、実は世界中で「寒冷化」が心配されていた。1940年をピークに1970年ころまで、地球の平均気温は下がり続けていたのだ。その頃、過去に何度もあったという氷期のような寒冷な時代が来るのではないかと、本気で心配されていた。当時の新聞には寒冷化を心配した記事が載っている。長野県北部のスキー場では、寒冷化で東京近郊にスキー場ができたら、こんな山奥にまでスキー客が来てくれなくなると、本気で心配していたらしい。人間には、過去に経験した傾向が将来もそのまま継続するだろうと考える癖がある。また「二度あることは三度ある」と、同じことが繰り返されるとも考えている。当時は、ひと世代分の30年にわたる経験から、このまま寒くなっていくと推測されていた。その頃の大人は「子供の頃はもっと暖かかった」と言っていたのだろう。
気候の予測は、とても難しいと言われる。スーパーコンピュータや気象衛星などの発達で、近年では数日先までの予報はかなり正確になっていて、信頼度が高まっている。しかし、長期予報や台風情報では、まだ確実に予測できない場合がある。もっと長い時間帯で見ると、地球の気候は、地球の公転軌道や地軸の向きも関係する。太陽の黒点の周期も影響する。地下のマグマ活動や火山の爆発も無関係ではない。過去の気候リズムが、そのまま再現されることはなく、ほんの小さな刺激で破壊的な変化をもたらすことがある。海流や大気の流体の解析には多くの要因が影響していて、とても人間が集められる範囲のデータでは正確な解析は難しい。それでも、いま、私たちは「○○年までに地球の平均気温を1.5℃下げる」などと、かなり具体的な「目標設定」をする。そして、その「目標」のために、様々な経済活動が規制され制限され、多額の予算を割いて対策が検討されている。
人間が関与してもしなくても自然には定常状態がない。目的設定は、人間が自然を、強制的にある種の定常状態にするということでもある。気象現象では、ほんの僅かな初期設定の違いが、全く異なる結果を生じることがあるのに、人間の計画通りに軌道修正することが可能だろうか。過去の気候の変化の原因が人為であってもなくても、今後の対策や行動は、将来を人為で決定しようとする「自然への関与」の試みである。
中川教授の研究チームでは、福井県南部の水月湖の湖底の堆積泥を掘削して45メートルの年縞堆積物を採取した。7万年に及ぶ堆積物の調査から、その間の気候を調査してわかってきたことを紹介したのが、著書『人類と気候の10万年史』(2017) である。水月湖の調査結果だけでなく、グリーンランドの過去8万年の氷床の調査や、古代の岩石や氷に含まれる酸素同位体の調査など、他の観測データや研究も含めて、何千万年何億年というスケールで地球の気候変動を説明している。(詳細は、この本を読んで頂くことにする。)
世界各地の岩石に含まれる酸素の同位体比から復元した過去5億年のタイムスケールで見ると気候は温かくなったり寒くなったり変化し続けていて、平均気温の差は10℃にもなる。この5億年の流れの中に限れば、現代は寒冷な時期に当たり、いまから1億年から7000万年前の地球には北極にも南極にも氷床が存在しなかった。IPCCが100年後に予測している地球よりもはるかに温暖だったということになる。特にペルム紀と呼ばれるいまから2億7000万年~2億5000万年前の地球の平均気温は、現在に比べて10℃も高かった。但し、温暖な気候には上限があるらしい。極地の氷がなくなることはあっても、海水が沸騰するほどにはならないという。温暖化によって生態系が豊かになると、地球全体の光合成が活発になり、空気中の二酸化炭素の含有量が減るためだという説もある。温暖化には何らかの「負のフィードバック」がかかり上限が設定されるのだそうだ。
これに対して寒冷化は暴走することがあるという。もっと古い時代、生命がカンブリア爆発を起こす前の、いまからおよそ6億5000万年前の地球は、北極から南極まで赤道地帯を含めてあらゆる場所が氷河に覆われていた。「全球凍結」といわれる現象で、この状態になると白い雪や氷が太陽エネルギーを反射して「正のフィードバック」が起こり、寒冷化に拍車がかかる。一度このような状態になると容易に抜け出せなくなり、生命体にとって寒冷化は温暖化よりも恐ろしい。この状態からの脱出のチャンスは地球内部のマグマ活動による。火山の爆発によって二酸化炭素などの大量の温室効果ガスが噴出すると、凍り付いた地上には光合成を行う陸上植物や液体の海水のような温室効果ガスを吸収するものが存在しないために、温室効果ガスが大気中の濃度をひたすら増加させる。その結果、大気の温度が上昇して氷を溶かし始めるのだそうだ。この6億5000万年前の全球凍結では、地球が凍り付いてから溶け始めるまでに数千万年かかったという。
そのような長いタイムスケールの中にも多くの変動がある。地球の公転軌道による10万年周期などの周期的な寒暖があるし、他の様々な要因も重なっている。変化の形や様子はその都度異なり、変動に周期性があっても現れ方は一様ではない。その周期性のパターンが突然劇的に変わってしまう場合がある。「相転移」といわれる現象である。
グリーンランドと水月湖の年縞堆積物のデータから、およそ1万2000年前にそのような劇的な変化があったことが読み取れる。過去6万年の気温の変化のグラフでは、約1万2000年前に、突然、ほぼ垂直にグラフの向きが上昇しているのだ。温度の振幅は5℃~7℃にも及ぶ。その変化は非常に短期間で起こった。それは長くても数十年、実際には数年で変化したと考えられている。変化の境界は急激だった。数年で平均気温が7℃も変化して「相転移」に近いことが起きたと言える。長い氷期が終わり、現在まで続く温暖期に入った瞬間である。
このグラフの6万年前には、すでにホモ・サピエンスは存在していた。私たちの祖先は、この大きな変動を生き抜いたのである。突如として、彼らの世界は一変したはずだ。急に暑くなっただけではない。数年から数十年で、海の氷も氷河も解けて、水面が急激に上昇した。多くの人類の生息地はあっという間に水没しただろう。川辺や海に近い居住圏は放棄され、内陸部に移動を迫られただろう。
勿論、温暖期になっても気候は常に変化していてグラフは上下運動を繰り返す。しかし、明らかにそれまでの氷期と異なるのは、その変動幅が小さいのである。氷期の変動の激しさに比べて、温暖期の変動は穏やかである。つまり、温暖化しただけでなく、気候が以前よりも「安定」したのである。
約1万2000年前に、人類社会は大変化を遂げた。何十万年もの長期にわたって狩猟採集によって生きていた人類が、この頃、定住・農耕の生活を始めたのである。それは、限られた地域ではなく、メソポタミア、中国、南北アメリカ、熱帯のアフリカ、ニューギニア高地など、世界規模で起こった。地球の各地で、多少の幅はあるがほぼ「同時多発的」に、それぞれが独自に農耕を始め、急速に拡大したのだ。
いくつかの原因が考えられている。温暖化によって食べ物が豊富になり、人口が急激に増大したこと。エネルギー源として重要な食料であった大型の野生動物が、捕獲によって減少したことなどで、増え続ける人口を賄う食糧確保の必要が生じたためという説である。しかし、農耕を始めた最も大きな要因は、「気候が安定した」ことだという。
氷期と比べれば、温暖な気候が植物の生育に望ましいことはわかる。温暖化が関係することは確かだろう。しかし、氷期は全球凍結とは異なり地球のすべてが凍っていたわけではない。東京がモスクワのようで、マニラが札幌のように涼しく、相対的に寒い時代であったということである。寒冷地に適した植物(作物)はあるし、赤道付近にはいくらか温暖な地域があった。寒い時期を乗り越えるためにも食糧確保は重要なはずで、どこかで農耕が起こってもおかしくない。それでも、氷期の期間は、人類は採集生活を選んでいた。そして、氷期を脱するころに、人類は各地で一斉に農耕を始めたのである。
氷期や温暖期という気温の条件以上に農耕に重要なのは、気候の「安定性」である。農地には、なるべく多くの収穫を得るために、たくさんの作物を植え付ける。種類を限定して1種類にすれば、管理が容易になる。農地は、地球上で「最も生産性が高く」「最も多様性が低い」生態系なのである。一方、自然な生態系には様々な植物が混在している。種の多様性は、気候の変化に応じて採集できる植物が異なるということでもあり、そのことが気候条件に応じて必要なものを調達する選択肢を与えていることになる。
この生態系の違いが、気候変動に対して人類に異なる対応をさせた。氷期の気候変動の激しさは、去年食べたものが今年も手に入るとは限らないという状態を意味する。異常気象では、次の年に何が不作になって何が調達できるかもわからない。しかし、何かが不作でも、圧倒的な多様性のなかでは、それ以外の別の種類に頼ることができる。これは、当時の人類に農耕を行う能力がなかったとか、農耕を始める必要がなかったというよりも、農耕よりも確実な食糧調達手段が「採集」だったということにならないだろうか。気温差だけでなく、豪雨や暴風、極端な乾燥など激しい気候変動の中で、単一種の栽培に特化してしまうと、不作の年は何も食べるものがなくなってしまう。採集に比べて、農耕は「労力」や「管理能力」を必要とする。予測不可能な激しい気候変化を伴っていた氷期には、寧ろ、少ない労力で食料を得られる採集を続けることに積極的なメリットがあり、あえて面倒な「労働と管理が必要な農耕」を選ぶインセンティブがなかったということだろう。
動物には学習能力がある。危険を回避するために、条件の因果関係を見つけ、予測しようとする。食糧確保に関しても、学習する。農耕を始めた人類は、どのような種子を選べば収穫が多いか、どこに植えればうまく育つか、どの季節に何をすればいいか、どのくらい収穫すれば余剰が生まれ不作の年に備えることができるか、どんな方法が保存に適しているか、などなど、多くのことを学習し予測して計画を立てた。農耕は、作物をコントロールすることである。人間が持っている「線形バイアス」と「周期モデル」は、安定した環境における一種の危機管理能力で、農耕にはこの能力が役に立つ。
しかし、気候は常に変動している。変化するのが「普通」なのだ。いまの変動の小さい安定した温暖な気候も、いつか終わるときが来る。そのときが「いつ」なのかが問題だ。温暖期は、もう1万2000年近く続いている。過去のデータから見れば、温暖な気候は数千年しか持続していないという。いまの温暖期は例外的に長く続いていることになるらしい。
研究者の中には、すでに「氷期」になっているはずなのに、人間の活動が温室効果ガスを放出しているために、次の氷期を遅らせているのかもしれないという考えもある。逆に、人間活動が気候の激変の引き金を引くこともありうる。確実に言えることは、いまの「安定した温暖な気候」は永遠に続かないということだけである。気候の境界は、しばしば「相転移」として起こり、短期間に激変することが知られている。但し、次の「境界」が、どの程度の激変なのか比較的穏やかなのか、どのような世界に突入するのか、その時が来なければわからない。非線形の気象現象において、「この時代が終わる」こと以外の予測は不可能なのだ。
気になるのは、最近の異常気象である。「50年に1度」という豪雨や水害や豪雪が、「毎年」世界各地で起きている。特にここ10年くらいは「異常」であることが「普通」になってしまった。IPCCは、なんとか穏やかな気候を取り戻そうと号令をかけている。しかし、もし、これらが「相転移」の兆候ならば、人間の力では止められない。産業革命以降のせいぜい400年ほどのデータに基づくIPCCの予測も線形バイアスの範囲内でしかない。
それが「いつ」なのかはわからないが、安定した温暖な気候が終了したら、「農業を基盤にした社会」は続けられなくなる。安定した気候は、毎年同じことを繰り返す。「農耕」は、自然が「予測可能」でなければできない。予測不可能ということは、計画が立てられないということで、農耕そのものを続けるのが困難になる。コメの問題も、農作業の効率化も、食糧自給率も、ひとたび不安定なフェーズに入ったら、どんな対策も政策も無効になる。過去の氷期の暴れまくる気候の時代には、「生産性の低い」狩猟採集生活のほうが、「生産性の高い」農耕生活よりも確実に食糧確保ができた。だからといって、人口80億を抱えていては、人類は狩猟採集生活には戻れない。私たちの社会は、農耕と科学を前提にして成立しているのだから——。
生物や社会のシステムは進化への大きな慣性を持っている。現在進行中の方向に生存の見込みがある限り、進路は変更されない。その方向がシステムの生存そのものを脅かすとき、はじめて進行が停止・変更される。もし、現在直面している激しい気候変化が「相転移」の兆候だとしたら、それほど遠くない未来に、人類が1万2000年以上経験していない予測不可能で乱暴な気候変化の時代に突入することになる。現在の安定した温暖期になる前の何十万年もの過酷な氷期を乗り越えた人類は、いつか必ずやって来る厳しい変化の時代を生き延びられるだけの適応力を再び発揮できるだろうか。
『人類と気候の10万年史』 中川毅著 /講談社ブルーバックス 2017
『ミルシル』2025 9月号 /国立科学博物館 2025 No.4 Vol.18 (通巻106号)
橋本由美
<編集部からのお知らせ1>
8/16発売の最新号『表現者クライテリオン 9月号 財務省は敵か味方か?』 好評発売中!
本誌の詳細はこちらから

<編集部からのお知らせ2>
クライテリオン叢書第5弾、『敗戦とトラウマ 次こそ「正しく」戦えるか』、書店・Amazon等で公表発売中!
|
|
敗戦とトラウマ |
執筆者 :
CATEGORY :
NEW
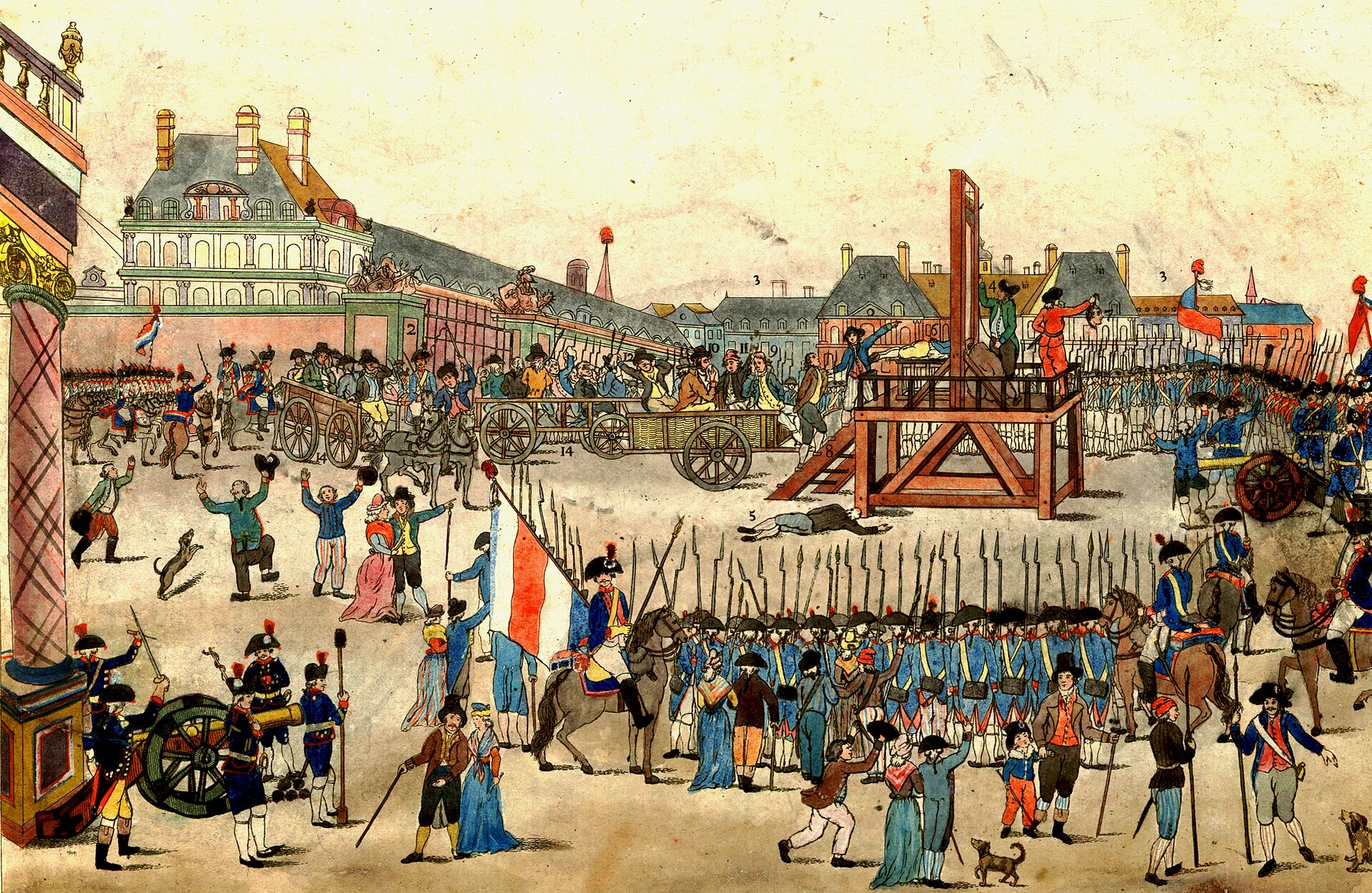
2026.02.20
NEW

2026.02.19
NEW

2026.02.18
NEW
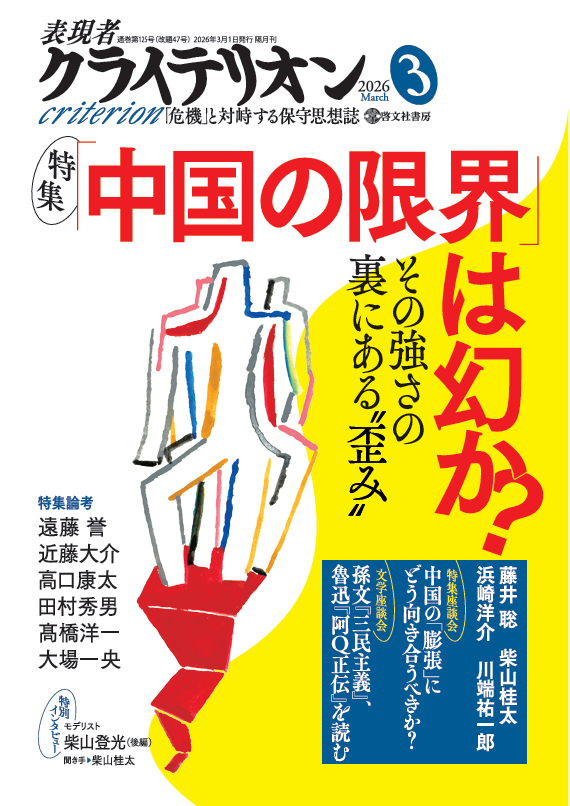
2026.02.16
NEW
.png)
2026.02.16
NEW
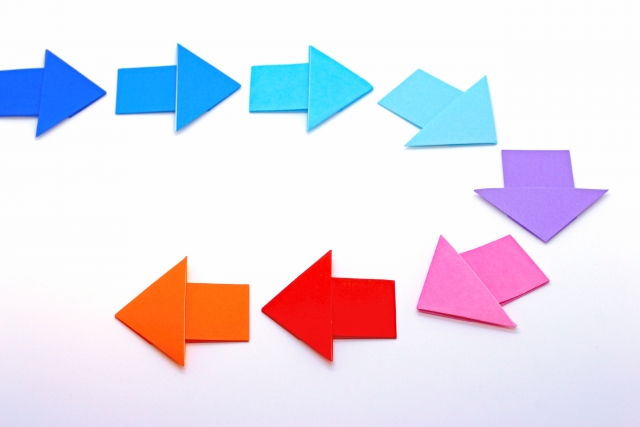
2026.02.16

2026.02.19
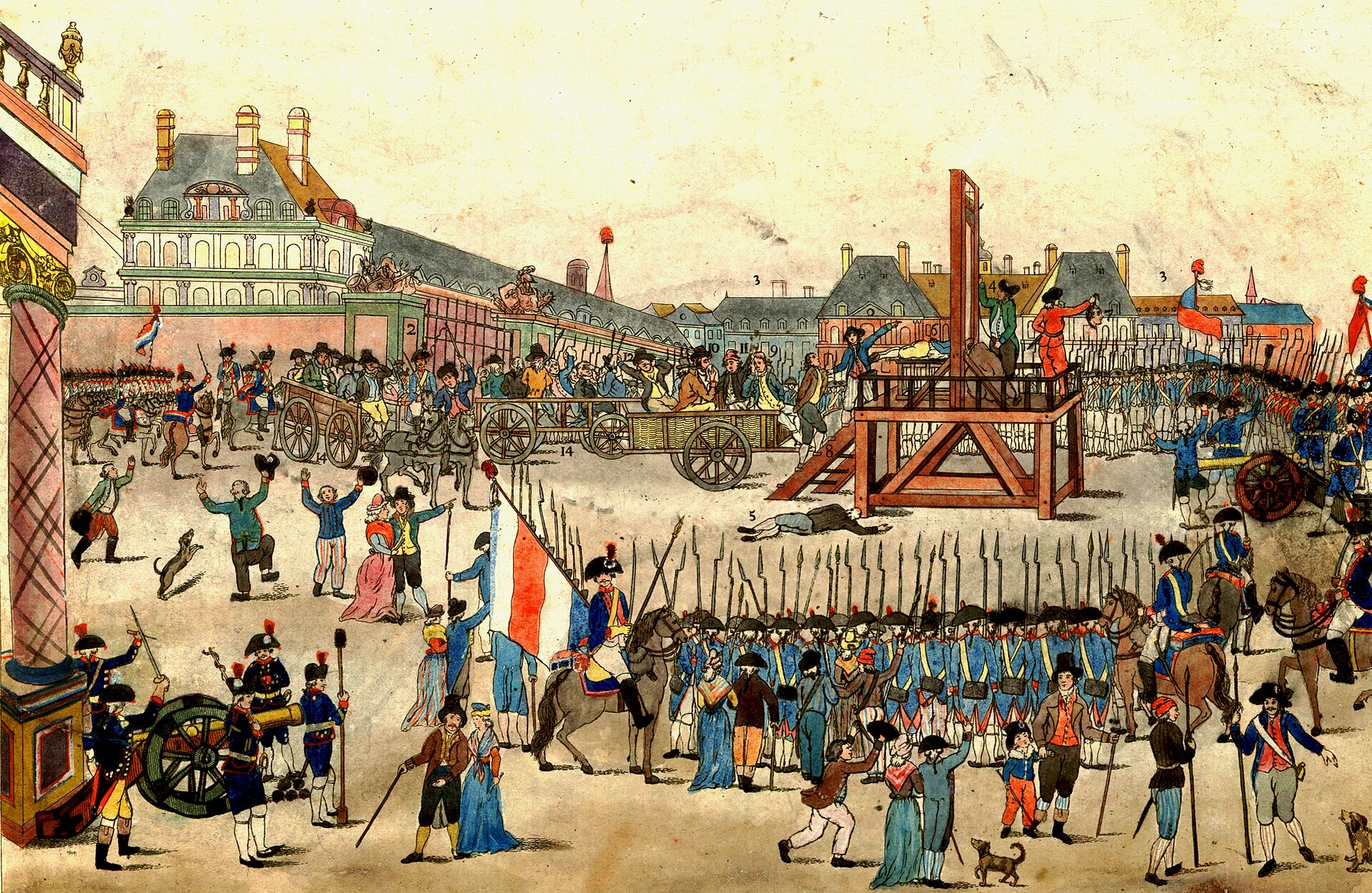
2026.02.20
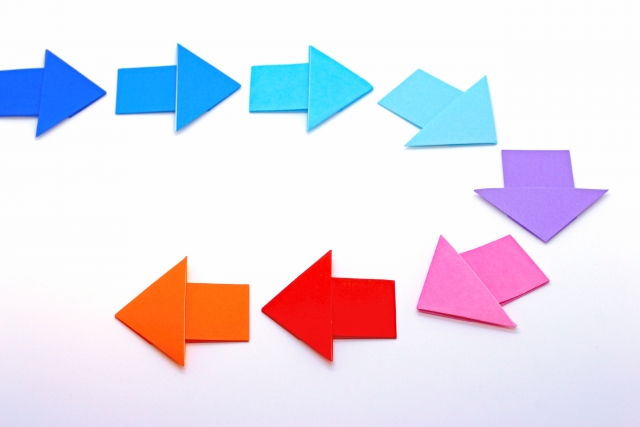
2026.02.16
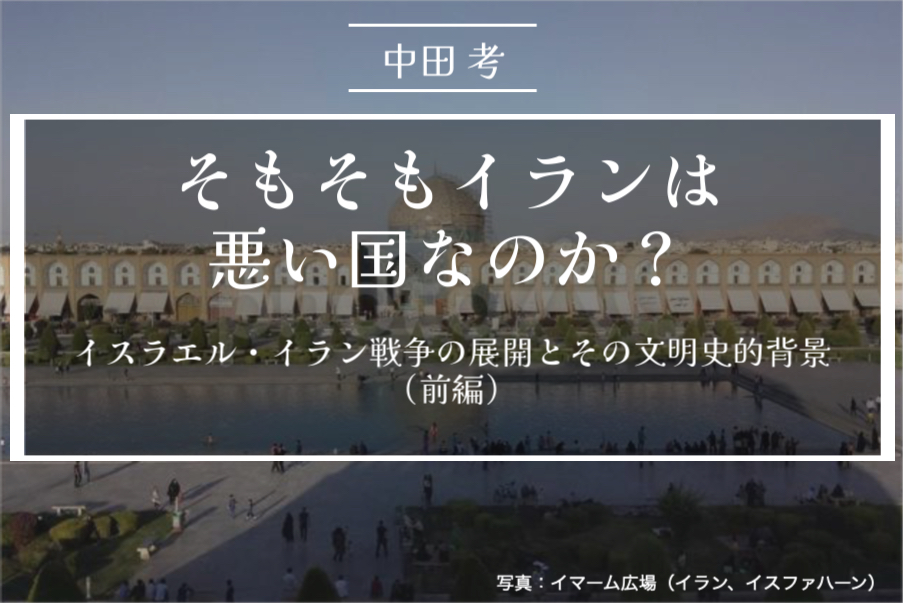
2025.06.24
.png)
2026.02.16

2026.02.11
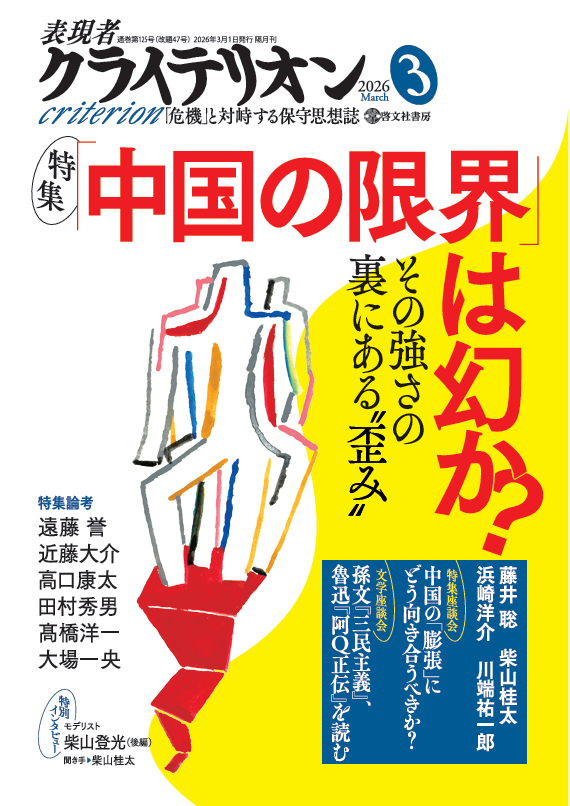
2026.02.16

2026.02.18

2026.02.12
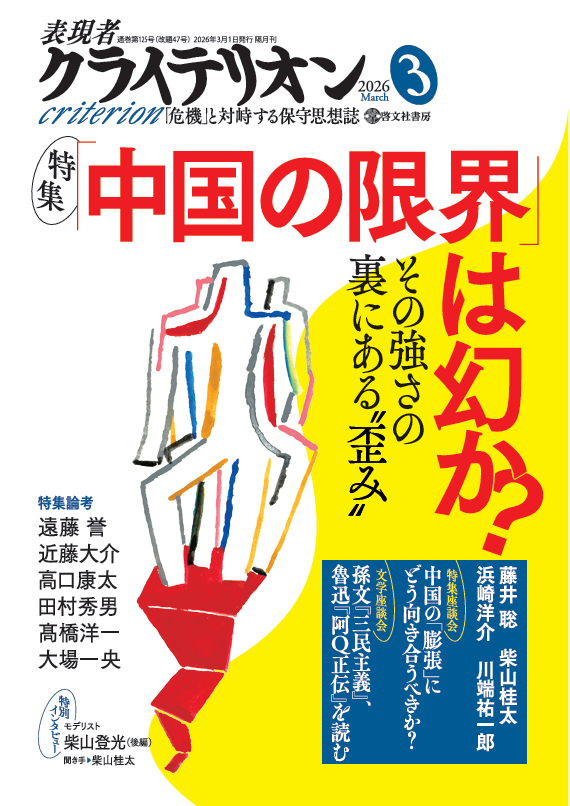
2026.02.16
コメント
水の惑星地球ではCO₂による気候変動はありえません。
なぜなら、水蒸気H₂Oの赤外線吸収モードの種類は多く強力で、かつ地球の平均湿度は80%と高いため、地球の温室効果は水蒸気H₂Oが主体でわずかにオゾンの寄与があるだけです。その中でわずかに「大気の窓」と呼ばれる赤外線波長8〜12μmの赤外線吸収欠損領域が有りますが、CO₂による赤外線吸収(温室効果)波長領域は13〜18μmのみなので、CO₂による温室効果はH₂Oの温室効果に完全にマスクされています。
CO₂気候変動論者は、砂漠地域など大気の窓が8〜17μmと大きく開いた僅かな箇所のCO₂による温室効果から、複雑な仮定や初期条件を設定して地球シュミレータ解析をこねくり回して、地球温暖化を主張しています。
詳しくは、少し長いですが下記の弊ブログ記事をご笑覧下さい。
http://rakuaki.blog.fc2.com/blog-entry-177.html