本日は10/16発売の最新号『表現者クライテリオン 11月号 この国は「移民」に耐えられるのか?』より、特集座談会お送りいたします。
藤井▼今回の巻頭座談会では、フランス文学者、思想家、武道家であり、合気道道場「凱風館」の館長でもあります内田樹先生にお越しいただきました。
先日の参議院選挙では参政党の躍進が話題になりましたが、その背景にあるのは「日本人ファースト」というキーワードだったとも言われています。最近、外国人の労働者が非常に増えたことで地域社会でさまざまな問題が起こり、それに対して日本人として反発する気持ちが高まっていることを反映しての結果だったわけです。
さらに、例えば我々がいる京都にも異様な数の外国人観光客が来られていて、一般市民がバスに乗れないなど日本人の日常生活にも支障が及ぶ事例が増えており、これについても反発が強まっているように思われます。
そうした状況であるにもかかわらず、政府はいわゆる「移民政策」を推進しています。それはなぜかというと、産業界における人手不足を解消するためには移民を入れるしかないと考えられているからであり、財界も外国人をどんどん入れて経済を維持・拡大させようという思惑を持っています。ならびに、内需がなかなか拡大していかない中で、外国人観光客を呼び込んでお金を使ってもらい経済を活性化させるという方針も強力に推進しています。
こうした背景から、日本は移民に耐えられるのかということをしっかり考えようということで今回の特集を組みました。もちろん、最終的には日本人の力だけで需要や労働力も維持できるような体制を目指すことが理想ですが、すでに多くの外国人が来られている以上、共生の道を探っていく必要もあります。その意味で、「単に移民を抑止すればいいじゃないか」というだけでなく、より複眼的な議論をいたしたいと思っております。
内田先生は十年ほど前に、「私は移民には大反対だ。なぜなら、この国は移民に耐えられるような国ではないからだ」といったことをおっしゃっていました。今も同じお気持ちだと思いますが、最近では「外国人排斥を乗り越えなければならない」という趣旨のご発言をされており、非常に賛同できると思いましたのでぜひいろいろとお話をお伺いしたいと思います。
まずはどこからでも結構ですので、内田先生からご発言をお願いいたします。
内田▼僕が「日本は移民に耐えられないだろう」と書いたのは、今の日本は未熟で幼児的な社会なので、他者との共生は不可能だろうと思ったからです。こうした市民的に未熟な社会に移民が入ってくると、すぐに世論は外国人排斥に傾いて、極右政権ができる。僕はそれに対して危機感を感じて、野放図に移民を入れることに反対したんです。
今すでに三八〇万人の外国人が日本で暮らしています。これからもっと増える。人口の一〇%に達するのも時間の問題です。しかし、彼らをどうやって受け入れて、共生するのかについての議論は全く進んでいない。外国人が増えると社会不安が増大するのは、受け入れ側の日本人の市民的な成熟が足りないからであるというシビアな現実認識が欠如している。
外国人をめぐる議論は、人手が足りないとか、インバウンドツーリストが活発に消費するとか、もっぱら経済の問題として語られています。後は不動産を取得しているとか、人種も言語も宗教も違う人間がたむろしていると不穏な感じがするといった感情レベルの話だけ。「言語も人種も宗教も生活文化も違う他者と共生するためにはどうしたらいいのか」という最も根本的な問題だけは誰も論じていない。参政党の「日本人ファースト」という主張は剥き出しの「外国人排除(xenophobia)」ですが、そこには「国際社会で名誉ある地位を得たい」という矜持のかけらもない。日本社会が不調なのはすべて「外から来る汚物」のせいだというのは、十九世紀末の近代反ユダヤ主義以来の極めて危険な社会理論ですけれども、これに対して日本の有権者があれほど無防備であるところを見ると、日本人は幼児的なので、これ以上移民を入れる能力がないと言わざるを得ない。
今回の特集テーマには「脱移民」という言葉がありますけれど、僕はこの言葉には留保をつけたい。移民の無原則な受け入れに僕が反対するのは、経済的な理由でも、政策的な理由でもなくて、端的に「日本人が幼児的だから」です。このまま幼児的でいたいと日本人の過半が思うなら、例えば選択肢として「日本人には移民と共生できる能力がないから、同質性の高い日本人だけの国としてだんだん縮んでゆこう」というものがあってもいい。国民全体がそう望むなら、そういう未来もあっていい。でも、それとは別に日本人が「他者と共生できるだけの市民的成熟を目指す」という未来があってもいい。でも、後者を選ぶためには「命がけの跳躍」が要る。日本社会は伝統的に共感と同質性をペースにした「共感共同体」ですが、外国から来る人たちと共に暮らすためには「契約共同体」に制度を作り替えなければならない。共感もできないし、同質的でもない他者と、それにもかかわらず共生し、協働することができるためには、国をある種の契約共同体に切り替えるしかない。社会契約さえきちんと守ってくれるなら、その人の人種も言語も宗教も生活習慣も「気にしない」という鷹揚な、というか「雑な」態度を取れる人間になるしかない。そこまで共同体の概念を広げていかないと他者との共生はできません。どこかで契約共同体に切り替えない限り、人口の一〇%が外国人というような社会を平穏に維持することはできません。果たして、その覚悟が日本人にあるのだろうか。僕はその点については極めて悲観的です。

藤井▼ありがとうございます。柴山さんはいかがでしょうか。
柴山▼日本政府は公式には移民政策を採用していないことになっていますよね。日本の労働現場で本当に足りていないのは単純労働者ですが、そういう人には基本的に出稼ぎで来てもらい、一定期間が経ったら帰ってもらうというのが大前提になっています。「特定技能制度」がまさにそうですが、これはかなり問題のある制度で、職業選択の自由を奪ってその仕事に縛りつけるわけで、耐えられない場合には逃げるしかない。そういう形でフロントドアから労働力を入れずに裏口から、例えば留学生にアルバイトをしてもらったり特定技能制度という形にして仕事に縛りつけたりして、しかも一定期間が経った後は帰ってもらうという制度設計にしてきたわけです。
要するに、長期的な展望の下に持続可能な移民受け入れの制度を作るという発想がそもそもないわけです。それでもだましだましやってきたわけですが、もうそろそろ維持できなくなりつつあるというのが今の日本の状況だと思います。
僕が移民論に関していつも思うのは、移民を入れることによって日本社会が抱えている本当の問題が隠されているのではないかということです。今の日本で人手不足の業界としては介護や清掃、解体、建設、運輸などがありますが、どれも社会に必要なエッセンシャルワークでありながら賃金が安く、若い日本人が仕事に就いてもすぐに離職、退職してしまう構造になっています。そこが問題なのだから、本来はしっかりと生産性と賃金を上げていって、場合によっては政府が補助することも必要です。しかし、それをせずに外国から安く、しかも人道上極めて問題のある形で移民を入れて働いてもらい、一定期間経ったら帰らせるということをやっているわけです。つまり、日本社会を変えないといけないのに、改革をせずに現状維持しながら使い捨てできる外国人を入れてくればいいだろうという発想でやっているために、結果的にいろんな問題が起こっているのだろうと思います。
移民を入れる、入れないの前に、まずは日本の労働者が敬遠する業界の現状にもっとメスを入れて、雇用環境を改善していかないといけません。今のように裏口から外国人に来てもらうようにしていると、これからもさまざまな形でトラブルが増えていくのではないかと思います。
藤井▶移民問題を考える際に、一つ目の問題として移民によって社会的被害が広がるということがあり、さらに人手が足りなくて困っているという産業界からの声にどう対応するかという問題もあり、この二つをどうやって調和させていくかが大事になりますが、僕はこの問題を変数を使って数学的に考えたいと思います。
まず、内田先生がおっしゃるように我々の社会は幼稚であるというのはその通りだと思いますが、さはさりながらすでに外国人を受け入れている現状もあります。おそらく、我々の社会にも「移民受け入れ可能容量」というものがあり、その容量以下であれば幼稚な社会なりに市民社会を運営できるのでしょう。
一方で、…続きは本誌にて
<編集部よりお知らせ>
最新刊、『表現者クライテリオン2025年11月号 この国は「移民」に耐えられるのか?ー脱・移民の思想』、好評発売中!
よりお得なクライテリオン・サポーターズ(年間購読)のお申し込みはこちらから!サポーターズに入ると毎号発売日までにお届けし、お得な特典も付いてきます!。
サポーターズPremiumにお入りいただくと毎週、「今週の雑談」をお届け。
居酒屋で隣の席に居合わせたかのように、ゆったりとした雰囲気ながら、本質的で高度な会話をお聞きいただけます。
NEW

2026.02.11
NEW

2026.02.09
NEW

2026.02.07
NEW
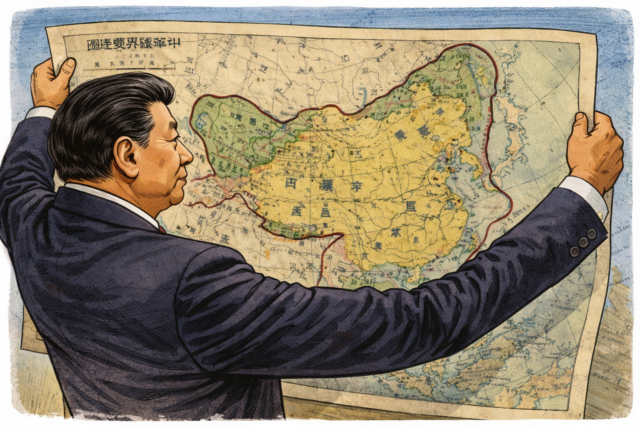
2026.02.06
NEW

2026.02.05

2026.01.30
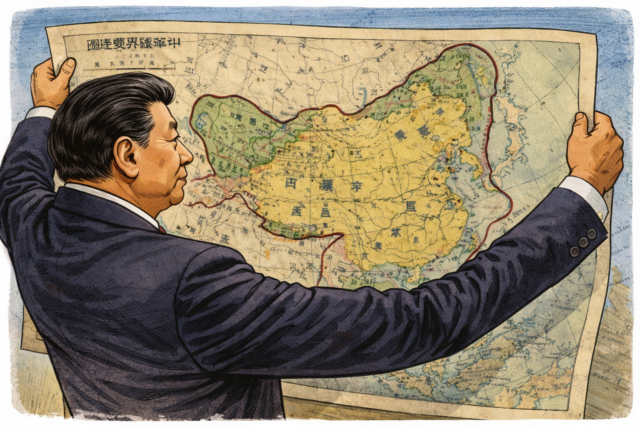
2026.02.06

2026.02.05

2026.02.09

2026.02.07

2026.01.20

2024.08.11

2026.01.18

2018.09.06

2026.02.11

2020.07.06