こんにちは、浜崎洋介です。
前回のメルマガ「人間の『成熟』について―イマギナチオ・老害・大衆人」(https://the-criterion.jp/mail-magazine/m20200107/)のコメント欄に、川口さんという方から、早速、質問が寄せられました(質問は文末に掲載)。
川口さんが言うには、「批評」という言葉を度々目にするものの、その「意味合いがどうしても掴め」ないとのことで、「解説や批判とは異なるこの批評という行為の目的や狙い、批評を行う者に求められる態度とはどういうものなのか」を教えてほしいとのことです。
なるほど、たしかに「批評」は、解説や批判と一見似ていながら、その文脈によっては、解説や批判と全く違うニュアンスを含ませて使われることがあります――私自身が「批評」に特別な意味を込めていますが――。とはいえ、それは、単なる言語フェティシズムではありません。少なくとも「批評」の伝統を省みれば、その言葉が、他者に対する特別な〈接し方=生き方〉を意味している言葉であることが見えてくるはずです。
では、解説や批判、あるいは研究論文と「批評」との違いはどこにあるのか。
それを説明しようとしたとき、いつも私が例にもち出すのが、英語やフランス語などで用いられる「自由間接話法」という概念です(1)。それは、「直接話法」や「間接話法」との「あいだ」にある「話法」(語り口)なのですが、その耳慣れない話法のなかに、おそらく「批評」という営みを理解する手がかりも隠れています。
「直接話法」とは、話者(伝達者)が、他者の語った内容に手を加えずに、そのまま伝えようとする形式、たとえば、「Aは言った『XはZである』と」/A said,“X is Z”.)などと、他者の言葉を、括弧に括って明示しようとする話法のことです。
対して、「間接話法」とは、話者(伝達者)が、他者の判断であることを明示しつつも、しかし、それを話者(伝達者)の描写のうちに取り込んだ形式、たとえば、「Aによれば、XはZである」(A said that X was Z .)などと、他者の判断・言葉などを、接続詞を使って第三者に報告するさいに使われる話法のことを指します。
この二つの話法が、主に解説、批判、研究論文で使われることからも推測できるように、それらは、明確に話者(伝達者)と他者の判断とを区別するための話法です。
しかし、「自由間接話法」は、それが「小説」で多く使われている話法であることからも推測できるように、あえて話者(小説家)と、他者の判断(登場人物の思考)を明確に区別しない(あるいは、区別できない)ときに使われる話法として知られています。
たとえば、前回のメルマガの例で言えば、スピノザやオルテガの判断(思考)を解説している文脈のなかで、しかし突然、私が引用符や接続詞抜きで「XはZである」(X is Z)と言ったとき、その一文は、たしかに「間接話法」のようでありながら(スピノザやオルテガの判断を伝えているようでありながら)、しかし、まるでそれは話者自身(私自身)の判断であるかのように伝えられることになります。つまり、この判断の帰属先――論じている対象の言葉なのか、それを論じている私の言葉なのか――が決定不可能であるように見えながら、なお、文脈のなかでは「自然」に読めてしまう話法、それが自由間接話法なのです。
しかし、だとすれば、「自由間接話法」は、解説や批判、あるいは研究論文においては、できるだけ避けるべき話法だと言うべきでしょう。それが、「正確」を期した文章(科学論文)である限り、主体と客体の混同は厳に慎まねばならないからです。
対して、「批評」は、むしろ「自由間接話法」を多用します。しかし、それは決して「韜晦」を気取るためではありません。いや、むしろ、このとき批評家は、対象に対して、解説や研究論文以上の(あるいは、それとは異質の)「正確さ」を求めていると言えます。さらに言えば、その「正確さ」への異様な欲望こそが、批評家に、主体(批評家)と客体(対象)とを一挙に結びつけることを可能とする「自由間接話法」を選ばせているのです。
どういうことか。
たとえば、私たちが、ある異性に出会った場合のことを考えてください。まず、その場で働くのは、その出会いを「快」とするか、「不快」とするかを判断する「直観」(先了解)でしょう。「知性」による分析(反省・解釈)は、その後にはじまります。逆に言えば、彼/彼女の印象を、その部分(背が高い/低い、顔が整っている/整っていない、上品/下品、教養がある/ない、社会的立場が高い/低いだとかetc…)、に分けて分析するには、まず、「出会い全体」の印象(快/不快)が与えられている必要があるのです。
実際、〈私(A)+他者(B)→快/不快への変化(X)〉という一連の流れ(全体の直観――ウィリアム・ジェームズの言葉を借りれば「純粋経験」)が手に入っていない限り、私たちは、私たち自身(A)を反省=分析することも、他者(B)を反省=分析することも不可能です。Aは、あくまで〈A+B→X〉の流れのなかに位置するAなのであり、Bは、あくまで〈A+B→X〉の流れのなかに位置するBなのですから、その「部分」(AやB)のあり方を正確に知るには、どうしても「全体」(A+B→X)の直観が必要なのです。
しかし、だとすれば、目の前の他者(B)について徹底的に正確に語るためには、その他者によって変容させられた私(A→X)についても語らなければならないということになる。しかし、それは逆に言っても同じです。私自身の直観=持続のリアリティ(A→X)について徹底的に正確に語ろうと思えば、その私を変容させた他者(B)について語る必要があるのです。もちろん、これは、単なる主体と客体の混同ではありません。他者との出会いに、真に正確=誠実であろうとする批評家は、主/客の二項性を乗り超えながら、その循環を見つめざるを得ないのだということです。そして、その極限において、ときに批評家は、他者の判断を自己の判断とする「自由間接話法」を生きはじめることになるのです。
日本近代批評の祖と言われる小林秀雄は、そのデビュー作である「様々なる意匠」(昭和4年=1929年)のなかで「批評」を定義して、すでに次のように書いていました。
「いわゆる印象批評の御手本、例えばボオドレエルの文芸批評を前にして、舟が波に掬われるように、繊鋭な解析と溌溂たる感受性の運動に、私が浚(さら)われてしまうという事である。この時、彼の魔術に憑かれつつも、私が正しく眺めるものは、嗜好の形式(単なる主観)でもなく尺度の形式(単なる客観)でもなく無双の情熱の形式をとった彼の夢だ。それは正しく批評ではあるがまた彼の独白でもある。人は如何にして批評というものと自意識というものとを区別し得よう。彼の批評の魔力は、彼が批評するとは自覚する事である事を明瞭に悟った点に存する。批評の対象が己れであると他人であるとは一つの事であって二つの事でない。批評とは竟に己れの夢を懐疑的に語る事ではないのか!」、括弧内引用者
まさに〈A+B→X〉の流れ「全体」を直観しつつ、その「部分」(私や他者)を正確に反省しようとすれば、小林秀雄が言うように、「批評」は、その「対象が己れであると他人であるとは一つの事であって二つの事でない」ことを自覚せざるを得ないでしょう。
が、このとき重要なのは、この自覚こそが、自/他における出会いの「宿命性」(吉本隆明なら、それを「関係の絶対性」と言ったでしょう)を示し出すと同時に、そんな自/他の関係性(出会い)を可能にした歴史の「宿命性」をも照らし出すのだという点です。
たとえば、「批評」と似ているようで、しかし、それとは異なる「論文」のことを考えると分かり易い。主(A)/客(B)を完全に切り分けた研究論文に、私たちが「宿命」を感じ取ることは難しい。そもそも〈A+B→X(変容)〉という「全体」の流れ(直観)に対して距離をとることを要求される研究論文において――予め、X(快/不快、好き/嫌い)を先どってなされた解釈は「循環論法」と言って、その「客観性」を担保し得ないのです――対象に対する距離感は、Bでも、Cでも、Dでも同じである必要があります。
しかし、〈A+B→X〉という「全体」の流れ(直観)を生きる「批評」において、X(快/不快)の経験は決定的です。しかし、だとすれば、そのXをもたらしたものとしての対象B(たとえば、小林秀雄の場合で言えばドストエフスキー)も決定的だということになる。つまり、X(一つの圧倒的感動)という経験を問う「批評」において、その対象がC(トルストイ)や、D(ゴーゴリ)であることは不可能で、ほかならぬB(ドストエフスキー)である必要があるということです。が、だとすれば、さらに、その対象B(ドストエフスキー)を受け取った私(A=小林秀雄)も、私ではない誰か(河上徹太郎や、白洲正子)であることはできず、ほかならぬ「この私(A=小林秀雄)」である必要があるのです。
つまり、一つの「出来事」(分割不可能な持続)である〈A+B→X〉を描く「批評」において浮かび上がってくるのは、AはAであるがゆえにBと出会い、BはBであるがゆえにAと出会え得たという同語反復的事態であり、「私が私でしかない」ことの宿命性なのです。
さて、だとすれば、ドストエフスキー(B)を受け取った小林秀雄(A)が「日本」の歴史を生きていたという事実(宿命)も決定的だということになるでしょう。なぜなら、〈A+B→X〉のAをさらに細かく分解すれば、そこには〈ある批評気質な人間(a)+20世紀前半の日本(b)→小林秀雄(A)〉という構造が見出されるはずだからです。その限りで言えば、その土地の宿命性(日本)や、その時代の宿命性(戦前期・日本近代)を無視して、小林秀雄のドストエフスキー体験を描き切るということは、やはり不可能なのです。
かつて、小林秀雄は、デカルトの「方法」を語りながら、「彼の方法とは、出来上がったものとして、人に手渡しの出来る知識でも理論でもないという大切な事は、『方法の話』(方法叙説)で、自分の辿った道を一幅の絵のように語ってみるより他に伝えようがなかった」(「常識について」昭和39年=1964年、括弧内引用者)と語ったことがありますが、それは、そのまま「批評の方法」にほかなりません。それ以外に、「今、ここ」にある「この私」と「この世界」との出会いを正確に、徹底的に正直に語る方法はないのです。
「批評」における、この呆れるほどの「正確さ」への欲望(無私の精神)について、小林秀雄は、次のように語っていました。
「もし批評精神を、純粋な形で考えるなら、それは、自己主張はおろか、どんな立場からの主張も、極度に抑制する精神であるはずである。でも、そこに、批評的作品が現れ、批評的生産が行われるのは、主張の断念という果敢な精神の活動によるのである。これは頭で考えず、実行してみれば、だれにも合点のいくきわめて自然な批評道である。論戦は、批評的表現のほんの一形式に過ぎず、しかも、批評的生産に関しては、ほとんど偶然を頼むほかはないほど困難な形式である。(中略)批評は、非難でも主張でもないが、また決して学問でも研究でもないだろう。それは、むしろ生活教養に属するものだ。学問の援用を必要としてはいるが、悪くすればたちまち死んでしまう、そのような生きた教養に属するものだ。」「批評」昭和39年=1964年
果たして、川口さんからの質問に正確に答え得たかどうかは分かりませんが、以上を、私からの答えとさせていただければ幸いです(2)。
※(1)「自由間接話法」と批評的思考(哲学的思考)との関係については、たとえば国分功一郎氏『ドゥルーズの哲学原理』(岩波現代全書)の第一部をご参照ください。
※(2)より深く「批評」の本質と、その歴史について知りたい方は、拙著『アフター・モダニティ―近代日本の思想と批評』(先崎彰容氏との共著、北樹出版、https://www.amazon.co.jp/dp/4779304318/)や、『表現者クライテリオン』での私の連載、「近代/日本を繋ぐもの―日本近代批評試論」(2018年3月号~2019年9月)を参照していただければと思います。
※川口さんからの質問
いつも楽しく拝見しております。
度々目にする批評という言葉の意味合いがどうしても掴めません。
解説や批判とは異なるこの批評という行為の目的や狙い、
批評を行う者に求められる態度とはどういうものなのでしょうか。
ご教示いただけると幸いです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メルマガのバックナンバーはこちらで閲覧頂けます。
https://the-criterion.jp/category/mail-magazine/
雑誌『表現者クライテリオン』の定期購読はこちらから。
https://the-criterion.jp/subscription/
Twitter公式アカウントはこちらです。フォローお願いします。
https://twitter.com/h_criterion
その他『表現者クライテリオン』関連の情報は、下記サイトにて。
https://the-criterion.jp
ご感想&質問&お問合せ(『表現者クライテリオン』編集部)
info@the-criterion.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
執筆者 :
TAG :
CATEGORY :
NEW

2026.02.13
NEW

2026.02.12
NEW

2026.02.11
NEW

2026.02.09
NEW

2026.02.07

2026.02.06

2026.02.09

2026.02.12

2026.02.11

2026.02.07

2026.02.06

2024.08.11

2026.01.20

2026.02.05

2018.09.06
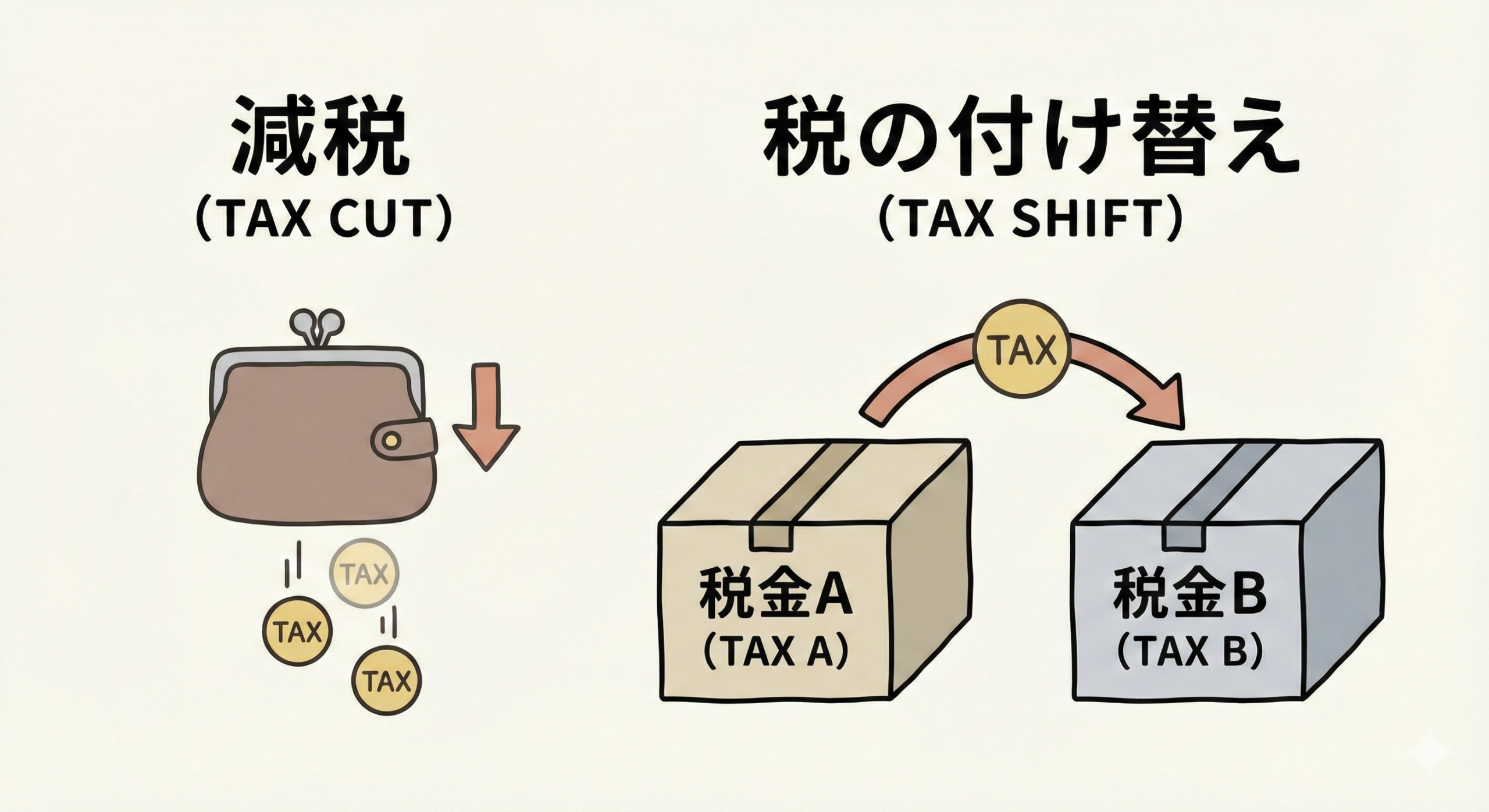
2026.01.18
コメント
ご回答及び参考図書までご紹介して下さり、ありがとうございます。
批評とは誰にでも行い得ることではなく、感受性、想像力、素直さが必要だと
痛感しました。参考図書を読んでみます。
文面から浜崎さんの誠実さ、力強さが伝わってきました。
今後も浜崎さんの表現者活動を楽しみにしております。
川口
36歳
東京都
不動産業