<明日発売!『表現者クライテリオン2024年3月号 特集日本を救うインフラ論 今、真に必要な思想』>
the-criterion.jp/backnumber/113
インフラは、経済活動になくてはならないものである。産業の生産活動や物流に、道路や港湾、電気や通信、上下水の施設などの社会資本の整備は欠かせない。最近の経済論義では、起業の促進が重要とされているが、インフラ状況の悪いところに企業が生まれないのは自明である。投資はつねに不確実性にさらされている。ある土地に工場を作る際に、電気代や水道代、物流や人材調達のコストが上がるかもしれないとなれば、どんなに勇敢な企業家でも投資を尻込みするだろう。国内の民間投資を活発にするには、政府による社会資本(social overhead capital)への投資、すなわち政府によるインフラ整備が不可欠である。
ところが、ここで問題が発生する。政府によるインフラ投資も、結果は確実なものではない。産業の基盤を準備しても、企業の集積は進まないかもしれない。産業の拠点とすべく莫大な資金を投じて道路や港湾設備を作っても、経済環境の変化で、計画通りの民間投資の連鎖は起きないかもしれない。民間投資の不確実性を減らすには政府によるインフラ投資が必要だ。しかし政府投資にも不確実性はつきまとう。費用に見合った効果が得られない場合は「税金の無駄遣いだ」として、政府に激しい批判の矢が飛んでくるのである。
だが、批判に尻込みしてインフラ投資を控えれば、産業の発展は見込めない。土壌改良や農道への投資なしに農業の発展はないし、電力や物流のネットワークが整備されていないところに工場の建設はない。通信や交通の便の悪いところでサービス業は発展しない──サービス業は人と人が顔をつきあわせるところに成立する産業だからだ。
もちろん、産業の発展には、法律や規制の適切な運用も必要だが、それだけでは十分ではない。ソフト面での制度改善は、ハード面での社会基盤整備を伴ってはじめて有効なものとなる。十分なインフラ投資のない地域で、産業の発展は見込めない。政府が不確実性を恐れて十分な投資を行わなければ、地域の衰退は決定的なものとなるだろう。企業は、インフラ環境が整っている他の地域へと逃げ出してしまうからである。
今から十五年ほど前に、ある財界団体の招きで中国の深圳や杭州に進出した日系企業の工場を訪れたことがある。印象的だったのは、誘致企業の不安を解消するために、中国政府が積極的な投資を行っていた、ということだった。杭州の日系企業では、進出にあたって優先的な電力供給や、工場から港湾まで直通の高規格道路の建設を約束されたという。人材調達の不安を解消するために、工場の近くに工業高校まで作っていた。地方から若者を集めて技術教育を施し、当の日系企業に優先的に就職させる、といった政策まで実施していたのである。
当時、日本では公共事業には冷たい目が向けられ、特に地方でのインフラ投資は無駄の象徴と改革派の目の敵にされていた。日本企業が国内投資から海外投資へと向かったのは、国内の税制や人件費の高さだけが理由ではない。生産や物流、人材調達に関わる様々な不確実性を政府が引き受けてくれる。政府(この場合は地方政府)が、そのような大胆な投資に踏みだしたからこそ、中国は世界中から企業を呼び込んで発展軌道に乗ることが出来た。二〇〇〇年代から社会資本ストックが頭打ちとなった日本とは対照的である。
どんな投資計画にも不確実性はつきものだ。計画が実行されても、予想された成果が得られないかもしれず、当初は想定していなかった困難が生じて追加費用が発生するかもしれない。これは民間投資でも政府投資でも変わらない。しかし、それでも計画が実行されるには、二つの条件が必要だとA・ハーシュマンは言う(『開発計画の診断』)。
一つは、計画によって得られる便益が、高い水準に見積もられるということだ。インフラが整備されれば、企業が集まり地域が発展する。増えた税収によって社会福祉など他に必要な行政費用をまかなうことができる。ハーシュマンはこのような期待を、「ユートピア・ビジョン」と呼んでいる。現代風に言い直せば、地域経済振興の「物語」の共有である。投資計画を実行する政府、民間の事業者、地域住民の間で、その投資が地域に多くの恩恵をもたらしてくれるはずである、という物語が共有されていないと、計画はなかなか実行されない。
もう一つ、大事な条件がある。それは、計画者に問題解決能力への自信が備わっていなければならないということだ。
計画にはトラブルがつきものである。例えば、計画通りに成果が上がらない、渋滞や環境破壊など計画段階では想定していなかった困難が新たに発生する、「話が違う」として地域住民の反対が大きくなるなどといったものである。投資には予期せぬ落とし穴がつきものだ。プロジェクトが長期的なものであるほど、計画段階では予想できなかった困難が次々に現れてくる。
こうしたリスクを、投資計画者が先読みしすぎると、投資は萎縮してしまう。投資計画が実行に移されるには、事前には予期できない困難が発生しても、その都度、解決できると構えておかなければならない。どんなに考え抜かれた計画でも、将来のリスクを十分には織り込めない。それでもプロジェクトが実行されるには、想定外の困難が発生しても必ず問題を解決できるはずだ、という自信や信頼が必要なのだ。
ハーシュマンはこれを「隠し手の原理(hiding hand principle)」と呼んだ。将来のリスクを数えあげているだけでは、計画や構想はいつまでも実行に移せない。実行に移すには、将来の困難がわれわれの目から「隠されて」いなければならない。問題が発生しても必ず解決できると信じていなければならない──言い換えると、問題を解決できないかもしれないという不安や疑念が「隠されて」いなければならないのである。「人間は、自分が解決できると考える問題だけを取り上げ、後になって、それが実際のところ予想以上に難しいと気づくが、そのときはもうにっちもさっちもいかぬ状態になって、その夢想だにしなかった困難とどうしても戦わざるを得なくなり、挙げ句の果て、時には大成功を収めるのである。」(麻田四郎、所哲也訳)
神様は、われわれの目をそっと目隠しして、将来の困難や疑念が、見えすぎないようにしている。そしていざ行動に移すと、深刻な困難が次々に現れるが、いまさら行動を止めることはできないので、何とか対処しようとする。この悪戦苦闘の中にしか成功の可能性はない。これは人間の行動一般に当てはまる原理だが、とりわけ大規模で長期的な政府投資について当てはまる。「隠し手の原理」が働いて、計画が動き出さなければ何も始まらない。十分なインフラ投資がなければ、地域の発展は見込めないからである。
今、世界的に産業政策が回帰しつつある。アメリカではバイデン政権の下、クリーンエネルギーやEVなど新産業分野への政府支援や、蓄電池や半導体など重要物資の国内生産強化に向けて動き出している。日本でも、二〇二一年に経産省が「産業政策の新機軸」を発表、気候変動やデジタル化、経済安全保障といった現代的課題に、政府が積極的に関与する方針を打ち出した。
自由貿易全盛の時代には、産業政策は時代遅れとされていた。しかし、グローバル化による産業の空洞化や良質な雇用の喪失、地方の衰退や格差の拡大といった課題が見えてくるにつれて、流れが変わってきた。明らかな転換点はトランプの登場である。アメリカが関税政策や露骨な補助金政策をとり出したことで自由貿易の規範が緩み、各国が独自に産業政策を追求する余地が生じたのだ。
問題はこの先である。日本でこれから生産拠点の国内回帰を促すとしよう。そのためには、税制優遇や補助金といった政策だけでなく、社会資本の拡充、とりわけ地方でのインフラ投資が不可欠なはずである。産業政策というソフト面での政策は、産業活動の基盤を整えるというハード面でのインフラ政策と結びついてはじめて力強いものとなる。というより、インフラ投資が先行しなければ、他のどんな政策も十分な効果を上げられずに終わる。社会基盤の整備は、文字通りあらゆる政策の基盤なのだ。
戦後日本では、数度にわたって国土計画が策定された。現在では役割を終えたと見なされることが多いが、産業政策の再評価が進む昨今、国土計画もその意義を見直されてしかるべきである。重点産業の指定や企業間競争の調整に代表される戦後日本の産業政策は、産業の集積や分散という地理的な空間編成と軌を一にして進められてきたからである。
よく誤解されることだが、日本の産業政策は、社会主義の指令経済システムとはまったく異なるものである。社会主義国では、生産・分配・流通・金融の全ての分野にわたって、政府が命令権を持ち、政府の策定した計画通りに資源が割り当てられる。しかし、日本の経済システムはそうではない。戦後の欧州諸国、例えばイギリスで広範囲にわたる産業の国有化が行われたのとは対照的に、日本では国有化はほとんど行われなかった。私有財産を保障する法的拘束力は強く、政府の進める土地収用はしばしば困難に直面した。民間の市場競争は活発で、過当競争が問題になるほどだった。軽工業から重化学工業への転換に政府が大きな役割を果たしたのは事実だが、そのやり方は政府による指令とはほど遠い。民間は自由主義的で、政府による直接的な介入には抵抗があった。一九六三〜四年の特振法廃案に見られるように、政府が重点産業の特定企業を支援しようとすると、経済界から激しい反発が起きるのが常だった。そのため政府の産業政策は、行政指導のような間接的で誘導的な手法をとらざるを得なかったのである。
C・ジョンソンの古典的な研究(『通産省と日本の奇跡』)にも示されている通り、日本の産業政策の特徴は「国家として掲げる総合的な経済目標の設定」にある。明治期の富国強兵や、高度成長期の所得倍増計画のように、政府が国家目標を設定し、社会的合意をつくる。バラバラな方向を向きがちな民間部門に一定の方向を指示し、その下で重点産業に資本や労働力を誘導し、企業間競争を調整するのである。政府は頻繁に計画を策定するが、その計画は計画経済・指令経済のものとは異なる。民間の自由な経済活動を前提としつつ、政府が全体の調整器の役割を果たす、というところにその特徴があった。
国土計画も同様である。一九六二年の全国総合開発計画(一全総)は、地域間の「均衡ある発展」を国土政策の目標に掲げた。これは、当時の池田勇人内閣が当初打ち出した、太平洋ベルト地帯構想に反発する地方の声を受けてつくられたものだった。
(本誌に続く…)
〈編集部より〉
本記事は明日発売、最新号『表現者クライテリオン2024年3月号』の特集に掲載されています。
特集タイトルは、
です。
巻頭言と目次を公開しています。
インフラを実践的かつ思想的に論じた特集となっています。なぜ知識人はインフラを論じないのか、なぜ日本人はインフラに関心がないのか、ご関心を持たれましたら是非ご購入予約の方をお願いいたします。
購入予約・詳細はこちら
定期購読にお申込みいただくと10%OFF、送料無料、発売日前にお届けいたします。

執筆者 :
NEW

2026.02.27
NEW

2026.02.26
NEW

2026.02.26
NEW

2026.02.24

2026.02.23
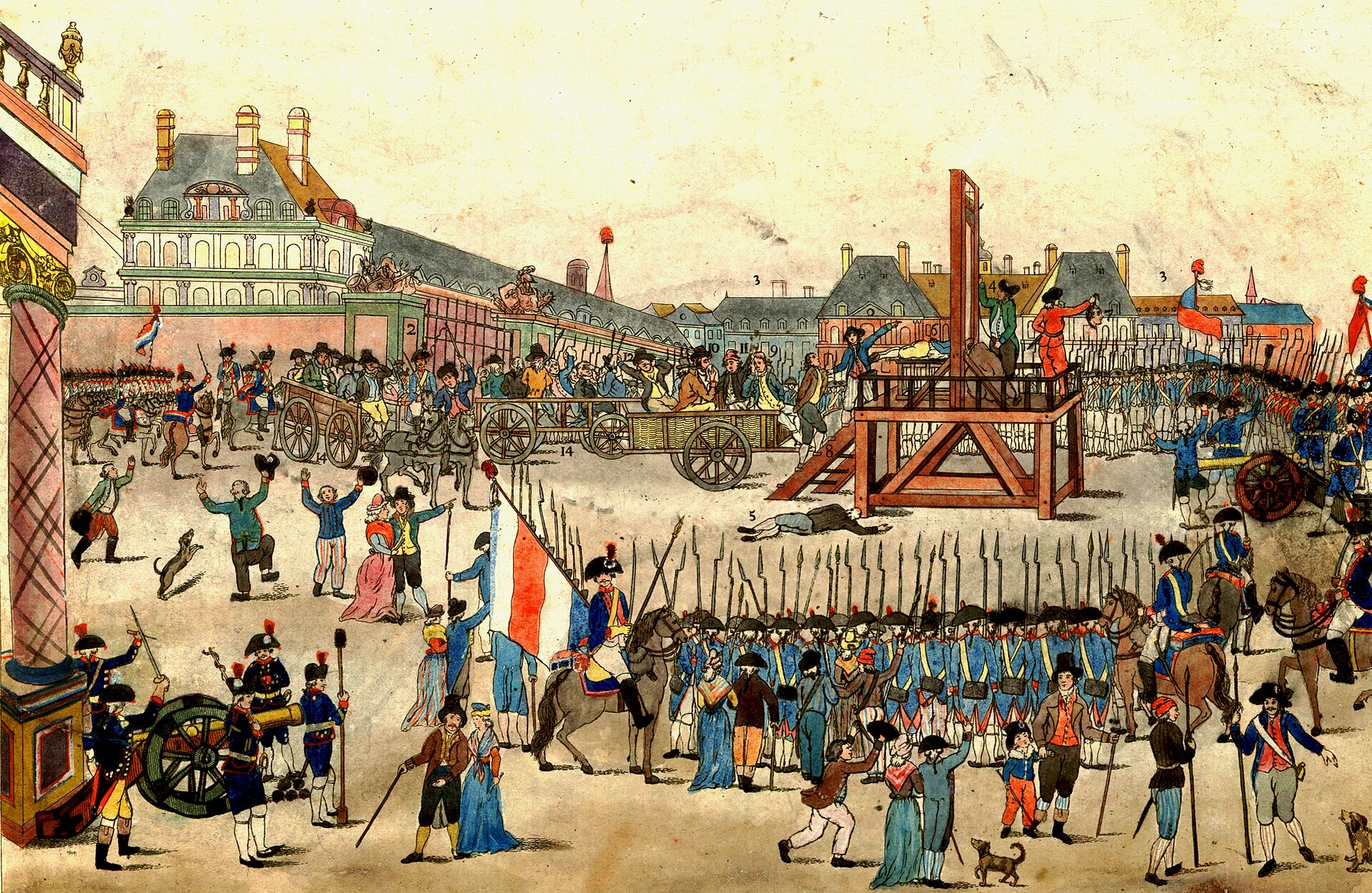
2026.02.20

2025.06.24

2025.07.07

2025.07.09

2021.06.23

2021.06.22

2026.02.27

2026.02.26
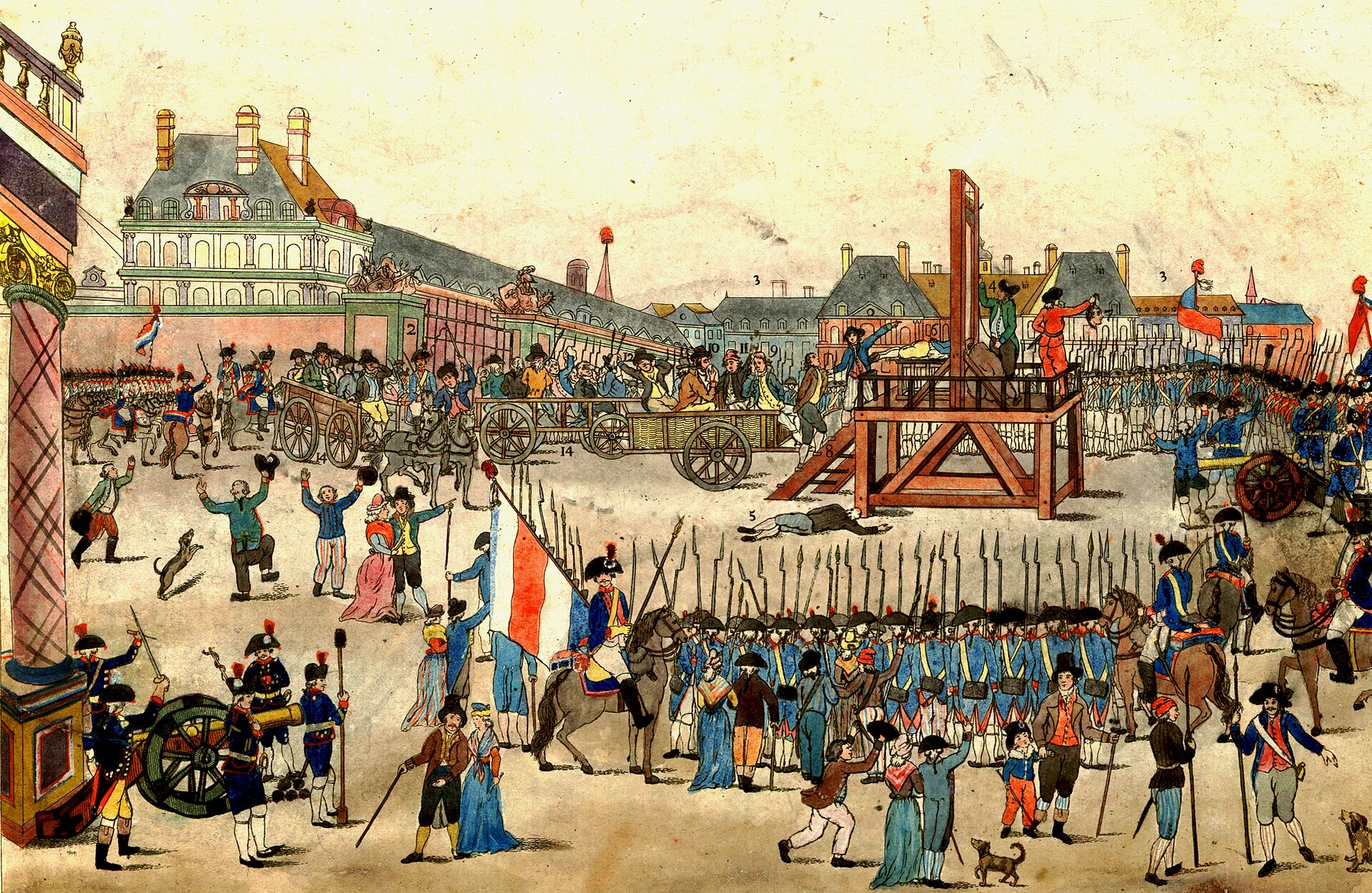
2026.02.20

2026.02.16

2026.02.23