今年は明治150年ということで、いろいろと明治維新回顧のイベントが催されていますが、私も先日、「明治維新とは何だったのか」と題された討論番組(チャンネル桜)に参加してきました。
https://www.youtube.com/watch?v=BgfC5843nr0
それに参加して改めて感じたのは、明治維新という事件の「アイロニカル」な性格です。明治維新の功・罪について語ろうと思えば切りがありませんが、今日は、それがどのように「アイロニカル」だったのかについて書いておこうかと思います。
まず、明治維新とは何なのかと言えば、「西洋に適応するために日本が選択した改革」の一つだと言うことができるでしょう。西洋列強の「力」に直面した日本人は、それに「適応」するために必死で論争し、闘争し、そして「維新」を実現したのでした。
が、その実現までの道のりは、決して単線的なものではありませんでした。事実、明治維新において、もっとも目を引くのは、志士たちの振れ幅の大きさ、言ってみれば、その「豹変」ぶりです。なかでも最大の「豹変」が「攘夷」から「開国」への方針転換でした。しかし、この「豹変」のうちにこそ、後に「自主独立による自己喪失」という、近代日本最大の「アイロニー」が孕まれることになるのでした。どういうことか。
まず、最初に「豹変」したのは、薩摩と長州でした。はじめ「攘夷」を語っていた薩摩と長州は、しかし、薩英戦争(1863年)と下関戦争(1864年)を契機として、一気に「開国」の方に傾いていきます。つまり、自ら西洋と戦うことで「攘夷の不可能」を悟った薩摩と長州は、ほぼ一年間で、過去の怨恨(京都に攻め上った長州を、薩摩を中心とした諸藩が迎え撃った禁門の変)を乗り越えて手を結び(薩長同盟)、一気に「倒幕」に向かって突き進んでいくことになるのです。いつ見ても、この転回の早さには心底驚かされます。
しかし、この「豹変」は単なる「転向」ではありませんでした。その裏には、「国家の自主独立」を守るための武士たちの苦渋の決断があったのです。つまり、「攘夷の不可能」を知った以上、ここは一度涙を飲んで「開国」に向かい、実力を十分に蓄えた後に「真の攘夷」を実現しようという志士たちの決断があったのだということです。そして、その方針転換のうちに、あの「和魂洋才」という言葉も生み出されていったのでした。
しかし、おそらく、この「和魂洋才」という言葉のうちにこそ、近代日本の「アイロニー」も孕まれていました。日本の「自主独立」を目指せば目指すほど、「西洋化(洋才)」を推し進めざるをえず、「西洋化(洋才)」を推し進めれば推し進めるほど、「我々とは何者なのか」という日本人のアイデンティティ(和魂)をめぐる問い=手触りは希薄化していかざるをえない…それを「アイロニー」と言わずして、何というのでしょう。
なるほど、それでも「和魂」が自明であるうちは、「洋才」への距離のなかに、私たちの「主体性」はよく守られていました。たとえば、その好例が福沢諭吉です。
福沢諭吉の『学問のすすめ』を少しでも読めば分かることですが、福沢は、決して単なる「西洋かぶれ」の「啓蒙合理主義者」ではありません。あの有名な「一身独立して、一国独立す」にしても、そこには福沢の武士のエートスが込められていました。
「独立とは自分にて自分の身を支配し他によりすがる心なきを言う。…外国に対してわが国を守らんには自由独立の気風を全国に充満せしめ、国中の人々、貴賤上下の別なく、その国を自分の身の上に引き受け、智者も愚者も目くらも目あきも、おのおのその国人たるの分を尽くさざるべからず。…わが国人の土地なれば、本国のためを思うことわが家を思うがごとし。国のためには財を失うのみならず、一命をも抛ちて惜しむに足らず。これすなわち報国の大義なり。」(『学問のすすめ』明治5~9年)
この「報国の大義」を説く言葉が、単なる「西洋かぶれ」のものでないことは明らかです。
実際、何のために洋学を志したのかと尋ねられて、「即ち余は日本士族の子にして、士族一般先天遺伝の教育に浴し、一種の気風を具へたるは疑もなき事実にして、其気風とは唯出来難き事を好んで之を勤るの心、是なり」(「成学即身実業の説、学生諸氏に告ぐ」明治十九年)と答えていた福沢は、その後も『痩我慢の説』を書くなど、一貫して日本人の「士魂」を擁護し続けたのでした。ただし、それは何も福沢一人に限った話ではない。それは、内村鑑三や、新渡戸稲造や、森鴎外などにも分け持たれていた「和魂」だったのです。
が、この明治維新を担った世代が亡くなり、時代が下ってしまえば、この「和魂」は次第に見え難くなっていってしまいます。とすれば、残されるのは「西洋かぶれ」の「洋才」のみということにもなりかねず、それがまた自分自身の「アイデンティティ」を疑わせ、日本人の「ぼんやりした不安」を加速させていってしまうことになるのでした。
実際、大正も半ばを過ぎはじめると、「明治維新」は不完全な「御一新」であったがゆえに、再度の「維新」によって日本の近代を完成させなければならない(大正維新・昭和維新)、と語る中間イデオローグ(右翼たち)が続々と登場してくることになります。
しかし、だからこそ、彼らが語った「和魂」には、抽象的な響きが入り込んでいたのではなかったでしょうか。あるものを発見するのではなく、失くしてしまったものを発明しようとすれば、それは、どうしても人工的なものにならざるをえません。そして、おそらく、あの大東亜戦争において唱えられた「皇国思想」も、そんな人工品の一つでした。
ところで、かつて明治維新という大業を成し遂げた西郷隆盛と大久保利通は、しかし後に、その「近代化の進め方」をめぐって激しく対立することになります。欧米視察を終えた大久保が、帰国後に「殖産興業」と「文明開化」を唱え出したとき、西郷は、その西洋の「猿マネ」に背を向けるように、鹿児島へ帰って行くのでした(明治6年)。そして明治10年、西南戦争のさなか、西郷は生涯でただ一回「陸軍大将」の肩書で政府に手紙を書き送ることになります。「拙者儀、今般政府へ尋問の廉有之」(政府に尋ねたいことがある)と。
果たして、西郷南洲は何を「問い質し」たかったのか。それは、「いくら精神論などに拘ったところで、国など立つものではない」といった明治政府の「現実主義」に対する「尋問」だったのか、あるいは、「和魂」と「洋才」を器用に使い分けられると思い込んでしまったがゆえに、結局は、その両者から見放されることになってしまう日本人の運命の自覚に対する「尋問」だったのか。それも、今となっては分かりません。
が、いずれにしろ、私たちが未だに西郷南洲のことを忘れられないということ自体のうちに、私たちが、まだ「近代の疼痛」から癒えていないことが示されています。その「疼き」が完全に癒えるまでには、最低でも後100年はかかるでしょう。歴史とは、そういうものです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メルマガのバックナンバーはこちらで閲覧頂けます。
https://the-criterion.jp/category/mail-magazine/
雑誌『表現者criterion』の定期購読はこちらから。
https://the-criterion.jp/subscription/
その他『表現者criterion』関連の情報は、下記サイトにて。
https://the-criterion.jp
ご感想&質問&お問合せ(『表現者クライテリオン』編集部)
info@the-criterion.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
執筆者 :
CATEGORY :
NEW

2026.02.12
NEW

2026.02.11
NEW

2026.02.09
NEW

2026.02.07

2026.02.06

2026.02.05

2026.02.09

2026.02.06

2026.02.07

2026.02.11

2026.02.12

2026.02.05

2024.08.11

2026.01.20
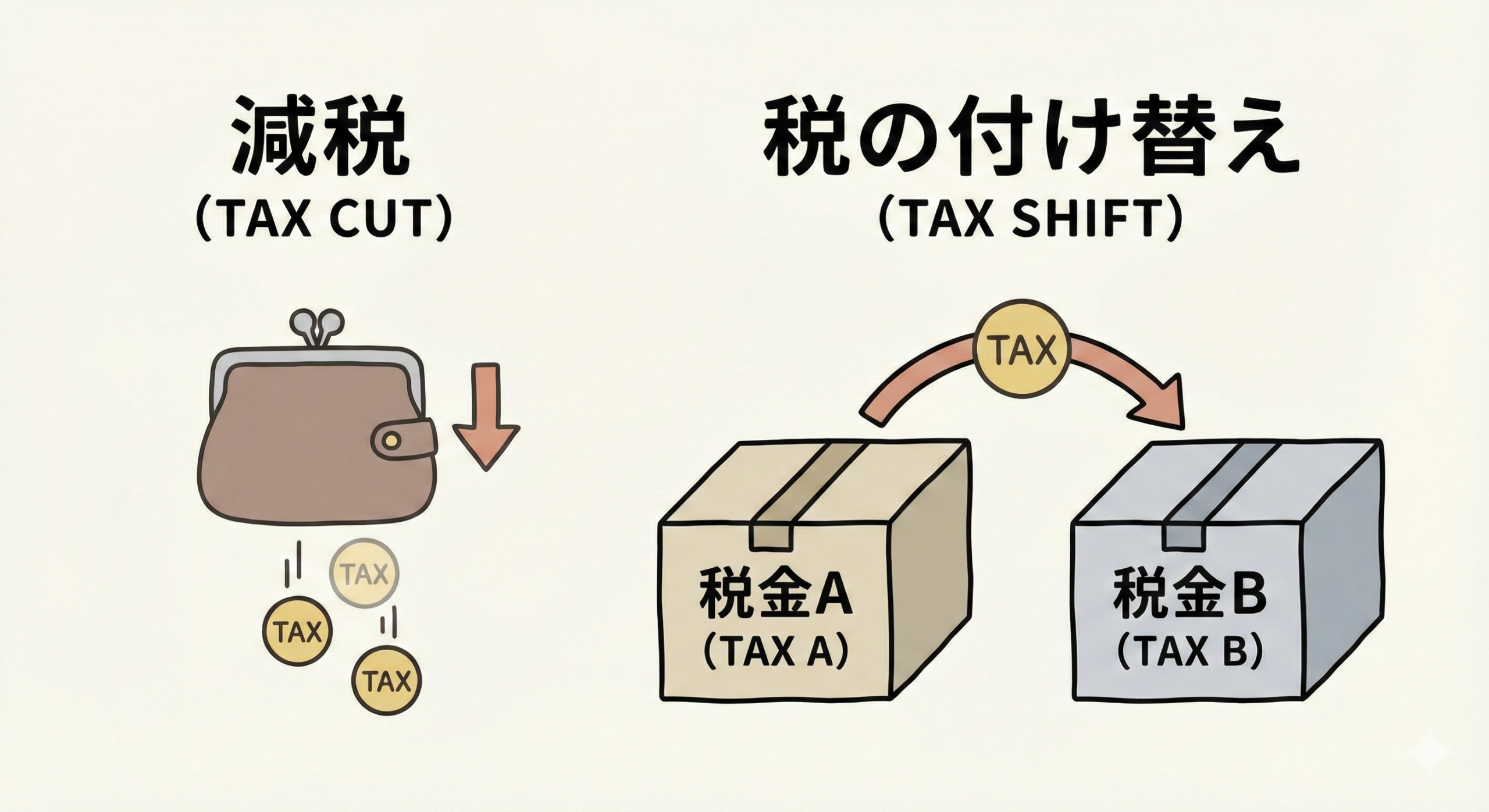
2026.01.18

2018.09.06