学校教育という制度を改めて考え直してみたい。10月に、不登校が約30万人という報告が発表され、滋賀県東近江市の市長が「文部科学省がフリースクールを認めたことに愕然としている。国家の根幹を崩しかねない。不登校の責任の大半は親にある」と述べて、喧々囂々の騒動になった。市長が謝罪して騒ぎは一応収まったようだが、問題の本質は放置されたままだ。
Educationという語彙はラテン語から派生したもので、英語としての初出は1531年だという。ラテン語が意味するのは「人間の能力を引き出し育成すること」で、おそらくルター派のプロテスタント諸国での宗教教育が関係しているのだろう。聖書の内容を知ることで各自の能力を引き出すためには、まず、文字が読めなくてはならない。実際、読み書き人口の増加はプロテスタント地域から始まる。教会の司祭ではなく、聖書から学ぶためには読み書きが必要だった。
どの国でも教育の始まりは「読み書き算盤(3R)」である。文字が書けて読めるようになれば、人生の可能性は広がる。簡単な計算ができれば、生活が成り立つ。エマニュエル・トッドは、彼の論考の基本指標のひとつに識字率を用いているが、「読むことを通して子供たちの頭がよく機能するようになる」「識字化によって頭の構造が変わる」とまで言っている。「読むという活動が新しい人間を創造する。読むことを覚えた人間においては、世界との関係が変わる。前よりも複合的な内面生活が可能になり、人格が大きく変わる。それが最良の結果に繋がることもあれば、最悪の結果を生むこともある」と言う(『我々はどこから来て、今どこにいるのか?』)。3Rは「能力を引き出す」のに必要な基礎的手段であるが、それは「学習」しなくては習得できない。学校では学習内容が増えるに従って、次第に「能力を引き出す」ことよりも「教える、与える、押し付ける」ことが、education教育になったようだ。
かつては教育を受けることは自由意志であった。自由意志と言っても、殆どの大人でさえ文字が読めない時代では、教育を受けられる子供は資産家や上流階級に限られる。教師の数も限られていたし、そもそも教師と言う職業などはなかった。セネカは教員免状があったからネロの教師に招かれたのではないし、アリストテレスが少年のアレクサンダー大王を教えたのも職業だったからではない。貴族や有産階級は、教養人を子供の教育係に雇えたが、一般の人々は社会生活の中で何かを学び取っていた。農民の子は作物についての知識や育て方を大人と一緒に働きながら覚え、職人は親方を手伝いながら技術を修得した。しかし、近代産業構造の変化は、求められる労働力の質を変えた。
Education が 広く一般に使われるようになったのは、産業社会の到来による。産業革命期には労働者階級の子供たちが工場や炭鉱などの労働力として使われていた。昔は、世界の殆どの地域で、子供が10歳近くになると大抵社会の労働力に組み込まれた。日本でもそのくらいの年齢になると、子守や奉公に出されるのが普通だった。産業革命期のイギリスの炭鉱では四つん這いになって石炭の車を曳いていくような狭い坑道で、子供たちは長時間働いた。劣悪な環境での子供の雇用が問題になり、工場法などで年少者の雇用は禁止される。イギリスでは1870年に初等教育法による義務教育が始まった。当初は、児童労働からの保護や治安維持などの側面もあったが、産業界からの均質な労働力確保の要求が大きかった。日本では寺院や学問所などで経典や古典を学び、町家の子供たちには読み書きを教えてくれる寺子屋があった。武士の家庭では論語の素読を繰り返して、身体で古典の意味を体得していた。明治政府になって、1872年には学制が公布されるが、当初は授業料が有料であったため効果はなく、1890年の小学校令改正で尋常小学校の授業料無償化により普及する。大正期には通学率が9割を超えていたという。教育の義務化が必要だったのは、親の無理解から教育を受けられない子供をなくすためでもあった。子供を学校に行かせるよりも働かせたいという親や雇用主はたくさん居た。子供たちを環境の悪い労働現場や虐待から守る必要もあった。
現在、『世界人権宣言』では「すべての人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の 及び 基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。(第26条)」と定められている。いま、初等中等教育は「権利」であり「義務」である。私たちは、義務教育を無条件に「いいこと」だと思っている。読み書きができるようになれば、世界が広がる。読み書きを教えてくれる学校制度は、人生に「価値のある」ものだと思っている。しかし、今日、教育現場で直面するのは、学校が子供にとっても教師にとっても、必ずしも「楽しい」場所ではなくなっているという現実である。教員は長時間労働で疲弊し、子供たちはひきこもりやフリースクールに逃げて、東近江市長の「懸念」を引き起こす状況になっている。学校が「楽しくない」子供たちが増えただけでなく、中にはいじめや競争で「苦痛」な場所、もっと酷くなると「人生を破壊する」場所にさえなってしまった。ここには、時代や社会が変わったからというだけでは済まない、もっと本質的な問題があると思われる。
日本でも途上国でも、産業社会の確立と並行して学校制度が導入されている。このスタイルはヨーロッパで17世紀から18世紀にかけて発達したようで、19世紀の先進国で一斉に義務化された。それでは、17~18世紀のヨーロッパでは何が起こっていて、何が学校制度の成立やその義務化を方向づけたのだろうか。
この時代のヨーロッパは戦乱の時代だった。プロテスタントの勃興、それに伴う宗教戦争、封建制に代わる絶対王政の台頭で君主が力を持ち、国家間の抗争が激しくなる。経済規模の拡大と戦争は、国家間競争の両輪だった。プロイセンのフリードリヒ・ヴィルヘルムI世(在位1713-40)は異常なまでの熱意を持って民衆教育政策を強行した。1717年には、早くもプロイセン領内で義務教育を実施している。産業革命前の経済は農業生産力が基本である。このときの義務教育は、封建領主下の農地を解体してプロイセンの直轄領とし、そこで働く農民を育てるためのもので、農業生産力を上げるための移民政策にも関係していた。プロイセンは、三十年戦争で荒廃した国土と極度の人口減少を移民による人口増加策で補おうとした。その際、カトリック教徒やユダヤ教徒ではなく、自主独立精神を持ったオランダ人やユグノーなどのプロテスタント系の移民が選ばれた。フリードリヒ・ヴィルヘルムI世の教育方針の基調となる「敬虔主義」は、勤勉さや規律遵守の精神、勤労愛好、忍耐、秩序、快楽に対する憎悪と軽蔑といったプロテスタント的なイデオロギーにある。
同じ時期に大航海時代と植民地獲得競争があり、ヨーロッパの抗争は地球規模になった。植民地からの資源の流入や市場の拡大は、手工業から資本主義へと産業構造を変えて、ブルジョアジーが現れる。宗教的にも政治的にも経済的にも相互に玉突きのような変化が起こっていた。特に大きく変わったのが軍隊である。戦争に明け暮れていたヨーロッパでは、強大な君主制を支えるために常備軍が創設されるようになった。兵器の発達や戦争規模の拡大で、封建時代のように、諸侯が戦争の度に兵士を集めて戦争が終われば解散するような「一時的傭兵制」の軍隊では勝てなくなったのだ。
軍事費や軍備・制度の詳細な資料を用いて、ヨーロッパ各国の軍隊の変化や特質を考察したのがヴェルナー・ゾンバルト(1863-1941) の『戦争と資本主義』(1913)である。この著作の中でゾンバルトが近代的軍隊の先駆として注目するのが、やはりプロイセンである。フリードリヒ・ヴィルヘルムI世は国家官僚制度や税制と共に軍制を整備して近代的軍隊を確立している。
「近代的軍隊」とは、どのようなものだろうか。それまでの諸侯や領主に忠誠を誓う武士団が率いる軍隊に比べて、国家の軍隊は規模が大きい。武士団ではなく、君主の統治下にある民衆が兵士の供給源になる(徴集兵)。民衆の軍隊は戦術的に統制のとれた大勢の兵士が部隊ごとに「全体のための役割」に従って行動する大規模なものである。嘗ての戦場では、各武将が率いる一団がそれぞれの判断で戦っていて、戦略全体としては統一されたものではなかった。近代の軍隊は、各連隊や部隊が国家の意思を遂行するための部分として戦う。ゾンバルトによれば「共通の精神に満たされた大集団の超個人的な統一体」ということになる。司令官から発せられた命令通りに動く兵士は、没個性的単体である。軍命は絶対である。個人の判断は全体を乱す。これをゾンバルトは「指導する機能と、実行する機能の分化」という。そのために必要になるのが、訓練と規律である。ゾンバルトは、イギリスにおいても、この軍隊精神がクロムウェル(1599-1658)のニューモデルアーミーに導入されていたという。軍隊の一部として作られた人間を「新人類」と呼び、新しい人類は、自然人である自分を「破壊する」ことで生み出されると考えた。「ピューリタニズムと軍隊精神の理想は同一である。すなわち、生物そのままの人間性の克服と、個人を卓越した全体の中に組み込むことである」という。彼は、自己を消滅させることで全体の一部として機能するように造り変えられた人間を「新人類」と呼んだ。訓練や識字化によって人間の質に何らかの変化が起こるということでは、エマニュエル・トッドも同様な視点を持つ。但し、どのような質に変化するかは、また別の問題である。
近代的軍隊で要求される分業化、専門化、義務の遂行、規律の遵守は、訓練によって培われる。それらは、産業界に移植される。ゾンバルトによれば、資本主義は「まったく同種の人間」を必要としているからである。17世紀から18世紀にかけて、手工業から資本主義生産への過渡期に、民衆労働者の訓練の必要性が明らかになった。産業界で必要な働き手を効率よく育成するのが学校制度である。これは、educationの本来の意味である「人間の能力を引き出すこと」ではなく、個人の潜在能力の封印である。敢えて肯定文にすれば、「全体の一部となる能力」を引き出すためのtrainingの場と言えるだろうか。
軍隊で生まれた規律やシステムの多くは、学校制度に導入されている。カリキュラムの編成、同年齢の子供の就学、時間割による管理、試験による到達度の評価、評価の数値化、到達目標の設定、学年制、課程修了による進級、等々がそれに当たる。義務教育で教える内容は、軍隊や産業界や国家が「教えたい」ことである。それらを知らなければ、戦争に勝てず、生産性を損ない、いずれ国家に反旗を翻す、と、教育する側が認定したことである。教師という専門職も必要になった。教師は指導要綱に沿って、一定期間内でカリキュラムを終了させなければならない。ある年齢に達したら一律に入学し、学年ごとに何をどれだけ教えるかという指標がある。これは、マイケル・ヤングが『メリトクラシー』で述べているように「平等でないものを平等と見做して」個人の資質を無視したシステムである。これを評価の対象にすれば「格差」が生じるのは必然であると、彼は警告した。極論で言えば、学校教育で教え測る能力は「生産性に関わる知能」であり、そのための教育は他の豊かな潜在能力を封印してしまいかねない。それならば、学校教育で「個性を伸ばす」とか「多様性の重視」などという目標は、それ自体が自己矛盾である。
学年ごとに教科内容が決められ、到達度を測る試験を実施し、それを通過すれば修了と認められる。その到達度や評価に応じて進学先が決まれば、競争が起こる。義務教育が「たとえ有益な目的のためであっても、自分の手の中の一層御し易い道具」(J.S.ミル『自由論』)を作るためだとしたら、それに耐えられない子供たちは必ずいる。自然な状態でいることが許されない場所になっているからである。自然状態では発生しないことを、敢えて「させる」から「義務」になる。「義務化」は、自発的でないことを強要するときに生まれる。
教育は「社会の持続と発展のために、個人または特定の機関が一定の価値を志向して未熟な者をその社会に適応させる意識的な活動であり、社会統制の一種として制度化されるもの」と定義される。ここで、東近江市長の「国家の根幹を崩しかねない」という発言を思い出してみよう。市長が教育を「国家」と結びつけて考えているのは、義務教育の社会統制的な目的を把握していると言える。但し、国家による統制や規律を全体の善と見做して、学校教育が一人ひとりの生徒の発育に与える影響については考えていない点で、フリースクールの問題をまったく理解していないこともわかる。勿論、公共心は必要であるし、好き勝手に我儘なふるまいをしていいというわけではない。他者へのいたわりを「学ぶ場」として「学校」を全否定はできない。寺子屋や適塾は「学びの場」であった。知的好奇心を刺激する「学びの場」は必要である。いま、問われているのは「学びのシステム」である。そもそも近代の学校制度の要求が資本主義であれば、その目的は個人の生物的な育成ではなく、産業界に奉仕する人間の育成にある。近年、産業界の要求が明瞭に表れたのが、「小学校の英語必修」である。改革やカリキュラム変更に、学ぶ側の意思や適性が反映されるわけではない。
「脱学校」を主張したイヴァン・イリイチは、この一方的な学校教育の在り方を明確に否定した。彼は、学校制度も「たえず需要の増大する世界」と考えている。「学校は近代化された無産階級の宗教」となっていて、人々はカリキュラムを消化すれば未来があると期待する。しかし、修了すればその先にも階段があり、これを等級化された学校階段だという。まさにメリトクラシーの確立である。その期待のために教育は終わりのない消費で成長市場となっている。学校制度は競争を生み、競争は格差を作る。格差はさらなる競争を生み、生徒の側からも保護者の側からも「学校」という信仰に迷わされ、他人より上級の学校を目指すようになるのだという。(『脱学校の社会』東京創元社/1977)
ところで、学校で私たちは何を学んでいるのだろうか。カリキュラムの編成や試験による到達度の評価、評価の数値化、到達目標の設定、課程修了による進級というのは、「問題設定と用意された解答」によって成立する。答えの提示は好奇心を失わせる。答えが提示された時点で、その学習は終わる。正解を出すための勉強はトレーニングであって、その記憶力と到達時間を競争するのが試験である。そのような効率のいい方法論を学ぶ場が、学校になっている。実際、義務教育以前の幼稚園から、用意されたカリキュラムが伝授されている。お遊戯にしても歌にしてもゲームにしても、先生が教えるとおりに行う。学校側で用意されるものならば、需要はいつまでも開拓できる。そのために、教育はそれ自体が成長産業として、無限への希求で拡大しようとする資本主義経済に参加しているのだ。今日、中高年に奨励されるリスキリングも、新たな需要による消費活動と言えるだろう。
義務教育や学校制度は世界的に実施されている。中国でも韓国でもインドでも、経済成長と共に受験競争が激しくなって、予備校や塾が増えた。義務化された競争からの脱落は社会的敗北を意味し、その時点で将来が閉ざされるからだ。イリイチがいくら「脱学校」を主張しても、最早このシステムを変えることは不可能に思える。国家は経済成長を望み、産業界が教育を要求している以上、学校制度は不可逆的である。義務教育だけでなく、産業界は大学にも「即戦力」を育てる教育を求めている。大学は、もう随分昔から就職に必要な認定機関になっている。教育を受ける側が変化を求めなければ、学校制度は、寧ろ更に詳しく更に専門的にと拡大する。「脱学校」が起こるとすれば、それは近代の終焉を意味する。学校制度は近代資本主義の要請として生まれたものだからだ。しかし、近代の終焉がAIによる世界への移行だとしたら、それもまた生物としての人間にとっては不自然な世界になるだろう。
J.S.ミルは、1867年にスコットランドのセント・アンドルース大学の名誉学長に就任したとき、「大学は職業教育の場ではない」と述べ、イギリス社会の金儲け主義とピューリタニズムを批判した。既にこの頃、大学は格付けされた認定書発行機関の性格を持っていたようである。彼は、この就任演説の最後に、学問には利害を超越した報酬があると述べている。
「(学問によって得られる報酬とは)諸君が人生に対してますます深く、ますます多種多様な興味を感ずるようになる(ことです。)—中略—それは、人生を何十倍も価値あるものにし、しかも生涯を終えるまで持ち続けることのできる価値です。単に個人的な関心事は、年を経るに従って次第にその価値が減少していきますが、この価値は減少することがないばかりか、増大してやまないものであります。」(『大学教育について』岩波文庫/2011)
人生を豊かにする知的興味を持ち続けるために、そして、自己の潜在的な能力を失わないために、更に、よい人間関係を築くために、学校に対する自らの態度に「自覚的」であることが、私たちにできる自衛策かもしれない。
〈編集部より〉
最新号『表現者クライテリオン2023年11月号』

絶賛発売中。
是非ご一読の上、ご感想等お寄せください!
購入・詳細はこちら
定期購読のお申し込みはこちら(10%OFF、送料無料)
執筆者 :
CATEGORY :
NEW

2026.01.30
NEW

2026.01.30
NEW

2026.01.29

2026.01.23

2026.01.23

2026.01.22
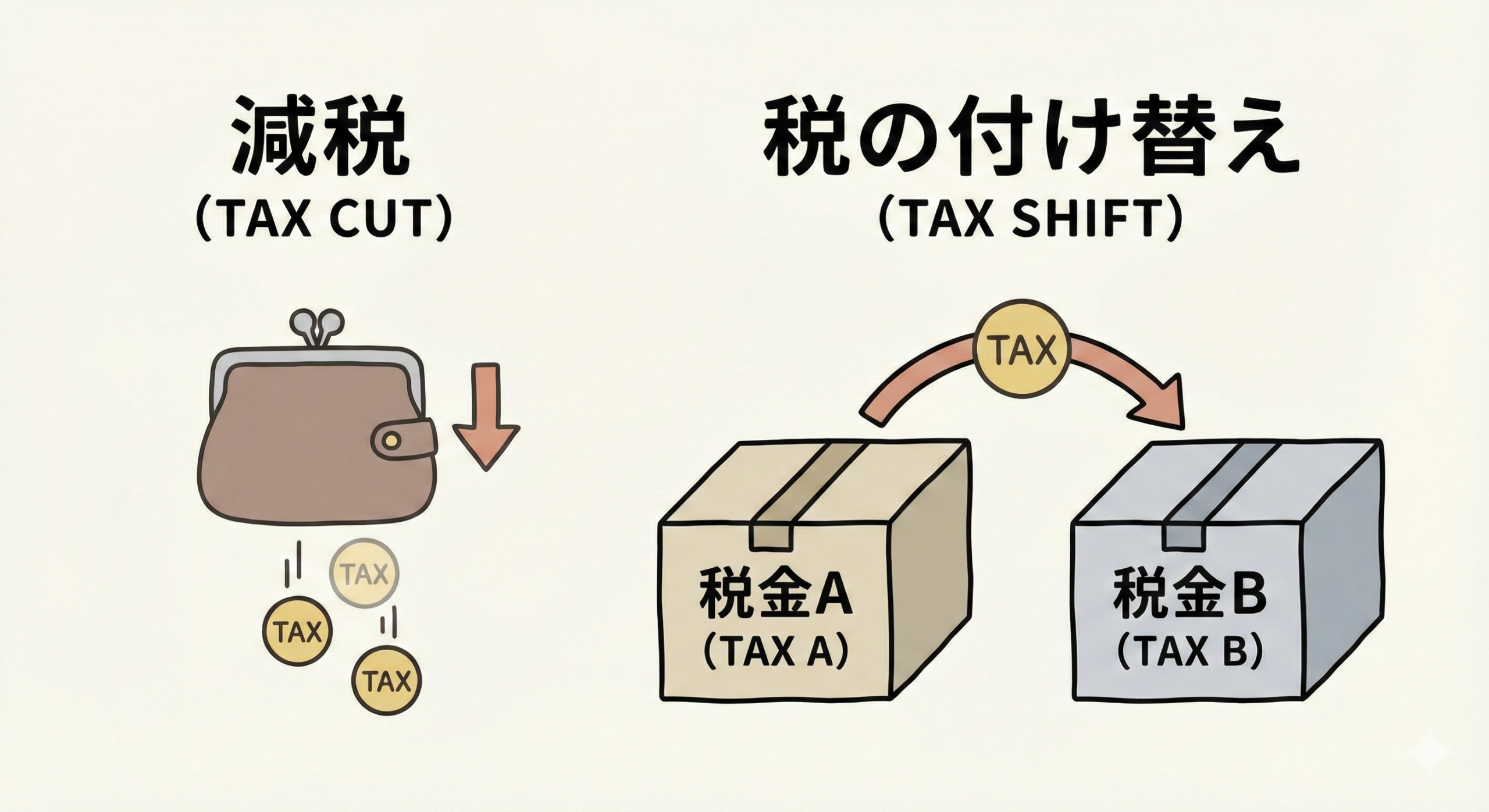
2026.01.18

2026.01.20

2026.01.30

2024.08.11

2026.01.30

2018.04.06

2026.01.22

2026.01.29

2018.09.06

2018.03.02