『どもる体』(二〇一八年)や『手の倫理』(二〇二〇年)などの著作において、さまざまな具体的な事例から、個別の〈生の現場〉を描き出す哲学者の伊藤亜紗氏は、博士論文を元に書かれた本書からそのキャリアを開始した。私たちの身体と世界の関係を問う、以降の身体論のモチーフは、すべてここから展開されたものだと言えるが、しかし何故その対象に選ばれているのが、ポール・ヴァレリーという二十世紀前半を生きた、ひとりの作家なのだろうか。第一次大戦直後に発表した「精神の危機」で西洋の絶望的な行く末を見つめ、詩人としては散文的要素を排する「純粋詩」を理想視したこの作家は、私たちの生=身体を考える上で、いかなる示唆を与えるのか。本書が問うのは、ヴァレリーの詩のなかで読者がある行為を促されるような、「芸術」と「身体」が交差する、その領域である。
まず、本書はヴァレリーの「純粋詩」という一見空疎かつ理念的なタームについて、その内にある意味を解きほぐしていく。前述のようにそれは、作家の設定した主題のなかで登場人物を視覚的に描写する散文(小説)形式を批判しながら、歴史によって洗練された「型」に従って対象を捉える方法である。だが、注意すべきなのは、ヴァレリーがこの語を用いてなによりも非難する ものが、作家の「わざとらしい演出」=「気取り」だという点である。
言い換えれば、ここで槍玉に挙げられているのは、作者の自意識にほかならない。つまり、「純粋詩」を語るヴァレリーの真の目的とは、作者の思想を一方的に読者へ伝えるといった構図をしりぞけ、その作品を読む者が(たとえば朗読という形で)行為に促され、各々の身体を組み立てていくことだと、本書は主張するのだ。
その上で、本書はこのような作品=詩が私たちに齎す、「時間」の感覚をめぐる議論へと発展する。ここでの「時間」とは、過去を引き受けたひとがその後の行動を予期するという生きたそれだが、重要なのは、主体と世界が一致する感覚を持つかどうかによって、「持続」と「リズム」という二つの時間様式が現れるという指摘である。前者は細い針に糸を通す場合のように、なにかに注意を向けるときに生まれ、後者は音楽に身を任せる場合のように、思考を止めて行為を一定に保つときに生まれるのだが、それらは私たちの自意識を鎮め、「あるがまま」を肯定して人々を「身軽」にする、「調和的な時間」にほかならない。
そして、ヴァレリーの目指す詩とは、この「調和」へと読者を誘うものだとして、最後に本書は〈作品─時間〉を受けて変容する人間の「身体」の探究に入っていくだろう。ある偶然的な出会いを通して、〈自分の知らない自分〉を発見し、生きたままみずからの「身体」を「解剖」すること。本書が言うように、ヴァレリーの語る詩的体験とは、普段目に留めることのない「無意識」への気づきを与えてくれる。その意味において、本書の〈芸術=身体〉論は、私たちにとって重要な「生の哲学」となるのである。
〈編集部より〉
最新号『表現者クライテリオン2024年1月号』が好評発売中です。
ぜひお手にお取りください!
購入予約・詳細はこちら
定期購読にお申込みいただくと毎号10%OFF、送料無料で発売日までにお手元に届きます。

執筆者 :
NEW

2025.06.27
NEW

2025.06.26
NEW

2025.06.24
NEW

2025.06.24
NEW

2025.06.24
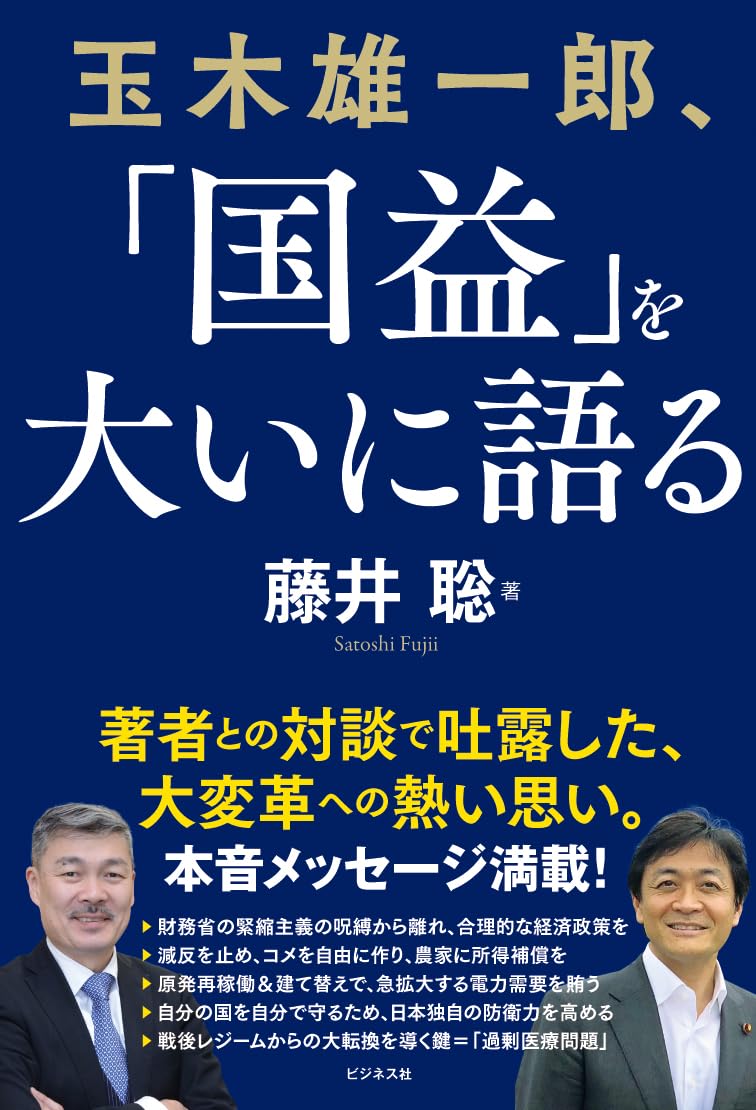
2025.06.21

2025.06.24

2025.06.26

2024.08.11

2025.06.27
.jpg)
2025.06.03

2024.07.13

2025.06.20

2025.06.24

2025.04.21

2025.06.24