日韓併合は日本民族派にとっての大きな挫折であった。黒龍会を設立した民族派の首領内田良平が樽井藤吉、武田範之、権藤成卿らと邁進したのは、「日韓合邦」であって「併合」ではない。 欧州の植民地支配とは違う、決して韓国を隷属視しない対等な合併こそが民族派の夢であった。そのために一進会の李容九らと連携し運動を進めた。しかし軍事、外交的事情からその理想は骨抜きにされ、「併合」でありながら「総督府」などという植民地施設が置かれることになる。以来満洲国の「五族協和」、大東亜会議での「人種平等」などと、戦前日本は「スローガンとしての反植民地主義」と「軍事外交的国策」の間を敗戦までどっちつかずでうろつくことになる。
併合期について、韓国人は「収奪」で語り、日本人は「贖罪」で語りがちである。近年では日本側からもインフラ整備やハングルの普及における日本の貢献なども語られるようになった。だがそれらが現代の朝鮮半島に多大な利益をもたらしていたとしても、当時の韓国人がそれを望んでいたわけではない。そろそろ現代の政治的な動機からなる親日─反日論争を超えた朝鮮観、韓国観が定着してもよい頃ではないだろうか。
本書が紹介するのは、日韓併合期の日本人の朝鮮半島に対する発言である。当時のほとんどの日本人は、併合によってはじめて韓国に向き合った。朝鮮半島に広がっていたのは雄大な山河であり、人々の素朴な生活であり、陶磁器などの古き良き文化であった。それは、欧米に植民地支配されないために富国強兵殖産興業に邁進していくなかで、日本が切り捨てざるを得なかった自文化を思い起こさせるものであった。谷崎潤一郎は朝鮮の山河を「日本画の絵の具の色」と表現し、街並みを「平安朝」の光景だと表現した。谷崎ばかりでなく、雄大な自然などの朝鮮の風景に打たれた人物は多かったのである。柳宗悦は朝鮮で飲んだ濁酒(マッコリ)に、「自分の身体の中の眠っていた者が呼び覚まされる」とまで書いている。まさに朝鮮は「忘れていた日本」だったのだ。柳宗悦は朝鮮白磁との出会いで民藝運動に開眼した人物である。朝鮮との出会いで、民衆の生活の中に本当の美があると気づいたのである。穂積重遠もまた「僕は古朝鮮の歴史と芸術と音楽とに接して、朝鮮と朝鮮民族とを尊敬すべきことを教えられた」と書いている。本来捨ててはならなかったアジア人としての文化、習俗に、朝鮮に触れることで気づかされたのである。だからこそ日本の韓国統治は「西洋帝国主義者のそれに比べると、いかにも自信なきものたちの統治」となった。
当時の日本人には、韓国に西洋近代を押し付ける存在となっている後ろめたさがあったようにも思える。だからこそ併合では朝鮮文化を生かした統治を考えようとしたのであろう。「反日」「嫌韓」では語れない併合史が、ここにはある。
〈編集部より〉
最新号『表現者クライテリオン2024年1月号』が好評発売中です。
ぜひお手にお取りください!
購入予約・詳細はこちら
定期購読にお申込みいただくと毎号10%OFF、送料無料で発売日までにお手元に届きます。

執筆者 :
NEW

2025.06.27
NEW

2025.06.26
NEW

2025.06.24
NEW

2025.06.24
NEW

2025.06.24
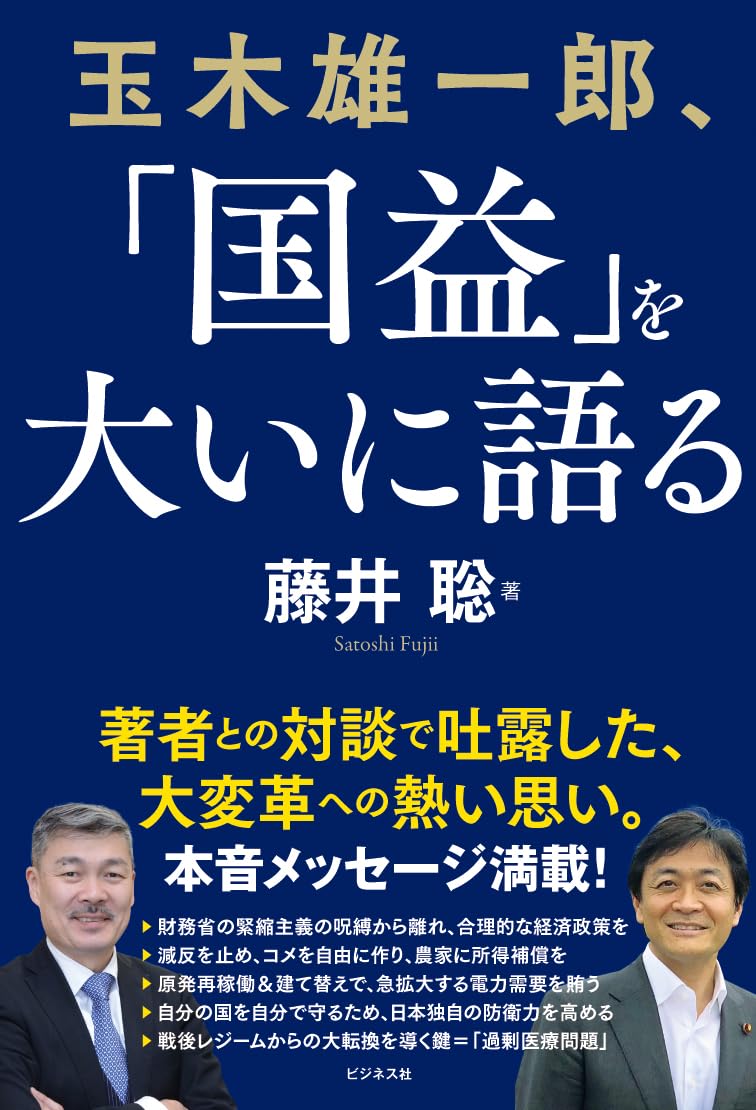
2025.06.21

2025.06.24

2025.06.26

2024.08.11

2025.06.27
.jpg)
2025.06.03

2024.07.13

2025.06.20

2025.06.24

2025.04.21

2025.06.24