海外からの観光客が異口同音に感心するのが「日本の街はどこへ行ってもきれいだ。ゴミが落ちていない。」という感想である。電車の中にも地下道にも路地裏にも、滅多にゴミは落ちていない。確かに日本人はきれい好きである。
街にはゴミがないが、それでは、私たちはゴミを出さない生活をしているのだろうか。とんでもない。我が家は要らないもので溢れている(我が家だけかもしれないが……)。毎日、マンションのごみ置き場に生ごみや不燃ごみやペットボトルや資源ごみなど、何か抱えて運んでいる。ゴミの出ない日はない。ゴミ置き場は、収集日にすっきりしても、すぐに溜まってゴミ袋が積み上がる。各家庭が出す1年間のゴミの量は相当なものだろう。東京のように人口が1千万を超えるような巨大都市の廃棄物の量など、ちょっと考えただけでも想像を絶する。そして、その街をきれいに保つためのシステムが機能しているということ自体が驚きである。
私たちは、ゴミ置き場にゴミを捨てればそれで終わりで、その先のことを滅多に考えることはない。焼却処分をしたり埋め立てたりしているのだろうと、漠然と知っているが、どこでどのように分別し、どのように処理して運んでいくのか、詳しく知ろうともしない。部屋の中からゴミや不用品がなくなれば、それで終わったと思う。しかし、ゴミの問題はしばしば報道されるから、誰もが、ゴミを減らしたりリサイクルしたりする必要があるとは思っている。
江戸の町のエコシステムはよく知られている。「東の葉もの、西の根もの」と言って、葛飾村の小松菜や練馬の大根などを育てる近郊の農民が江戸の下肥を買っていた。下肥は金肥と言われた。練馬の農民はいくつもの桶や干した大根を大八車に積んで、江戸市中で契約している武家屋敷や長屋の下肥を貰いに行った。下肥の代価として、空になった厠の掃除をして、持って来た大根を沢庵に漬け込んでやる。下肥はそれだけの価値があった。沢庵を漬けてもらうのは長屋の大家さんだから、落語では、店子の八っつあんが、「長屋の厠はもう使ってやらねえぞ。人の造ったものを勝手に売りやがって!」と大家に毒づく。
江戸の町では、河川や掘割は本来の軍事的な用途だけでなく、物資運搬のための水路として重要だったから、勝手にゴミを捨てられては困る。長屋や町内には何軒かが共同で使う「掃き溜め」が作られ、そこで集めたゴミを深川の湿地帯の埋め立てに用いるシステムができた。業者が請け負って、ゴミを永代島の集積所に舟で運んだ。しかし、江戸庶民はあまりゴミを出さなかったという。なんでも捨てずにリユースやリサイクルをしていたためだ。藁は重宝な素材で、筵や草鞋や縄など使い道が多い。藁を燃やした灰も商品になった。カリウムを含む灰は、肥料や製紙、製糸、染色など用途が多く、「灰買い」という商人が町で灰を集めて回った。壊れたり破れたりした傘や提灯も、張り直したり修繕する職人が集めた。金属や板切れも回収業者がいた。布切れも反古の紙も回収された。モノが少ない時代にはゴミにも商品価値があって、それ相応の値が付いた。人々は、不要になったものが、とことん使い回されて最終的に処分されるまでの過程を知っていた。
廃棄物や汚物をきちんと処理していた国は少ないようだ。途上国ではいまでもトイレのない住居は多いし、中世ヨーロッパの都市ではゴミや汚物を窓から通りに投げ捨てていた。産業革命初期の労働者の居住地は悲惨な状況だった。河川は工場からの廃棄物で汚染され、排水溝を敷設する費用のない労働者の住居から出た残飯の臓物や汚物はすべて通りに捨てられた。マンチェスターの町は「地獄の入り口」と言われたほど汚れ、汚臭に満ちていた。
高度成長期の初期までの日本には、家庭を回ってゴミを買う人々がいた。都会でもゴミは焚火で燃やすこともあった。都市化が進んで、失火や延焼の危険から焚火は禁止になった。ゴミが増えて、お金を払って処分する時代になった。
現代のゴミの行く末を知っている者は少ない。私たちの目の前から消えた廃棄物はどうなるのだろうか。都市で排出されるゴミの量が、江戸時代の比でないことは明らかだ。自治体や廃品回収業者が集めることは知っているが、その先どうなるかを殆ど気にせずに都市は活動している。自宅のゴミの量、催し物で出るゴミ袋の山、コンビニの外に置いてあるダストボックスの大きさ、ゴミ収集日に積まれているゴミ袋、どれを見ても、それが一つの町や都市全体になったら凄い量になるということは容易に想像がつく。先進国では、ゴミの収集・回収システムにより、ゴミは決められたとおりに捨てれば、そのまま忘れてしまう。税金を払い、料金を払えば、それ以上の関知はしなくていい。現代は、「見たくないものを見なくていい」時代になった。私たちの目の前から消えたゴミは、分業によりアウトソーシングされ、多くがオフショアされている。ゴミを受け入れる国があるのだ。
コンテナ船はゴミを積んで大洋を移動している。大型コンテナに満載されたプラスチック廃棄物や化学繊維の衣料品などの廃棄物のなかには、余剰生産で新品のまま廃棄されるものもある。インドやカンボジアやチリの内陸では、海外から運ばれて最終的にここに辿り着いたゴミの山が、化学反応を起こして住民の健康被害や土壌汚染を引き起こしている。そんな有毒な大気が漂うゴミの山に、廃棄物の中から再利用できそうなものを拾い集めるために住民たちが集まって来る。捨てられた事務用機器や電化製品や工業製品は宝の山で、分解して再利用できる部品を取り出せば引き取ってくれる業者がいる。
ゴミや商品を運ぶコンテナ船もタンカーも漁船もクルーザーも、いずれは廃船になる。南シナ海やインド洋の海岸に「船の墓場」がある。バングラデシュやパキスタン、インド、中国南部の沿岸地域の何キロもの長い浜辺には解体を待つ数百数千という廃船が引き上げられて並んでいる場所がある。インターネットで検索すれば、廃船の屠殺場の風景がいくらでも出て来る。先進国の造船所の巨大ドックで重機を使って解体するはずの船舶が、いつの間にか途上国の浜辺に運ばれている。先進国での解体には、有害物質の除去、安全管理基準、人件費など、多くの厳格な法規制によって、高額な経費がかかる。しかし、途上国の海岸に持っていけば、地元の労働者たちが群れを成して集まって、手仕事で解体してしまうのだ。貧困地帯の多くの労働者たちは、日当1ドル、2ドルという仕事を求めている。解体された部品や鉄板は地元の業者のいい収入源であるが、有毒物質や危険物が多い解体作業を、防護服もなく裸足と素手で行う労働者にとっては危険な仕事である。怪我や死亡事故があっても保障されない。船舶の登記も解体も、法規制の届かないどこかにオフショアされている。
ゴミの最終処分場になることは、国家の選択である。先進国から持ち込まれる廃棄物に依存するようになってしまっているのだ。Waste Pickerと言われる、ゴミの中から有価物を選り分けて処理する業者は、途上国を中心に150万人とも200万人とも言われ、一大産業になっている。大量の廃棄物になった製品を「過剰生産」したのも、途上国の労働者たちである。生産段階で先進国からオフショアされた労働力の生んだ製品が、廃棄されたあとの処分段階で再びオフショアされる。当然、消費国になった先進国では自国の労働力は不要になって、賃金は上がらない。移民労働者が流入すれば、彼らが安い労働力で仕事を奪っていく。
いま、急速に増えているのがデジタル廃棄物である。デジタル機器の解体は、環境と衛生に深刻な影響を及ぼす。中国の南シナ海沿岸にある貴嶼には世界からデジタル廃棄物が集まって来る。先進国ではリサイクルは環境によいことだと認められているから、業者は補助金や税の控除で優遇される。しかも、それらは途上国に売り払われることで彼らの収益になる。デジタル廃棄物の輸出が違法になっている国は多いが、どういうわけか監視をすり抜けて受入国に辿り着く。バーゼル条約に加入していないアメリカは、堂々と廃棄物を輸出している。
金属・アルミ・プラスティック・レアアース・配線・ケーブル・ガラスなど多様な素材からできているデジタル機器には、特殊で危険な物質も含まれている。貴嶼の労働者たちは古いコンピュータやプリンタや携帯電話などを分解して、部品を取り出し、ケーブルを切断し、回路基板から希少金属や希土類を取り出すために、化学処理をしたり熱を加えたりして作業をする。そこで発生する有毒ガスを吸い込み、健康に害があっても、平均を遥かに上回る賃金が労働者を引き寄せる。
デジタル廃棄物の増加も、ムーアの法則に従う。技術革新のスピードが製品に反映することで、まだ十分に使えるはずの製品が旧式になって使えなくなる。ユーザーが望んでいるわけでもないのに、新機種にしかインストールできないアプリを搭載した新製品が発売される。ユーザーは数年で買い替えを強いられ、そのたびに大量の廃棄物が生じる。新車でも住宅でも家電でも、新機種やモデルチェンジで消費者に不必要な買い替え需要を促したが、デジタル機器の変化は恐ろしく早い。
既に100年も前にヴェルナー・ゾンバルトが「近代経済人が、意味無く生産し、そして常に増産に励むこと」や「とりわけ技術上の完成に対する子供じみた彼らの喜び」「推進力として働く『進歩』に対する情熱」を揶揄しているのが、そのまま当てはまる。ゾンバルトは「『進歩』という無意味な理念」は、近代経済人の精神を「目的に対する手段の昇格」に変化させたという。そして、「ブルジョワの精神は人類の運命に対し、完全に無関心」になっていて、彼らにとって「生産は行われなければならない。たとえ、そのために人間が滅びようとも」と皮肉っている(『ブルジョワ 近代経済人の精神史』1913)。
人類が農業を始めたときから、技術革新は常に貧富の格差を増大させるように働いているのだという(『技術革新と不平等の1000年史』2023)。農業そのものが技術革新である。そして、農に関わることだけでも、多くの技術が改良され、時には飛躍的なイノベーションを生み出して来た。技術革新は労働力の不足を補ったが、裏を返せば、それは労働力の削減にも利用できるということである。テクノロジーを支配する者は、新しい技術を賃金の高い熟練労働者の代わりに使うことで経費を削減することができるのだ。仕事を失った熟練労働者は、非熟練労働者と同列に扱われ、支配者と非熟練労働者の二極化が進む。どの時代でも(少数の例外を除いて)新しい技術で増加した利益は、適正に分配されずに支配層が独占した。中世の農業改革も、近代の産業革命も、技術革新によって生産性が上がった結果、支配層と労働者の格差が広がったという。生産性の高さは、労働者の収入に結びつかなかった。
新技術によって新たな産業を生み出し、関連産業に雇用機会が波及するものになるのかは、開発者や出資者の意図にかかっている。新技術の生み出す利益が公益に用いられるか独占されるかである。例えば、AIが公益に寄与するのか、利益の独占に進むのか、それによって全く違う世界像が描かれる。利益の独占が進むとき、AIが代替するのは、最も経費のかかる現代の熟練労働者層、即ち稼ぎのいいスペシャリストやエキスパートといわれる人々の仕事になるだろう。生産労働力のアービトラージは植民地や途上国という地理上の場所へオフショアされたが、デジタル社会の知的労働はアルゴリズムが担う。
国家の規制やルールを嫌う新自由主義で成長したテック産業が、今後、自らのテクノロジーの生み出す利益を適正に分配するだろうか。どんな政治体制になっても、情報をお金に変えるAIを手放すことはないだろう。AIのスケールの拡大競争には膨大な資金とエネルギーが必要だ。成果を分配するよりも、占有が招く監視社会の兆候を感じている人は多い。
高度化する技術はいままで以上に厄介な廃棄物を増やす。ゾンバルトの時代でも「常にいっそう短縮される時間的間隔をおいて、技術革新が続けざまに出現する」と言われ、「創造」によって「破壊」される旧式の製品が次々に廃棄物となっていた。グローバル化によって、生産と消費と廃棄のスピードが世界規模で加速され、アウトソーシングとオフショアリングと移民の非熟練労働者によって、経済格差も世界規模で拡大した。廃棄物処理のオフショアリングは、自国内では処理しきれない廃棄物の量が増え続けることによって加速する。廃棄物はデジタル空間では引き受けてくれない。先進国の消費者からは見えないところで大量なオフショアリングが行われていて、プラスティック・ストローを禁止するくらいでは、どうにもならない話なのだ。
『オフショア化する世界—人・モノ・金が逃げ込む「闇の空間」とは何か?』ジョン・アーリ著 須藤廣&濱野健 監訳/ 明石書店 2018
『技術革新と不平等の1000年史』ダロン・アセモグル&サイモン・ジョンソン著 鬼澤忍&塩原通緒 訳/ 早川書房 2023
『ブルジョワ 近代経済人の精神史』ヴェルナー・ゾンバルト著 金森誠也訳/ 講談社学術文庫 2016
『大江戸えねるぎー事情』石川英輔著/ 講談社文庫 1993
『百万都市 江戸の生活』北原進著/ 角川ソフィア文庫 2014
〈お知らせ1〉
3/30日(日)に沖縄シンポジウムを開催!
戦後80年、日本が見て見ぬふりを続ける戦後の矛盾は、
沖縄の地に濃縮され、露出しています。
本誌編集委員が沖縄で「戦後の矛盾」、そして「対米独立の道」を徹底議論します。
皆様ぜひご参集ください!
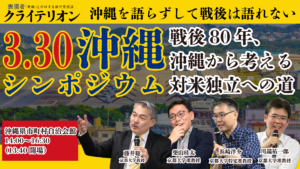
会費:一般、3000円、塾生・サポーター:2000円
懇親会:17:00〜19:30(5000円)
登壇者:藤井聡(京都大学教授)、柴山桂太(京都大学准教授)、浜崎洋介(京都大学特定准教授)、川端祐一郎(京都大学准教授)、藤原昌樹(沖縄国際大学・沖縄大学非常勤講師)
https://the-criterion.jp/symposium/250330okinawa/
〈お知らせ2〉
2025年度(第7期)表現者塾の塾生募集を開始しました!
来年度も豪華なラインナップとなっております!
◯期間:2025年4月〜2026年3月(第7期)
◯毎月第2土曜日 17時から19時
◯場所:新宿駅から徒歩圏内
◯動画会員(ライブ配信、アーカイブ)も募集
多様で幅広い分野から講師を迎え、時に抽象度の高い議論を交わしながら、保守思想の根幹を探っていきます。
知識は不問、どなたでもご参加いただけます!
現代社会に生きるためのクライテリオン(規準)を探求する仲間になっていただければ幸いです。
2025年度「表現者塾」塾生募集!
執筆者 :
CATEGORY :
NEW

2026.01.01
NEW
.png)
2025.12.31
NEW

2025.12.30
NEW

2025.12.28

2025.12.26

2025.12.25

2025.12.25

2025.12.30

2024.08.11

2025.12.26

2025.12.28
.png)
2025.12.31

2025.12.19

2018.03.02
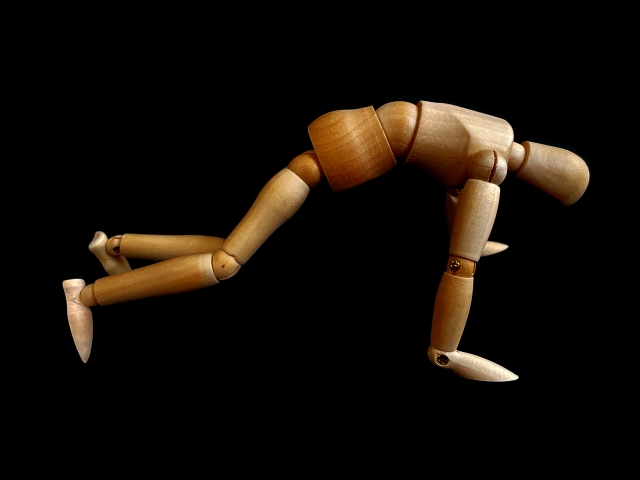
2025.07.29

2026.01.01