前回まで、頼るべきものを奪われ、根を失ってしまった孤独な人間のなかに巣食う「ニヒリズム」の問題について、オウム真理教や少年Aの事例を引きながら述べておきました。
が、この「ニヒリズム」の問題は、今、現在において猖獗を極めているとはいえ、しかし、決して新しい話ではありません。それは、まさに「近代」はじまって以来の問題です。
たとえば、少年Aの「理由なき殺人」――あるいは、「理由を虚構しなければならない殺人」――という問題は、すでにドストエフスキーによって徹底的に描かれていました。それを描いたのが、ドストエフスキーの『罪と罰』(1866年)です。
家庭教師の口を失い、大学に通うのも辞めてしまった極貧の大学生ラスコーリニコフは(その名の由来は、ロシア語のラスコーリニク――つまり、分離派教徒=異端的な考えの持ち主という意味です)、ある日、郷里の母からの手紙で、お金の工面の為に、金回りのよい弁護士と妹が結婚しなければならなくなったことを知ります。そして、ラスコーリニコフは、家族と、そして自分自身を救うために、ついに、ある計画を実行に移そうとします。
その計画というのは、高利貸しの老婆を殺すというものでした。ラスコーリニコフは、ナポレオンがそうであったように、凡人を殺しても、それが人類の進歩と発展に役立つなら、それは善になり得るという考えに憑りつかれていたのです。そして、その考えを実行に移し、ついに、老婆を殺してしまうのです……が、そこで偶然に遭遇した、老婆の妹=知恵遅れのリザベータまで殺してしまったことから、次第に彼の計画に狂いが生じはじめます。
心理的に動揺したラスコーリニコフは、その後に、予審判事のポリフィーリイの追及を受けながら次第に追い詰められていきます。が、そのなかで出会った娼婦ソーニャとの関係を通じて、自首に向かう長い苦しい道を歩みはじめることになるのでした。
ところで、この小説を読む上で見逃せないのは、故郷喪失者=ラスコーリニコフの近代的孤独です。田舎から人工都市ペテルブルクに出てきた一人の青年知識人であるラスコーリニコフには頼るべきものがない。いや、もし、かろうじて頼れるものがあるのだとしたら、それは彼自身の「意識」しかない。そして、そんな孤独な「意識」が編み出したのが、この世を進歩させる天才には、凡人たちを踏み超える権利があるという「超人理論」でした。彼は、それによって動き、また高利貸しの老婆と、その妹を殺してしまうのでした。
が、注意したいのは、不意に殺してしまったリザベータの「存在」が、次第にラスコーリニコフの「理論」を動揺させていくことです。正義の遂行(革命)に犠牲と混乱はつきものだという「理論」は、しかし弱く小さいリザベータの「存在」に勝てないのです。
おそらく、ここには、若い頃のドストエフスキーの苦い経験が反映しています。『貧しき人々』(1846年)を書いて、一躍ロシア文壇の寵児になったドストエフスキーは、しかし、まもなく社会主義の秘密結社に関係した疑いで逮捕され、銃殺刑を宣告されてしまいます(ペトラシェフスキー事件)。が、刑の執行直前に恩赦が下されたドストエフスキーは、その後にシベリアに送られ、そこで4年の懲役生活を過ごすことになるのでした。
そして、そこでの経験が彼の肉体に刻みこんだもの、それこそ「理論」による社会改造(人々の意識改革)の不可能であり、また、その「理論」そのものが、人々の孤独な「ニヒリズム」からもたらされているのだという確信でした。ロシアの「見捨てられた人々」(殺人犯や政治犯)と共に生きることでドストエフスキーが知ったのは、人間の「存在」が、「理論」によってではなく、「生活」によってこそ支えられているのだということ、そして、その「生活」によって齎される感情、それこそが「愛情」なのだということでした。
実際、リザベータの殺害によって動揺しはじたラスコーリニコフの「意識」が決定的に破綻してしまうのは、予審判事による「理論」的な追及によってではなく、逆に「見捨てられた人間」である娼婦ソーニャの素直な「愛情」に触れることによってでした。
ソーニャは、多くのロシア民衆(土着民=ナロード)がそうであるように、ロシア正教を盲目的に信じる無知な女性として描かれています。が、その彼女だけがラスコーリニコフの「不幸」を直感し、それを受け止め、彼を抱きしめることができるのです。
果たして、予審判事に追い詰められたラスコーリニコフは、「意識」の上では、未だ自らの「罪と罰」を認められないまま、しかし、ソーニャの後押しを受け、高利貸しの老婆とその妹の殺人を自白し、シベリア流刑を自ら引き受けることになるのでした。
けれども、この小説のクライマックスはそこではありません。最も重要なのは、この「意識」の上では、未だ自らの「罪と罰」を引き受けることのできないラスコーリニコフが、しかし、長い時間をかけて、まさに「無意識」に身を任せるようにして次第に回心していったことです。そして、そこでラスコーリニコフの「無意識」に触れ続けることのできた人間、それこそが、無知で小さいソーニャだったという事実です。
「いっしょに苦しみましょう」という一言を守るために、ソーニャは、流刑となったラスコーリニコフを追ってシベリアに向かいます。はじめ、その「愛情」の重さに耐えられないラスコーリニコフは、そんなソーニャを拒みます。が、彼女との関係を積み重ねていく日々のなかで、次第に、その固く結んだ心の紐がほどけていきます。長く苦しい時間を経て、ようやくラスコーリニコフはソーニャへの「愛」を確信しはじめるのです。
そのときの「回心」の様子を、ドストエフスキーは次のように書いていました。
「この夜の彼は、何につけ、ゆっくりと落ちついて考え、何事かに考えを集中することができなかった。いや、いまの彼には、何一つ意識的に解決することだってできなかっただろう。彼はただ感じただけだった。思弁の代わりに生活が登場したのだ。意識のなかでも、まったく別の何かが作り上げられなければならないはずだった。
彼の枕の下には福音書があった。彼は無意識にそれを手にした。この本は彼女のだった。彼女がラザロの復活を彼に読んでくれたあの福音書だった。」(江川卓訳)
ドストエフスキーが生きた19世紀後半のロシアは、急激な近代化と、それに伴う人口増加と不景気のなかで、都市(近代)と地方(前近代)とが引き裂かれ、激しい価値の混乱に見舞われていました。それは、ロシア人が「神」を見失い始めた時代だったのです。
ドストエフスキー自身は、ソーニャ側(ロシアの大地とロシア正教)の人間ではなく、おそらく、ラスコーリニコフ側(近代都市と個人主義)の人間だったはずです。が、少なくとも、ラスコーリニコフの「ニヒリズム」は、ソーニャの「愛」なくしては癒されなかったのです。個人の「意識」は、大地に「根をもつこと」(シモーヌ・ヴェイユ)なくしては癒されず、その「大地」に根付いた「生活」は、現世的打算を超えた「愛情」なくしては営まれない。それは、ドストエフスキーの紆余曲折に満ちた人生そのものが教えた思想でした。
この物語が、21世紀の私たちと無縁でないことの意味も、おそらくここにあります。それは、私たちに「ニヒリズム」の乗り越え方を指し示し続けています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メルマガのバックナンバーはこちらで閲覧頂けます。
https://the-criterion.jp/category/mail-magazine/
雑誌『表現者criterion』の定期購読はこちらから。
https://the-criterion.jp/subscription/
その他『表現者criterion』関連の情報は、下記サイトにて。
https://the-criterion.jp
ご感想&質問&お問合せ(『表現者クライテリオン』編集部)
info@the-criterion.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
執筆者 :
CATEGORY :
NEW

2024.07.26
NEW

2024.07.25

2024.07.19

2024.07.18
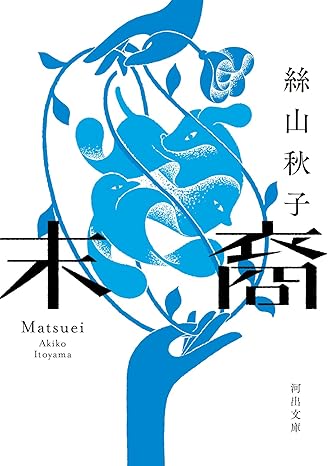
2024.07.16

2024.07.13

2024.07.19

2024.07.13

2024.07.25

2024.07.18

2024.07.10

2024.07.26

2024.07.11

2018.07.25

2024.07.12

2023.06.07