私たちは日本語で会話したり、読み書きしたりします。そうした言葉は空気のように存在するので、遠い昔に生まれ、徐々に姿を変えながら現在に引き継がれてきた「自然なもの」という印象を受けがちです。
しかし、現在使われている日本語(この文章もそうです)は、極めて人為的に「開発」されたものです。明治維新後、国民国家を急いで建設するため、言語学者や小説家、ジャーナリストなどが編み出し、学校やメディアを通じて広めたものなのです。
その事実は、明治から大正にかけて新聞に掲載された記事と、同じ紙面に連載された連載小説の変遷をたどるとよく分かります。今回は朝日新聞を例に、現在の日本語が形作られていった過程を振り返ってみましょう。
朝日新聞が大阪で創刊されたのは1879(明治12)年1月25日のことです。当時の新聞は漢文調でエリート向けの「大(おお)新聞」と、漢字にルビを振って読みやすくした大衆向けの「小(こ)新聞」に分かれていました。朝日は後者に属します。
創刊号を見ると、現在の新聞とまるで違っていたことが分かります。1面に載ったストレートニュース(雑報)はこんな感じです。
○大和国(やまとのくに)奈良東大寺(ならとうだいじ)の博物館(はくぶつくわん)は例(れい)の通(どう)り来(きた)る三月中旬(なかごろ)より開場になり本年(ことし)は該地(そのち)正蔵院(せいぞうゐん)の宝蔵(ほうぞう)を開(ひら)かれ珍器出品(ちんきしゆつぴん)なるに付(つき)当今御調(とうこんおしらべ)べ中(ちう)なりと (カッコはふりがな。表記を一部現代風に変えた。以下同)
現在は毎年秋に開かれている「正倉院展」に関する記事だと分かります。興味深いのは見出しが付いていないことです。記事の内容を一目で確認できる「見出し」という概念が、当時はまだ一般的ではなかったのです。ないと言えば句読点もありません。古文のように1文が長いので、現代人には読みにくく感じます。それでも当時の庶民は、江戸時代の戯作などと比べ読みやすいと感じたことでしょう。
一般市民が使いこなせる表記法や文体が求められる中、話し言葉と書き言葉を近づけようという言文一致運動が始まります。その嚆矢とされるのが、1887(明治20)年に発表された二葉亭四迷の「浮雲」です。しかし、会話文は「言文一致」で読みやすいものの、それ以外の「地の文」はまだ新聞記事の文体とあまり変わりません。
<会話文>
「イヤあれは指図じやアない、注意サ」
「フム乙う山口を弁護するネ、やつぱり同病相憐むのか、アハアハアハ」
<地の文>
千早振る神無月ももはや跡二日の余波となツた二十八日の午後三時頃に、神田見附の内より、塗渡蟻あり、散る蜘蛛の子とうようよぞよぞよ沸出て来るのは、孰れも顋を気にし給方々。
この翌年、東京朝日新聞が創刊されました。日露戦争が近づく中、ロシア語ができた二葉亭四迷は1904(明治37年)に大阪朝日に入り、後に東京朝日に移籍します。そうした中、1907(明治40)年に鳴り物入りで入社したのが、すでに売れっ子作家になっていた夏目漱石でした。
漱石の連載第1作「虞美人草」はこんな風に始まります。
「随分遠いね。元来どこから登るのだ」
と一人が手巾(ハンケチ)で額を拭きながら立ち留まつた。
ほぼ、現代小説の文体になっています。「吾輩は猫である」(1905年)や「坊っちゃん」(1906年)の執筆を通じ、漱石流言文一致体の原型はできていたと言えるでしょう。ただ、地の文を読むと、ところどころ新聞の雑報に近い文体が残っています。
反を打つた中折れの茶の廂の下から、深き眉を動かしながら、見上げる頭の上には、微茫なる春の空の、底までも藍を漂わして、吹けば揺くかと怪しまるるほど柔らかき中に屹然として、どうする気かと云わぬばかりに叡山が聳えてゐる。
漢文表現なども駆使して「凝った」結果のようにも見えますが、もしかすると新聞連載ということで、あえて記事風の文体を取り入れたのかもしれません。しかし、結果として現代人にはやや読みづらい文章になっています。
実はこの小説の次に連載されたのが、二葉亭四迷の「平凡」でした。冒頭はこんな風に始まります。
私は今年三十九になる。人世(じんせい)五十が通相場なら、まだ今日明日穴へ入らうとも思わぬが、しかし未来は長いやうでも短いものだ。過去(すぎさ)つて了(しま)へば実に呆気ない。
漢字や仮名遣いを除けば、ほぼ現代の私小説の文体だと言っていいでしょう。当時の新聞読者がどう感じたかは分かりませんが、細かい心理描写が可能な独白調の文体は新鮮だったに違いありません。
この作品に触発されたのか、続けて連載された漱石の「三四郎」は「虞美人草」と比べ明らかに洗練されています。

<「三四郎」の連載第1回が載った明治41年9月1日付の東京朝日新聞(コピー)>
うとうととして目がさめると女はいつのまにか、隣のじいさんと話を始めてゐる。このじいさんはたしかに前の前の駅から乗つたいなか者である。発車まぎわに頓狂な声を出して駆け込んで来て、いきなり肌をぬいだと思つたら背中にお灸のあとが一杯あつたので、三四郎の記憶に残つてゐる。
ちなみに、「三四郎」の第一回が掲載された日には、こんな記事が載っています。
清国国会開設期限決定
頃日地方の諮議局即ち地方議会開設を命じたる上諭の旨に依れば、清国の国会開設は猶多年の後に推し送らる可き模様に見えたるが、其後未だ幾ばくならざるに、今後九箇年を期していよいよ憲法を発布し中央議会を開く可き旨を約したる上諭、去二十七日を以て発せられたるは(中略)一頃勝を制して今度の上諭あるに至れり、と見て多分間違ひなかる可し。
見出しが付いたほか、小説と同じように句読点があります。しかし、1文が277字もある上、文語調で「三四郎」と同じ時代の文章とは思えないほどです。句読点も別の記事では「、」だけで「。」が使われていないものがあるなど統一されていません。新しい文体を編み出す試みは小説が先行し、そこで成功を収めたものが記事にも取り入れられていったと考えられます。
これが「こころ」(連載時の題名は「心 先生の遺書」)が掲載された1914(大正3)年にもなると、内面描写が完璧にできる文体が完成します。
私は其人を常に先生と呼んでゐた。だから此処でもただ先生と書く丈で本名は打ち明けない。是は世間を憚かる遠慮といふよりも、其方が私に取つて自然だからである。
連載第1回の横に載った記事も、小説ほどではありませんが、ほぼ言文一致になっています。
一条家に縁故ある函谷鉾の稚児 其名は嘉多丸
京都四条室町東へ入る函谷鉾町の町共有の宝物となつて年々祇園会の函谷鉾に祀る木稚児が一条家に縁故あるのみか皇太后陛下に浅からぬ御縁のあるといふ事を耳にし同町の古老を訪ひ詳しく聞いて見た(以下略)
ここまでくると、現在私たちが読み書きしている文体ができあがり、記事にも取り入れられていることが分かります。
実は二葉亭四迷が入社する前年、杉村楚人冠という記者が朝日新聞に入っています。彼は漱石と仲が良く、しばしば文章表現についても意見交換をしました。新聞記事は文学に近づかねばならないと考えていた楚人冠は、同時代の作家や欧米のルポルタージュの技法などを研究し、報道文に取り入れていったのです。
楚人冠は漱石の「心」が掲載された翌年、本格的なジャーナリズムの入門書である「最近新聞紙学」を出版。慶應義塾大学や母校の中央大学で教壇に立ち、記者養成にも乗り出します。1921〜35年には文部省の臨時国語委員も務めており、彼自身の紀行文も国語教科書に採用されています(ちなみに文部省唱歌の「牧場の朝」も彼の作詞です)。
もちろん、ここで挙げた作家や記者だけが現代日本語をつくったわけではありません。ただ、当時の最新メディアだった新聞が文章表現の実験場となり、その普及にも大きな役割を果たしたとは言えるでしょう。共通の言葉が地域や階級を超えて使われるようになることで国民意識が育ち、国家事業の基礎となったのです。
そうした試みが始まって約150年。現在の新聞は新しい表現を生み出す力を失っているように見えます。同時に、社会に対話を生み出すインフラというより、分断を深める装置になってしまっているのではないかという懸念も感じざるを得ません。
参考文献
「楚人冠の生涯と白馬城」「楚人冠と漱石」「新聞記者・楚人冠の足跡」(いずれも我孫子市教育委員会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メルマガのバックナンバーはこちらで閲覧頂けます。
https://the-criterion.jp/category/mail-magazine/
雑誌『表現者criterion』の定期購読はこちらから。
https://the-criterion.jp/subscription/
その他『表現者criterion』関連の情報は、下記サイトにて。
https://the-criterion.jp
ご感想&質問&お問合せ(『表現者クライテリオン』編集部)
info@the-criterion.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
執筆者 :
CATEGORY :
NEW

2026.02.16
NEW
.png)
2026.02.16
NEW
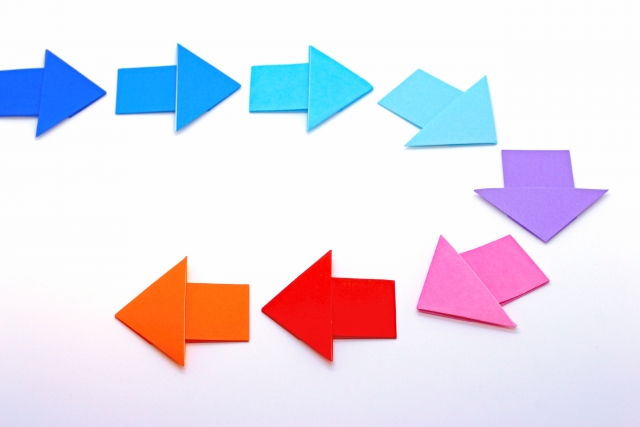
2026.02.16
NEW

2026.02.16
NEW

2026.02.13
NEW

2026.02.12

2026.02.12

2026.02.11

2026.02.13

2026.02.09

2024.08.11

2026.02.16

2022.10.25

2026.01.20

2018.03.02

2023.10.12