本日は6月14日発売、『表現者クライテリオン2024年7月号 [特集]自民党は保守政党なのか?』より、巻頭コラム「鳥兜」をお送りいたします。
本書のご予約はこちらから!
よりお得な年間購読(クライテリオン・サポーターズ)のお申し込みはこちらから!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
それほど広く浸透しているわけではないが、「新異教主義」(ネオ・ペーガニズム)という言葉がある。日本語では「復興異教主義」と訳されることも多く、英語では「モダン・ペーガニズム」(現代の異教)と呼んでいる場合もある。「異教」とはキリスト教化される以前の土着的な信仰のことで、古代ゲルマン、ギリシア、北欧、スラブなどヨーロッパ周辺の神話や儀式を指す場合が多いが、文脈によってはヒンドゥー教や神道なども含まれる。「新異教主義」は、異教に共通している多神教的、アニミズム的、自然崇拝的な世界観を、現代に復活させようという運動である。
たとえばロシアにワグネルという民間軍事会社があり、一年ほど前に創設者のプリゴジンが暗殺されて話題になったが、ワグネルの兵士の間では「ロドノヴァリー」と呼ばれる、スラブ神話に基づく新異教運動が流行っているらしい。ただし多神教的であるためか、崇拝の対象はスラブの神に限られない。彼らは自身のタトゥーや軍用車両のペイントに、古代ゲルマンのルーン文字を好んで用いているが、これはこの文字にゲルマン神話を想起させる秘教的な力があるからだそうだ。また、捕虜を拷問したり脱走兵を処刑したりする際にしばしばハンマーが用いられており、二〇二二年にはワグネルをテロ組織に指定した欧州議会に対し、プリゴジンが血まみれのハンマーを送りつけたが、これは北欧神話の最高神トールが持つ「ミョルニル」という武器を模したものだと言われている。
一見、日本人にはあまり関係がない動向のように思われるが、興味深いのは、極右の政治運動が新異教主義的な想像力と結びついていることである。欧米のネオナチのグループの中には、行き過ぎたグローバル化やリベラル化に対抗して移民排斥や白人至上主義などの政治イデオロギーを唱える一方で、異教的な信仰や儀式を好む人々がいる。ことさら宗教的なメッセージを発していない場合であっても、黒ずくめのユニフォームを着て鉤十字その他のシンボルが描かれた旗を振り回す姿は異様で、そこに呪術的で古代宗教的な趣向を感じ取る人は多いのではないか。
日本でも、時代の主流となっている価値観に順応できない人々や、その転覆を志す人々が、ラディカルな政治的主張とともに前近代的なスピリチュアリズムを持ち出すことが稀にある。福島第一原発の事故からしばらくの間、霞が関の官庁街などで、「呪殺祈祷僧団」という僧侶の団体が、原発推進派に呪いをかけるとして祈祷を行っていた。これは一九七〇年代に公害病が問題化した際にも見られたものである。アニミズムとも極右とも異なるであろうが、現代文明の病理を討つという名目で文明化以前の宗教的感性が呼び起こされるという点では、欧米の新異教運動と似ていなくもない。
最近で言えば、食品添加物やワクチンの危険性を熱心に訴え、有機農法を強く推奨している参政党の政策理念や運動形態が、欧米の新異教主義と比較されるべきものの一つかも知れない。参政党は「カルト的」と批判されることが多いが、その形容は恐らく正確である。カルトという言葉には、「狂信的」というネガティブな意味だけでなく、「異教的」という含意も込められている。参政党の支持者が唱える自然主義的な信念には、過剰なスピリチュアリズムが感じられる場合が少なくない。しかしこれは単なる狂信というより、社会システムが行き詰まり動揺する時代には、民族心理の古層に秘められた文明化以前の感性が不意に甦るということなのではないか。だとすれば、穏健な保守政治を志す人々は文明の側につくほかないとは言え、この動向そのものを軽くは見ないほうがよいだろう。
(『表現者クライテリオン2024年7月号)巻頭コラム「鳥兜」より)

雑誌と書籍の年間購読を通じて、『表現者クライテリオン』をご支援ください!
https://the-criterion.jp/lp/r6supporters/
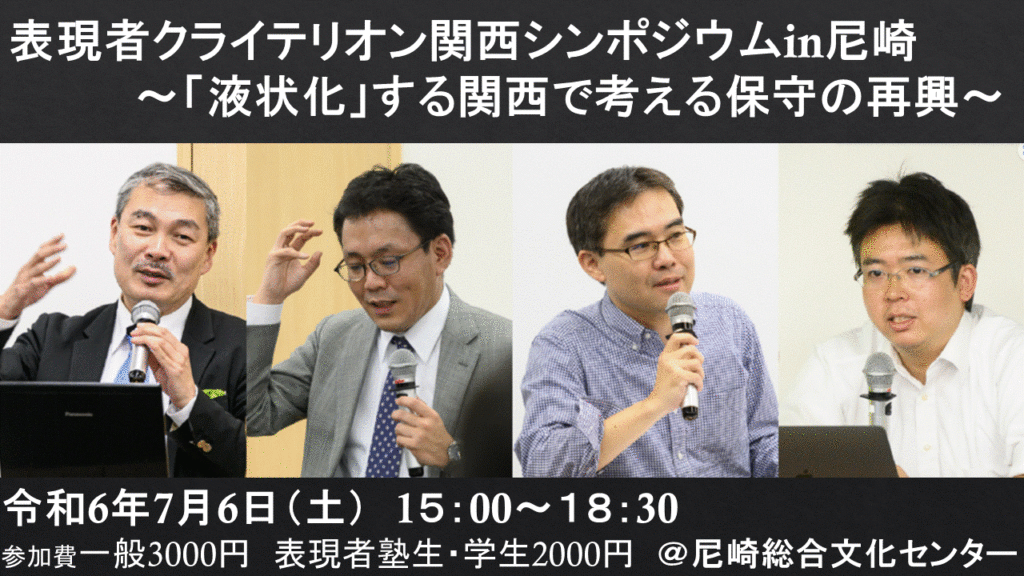
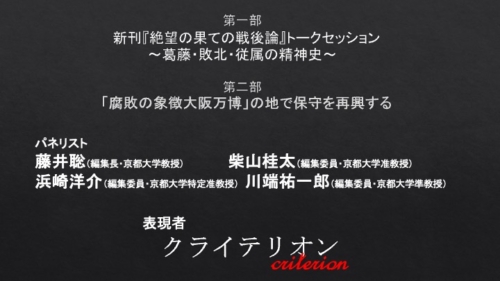
3年ぶりに関西でシンポジウムを開催!
「革新」の標語が力を強める関西において、本当の保守主義をどのように実践していくべきか、『表現者クライテリオン』編集委員が徹底議論!
詳細はこちらから

クライテリオン誌上で行われた「座談会 対米従属文学論」がクライテリオン叢書第4弾として待望の書籍化!
第二部に浜崎洋介先生の戦後文学批評の決定版とも言える論考「観念的な、あまりに観念的なーー戦後批評の「弱さ」について」を収録!
※本体価格2,600円ですが、6月から始まるクライテリオン・サポーターズの特典に加えることが決定しました。
サポーターズ加入がますますお得になりましたので、ぜひご検討ください。
執筆者 :
NEW

2026.02.13
NEW

2026.02.12
NEW

2026.02.11
NEW

2026.02.09
NEW

2026.02.07
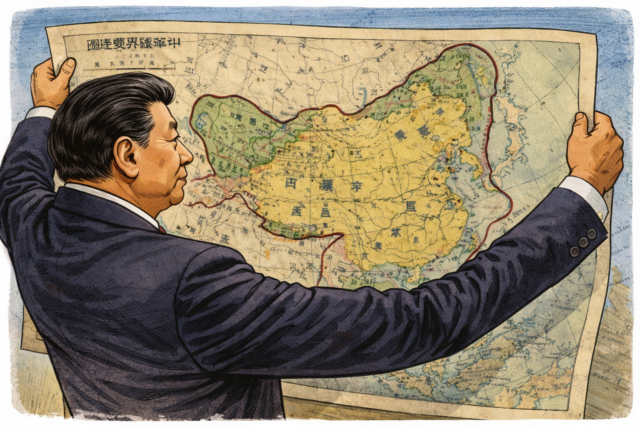
2026.02.06

2026.02.09
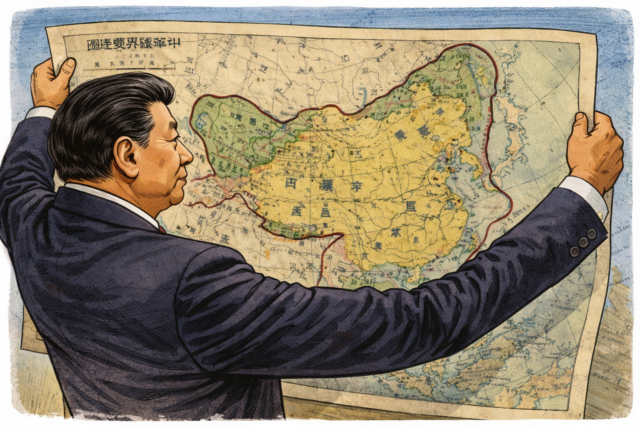
2026.02.06

2026.02.07

2026.02.12

2026.02.11

2026.02.05

2024.08.11

2026.01.20

2026.01.18

2018.09.06