先日ある映画を観ました。2017年に製作され、現在も日本で公開されているスペインとアルゼンチンの合作映画 El Último Traje(スペイン語による原題、英語ではThe Last suit )です。
映画は、アルゼンチンのブエノスアイレスに住む88歳の仕立て屋ブルスティン・アブラハムが、自宅のソファーに腰かけ孫たちに囲まれて写真撮影しようとしているシーンからはじまります。翌日には老人ホームに入居することが決まっているアブラハムが自宅で過ごす最後の日。娘や孫たちが集まって家族写真を撮影しようとしているのです。
それを聞くと仲睦まじい家族の微笑ましいワンシーンを思い浮かべるかもしれません。ところが、この老人は浮かない表情です。長年住み慣れた仕立て屋兼自宅を娘たちが売り払うと決め、どうやら翌朝アブラハムは老人施設に入居させられてしまうようなのです。アブラハムが「この家をくれ」と言っても、娘たちは聞く耳をもってくれません。
苛立ちを隠せないアブラハムに、お手伝いのパウリーナが尋ねます。「このスーツ、どうします?」と。パウリーナが手に持っているのは、アブラハムの仕立て屋に残されたブルーのスーツです。アブラハムは、思い出したかのように、娘や孫たちを自宅から追い払います。そして、一人になったその晩、航空チケットを購入してポーランドに向かうことを決心します。「さらば、我が家」と言って家の鍵を玄関先に放り投げ、最後に残されたスーツを携え、アブラハムは「家出」するのです。
さて、この映画には『家(うち)へ帰ろう』という邦題が付けられています。アブラハムが長年住み慣れた「家を出ていく」ことを考えると、『家へ帰ろう』というタイトルはなんとも不似合いです。『最後のスーツ』という原題の方がよっぽどわかりやすいとも言えます。
このような邦題が付けられた真意はわかりません。アブラハムが向かったポーランドのウッチという街は、第二次世界大戦の際にユダヤ人という理由でドイツ軍に連れ去られるまで、自分が親とともに住んでいた家があったところです。アブラハムがそこに70年ぶりに帰ろうとする映画だから、『家へ帰ろう』なのでしょうか。いやでも、ポーランドよりも長い期間住み、娘たちとの数多くの思い出が詰まったはずのブエノスアイレスの自宅もまた、アブラハムの「家」のはずです。それなのになぜ、「家へ帰ろう」なのでしょうか。
アブラハムが最後のスーツを持ってポーランドに行こうとしたのは、70年前に友ピオトレックと交わした約束を果たすためです。アブラハムは、第二次世界大戦が終わるころ、ホロコーストから逃れ、ウッチにある自宅に足を引きずりながら何とか辿り着きます。しかしそこには、アブラハムの父が営む仕立て屋で働いていたポーランド人家族が住んでいました。命からがら逃れてきたアブラハムを、幼なじみで親友のピオトレックの父は、「この家を取り返そうというつもりだ」などと激しい剣幕でアブラハムを中に入れようとしません。それを見たピオトレックは、父親を殴り倒してまで、アブラハムを匿おうとします。ピオトレックはアブラハムを抱きかかえ、以前自分たち家族3人が暮らしていた地下の部屋に連れていきます。そこでアブラハムを介抱するのです。
アブラハムが果たそうとした約束、それは、ブエノスアイレスに移り住むことになってピオトレックと別れる際に交わしたものです。アブラハムはピオトレックに「かならず会いに行く」と約束しました。アブラハムがポーランドに持っていくことにした「最後のスーツ」は、ピオトレックから別れ際に渡された型紙でつくったものだったのです。
アブラハムが帰ろうとする「家」とは何なのでしょうか。「家」は英語で「ホームhome」と言ったりします。そして「ホーム」には、「本拠」であるとか、「故郷」といった意味もあると考えられます。そして「故郷」は、「生まれ故郷」と言ってみたり、「ふるさと」などと読んでみたりするように、多くの人にとって、懐かしさや親しみといった情緒をともなう言葉として、忘れがたい思い出を呼び起こす言葉として理解されています。であれば、「故郷」はすでに目の前から失われてしまったものです。確固としてそこにある実在とは呼べないものです。「思い出のない処に故郷はない」(小林秀雄)と言われるように、人は「故郷」という観念によって、すでに失われたものをいまここに引きとどめようとするのでしょう。
主人公のアブラハムは、自分の娘や孫たちのもとから去っていきました。約13,000キロも離れたポーランドのウッチへの長い旅に出ます。自らの死期が迫っていることを敏感に感じとりながら、家族のもとを去り、故郷への帰還を果たそうとします。ですが、そんな彼にとって家族のいる場所は、「家」=「故郷」と呼べるものにはなりえなかった。オルテガが言うように、わたしたちの生は、必然的にかつ根本的に孤独です。でも同時に、その孤独の深い底から、わたしたちの生は、根本的な共存と社会への憧憬のなかへと浮かびあがろうともします。そうであれば、家族にあって可能なのは、せいぜい、互いの孤独への気遣いをさり気なく示すこと、交わされる言葉のなかに、また、相手の姿を見やる視線や表情に、互いの孤独への気遣いを休みなく忍ばせつづけることくらいのように思います。
でも、それが難しい。家族にあってもそうなのでしょう。アブラハムが最期に帰ろうとしたのは、友ピオトレックと過ごした場所でした。アブラハムにとって、そうした気遣いの交換がなされたのは、友ピオトレックとの関係であったと思われます。アブラハムは、そんな忘れがたい「思い出」へと帰ろうとする。そんな望郷の念は、アブラハムがそうであったように、人が抱くもっとも強い感情の一つのように思います。ですが、それを遂げることは、いまや多くの人にとってどれほど難しいことか。「故郷」や「ふるさと」という言葉、それへの回帰が各所で言われるこの国では、アブラハムが遂げようと決意した故郷への静かな帰還はとても難しくなってしまっているように思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メルマガのバックナンバーはこちらで閲覧頂けます。
https://the-criterion.jp/category/mail-magazine/
雑誌『表現者criterion』の定期購読はこちらから。
https://the-criterion.jp/subscription/
その他『表現者criterion』関連の情報は、下記サイトにて。
https://the-criterion.jp
ご感想&質問&お問合せ(『表現者クライテリオン』編集部)
info@the-criterion.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
執筆者 :
CATEGORY :
NEW

2026.02.09
NEW

2026.02.07
NEW

2026.02.06
NEW

2026.02.05

2026.01.30

2026.01.30

2026.02.05

2026.02.06

2026.02.07

2026.01.20
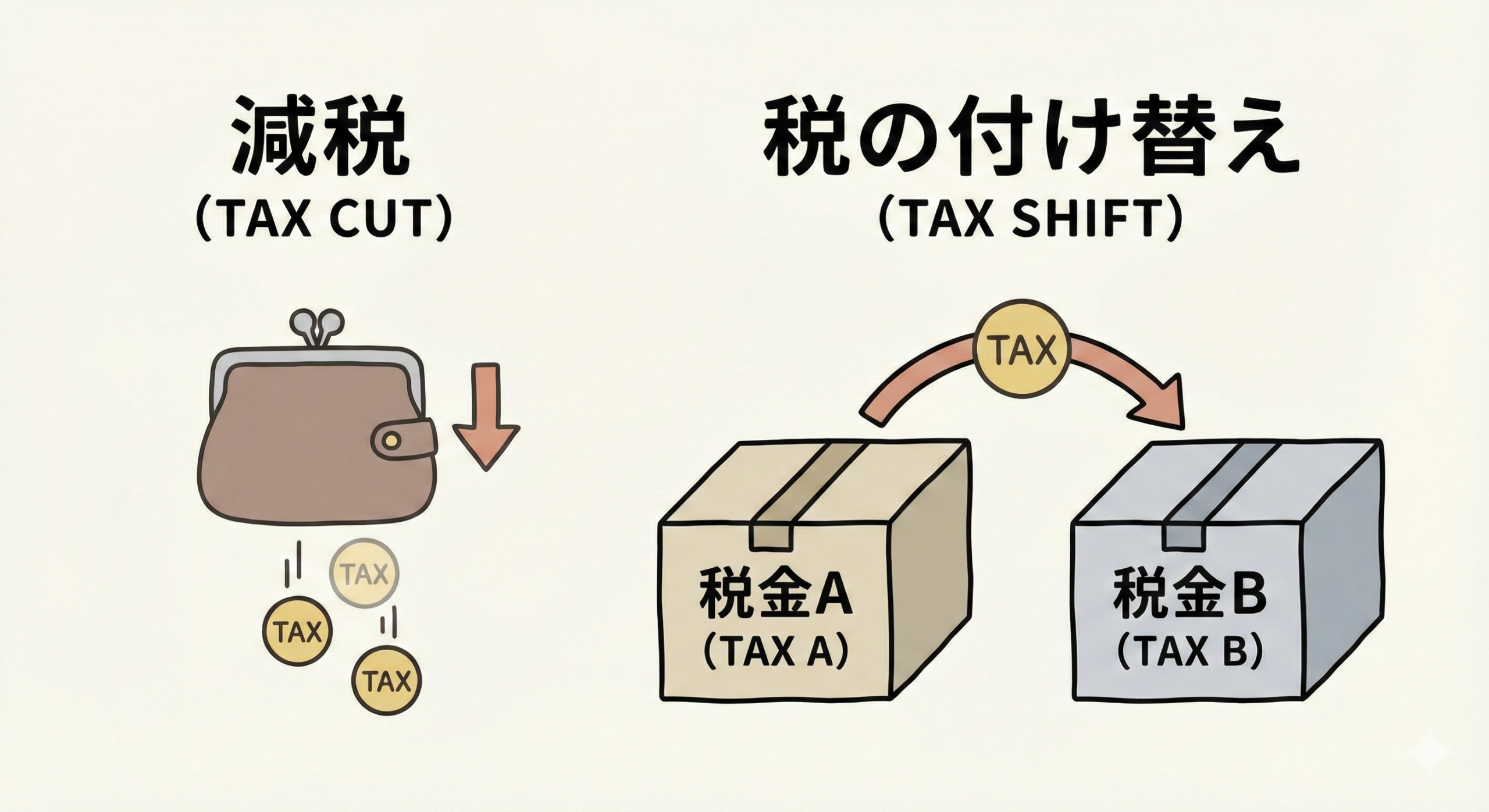
2026.01.18

2026.02.09

2024.08.11

2018.09.06

2026.01.30

2020.07.06
コメント
故郷、かぁ…幼少期、複数回引っ越しをした身としては、
自分の故郷を1つと定める事自体難しいですが、
やはり中学高校と過ごした地、という事になるのかな。
自分は都会経験も少なく、地方にずっと住んでいるので余計かもしれませんが、
都会に出ていったり、戦争の惨禍から逃れて他所に移った人達が、
老いて故郷に望郷の念を抱くというのはちょっと理解しがたい所があります。
要は、行った先で過ごした事が苦痛を伴うほどの停滞であるとか、
心痛を感ずるようなものだったから故郷に戻りたいと考える訳で、
現地で成功とまでいかなくとも、安穏と過ごせていればそんな気持ちにはならないのではないか…
そんな風に邪推してしまいます。
死に際の事はもちろん分かりません。単なる戯言です。まだ三十路にもなっていないので。
しかし、その映画の冒頭は、切ないですね…