前回は、「文章表現」というごく日常的な営みを例にとりながら、「何を選ぶべきか分からない迷い」(クライシス=危機)のなかで、それでもクリティーク(批評)の無限後退を止め、自らの決断(飛躍)を促してくるものとは一体何かという問いを提示しておきました。ただ、これは何も「文章表現」に限った話ではありません。
かつて、福田恆存は「行動というものは、つねに判断の停止と批判の中絶とによって、はじめて可能になる」(『人間・この劇的なるもの』)と言いましたが、このような契機、つまり、一旦、自分自身の反省に見切りをつけて、「これでいくしかない」と一歩踏み出すという契機は、あらゆる「行動」に必ず付随している瞬間だと言えます。
では、そのとき、見切り(ある種の諦め=覚悟)を自分につけさせているものとは何なのか。結論から先に言えば、それは、後ろから自分を押してくる「力」、つまり過去からもたらされる自らの「歩き方」の一貫性に対する暗黙の信頼感以外のものではないでしょう。
知識は無限であり、それも刻々と増すものである以上、人は完璧な未来予想図を手にすることはできません。しかし、だからこそ人は、この過去からもたらされる「型」への信頼なしでは、自分の一歩さえ容易には踏み出せないのです。ただし、その信頼感は、知識や論理に対するものではありません。むしろ、知識や論理の操作性が無力となる地点で、なお、自らの一歩を支えているものの手応えとして甦ってくるようなものです。
それは、ふたたび福田恆存の言葉を借りれば、「将来、幸福になるかどうかわからない、また『よりよき生活』が訪れるかどうかわからない、が、自分はこうしたいし、こういう流儀で生きてきたのだから、この道を採る」(『私の幸福論』)という「生き方」だといってもいいでしょう。言い換えれば、自らの「無垢な欲望」に対する強烈な自覚の力です。
「流儀」が個々人で違っているように、「歩き方」「生き方」は個々人で違っていて当然です。が、逆に言えば、その「歩き方」のリズムは、それぞれに固有のものですから、他人の「より良き生活」に目を奪われても、あるいは「過ち」や「不幸」を過剰に恐れても、結局のところ自己喪失してしまうしかありません。
だから、私たちは自分の過去に耳を澄ませることが必要なのです。過去からの「歩き方」を見つめ、それと齟齬を来さないように次の一歩を出す。しかし、それは考えてみれば、言葉の流れを鑑みつつ、その流れのなかに次の言葉を用意するという、あの文章作法の極意と何と似ていることでしょうか。
とはいえ、もちろん、そのリズムを独力で実現する必要はありません。家族・友人・師匠など“過去を共有する他者”に相談するということも、自らの一歩を踏み出す際には、重要なモメントとなります。というのも、彼ら/彼女らは、「お前は、こういう流儀で生きて来たのだから、次の一歩はこう踏み出すだろう」ということを無意識にでも確信している場合が多いからです。いや、そもそも、自分の「歩き方」を信頼している人間のことを、“過去を共有する他者”、つまり家族、友人、師匠と呼ぶのかもしれません。
ただ、ここで注意しておきたいのは、この自分の「生き方」に“筋を通す”ことは、決して自分に“無理をする”ことと同じではないということです。いや、それは、むしろ自分のなかの「自然」を見つけることだと言った方が正しい。なぜなら、自分の「歩き方」や「歩幅」を自覚するということほどに、自分が自分になっていくこと──己の「自然」を育て、取り換えのきかない自己を造っていくということはないからです。
だから、その結果が「失敗」に終わったのだとしても、その取り換えのきかない「自然」の姿は、私たちに、なお人生が美しいものである可能性を示し続けるのです(醜いのは、失敗を「悔やむ」場合であり、また失敗を引きずって己の「欲望」を素直に表現できなくなる場合です)。
いや、そんなことは、私が一々言葉で語るよりも、様々な魅力ある英雄の姿──「失敗」した吉田松陰や西郷隆盛と言いたいところですが、そんな「偉人」でなくても、たとえば小学校しか出ていない私の祖父もそんな人間の一人でした──を見れば一目瞭然でしょう。彼らは、「自分はこうしたいし、こういう流儀で生きてきたのだから、この道を採る」、そういう生き方を貫いた人々であり、また、それによって生き甲斐を得た人たちでした。
果たして、人間にとっての「クライテリオン」の手応えが何であるかについては、もはや詳説の必要はないでしょう。
それは、まず、自分の過去に耳を澄ますことからやってくる「宿命感」であり、また、ときに“過去を共有する他者”の頷きによって与えられる「必然感」としてあります──ただし、この場合の過去は、単に終わってしまった現実という以上に、将来に向き合う「この私」において解釈され、現在において生成しているものであるということを忘れてはなりません。つまり、ここで言う「宿命」は、決して決定論的な「宿命論」ではありません──。
そして、それは、個人のみならず国家にとっても同じことが言えます。戦後日本を見れば分かるように、人間の営みにおいて、過去と整合できない一歩、あるいは過去と矛盾する一歩ほどに、自信を失わせるものはほかにないのです。
では、なぜ、現在において「過去」を整合すること、自分の「生き方」に筋を通すことは、人々に自信と充実を与えることができるのか。次回は、そのあたりのことについて、もう少し踏み込んだ形でお話しさせて頂ければと考えています。
執筆者 :
TAG :
CATEGORY :
NEW

2026.02.11
NEW

2026.02.09
NEW

2026.02.07
NEW

2026.02.06
NEW

2026.02.05

2026.01.30

2026.02.05

2026.02.06

2026.02.09

2026.02.07

2026.01.20
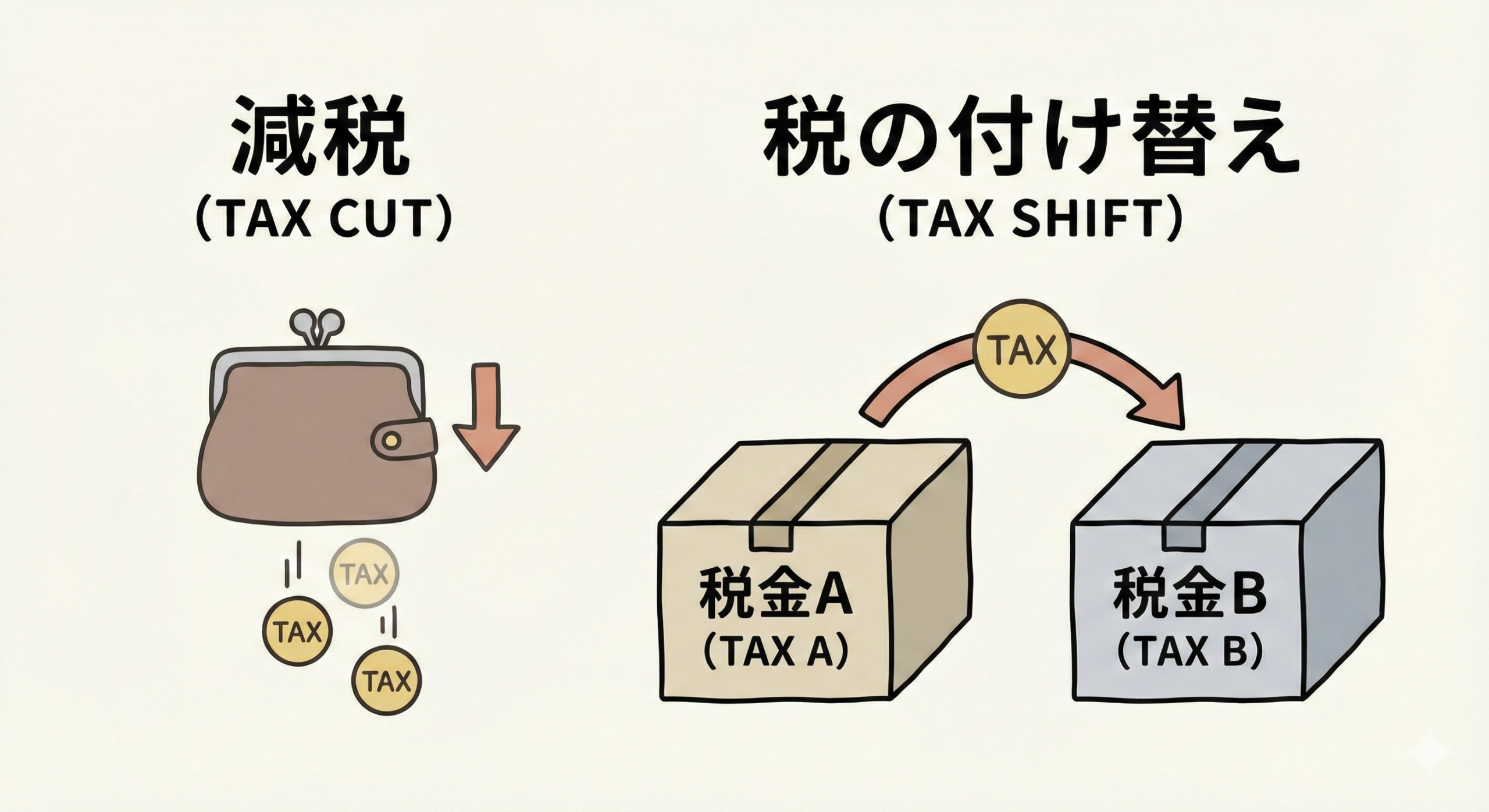
2026.01.18

2024.08.11

2018.09.06

2026.01.30

2020.07.06