日本語では、話し言葉と書き言葉は随分違う。比較できるほど他言語について知らないので日本語に限って考えるしかないが、こんなに違う言葉はそうないのではないかと思う。随分昔のことだが、海外の大学で日本語の授業を受け持ったことがある。初心者用の教科書は「書き言葉の会話」から始まる。周囲に日本語環境がまったくない海外では、最初から日本語の口語を教えるわけにはいかないだろう。口語表現は、場面や状況や人間関係の諸条件によって随分違ってしまう。学習の目的が、留学なのか、友人との会話なのか、仕事で必要なのか、旅行なのかでも違う。学生が将来必要とする場面設定が未定である以上、誰に対しても失礼のないように話が伝わることを学習の目的にすると、やはり「書き言葉」を学ぶのが無難な選択になる。
日本語には自分のことを表わす単語が多い。とくに口語では一人称や二人称が無限に思えるほどある。それぞれに生活属性が異なりニュアンスが違う。相手や場面などの条件によって変化させることもある。例えば、一人称を二人称に転用することがある。小さい子供に、「ボクのお名前は?」とか「ボクの靴はどれ?」と聞くときの「ボク」は話し手のことではない。一人称を使って、子供の視点に立って話している。妻が夫に「パパ、どこへ行くの?」などと言うのも、自分の父親のことではない。夫婦が子供の視点で「パパ」「ママ」と呼び合う。市場の呼び込みの声が「お母さん、これ安いよ」、繁華街で「お兄さん」と呼び掛けるのも、自分の母や兄のことではない。人称が転化されても、私たちはその違いをちゃんと嗅ぎ分ける。日本語の話し言葉で、「場」や「属性」がないというのは考えられない。
小説の中で、長い会話が描写されるとき、「 」ごとにI said/ you told her/ he saysなどの断りがなくても支障はない。いちいち話し手を明示せずに「……」「……」「……」「……」「……」と、会話文が延々続いていても、話し方や口調などで、大抵はそれぞれの「 」の話し手が誰なのかがわかる。何について話しているのかわからなくても、語り口、喋り方で発言者がわかるのである。男女、親子、身分、主人と使用人、大人と子供、先生と生徒、友人同士、そして、話者同士の親密度の濃淡までわかる。勿論、英語でも乱暴な言葉や丁寧な言葉、上品下品、知的幼稚など話し方の違いはあるが、それでも「 」が続くと、途中でどちらの台詞だかわからなくなることがある。相手のことはみんな“you”だし、自分のことは“I”である。KingでもQueenでも僧侶でも職人でも売り子でも乞食でも、自分のことは“I”という。日本語の話し言葉が書き言葉とかなり違うのは、話し言葉に含まれる属性の圧倒的な豊かさにある。
参勤交代で殿様の御供でやって来た地方の藩士は、江戸の町で言葉が通じないこともあっただろう。その頃は、地元語と共通語のバイリンガルなどはいなかった。巷で通じないだけではない。異なる地方の藩の出身者同士の会話で、お互いがお国訛りで喋っていては意思の疎通が難しいこともあったはずだ。テレビもラジオもなく、他の地域との交流も少なかった頃の「お国訛り」は、現代の比ではないほど激しかった。諸国から集まった武士が公的な話や議論が通じなくては困る。公的な場では武士の書き言葉が使われた。「候(そうろう)文」である。漢籍を学び、真名書きの書簡の文章を読み上げるように会話すれば、相手にも通じる。
昔の書き言葉は、もとを辿れば漢文の書き下(くだ)し文である。近代以前、外国との人の交流は海峡に隔てられて容易ではなく、大陸のように異民族との頻繁な接触での音声言語による変化は起こりにくかった。日本人にとって、外国語を知ることは文書の意味を解読することだった。
「漢語を和語によって理解する/和語を漢語によって理解する」システムが、漢字の訓読みである(今野真二『日本語の近代』)。明治期に西洋の文を翻訳するのにもこのシステムが使われ、「洋語を漢語によって」理解しようとしたのが、和製漢語である。西洋的発想の数々の抽象語を理解するのに、日本人は漢語を用いた。「社会・個人・科学・自由・権利・自然・存在」等々の新しい概念が『明六雑誌』など多くの啓蒙書で世に送り出された。そのときの造語は「漢語」であって「和語」ではなかった。和語と漢語は「漢字」が視覚的に介在することで一体化し、「漢語」は、最早中国語とはいえないものになっていた。漢字が入って来た初期の頃には、漢字を和語で発声することは、「coldい」と書いたものを「さむい」と音読みするような違和感があっただろう。長年の訓練と慣れで、和漢は独自に融合した。漢字を中国音だけでなく、訓読みにも用いたのは日本語だけだ。そのために、書き下し文はそれ自体が中国語の「翻訳文」でありながら、その書き下した邦訳に、更に翻訳を必要とするくらい日常の口語文とかけ離れている。
日本で書簡に使われたのは、漢文を真似た文章である。漢籍を読み下すとき、返り点や送り仮名を書き込んで日本語読みにする。中国音と似ても似つかぬ読み方の定型が生まれる。書簡で使うような「以為(おもえらく)」「而して(しこうして)」「安んぞ/焉んぞ(いずくんぞ)」などという読み方は「極めつきの意訳」で、文字を見ただけではわからない。会話では使わなくても、戦前までの文章では便利に使われた定型である。
経典などの漢籍が日本に入って来た当初、文字を知っていて書く機会のある者とは、それなりの身分や教養のある者、僧侶や貴族や武士であった。書簡を読む相手も身分のある者だから、文末に謙譲の意味で「侍る(控える/仕える)」を用いた。平安時代の終わりから室町にかけて「侍る」の代わりに「候」を使うようになる。これらは丁寧語であり「です・ます」と同じである。この文体には地域性がないから、書簡として全国に往来した。日本語の書き言葉が「翻訳文」であったことを思えば、地域色がないことが納得できる。書き言葉は、こうして、お互いの属性を削ぎ落すことによって「役に立つ」言葉になった。口語の属性が消されたからこそ「通じる」言葉になったのである。真名書きの書簡の読み方を知らなければ、幕末維新に薩長や土佐や会津の藩士たちが議論などできなかっただろう。
書き言葉は何よりも内容が優先される。レポートや論文などの知の伝達や、演説などの意見の表明や、新聞記事などの状況説明に適した言葉である。書き言葉はギリシャ演劇の「コロス」である。あるいは能の地謡である。感情の吐露ではなく、情況の説明である。書き言葉は生活の上澄みだから、生活そのものを語らない。道を尋ねたり、値段を聞いたり、口頭試問や質疑応答などの内容さえ分かればいいという会話以外での生活の場で、書き言葉を使う人はいない。そんな言葉で話されたら、聞き手は他人行儀に感じ、馬鹿にされたような気になるだろう。逆に、報告書や書類や裁判記録に「隣のおじちゃん」に話すような言葉を使ったら、「買い物ブギ」や「寅さん」になってしまう。
書き言葉には生活属性がない。属性を消すことによって、書き言葉が成立したとも言える。報道は、活字媒体だけでなく音声メディアでも書き言葉が使われる。誰にでも理解できる共通語として、学校の教科書、新聞やテレビやラジオで使われる言葉である。ニュース原稿は、生活属性のない主体が、生活属性の不明なだれかに向かって発する文章、または、「誰」でもない発信者が「誰」でもない相手に語ることばである。
国民という「平均的日本人」を想定して話す文章を全員が採用すれば、そこにひとつの仮想空間が出来上がる。「平均的日本人」など実在しないのだから、それが作り上げる空間も架空である。集権的な支配は、書き言葉でなければ達成できない。国家が言語を統一する、あるいは標準語制定の欲求を持つのは、幕末維新の各地の藩士たちの議論を成立させたのと同じで、国民それぞれの属性がどうであれ平均的な個体として扱う以外ないからである。J.S.ミルは言語の限界が議会制民主主義の限界だとみなし、「とりわけ別々の言語で読み書きをしている場合は、代議制統治を機能させるのに欠かせない統一された世論が存在しえない(『代議制統治論』1865)」と、言語の統一を代議制民主主義の決定的要件とし、国民の一体性に不可欠なものとした。共通言語による仮想空間という「新たな属性」をもつ集団が「国民」である。
学校教育は「国民」を作る場であったから、教科書は仮想空間で使われる「書き言葉」になる。初期の教科書は漢文の書き下し文に近いものが載せられていたようだ。前出の今野真二氏の著書の中で引用されている当時の小学校高学年の教科書の文章に次のような例がある。
「宮門ヲ守ラシムト雖モ猜忌多ク猶自ラ安ンセズ…」
「河水ヲ其中ヘ漑キ去ラシメ本河ヲ斥瀬トシテナシテ…」
——カナが振ってあり、単語の意味も簡単な漢語で添えられているが、その頃の12歳の子供に意味がわかったかどうかは不明である。初期の教科書は江戸時代からの継承で、寺子屋での年長の子供に漢籍の素読をさせていた名残があったらしい。江戸時代の漢籍の素読は武士階級の教養のための限定されたもので、庶民の言葉ではなかった。近代国民国家は、国民の一人ひとりを取り込まなければならないのだから、もっと平易な共通の言葉が必要だった。
日清戦争以後、西洋列強から学び取ることが急務になる。清に勝った日本は、弱い清から学ぶより、強国の西洋から学ばねばならぬと、一斉に西洋の方を向いた。教科書も漢文風な「文語体」から、「言文一致」に変わっていく。方言の言文一致では全国に通用しないから、基準を考えなくてはならない。言文一致の書き言葉は、「東京(江戸)の方言」を基本にした話し言葉に近いものを、全国共通の書き言葉にしようというものである。
漱石の文章は漢語が多く現代の文章とはかなり違うが、当時の知識人の中でも最先端のハイカラな「言文一致」だったに違いない。東京出身者のアドバンテージとして、日ごろ使っている自然な言語で書けば、言文が一致しただろう。使いこなせるだけに、確かに切れ味が違う。しかし、津軽や津和野から出てきた太宰でも鴎外でも、出身地を問わず共通語を使うことで同じ土俵に立つことができた。但し、彼らにとって言文一致は属性が貼りついた日常語との一致ではない。The Second Mother Tongueである共通語で書くことであった。太宰が津軽弁で書いていたら、全国区の作家にはならなかった。ミルの言う「言語の境界」が、藩という地域の境界から日本全土に広がったのは、書き言葉によるものである。
学校教育の普及もあって、印刷物が果たした役割は大きい。『明六雑誌』の文は、まだまだ漢語的で庶民の理解には程遠い。国定教科書の言文一致化の方針で、印刷物の俗語化が進み、出版物の消費市場が生まれたことはアクセルになった。新しい国家システムでの役人や事業家、産業の専門職などが出版物を手にし、彼らが言語学革命の「潜在的消費者」となり(ベネディクト・アンダーソン)、産業と共通言語は互いに推進力になったといえる。
脳が自動的に相手をカテゴライズしてしまう能力には驚くべきものがある。初対面の人と話せば、私たちは意図せずに一瞬にして、相手の属性のいくつかを認識している。例えば、相手がネイティヴな話し手であるか否かはすぐにわかる。日本人と区別のつかない外国人に流暢な日本語で話しかけられた場合、それがその人物の母語なのか学習した日本語なのか、瞬時に識別する。日本人同士が共通語で話していても、アクセントの微妙な違いで、出身が「西の人」「東の人」くらいのことはわかる。どこの国でも同じように、相手の言葉の違いを敏感に受け止めている。脳は、対面でも音声通話でも、無意識のうちに相手の属性のいくつかを瞬時にキャッチしている。
属性は出身地だけではない。江戸時代には、武士の言葉・僧侶の言葉・町人の言葉は違った。町人でも、お店者と職人では言葉遣いが違う。大店の主人、番頭、小僧、行商人、水商売、親方はそれなりの言葉を使った。農民と庄屋の間にもことばの等級があった。身分という属性が、会話では即座にわかっただろう。身分制度のない現代でも、上司や先輩などの立場の違いが会話には現れる。男女、年齢、社会的地位、居住地、学問、育ち、家庭環境等々、その人の生活属性が現れるのが「話し言葉」である。時代劇でも現代劇でも、映画や芝居では、台詞や口調で役者の演じている人物がどういう属性にあるのかが、説明なしで観客にわかるようになっている。
会話は全身体を総動員して行う。会話には場所がある。時もある。他愛のない呟きでも、世間話でも、議論でも、その場では視覚も聴覚も嗅覚も触覚も何かを捉えて言語化に微妙な影響を与えている。身体を総動員しているのだから、肉声とはよく言ったものだ。そこは属性が満ちている場である。属性に満ちた会話は「平均化」が不可能である。会話において話の内容以上に大切なのは「場の共有」にあるのではないか。学校教育やメディアによって「共通語」を使いこなすようになっても、地域の言葉は消えない。日常の現実世界は仮想空間に勝る。風土が生み出す生活属性をまとってこそ、生き生きとした会話が成立するのではないだろうか。
言語学を学んだことがないので、個人的な感想としてしか言えないのだが、和語に現れる主体は、主張する「個」ではなく「場」や「属性」によって立ち現れるもののような気がする。それを強く感じるのは、日本の「うた(短歌)」や「俳句」である。短歌や俳句は、圧倒的に自然を詠んだものが多い。自然のなかでは、動物よりも植物が多い。動物では獣ではなく小さな虫の出番が多い。桜が散り、梅の香が漂い、月明かりに照らされる情景に感じ入っている「私(詠み手)」の視点があるが、「うた」の場面に「私」は居ない。
「山深み春とも知らぬ松の戸に絶え絶えかかる雪の玉水」という情景の中に「私」は見えないが、その雪解けの雫をくぐって行く「私」の存在がある。「私」は視界にはないが、そこに「いる」。強い個性を持った人物が、自らの意思で雪解けの山の奥を進んでいくような能動的な場面ではない。「古池や、蛙飛び込む 水の音」も、そこに「ある」だけの古池に小さな動きが生じ、一瞬の水の音が静寂を破るが、余韻を残してすぐにまた深い静寂に戻る。そんな自然の「場」のなかに「誰か」の存在があるのだが、主観と客観が同一になった瞬間には「行為者」はない。日本語にとって、属性や場はただの付随物やステージではなく、主体を主体たらしめるもののようだ。主語がなくても、場と属性が主体の存在を語る。日本語にとって、主体は「行為者」ではなく「存在」なのだと思う。
日本語を教えていて感じたのは、日本語なのに、文法が西洋言語を基準にしているということである。すべての文をS+V+Oに分解しようとする。(だいたい、何故、Subject(従)が「主語」なのか、私にはよくわからないのだが。)ヨーロッパ言語でも、特に英語のように語順によって「格」が決まる文章では、主語は「明確な行為者」である。語順は「主語」と「行為」を確定する。語順に拘泥しない日本語では、主体は「行為者」ではなく「存在」である。属性、つまり他の要素との関係性で「主体」を捉えるのが日本語であるが、西洋言語の「主語」は周囲の属性を切り離して独り超越した「絶対的」な行為者である。どの「場」にあっても、どんな「時」にあっても、行為者としての自己を曲げない。だから、自分が横に「なる」のにもI laid myself on the bed と、自分を横に「する」という能動的な行為になってしまう。膝に手を置くのもShe lays her hand on her kneeと、わざわざ「どっこいしょ」と膝の上に運ぶようなニュアンスになる。日本語検定2級程度のアメリカ人を教えたとき、主語のない文章があると、いつも「主語がない~!」とパニックになった。「行為者」がいないと成立しない言語のほうがよほど面倒で異常なのではないだろうか。
西洋文法的に考えると、主語のない文章は、主語が「省略」されたとみなされる。しかし、主語がない文章は日本語だけではない。寧ろ、主語が必須なヨーロッパ言語のほうが「例外的な言語」なのではないかと、疑っている。ユーラシアの西の端の狭い範囲で生まれた強烈な自意識をもつ言語である。植民地時代に新大陸でも使われるようになったために、現在のヨーロッパ言語人口は多いが、だからといって、文法的に「基準」であるわけではない。他言語をヨーロッパ言語と比較して説明することは、彼ら自身の理解のためである。スワヒリ語もヒンディー語も中国語も、それぞれの言語がそれぞれの文法をもっているのだ。「山深み…」の情景には「行為者」が居ないから、味わい深いのである。
ところで、インターネットの言語空間は新たな属性をもたらすのだろうか。書き言葉による集権的な統一空間ではなさそうだし、チャットは話し言葉であってもリアルな身体性は見えないし、群れていてもそこに生活属性はなく、ニッチで翻訳不能な言語空間が離合集散を繰り返す。「誰」でもない発信者が「誰」でもない相手に語るのは、マスメディアの「平均的な誰か」を相手にする世界に似ているが、平均的なのか均一性があるのかと問われれば、それもちょっと違う。AIの学習によって「平均化」される方向にあるのかもしれないが、それぞれが一部の属性だけを見せて単純化した情報だけを提供しているなら、そんなものを平均化して何が出て来るのだろう。英語、ロシア語、中国語、ヒンディー語、アラビア語などそれぞれの言語の世界のなかで平均化が起こっても、他言語との融合は起こりそうもない。AIによる「翻訳」はあくまでも他言語のままだということだ。寧ろ、各言語が孤立して内部で精鋭化しそうな気がする。デジタル空間での「ことば」は、私たちにどのような影響を与えていくのだろうか。
『日本語の近代—はずされた漢語』今野真二著 /ちくま新書 2014

『底本 想像の共同体』ベネディクト・アンダーソン著 /白石隆・白石さや訳 /書籍工房早山 2007

『日本語に主語はいらない』金谷武洋著 /講談社選書メチエ 2002

〈編集部より〉
最新号『表現者クライテリオン2024年3月号』好評発売中!
インフラにこんな意味があったなんて!
インフラの持つ思想性を徹底的に論じる特集、ぜひご一読ください!
定期購読にお申込みいただくと10%OFF、送料無料、発売日前にお届けいたします。
<お知らせ>
表現者塾は『表現者クライテリオン』の編集委員や執筆者、各分野の研究者など豪華ゲストを講師に迎え、「クライテリオン=(規準)」をより一層深く探求する塾(セミナー)です。
毎回、浜崎洋介先生が司会進行を務め、前半は講義、後半は浜崎先生との対談となっています。
浜崎先生のガイドに沿って学べるので、幅広くも一貫した体系性をもって自らの知を深めていくことができます。
現地での参加以外にも、「ライブ配信」、「アーカイブ視聴」が出来る動画会員も募集しております。
◯毎月第2土曜日 17時から約2時間の講義
◯場所:新宿駅から徒歩圏内(リモート参加可)
◯期間:2024年4月〜3月
◯毎回先生方を囲んでの懇親会あり
◯ライブ配信、アーカイブ視聴あり
編集長の藤井聡先生や編集委員の川端祐一郎先生もかつて西部邁先生時代の表現者塾(発言者塾)に通っておられました。講義の受講、議論(ディスカッション)、社交を通じて、『表現者クライテリオン』の言論運動を共に作り、支えていく核となる組織となっています。
【藤井聡】今の自分があるのは「塾」や「シンポ」があったからです。~表現者の塾とシンポジウム、是非ご参加下さい~
【浜崎洋介】表現者塾「5年目」に向けて——その「場」の力について
【浜崎洋介】第3期「後期表現者塾」開講決定!受講生募集します!
編集委員の藤井先生、柴山先生、浜崎先生、川端先生、顧問の富岡幸一郎先生、
毎年レギュラーで講師をしてくださっています施光恒先生に加え、
来期は、以下の先生方を迎えます。
古田徹也 先生(哲学・倫理学、東京大学准教授)
片山杜秀 先生(政治学・音楽評論、慶應義塾大学教授)
小泉悠 先生(軍事評論、東京大学准教授)
苅部直 先生(政治学・日本思想、東京大学教授)
大場一央 先生(日本思想・中国思想、早稲田大学非常勤講師)
小川さやか 先生(文化人類学、立命館大学教授)
講義テーマはこちらからご確認ください!
皆様のご参加、心よりお待ち申し上げます。
↓↓詳細・お申し込みはこちらから↓↓
https://the-criterion.jp/lp/2024seminar/
執筆者 :
CATEGORY :
NEW

2026.01.23
NEW

2026.01.23
NEW

2026.01.22
NEW

2026.01.20
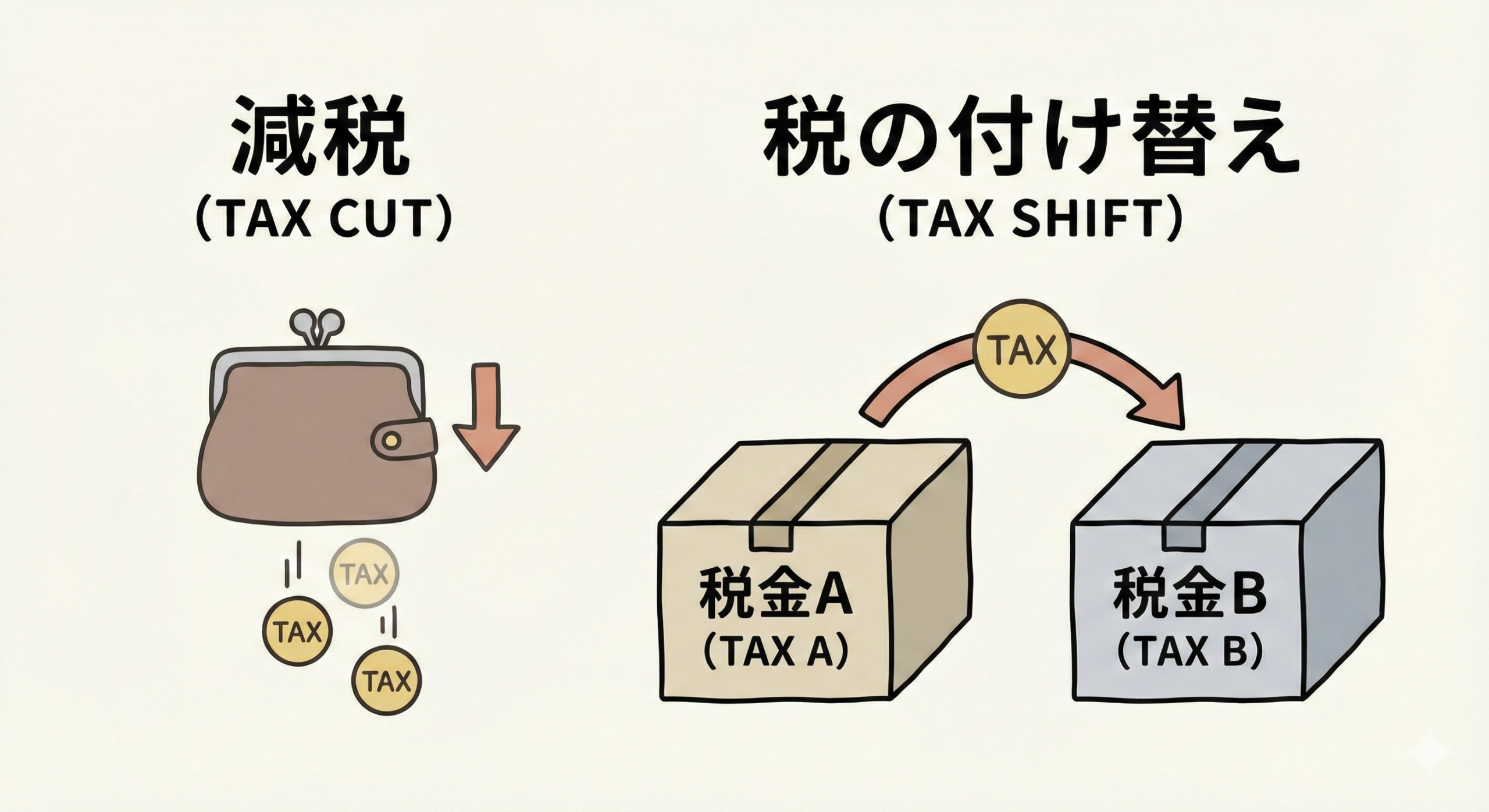
2026.01.18

2026.01.16
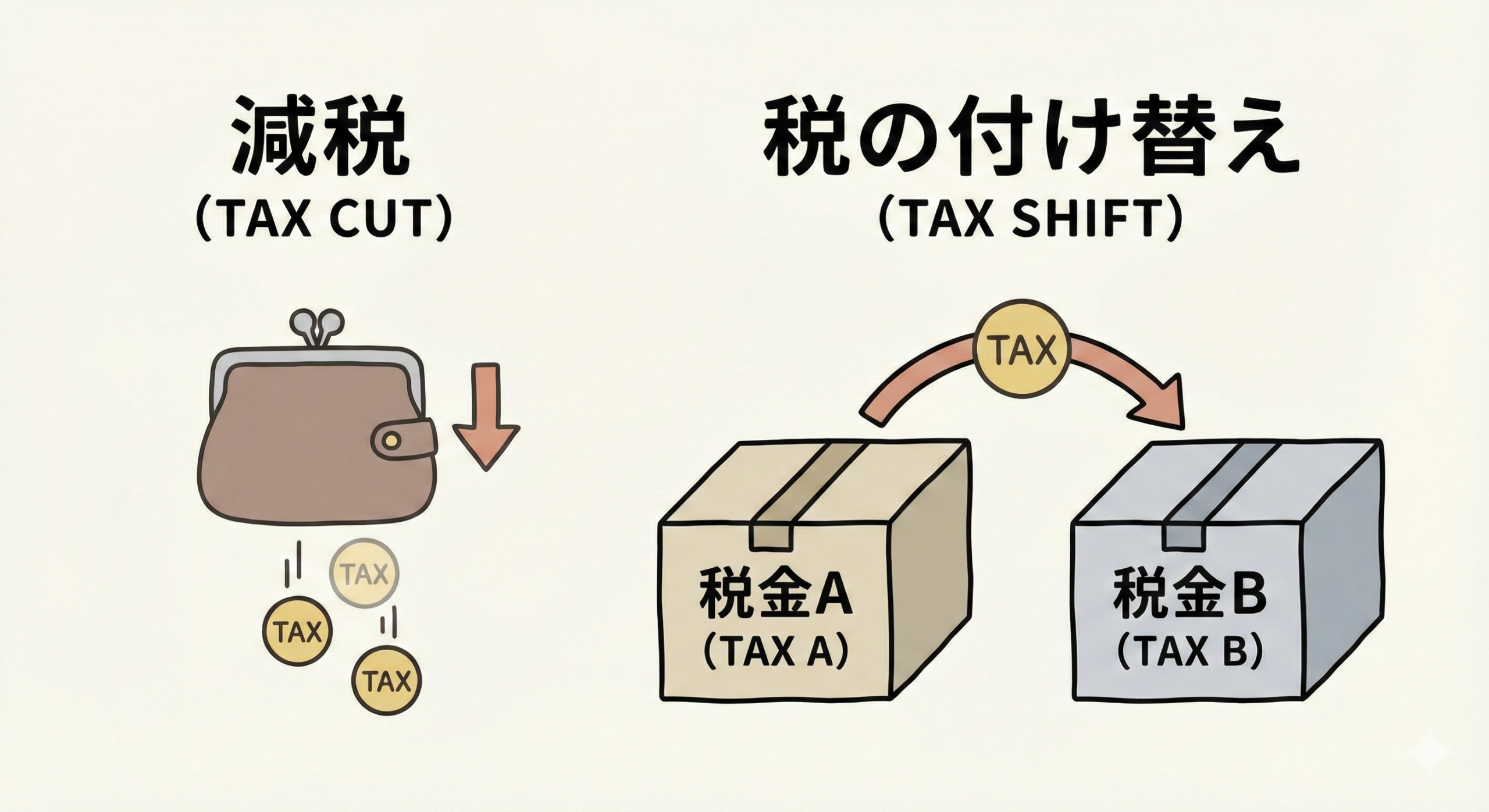
2026.01.18

2026.01.20

2026.01.22

2026.01.13

2024.08.11
.png)
2025.12.31

2026.01.23

2026.01.23

2026.01.16

2018.09.06