岸田首相の爆殺未遂事件の後、何人かの政治家が、「テロリストに同情すべからず」と警鐘を鳴らしているらしい。
「24歳の男がどんな境遇にあろうが、テロ行為にどんな理由があろうが同情の余地がないことをマスコミは報じるべき」(細野豪志)
「テロリストのバックグラウンドなどをさも同情的に書く媒体がある事に、本当に何の反省もないんだなと憤る。どんなバックグラウンドがあろうと、凶行に及んだあの殺人犯も今回の犯人も1ミリも許されるものではない」(小野田紀美)
しかし、岸田首相に爆弾を投げた木村隆二については今のところよく分からないものの(報道されている範囲ではどうやら稚拙な動機であったようだが)、安倍元首相を銃撃した山上徹也の生い立ちを聞いて、同情するなと言われても私には難しい。
山上は4歳の時に父親が自殺し、母親が統一教会に累計1億もの大金を貢いだおかげで兄妹とともに困窮し、学費が払えないので大学進学を断念して自衛隊に入った上、「兄と妹に自分の生命保険金を渡そう」と自殺を図るも未遂に終わり、その後に兄が自殺してしまった。要人を撃ち殺して許されるわけはなく、厳罰に処されて然るべきだが、「他にも苦しい者は大勢いるのだからお前も自棄にならず耐えぬくべきだった」などと言える資格は私にはない。
テロリストに同情するなと主張する人々は、「同情を誘うようなテロリストの個人史」を報じるマスメディアを批判していて、模倣犯を生む危険があるとか、反社会的行為に対する責任追及が不十分になるとかいうのがその理由のようだ。それも分からなくはないのだが、これから述べるように、「社会の安全」や「法的な責任」のような狭い枠組みに人間を押し込めようとする態度が、むしろ新たな危機の土壌となることもあるのではないか。
昭和35年10月12日、日比谷公会堂で演説中の社会党委員長浅沼稲次郎が、突如舞台に駆け上がった17歳の少年山口二矢に刺殺された。二矢は、運動方針への疑問から事件前に離党してはいたものの、大日本愛国党にしばらく所属していた右翼活動家で、「安保改定反対」のデモ隊を見たり愛国党への野次を聞いたりすれば見境なく殴りかかり、月に一度か二度は警察の厄介になるという典型的な鉄砲玉であった。そしてこの刺殺事件が最後の逮捕となり、まもなく鑑別所の独房で自決した。
浅沼の胴を素早く二度突き刺してすでに致命傷を与えていた二矢が、「次の一撃」に移ろうとした時、飛びかかった警官の一人が二矢の構える短刀の刃を素手で力強く掴んだ。その気迫に圧されて二矢が柄を手放したと言われていたらしいのだが、沢木耕太郎の取材と考証によると、これは当時の右翼の間で作り上げられた「伝説」だったようだ。
興味深いのは、その作り話が右翼の間に広まった理由のほうである。「二矢はその時、もう一撃を加えようとしたのではなくその場で自決するつもりだったが、警官に握られた短刀を引き抜けば彼の手がバラバラになってしまう。そのことに躊躇を覚えて、手放さざるを得なかった」という風に伝わっていたそうだが、要するにこの逸話は、「人の心をもったテロリスト」として二矢を美化する役割を果たしたというわけである。
私は、伝説の真偽の問題とは別に、テロリストに人間の姿を見ようとしてしまう我々の止みがたい「情」のはたらきについて、考える必要があると思う。結論から言えば、私はその種の人情を擁護したい。それがテロリズムの美化にあたり、模倣犯の誘発や刑罰の不徹底につながり得ると言う人はいるだろうが、テロリストを「殺人機械」としか見ようとしないのはそれこそ真実への冒涜であり、人間と歴史に対する侮辱である。
沢木は『テロルの決算』を書いた理由について、西部邁との対談で、「二矢は操り人形ではなく、直線的すぎたかもしれないけれど自分ですべて決断した一人の少年でした。……右翼少年の死は不当に貶められている。ならば、僕が書こうではないか。そんな義侠心だったんです」と語っている。沢木はテロ行為を賛美したのではない。紋切り型のテロリスト像の背景に「人間」が埋もれてしまうのを、見過ごすわけにはいかなかったということだ。
加えて言うと、既知の事実からかけ離れた物語を支持することはできないが、想像による脚色が混じったテロリスト像を語ることにも意味がある場合がある。「こうであって欲しい」という願望や、「こうであったなら救いがある」という仮定法の語りの中にも、人間の真実は含まれているからである。論点をはっきりさせるためにあえて危うい言い方をすれば、テロを美化してみせる語り口の中にすら、国民の「精神のかたち」という意味での伝統や文化が息づいている可能性はある。
以前紹介した『実録・連合赤軍』という映画(以前の記事を参照)では、あさま山荘に立てこもった連合赤軍のテロリストたちが、人質に取った山荘管理人の妻に「我々は労働者のため、革命のために戦っています。あなたに危害は加えませんのでしばらく辛抱してください」と約束する場面がある。また、「これだけ大事件になってしまえば、親父もお袋も村八分だろうなぁ」と田舎の両親を思い遣る様子も描かれている。(セリフはいずれも大意)
私はこれらが事実かどうか知らないし、連赤事件は戦後日本の最も忌まわしい出来事の一つだと考えるので、彼らを壊滅させた警察の努力に対しては敬意を持つ。そして何より犠牲者や遺族にしてみれば、「テロリストにも人の心があった」などという話は聞きたくもないであろう。しかしそれでも、テロリストを「人間」として描きたくなってしまうような人情と想像力を失った社会に、住みたいとは思えないのもまた確かである。
そもそも、「人を殺した」という行為しか見てはならないとなると、刑事裁判における量刑判断や情状酌量も成り立たない。「五・一五事件」の首謀者に対する助命嘆願運動や、「忠臣蔵」の赤穂浪士に対する切腹沙汰の話をしたくなるところだが、話題が偏向していると言われそうなので別の例を挙げよう。
平成18年1月に京都桂川のほとりで、54歳の男が86歳の母親を絞殺する事件があった。母親は10年前から痴呆をわずらっていて徘徊などの症状がひどく、介護に専念するため休職、そして退職に追い込まれた男は経済的にも行き詰まった。最後の親孝行にと、母の車椅子を押して市内の思い出の場所を散策し、コンビニのパンを二人で分けあった後、河川敷に至って、
「もう生きられへんのやで。ここで終わりや」
「そうか、あかんのか」
「すまんな」
「こっちに来い。お前はわしの子や」
と声を掛けあい心中を図ったものの、男だけが生き残ってしまった。男は取り調べでは「殺したのは自分だが、もう一度母の子に生まれたい」と述べ、執行猶予付きの温情判決を受けたのだが、何年か後に母親と自分の「へその緒」を抱えて投身自殺したとされる。
この事件を聞いて、真の問題は介護支援制度の不備であると議論することはできるし、もっと他人を頼るべきではないのかと、処世に疎かった息子に文句を言いたくもなる。「いかなる事情があろうと人殺しは人殺しだ」と責めたり、「他にも介護で辛い思いをしている人は大勢いる」と比較したりする立場もあるだろう。しかし、「親子心中の正当化につながるので、この男に同情してはならない」などと言われる筋合いはなく、実刑に処すべきとも思わないのが普通だろう。
この場合、母親が殺されることを恨んでいないという点がテロリズムと大きく違うのだが、私が言いたいのは、「問題の解決」や「法的な責任」と、「当事者の人間像」とは、物事の異なる次元に属する話でどちらも無視することはできないということだ。我々が持たなくてはならないのは、それらを両立させるような語り口である。
さて、その上で山上徹也のような現代のテロリストの人間像について考える時、冒頭で述べたように同情を覚えはするものの、どうも薄気味悪さがつきまとう。人殺しが不気味なのは当たり前だと言われそうだが、それとはまた別の「嫌な感じ」である。言い方を換えると、山上の行為には、派手な外形の割に、我々の心を躍動させるものがない。「心躍るようなテロ」を待望するわけではないのだが、仮に山上が小説中の人物であったとして、そこには血を沸かすような行為のダイナミズムが決定的に欠けていると言いたいのである。
「昭和維新」に打って出た青年将校たちには、救国の道を歩んでいるという自負があった。新左翼のテロリストたちにも、革命の情熱があった。そして山口二矢の短い生涯には、文字通り「短刀直入」と形容すべき鋭さがあったし、彼は60年安保闘争の熱狂をみて、日本を赤化の波から守らねばという使命感に動かされていた。
しかし山上徹也にみえるのは、ただ陰鬱な転落の道のりである。またそれは、テロリストとは言わないだろうが、同世代にあたる酒鬼薔薇聖斗(神戸連続児童殺傷事件)や加藤智大(秋葉原無差別殺人事件)にも言える。彼らも社会に対する一種の「叛乱」を仕掛けたのだが、背後にあるのは主として恨み節や喪失の物語で、行動を通じて獲得すべき積極的なものが欠けている。
かつてのテロリストたちは、誇大妄想や論理の飛躍が混じるものであったとは言え、「社会」や「理想」を背負い、「未来」を向いて戦っていた。賛否は措くとしても、行動家の至純な動機や、ほとばしる鮮血のような生命力には、それ自体心を打つものがある。彼らの個人史にも陰鬱な側面があるにはあるが、それを覆すだけの行為の迫力があった。
一方、現代のテロリストは孤独で、後ろ向きである。ただ外形的な意味で単独犯であるというだけでなく、彼らの動機の先には「国家」も「故郷」も「仲間」も見えず、むしろそれらに見放されたがゆえの凶行のように思える。かつてのテロリストは、言わば歴史のうねりに押されるようにして行動に及んだので、家族や隣人が制止しても無駄であっただろう。しかし現代のテロリストは、彼らに声を掛け、思い遣り、包摂する親身な関係のないことが、むしろ行動の重要な起因になっていそうである。
人が互いに包摂し合うには、人間を人間として、人生を人生として物語る習慣が不可欠であるが、「テロリストに同情するな」と主張する人々が言いたいのは、テロリストの存在を単なる「安全を脅かすリスク」としてのみ見よということだ。しかし、「このテロリストは同情に値しない」という個別的な評価はともかく、それを原則論にまで押し広げるのはいわゆる「排除型社会」の発想であって、現代の最も根深い病理の一つだと私は思う(以前の記事を参照)。
「リスクの統制」も「損得の勘定」も「規則の遵守」も、現代の強力な規範である。しかしこれらに言葉を支配されてしまった時、我々には人間を人間として描く余地が残されない。そしてその先にあるのは、異質な者とのあいだで「警戒心だけが交換される」ような世の中で、その無機質な空間がむしろリスクを再生産する。「テロリストに同情するな」という主張がテロを生み出しているとまでは言わないが、「紋切り型の言葉」はそれ自体が危機を胚胎するものであるということを忘れてはならない。
執筆者 :
TAG :
CATEGORY :
NEW

2025.05.09
NEW

2025.05.09
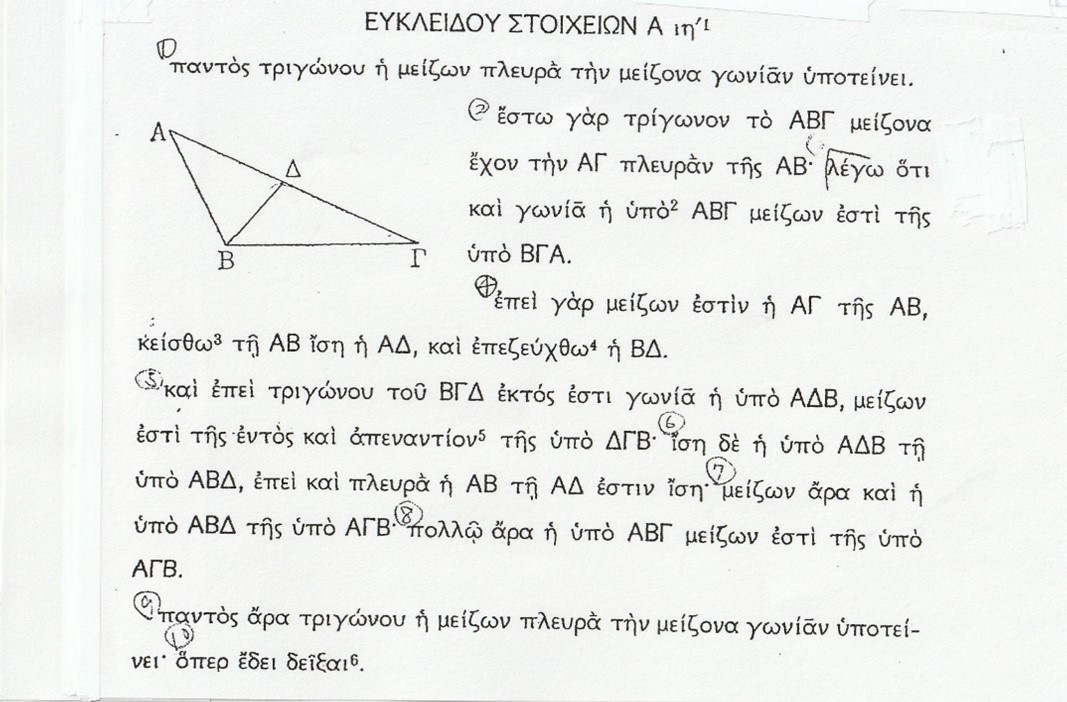
2025.05.02

2025.05.01
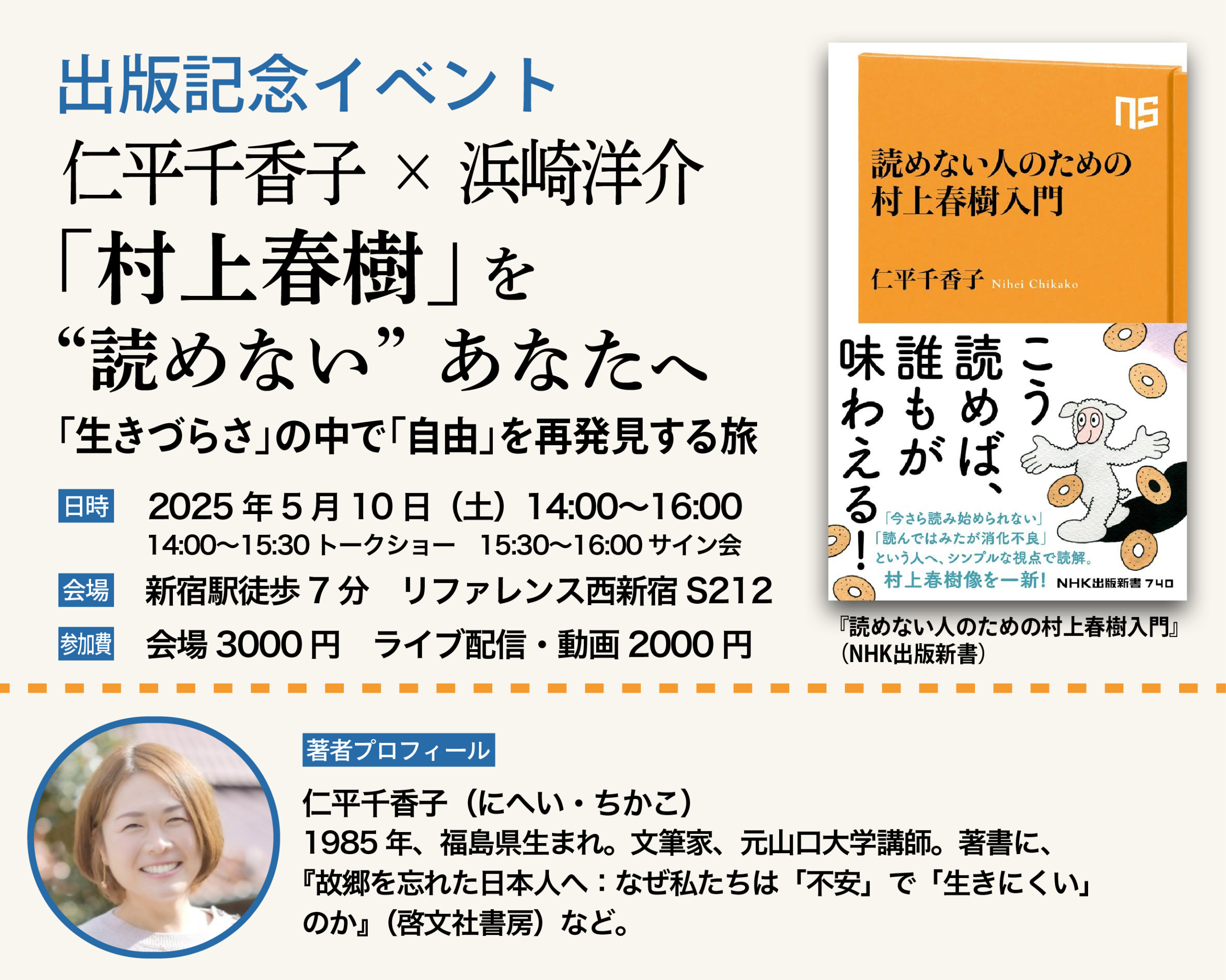
2025.04.27

2025.04.25

2024.08.11
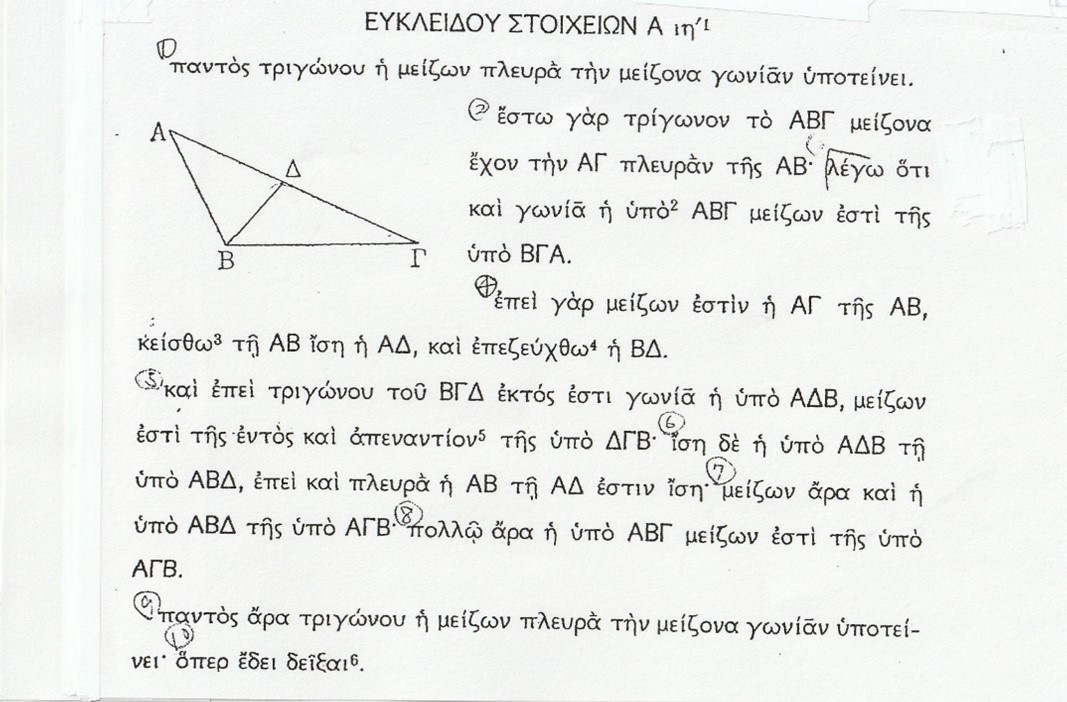
2025.05.02

2025.05.01

2025.03.26

2025.05.09

2018.07.18
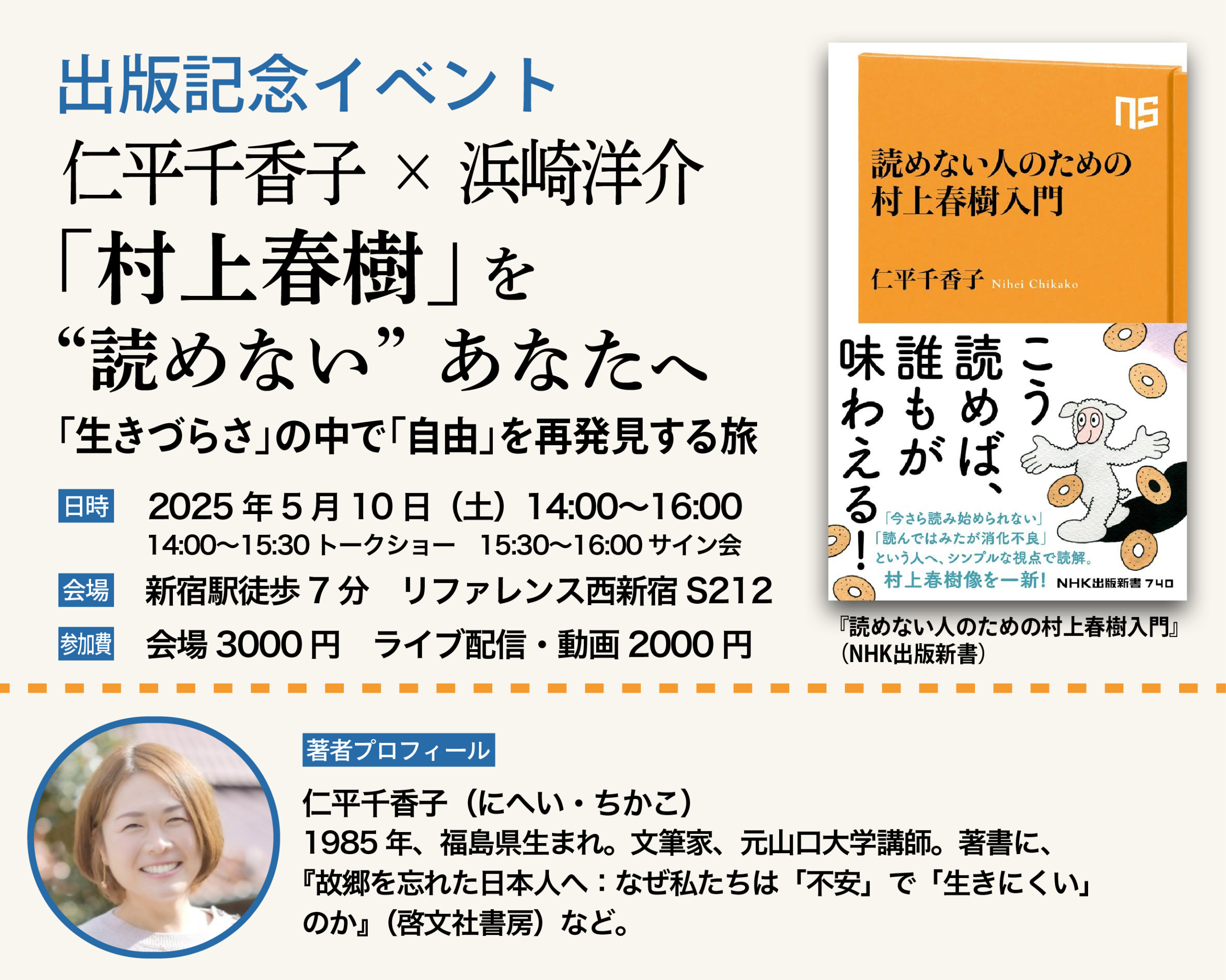
2025.04.27

2024.02.14

2025.04.21

2025.04.09
コメント
>〜血を沸かすような行為のダイナミズムが決定的に欠けていると言いたいのである。
>賛否は措くとしても、行動家の至純な動機や、ほとばしる鮮血のような生命力には、それ自体心を打つものがある
川端さんの本論考は深い洞察、示唆に富んでおられます。
昨今、市井では“テロリズム”なるものは、すっかり政治性より無差別殺人と峻別不能な認識へ倒錯している。
この様な価値判断は、精々リスクマネジメントの一環程度にしか論じられない。最早“恐怖(テロル)”とは、存在甚だ疑わしい矮小な個人感情に堕するより他ない。
正に、安い日本、の物語と考えます。
たしかに、行為に空恐ろしさを覚えて震え上がるようなことがなく、せいぜい「運悪くあのような場面に遭遇することがありませんように」というリスクマネジメントの発想しかないですね。
酒鬼薔薇聖斗やオウム真理教にはまだそれがあったかも知れません。良いものだとは思いませんが。
私も同じ感想を持ちましたが、「行動を通じて獲得すべき積極的なものが欠けている」という一文や過去と現在のテロリストを比較した一節など、川端さんはやたらと文章がうまいですね。
たんなる感想で終わらせず、ちょっと考えてみようかとペンをとりノートを開いたところで、私からは一生出てきそうにない文章です。
本題とは関係のない、これもただの感想で失礼しました。
私の記事は大したものではないですが、これをきっかけに、『山口二矢供述調書』や『テロルの決算』を読む人が1人、2人でも増えたらいいかなと思いました。別のものでもいいのですが、昔と比べることで、何を失ったかを考えることができるので。
あと安倍さんの襲撃事件についての論評としては、クライテリオン本誌でも何度か登場いただいている金子宗徳先生の、「安倍元首相暗殺が象徴するもの」(『国体文化』令和4年9月号)がおすすめです。
山上には安倍晋三を何が何でも殺さねばならないという思いつめた真剣さが感じられない。故人への深い恨みや国家、国民に対する義憤の念も無い。ただの見せかけの行動なのだ。
翻って警察側はどうかというと、事件当日までの山上の足取りを正確に検証している節が無い。おまけに致命傷を与えた銃弾を確保していないというのであるから全く真剣さが無い。
今の日本の社会への「嫌な感じ」はここから生ずる。
木村の事件はさらに迫力が落ちそうですね……。